奈良の大仏様
今年は歴史を学びたいと思っていますので、そういうネタが増えていくと思います。
今日もナショナル・ジオグラフィックのホームページを読んでいたら、古代インカ帝国で生贄にされた少女たちは、生贄になる1年ほど前から薬漬けにされていたことが分かったそうです。これは以前も「ケプラー疑惑」のところで紹介したX線分析手法が使われていそうです。(HPの中では分析手法については特に述べていませんでした)毛髪の中に含まれる元素成分が毛根からどの長さにどの程度含まれているのか、を調べることで死亡時刻からさかのぼってどのようなものを摂取したのかがわかるというものです。
生贄となった少女たちはトウモロコシで作ったお酒とコカインの基となるコカを摂取させられ、「その日」が近づくにつれてお酒とコカの量が増やされていったようです。いや本当こういう世界に生まれなくてよかったというが正直なところですが(笑)間違っても現代の視点で当時の判定をしてはいけないと思います。彼らにとっては怒れる神を鎮める神聖な儀式だったのでしょうし、民族の存亡に関わる問題として真剣にとらえていたのは間違いないでしょう。
ところで志村史夫『古代日本の超技術』を読んでいたら奈良の大仏様に関する面白い記載がありました。奈良の大仏様は幾多の戦乱などにより破損したため都度修復されてきたため、奈良時代から残っているのは腰から下の蓮の部分付近のみとなっています。そして銅に含まれている成分を調べることで、当時使われた銅は山口県美東町長登で産出されたものであるということがわかったそうです。面白いのはここからで、著者はなぜ山口県長登の銅が使われたのか?を考察しており、それはズバリ銅の中に含まれる不純物の中でヒ素と石灰成分が他の銅よりも多かったからだと指摘します。
私も初めて知りましたが銅に含まれるヒ素が多いほど銅の融点が下がるそうです。純粋な銅は1083℃までいかないと溶けないそうなのですが、ヒ素を多く含む長登の銅は1000℃前後で溶けるそうです。そしてこの100℃程度の差が大きかったというのです。それは当時の過熱が木炭・木材に頼っていたため、現在のように手軽に高温を得られるわけではないという事情があったためと考えられます。
もう一つ石灰成分が多いと粘性が下がるそうです。要するに銅を溶かした時にサラサラになりやすいというのです。奈良の大仏様は粘土で作った型の中に溶かした銅を流し込んで作られているので、粘性が低い方が都合がよいわけです。
著者はおそらく銅は日本各地から集められたが、その中で最も作業に適していたのが山口県長登の銅であり、それを当時の技術者たちは見抜いていたのだと推測します。堺屋太一も『日本とは何か』という本の中で奈良時代の日本の銅溶着技術が世界最高レベルであったと指摘しています。そもそも銅の溶着技術が日本に導入されたのが708年頃のようですが、奈良の大仏が752年に開眼供養会をしたことを考えると、中国から技術導入してわずか40年ほどで韓国や中国を追い抜くほどの技術力を手にしたということになります。ちなみに銅の「溶接技術」が発明されたのが1960年代とつい最近のことです。←これにも驚かされました!
※ちなみに山口県長登の銅にはヒ素は5%ほど含まれていて、通常の100倍ほどに相当する高濃度だそうです。また石灰は産地の近くに秋吉台があり、もとの地質が石灰が多いという特性があったためと考えられます。
いや~、古代にはロマンがたくさんありますね(^^)
読んだらクリックお願いします↓ ポイントが入り励みになります













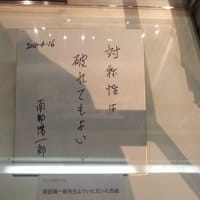



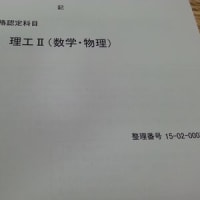
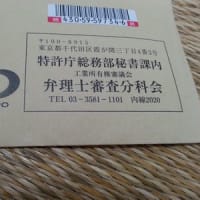


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます