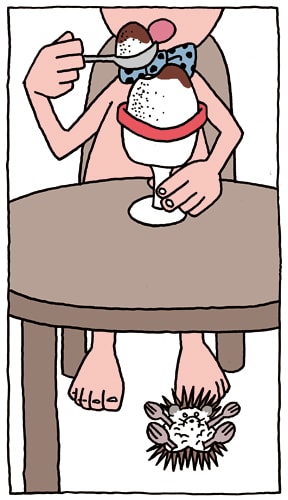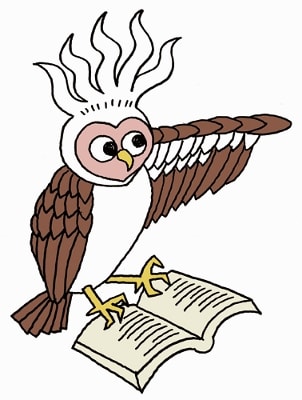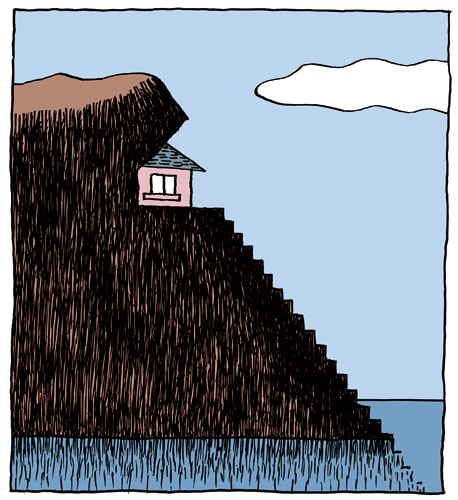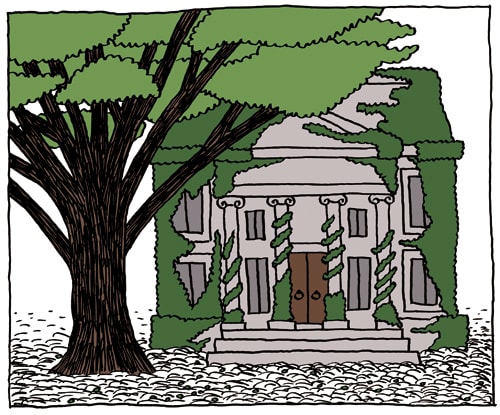作・鈴木海花
挿絵・中山泰
国境の町のむこう、
<ナメナメクジの森>を越えると
そこには、
ちょっと風変わりな生きものたちの暮らす国がある。
*はじめてお読みの方は、「その8」にあるバニャーニャ・ミニガイドを
ご覧ください。
バニャーニャ物語 その18 紅茶がおいしい夜でした!
窓から入る風が、ひんやりと肌をなでていく、秋の夜でした。
「明日のメニューにはポルチーニのチャウダーをのせよう」
ジロは、去年採ってすっかり乾燥させておいたポルチーニ茸を袋から出して、
たっぷりの水にひたしました。
一晩たてば、きっとポルチーニからすばらしい旨味が出て、
秋の訪れを堪能できる美味しいチャウダーができるでしょう。
デザートは、サツマイモのタルトにしようかな、とジロが考えていたとき、
スープ屋の入口の鈴がチリン、と鳴って、モーデカイが入ってきました。
「やあ、ごめん、ごめん、すっかり遅くなっちまったよ」
「陽が落ちるのが早くなってもう暗いから、どうしたかな、と思っていたんだ」
モーデカイが店のテーブルの上に大きなカバンを下ろすのを手伝いながらジロがいいました。
モーデカイは今朝早くから、国境の街へおつかいに行ってきたのです。
「きょうは配達が多くってさ。
はい、これ頼まれていた紅茶だよ」
モーデカイがカバンから、大きな紙袋を取り出してジロに渡しました。
「あれ、いつものと違うね」ジロが、お茶の缶を見ながら言いました。
「うん、お茶屋のおやじにすすめられて飲んでみたら、すごく香りがよかったんで
これにしてみたんだけど、気にいるといいなあ」
「モーデカイが美味しいって思ったんだったら、間違いないよ」
ジロがさっそく缶の蓋を開けて、香りを吸い込みながらいいました。
「うわー、ほんとにいい香りだ」
コーヒーが苦手なモーデカイはけっこう紅茶の味にはうるさくて、
国境の街の大きなお茶屋さんで選んできてくれる紅茶にはジロは絶対の信頼をよせています。
「よし、さっそくいま淹れるから、いっしょに飲んでいかない?」
「そりゃありがたいな」
ジロはとっておきの濃い緑色のポットに、封を開けたばかりのお茶の葉と、
熱いお湯を注いで、堅焼きのビスケットを添えてテーブルに置きました。

夏の終わりから秋のはじめにかけて、バニャーニャでは雨の日がつづきました。
そして、その雨があがると季節はがらりと様相をかえ、空はぐんと高くなり、
空気は澄んで、風がちょっと肌寒いくらいになりました。
「うーん、うまい!」
ジロがカップに注いだお茶をひと口飲んで、
舌の上の香りを味わうように目を閉じて満足そうにいいました。
丁寧に淹れたお茶はこっくりとした色。
湯気といっしょに香気がたちのぼります。
「紅茶の美味しい夜だねえ」モーデカイが、しみじみとした調子でいいました。
そのころカイサは・・・・・。
テーブルの上に広げたいろいろな葉っぱや枝や木の実を前に、とほうにくれていました。
「うーん、やっぱりこれも気にいらないか・・・・」
氷の洞窟からもってきた氷の花が溶けて、なかから出てきた1匹の虫。
それは見たこともない不思議な形をした虫でした。
長い間、冷たい氷のなかに閉じ込められていたにもかかわらず、
それは、おどろいたことに氷が解けると同時に、息を吹き返したように、
動き始めたのです。
シンカが「雨ふり図書館」にあるありったけの図鑑で調べてくれましたが、
どこにもこんな虫は載っていませんでした。
しかしこの虫は、もう一か月近くも、
綿にしみこませた水を
そのストローのような口でときどき吸うだけで、
カイサがあげるどんな食べ物も食べようとしません。
「困ったねえ・・・・・・早く食べられるものが見つからないと、生きていけないよね。
あしたも、さがしてみるか・・・・・・」
カイサはため息をつきながら、虫をハチミツの空き瓶にいれて、枕元において眠りました。
つぎの日の午後のことでした。
用意したポルチーニ茸のチャウダーはすごい人気で、
お昼にはすっかり売り切れてしまいました。
お客さんが途絶えた合間に、ジロがピーナッツクリームのサンドイッチをかじっていると、
戸口の戸が、ばーん!と、音をたてました。
びっくりして見ると、
なんと、そこにはあのラ・トゥール・ドーヴェルニュ王国の
ナナ・ウリエ・フォン・シュヴァンクマイエルが立っているではありませんか。

ナナはハアハア吐息をきらしながら、戸口に仁王立ちになって
ジロをにらんでいます。
「わあ、ナナさんじゃないですか、久しぶり!
またバニャーニャに来てくれるなんて。
さあ、はいったはいった」
ジロが笑顔でそういうと、ナナはなおもハアハア荒い息をしながら、
いきなり大声でいいました。
「カイサはどこなの?
あっちこっち探したのに、家にもいないじゃないの!」
「カイサはたしか、虫のエサさがしに毎日あっちこっちいってるみたいですよ」
ジロがいいました。
「とりあえず、ナナさん、なにか飲み物でもいかがですか?」
ジロがイスをすすめながらいいました。
ナナさんったら、いつもこんな調子だからな。
でも、また来てくれるなんで、きっとバニャーニャが気に入ったんだな、と思いながら。
「ふん、このびんぼったらしい食堂も、相変わらずだわね」
ナナは少し落ち着いたようで、スープ屋の店内を見回しながらいいました。
「またナナさんに会えるなんて、きっとカイサも大喜びですよ」
ジロが、きのうモーデカイが仕入れてきてくれた香りのいいお茶を淹れながらいいました。
「ふん、私がはるばるドーヴェルニュから来てあげたっていうのに、
虫のエサをさがしているですって!ゆるせないわ」
ナナはまた激高しそうになりながら、喉が渇いていたのか
ジロの淹れたお茶をひとくち飲みました。
「あら・・・・・・・」
「ふん、こんなド田舎にしては、ま、マシなお茶だわね」
「ところで、こんどはシャルルさん、いっしょじゃないんですか?」
「もちろん、国王の娘である私がひとりっきりで旅をするはずがないじゃないの!
あいつったら、バニャーニャに着くなり、ジャマイカインのコルネとキノコ話で夢中になっているのよ。
秋になるのを待ちかねて、ナナさま、またカイサさまにお会いにバニャーニャに行かれては、いかがでしょう?気候もよろしいですし、なんてうるさかったのは、
また自分がコルネとキノコをさがして食べたいからなのよ。
ったく、調子のいい軟弱者なんだから」
「あれ?シャルルさんは、今度はナメナメクジはだいじょうぶだったのかな」
ジロが、カラになったナナのカップにお茶のおかわりを注ぎながらききました。
はじめてバニャーニャに来た時、シャルルはナメナメクジの森でひどい目にあったのです。
「ふん、またシャルルがこの前みたいにかゆくて寝込まれたらたまらないじゃないの、
今度は近くの岬まで船で来て、コルネにボートで迎えに来てもらったのよ」
ナナがそういったとき、開けっ放しになっていた戸口から、
「ジロ、いるぅ?」とのんびりした声がして、フェイが顔をのぞかせました。
そして、テーブルに座っているナナをみると、「ぎゃっ!」と叫んで
後ずさりました。
「その失礼な態度、許せないわ!」
がたんと椅子を鳴らして立ち上がり、
ナナがフェイを怖い顔でにらみつけていいました、
「いえ、ちょっとびっくりしちゃったもので。
あのぅ、また・・・・・またいらしたんですね」
フェイが、しぶしぶといった様子で店に入って来ながらいいました。
「ナナさんはね、またカイサに会いにきたんだけど、
どこにいるか、わからないんだ。フェイ、知らない?」
ジロが、フェイにもお茶を用意しようと立ち上がりながらいいました。
「さあ、まだ虫の食べ物が見つからないとかいって、
毎日さがしまわってるみたいだったけどな」
同じころ、ホテル・ジャマイカインでは、
再会を喜ぶシャルルとコルネが、さっそく美味しいキノコの話で盛り上がっていました。
「もうそろそろ、バニャーニャの森には私の国では見たことのない
キノコがいっぱい生え出しているんだろうと思うと、いてもたってもいられなくなりましてね。
ナナさまをそそのかして・・・・いえその、おススメしてこうやってやってきたわけです」
シャルルが満面の喜びを浮かべた笑顔でいいました。
「あのリュウゼンコウは我が国の歴史でも最上の品質でして。
おかげで、我が国はいままでよりさらに高品質の「一なる香油」をつくることができ、
空前の繁栄を謳歌しておるのです。
これもみんなバニャーニャのみなさんのおかげだと、国王も、ことのほかお慶びで。
ナナさまも、ラ・トゥール・ドーヴェルニュ国特製の「一なる香油」をぜひひとビン、
カイサさんに届けたいと、思っていらっしゃったわけでして、
つまり今回の訪問はわたくしめの
キノコ欲を満たすためだけではないのであります」
「いやあ、ひとりで賞味するより、
美味しさがわかる人といっしょに食べるキノコの味は格別だからね。
明日はさっそく、森へキノコ狩りといきましょうや!」
コルネもうれしそうにいいました。
ジャマイカインで夕ごはんを済ませたナナとシャルルは、
日が暮れて暗くなった道を、
バニャーニャの西にあるカイサの家に向かって、歩いていました。
「ナナさま、待ってくださいませ。長旅をしてやっとバニャーニャにたどり着いたばかりですのに、そんなに早く歩かれては、お体にさわりますです」
シャルルが先を行くナナにいいました。
「うるさいわね!私はあんたのように、軟弱ではないのよ。
もうカイサも家にかえっているはずよ。
今夜じゅうに、これを渡すと、わたしは決めているんだから」
カイサの家には灯りがついていました。
ナナがいきなりドアを開けようとするのをなんとか押しとどめて、
シャルルがノックしました。
「はーい・・・・いまごろ、だれだろう?」
そういいながらドアを開けたカイサのびっくりした顔。
「ナナちゃんじゃない!!!いつバニャーニャにきたの?!
また会えたなんて、うれしいよー」
「いつ来たのって、きょうの午後には着いていたのに、
どこをさがしてもアナタがいなかったんじゃないの!
まったく、あちこちさがしまわってしまったわ。
いったいどこに行ってたというの?」
「うん、ちょっとね、この虫がなんにも食べないんで
困っているんだよ。だからあっちこっち探していたの」
カイサはナナに会えたうれしさに、顔を輝かしていましたが、
ちょっと疲れているようにも見えました。
このところ、虫が何も食べないので、カイサもすっかり食欲をなくしていたのです。
「カイサさん、ちょっとお痩せになったのではないですか?」
シャルルもカイサの顔を見て心配そうにいいます。
「うーん、そういえば、きょうも何食べたっけかな?」
「いけませんです!食べものこそ、体をつくり、心を強くするのです」
シャルルが間髪をいれず、きっぱりといいました。
「カイサさん、明日はごいっしょに、キノコ狩りにおいでになりませんか?
コルネがキノコ料理に腕を振るってくれることになっています。
美味しくて滋養のあるものをしっかり召し上がって、力をつけてください」
シャルルが力を込めていいました。
「ありがとう!そうだね、またナナちゃんと歩きたいし、
いっしょに行くことにしようかな」
「こんな田舎でほかにすることもないし。私もいっしょに行ってあげることにしようかしらね。
あ、シャルルがどうでもいいキノコのことなんかいうから、
肝心なことを忘れるところだったじゃないの。
私がここに来たのは、カイサにこれを渡すためなのよ」
ナナはそういうと、肩にはおったケープのなかから、
上等そうな絹の綾織りでできた、小さな布袋を取り出して、カイサに差し出しました。
「我がラ・トゥール・ドーヴェルニュ王国が誇る、世界にふたつとない<一なる香油>よ。
ありがたいと思いなさい!」
「わあ、すごーい、<一なる香油>って、世界でナナちゃんの国でしか作れなくて、
すんごく貴重なんでしょう?こんなもの、もらっていいのかなあ」
布袋からガラスでできた小瓶を、おそるおそる取り出しながらカイサがいいました。
「カイサさんたちのおかげで、<一なる香油>の調合に欠かせないリュウゼンコウを手に入れることができたのですから、これはナナさまからの、心からの感謝のしるしなのです、はい」
シャルルがいいました。
「よけいなことを言わなくていいのよ。
ちょっとした手土産なんだから、感謝のしるしなんて、おおげさな!」
「ふぁ~・・・・・」
ガラスの小瓶を鼻に近づけたカイサは、その香りに言葉もなく目をとじて
うっとりしました。
それはいままで嗅いだことのない、体と心を満たす圧倒的なパワーをもった香りでした。
「これが<一なる香油>の香り・・・・・・なんだかすごく、幸せな気持ちになっちゃった」
「ふん、やっと、「一なる香油」のなんたるかが、少しはアナタにもわかったようだわね」
「おや、小雨が落ちてきたようでございますよ。
この雨で森にはにょきにょきとキノコが・・・・・・。
明日は絶好のキノコ日和になることでしょう!」
シャルルは顔を輝かせながらそういうと、ナナといっしょに帰って行きました。
朝がたは昨夜からの小雨が残っていたものの、
お昼前には木々のあいだから薄日がさしてきて
シャルルの期待通り、森のなかでは、次々とキノコが見つかりました。
「エクセレント!コルネ殿、これをご覧ください!ヤマドリタケの幼菌ですぞ、
間もなく傘が開くでしょうが、このタイミングで食すのがこのキノコの醍醐味なのです。
あっ、あれ、あそこにも、ムラサキホウキタケが。ぜひこれは色を残したまま、コルネ殿の料理の腕でソテーにしていただきたいものです」
針葉樹の葉を敷き詰めたカゴのなかに傷つけないように、
慎重な手つきでキノコをいれながら、シャルルが弾んだ声でいいました。
「ソテーにシチューに網焼きに、と、料理はおまかせあれ」
コルネが、自分のカゴにオレンジ色のフウセンタケモドキを入れながら答えました。
「私はもう帰るわよ。靴が泥だらけだわ」ナナが口をとがらせていいました。
「うふふ、シャルルもコルネも楽しそうだね」とカイサ。
そのとき、「コルネ殿、これはいったい!?」
熊笹の茂みのなかから、にょきっと出ていた1本の大きなキノコをつみとったのを
コルネに渡しながら、シャルルが頓狂な声をあげました。

「ううむ、見たことのないキノコですなあ」
コルネも首をひねっています。
「なんと、傘のまわりから、さかんに胞子を飛ばしておりますぞ!」
ふたりの熱狂した会話をきいて、ナナも寄ってきました。
「こんな見るからにヘンチクリンなキノコ、毒があるに決まっているではないの」
「さよう・・・・・たしかに毒を持っている可能性もなきにしもあらずですが・・・・・
なにぶんにも、食してみないことには証明はできない」
シャルルが意味ありげにつぶやきました。
「とりあえず、持ち帰ってみましょうや」コルネがいいました。
その夜、ホテル・ジャマイカインの食堂のテーブルは、まさにキノコ尽くし。
はりきって腕をふるったコルネがつくった料理がこれでもかというほど並びました。
「わあ、ひさしぶりに、いっぱい食べちゃった。
シャルルさんのいうとおりだね、ちゃんと食べたら体に力が湧いてきたよ」
カイサがおなかをなでながらいいました。
「ああ、もううんざり。おんなじ食材でよくも飽きないものだわね。
私はもともとキノコってあんまり好みじゃないし」
ナナがシャルルとコルネを横目で見ながら苦々しい口調でいいました。
「今宵はまさに、至福のときでありました!」
シャルルが目をとろんとさせていいました。
「では、キノコの夕べもそろそろお開きとしましょうや」
コルネがシャルルに意味ありげに目配せしながらいいました。
その夜も更けたころ。
ナナは、となりの部屋から聞こえものすごいうなり声と、
物がぶつかる音で目を覚ましました。
音は、ますます大きくなるばかりです。
「いったいこんな夜中に、なんの騒ぎかしら?」
すっかり目が覚めてしまったナナが、そっと部屋のドアを開けて廊下を見ると、
シャルルが両手を頭の上に振り上げ、踊るような格好で、
階段をころげるように、降りていくのが見えました。
びっくりしたナナがなおもドアの隙間から見ていると、
今度は、同じように両手を振り回しながら、コルネが
踊るような足取りで、階段を上ってくるではありませんか。
階段の真ん中あたりで出会ったコルネとシャルルは、
大声で吠えるように笑いながら、なおも奇妙な踊りをつづけています。
「まったく、こんな夜中に、なんの騒ぎなの!!!」
ナナがガウンをひっかけて廊下に出ていくと、
シャルルとコルネは、泣き顔で笑いながら(?)
奇妙な踊りをつづけています。
「ナナさまー、お許しください」
息もたえだえに、苦しげな笑顔を浮かべたシャルルが叫びました。
どうやらシャルルとコルネは、みんなにないしょで
あの、見たこともない怪しいキノコを食べて、
毒にあたってしまったようです。
ふたりの苦しげな踊りは朝方までつづきました。
騒ぎをきいて、駆けつけてきたフェイが砂薬を飲ませると、
やっと気分がよくなったようです。
「症状からみて、これはワライダケの一種にあたったんだな」
フェイがいいました。
「キノコマニアっていうのは、たとえ毒があるかもしれないと思っても、
未知のキノコを見たら、食べてみないではいられないというからね」
いっしょに来たシンカがあきれたようにいいました。
一晩中、笑ったり踊ったりしないではいられない毒にあたったシャルルは、
体力が恢復するまで、バニャーニャに留まることになりました。
ホテルの仕事ができなくなったコルネに代わって、シンカがふたりの介抱にあたり、
フェイも毎日、薬を届けにやってきます。
そんなわけで、このところナナは、
「この不祥事は国に帰ったらお父様に報告して、即刻、シャルルは解雇してやるから!」
と息巻きながら、毎日ジロのスープ屋で食事をしています。
「まあまあ、シャルルさんも好きが高じて、つい度が過ぎちゃったってことで、
勘弁してあげてください」
ジロが、ナナのお皿を片付けながらいいました。
「そうだよ、シャルルさんって、あんなにナナちゃんに一生懸命仕えてるしさ」
カイサもいいます。
「そういう問題ではないのよ!」ナナがついに癇癪を起して、
テーブルをドン!と両手でたたいて怒鳴りました。
「ねえ、ナナちゃん、明日はさ、海岸のほうへ行ってみようよ。
今頃はきれいな貝殻が打ちあがるから、貝拾いしない?」
ナナが興奮しているときには、話題を変えるに限ると知っているカイサは、
さりげなくそう言いました。
「えっ?、ええ・・・・・・他にすることもないし。
あら、わたし、なんだかすごくノドが渇いてしまったわ。
あのなんていったかしら、ポ、なんとかっていう、バニャーニャにしかないっていう果物」
「ポポタキス?」
「そんな名前だったわね。ジロ、あのジュースをもう一度飲みたいのよ。
この前ここに来た時には、あっちこっちで見かけたのに、
今はどこにいっても見ないわ、あのピンクのオレンジみたいな実」
「ええ、ポポタキスが実をつけるのは、春から夏なんです。
だけど、収穫した実が地下室にたくさんありますから、
今、すぐジュースにしておもちしますよ」
ジロがいいました。
「ポポタキスは、ほんっとに美味しいからね~。
ナナちゃんが気に入るものがバニャーニャにあってよかったよ」カイサがいいました。
「べつに、気にいったというわけではないのよ、ただ、喉が渇いただけだわ」
「はい、お待ちどうさま、しぼりたてのポポタキスのジュースですよ」
ジロがそういって、ナナの前にジュースのグラスを置いた時でした。
カイサの上着のポケットから、
目にも留まらぬ早さで、あの氷の花から出てきた虫が
飛び出したのです。
そして、それはまっしぐらにナナの前のポポタキスジュースの入ったグラスのふちにとまり、
そのストローのような口で、ぐいぐいと、美味しそうにポポタキスのジュースを飲み始めました。
「ぎゃー、なによ!!!
私のジュースに虫が、虫が・・・・」
ナナがイスから立ち上がって、叫びました。
カイサは、顔を輝かせながら、虫がジュースを飲むのをまじかで覗き込んでいます。
「アンタが好きだったのは、ポポタキスだったのか!
秋には木に実がないから、ポポタキスのことはすっかり忘れていたよ。
よかったー、ポポタキスならうちの地下室にいっぱい貯蔵してあるから、
これで冬がきても食べもののことは安心だね」

「はい、新しいのをおもちしましたよ」
ジロがナナの前に、新しいグラスを置きながらいいました。
「まったく、飲もうとしているジュースに虫が飛び込むなんて、
田舎って、これだから・・・・・」
ぶつぶついっているナナに、
「ナナちゃんっ、ありがとうっ!
この虫の好きなものがわかったのは、ナナちゃんのおかげだよ」
カイサが心からうれしそうに、ポカンとしているナナの手をとっていいました。
「ああ、なんだか私もおなかが空いてきちゃったぁ。
ジロ、パプリカのスープ、まだ残ってる?」
カイサの声がはずんでいます。
秋の夜長、空には煌々と満月が輝き、
冷たさを増した風が、川面をわたっていきました。
*********************************
野外の観察で、育てててみたい虫を見つけた時、
その食べ物である食草を確保するのは、けっこう重要な問題です。
虫は必ずしも止まっていた場所の植物を食べるとは限らないので、
食草がわからないこともあり、そんなときは苦労します。
だから、未知の虫の食べ物がやっと判明した時の、カイサの気持ち、
よくわかります。
今飼っているラデンキンカメムシ(外来種なのでまだ正式な和名がない)という、
南西諸島の美しいカメムシ。

本来の食草はアカギという奄美諸島などにある木の実なのですが、
東京でそれを常備するのは難しいので、
代替食として、生の落花生を千葉の農家から取り寄せ、
富沢商店で生のアーモンドを買い、(カメムシはナッツ類が好き)
お友達の家の近所で、ヤマモモの枝を集めました。
食べものがわかり、準備できるといつもほっとします。
カイサが飼っている虫は、どうも何かの幼虫のようです。
春にはきっと羽化して成虫になるんじゃないかな。
どんな虫になるのか楽しみです。