
作・鈴木海花
挿絵・中山泰
国境の町のむこう、
<ナメナメクジの森>を越えると
そこには、
ちょっと風変わりな生きものたちの暮らす国がある。
バニャーニャ、というのが、その国の名前でした。
となりにある大きな国の海岸から突きでた、
タンコブのような形の国で、
潮が満ちると、大陸から切り離され
島のようにぽつんと、海のなかに取り残されます。

バニャーニャのまん中あたり、高い丘の頂には、
「石舞台」と呼ばれる、古い不思議な言い伝えのある場所があります。
ここにはフクロウのバショー一家が代々住みついているだけで、
バニャーニャのものたちは夏の雨乞いの儀式をするときの他は、
あまり近寄りません。
丘からは、たくさんの川が流れ出ていて、
スープ屋のジロが店を開いているのも、ある川のほとりでした。
曲がりくねった、中くらいの幅の川で、
水が澄んでいるので、
川底のコケのはえた石ころや、
魚の姿がよく見えます。
だからジロの店のお客さんたちは、
店の前の木立に囲まれた岸辺のテーブルで
スープを飲むのがすきです。
でも今は、そのテーブルも椅子もすっかり片付けられて、
お客さんたちは大きな石の暖炉のある店の中で、
このとびきりスープのおいしい季節を
心ゆくまで楽しもうと、やってくるのです。
そんな冬のある日のことでした。
午後3時。ジロは海辺にいました。
冬の海辺はひとけもなく、
空は今にも落っこちてきそうなほど重い鉛色。
でもジロは毎日海を見にきます。
そして毎日思います
―この向こうに、なにがあるんだろ?と。
海辺の散歩から店の戸口に帰ってきたとき、
空気が急にしーんとなり、雪が降りはじめました。
ジロはしばらく戸口にもたれて、雪にみとれていました。
びっしりと体をおおっているウロコのすきまから、
寒さがしみとおってきます。
でもこんなふうに、世界がみるみる変わっていくのをながめているのは、
なんともいいものです。

さあ、そろそろ店を開ける用意をしなくては。
ジロは黄色い長靴を、やわらかい皮のモカシンにはきかえると、
カウンターの横の黒板に、今夜のメニューを書きはじめました。
*インゲン豆のスープ・・・・・・3ルーン
*ムラサキにんじんのポタージュ・・・3ルーン
*17種のピメント(トウガラシ)入り辛いスープ・・・・・・・4ルーン
*夜光貝のチャウダー・・・・・・9ルーン
全部焼きたてパン付
本日のデザート
*サツマイモのタルトとろりクリーム添え
*アズキ豆のアイスクリーム
「ルーン」―というのは、
バニャーニャで使われているお金ですが、
持っていないお客さんはなにかほかのもの
―ほりたてのピーナッツとか、
銀色のぴちぴちしたマスとか、
来るとちゅうでつんだ青いヤグルマギクとか、
またはギル族たち(エラを持っていて水の中で息ができるものたちを
バニャーニャではこう呼びます)がよくするように、
海の底から持ってきた美しい貝殻とか―ではらってもいいのです。
それは、バニャーニャでは、どこの店でも同じです。
戸口の鈴がチリン、となって、
川向こうの「砂屋」のフェイが入ってきました。
「うう、さむ。とうとう降ってきたね。
えーと、ぼく今夜はトウガラシのスープにしよおっと」

フェイの店は、253種類(現在のところ)の、
世界中の砂浜や、砂漠や、川底や、砂丘の砂を売っています。
砂は場所によってみんな違う、ということが、
フェイの店へ行くとわかるでしょう。
バニャーニャでは砂は、ビンにいれて飾ってながめたり、
花壇にまいたり、
砂絵を描いたり、
せっけんに練りこんだり(肌がスベスベになります)
また砂シェイク(フェイが調合する特効薬)にして飲んだり、
といろいろな使いみちがあるのです。
「暗くなってきたね」
ジロは、フェイに手伝ってもらって、
3つのランタンに灯を入れました。
鈴がまたチリンと鳴って、
こんどは大きな体の「お使い屋」のモーデカイが、
のっそりと入ってきました。
モーデカイは背なかを丸めて、
いつものように暖炉の前にすわります。
とけかけの雪で毛皮がきらきら輝いています。

「この雪が降りつづいたら、あしたの国境の町行きは延期?」
フェイがモーデカイにききました。
「うん、2、3日ようすをみることになるかな」
となりの国との境にある深い森をぬけて、
その先の「国境の町」へ行けるのは、
お使い屋のモーデカイだけです。
というのは、この森には、アリと同じくらいたくさんの
「ナメナメクジ」がいるからです。
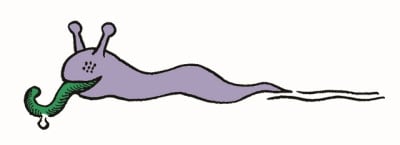
ナメナメクジは見たところごく無害な生きものですし、
とてもなつっこくって、森に入ると、
すぐピタピタはいのぼってきます。
そしてそのきれいな緑色の舌で所かまわずナメまわします。
ところが、ちょっとでもこれになめられたが最後、
毛皮の毛は抜け落ちるし、
かゆくて気が狂いそうになり、
やがて肌が厚いかさぶたでおおわれてしまうのです。
そして何よりもコワイのは、
その後も長い間、
窓を閉めても閉めても
ナメナメクジが自分の部屋に入ってくる悪夢を見つづける、
という後遺症に悩まされることです。
でもモーデカイには、なぜか
ナメナメクジが一匹も寄ってこないのです。
そこでみんなはバニャーニャでは手に入らない、
なにか遠い世界のものがほしくなると、モーデカイにたのみます。
国境の町には、
世界中の商人や旅人が集まってくるので、
いいものも悪いものも、何でもありましたから。
「わあ、いいにおーい!」
と言いながら入ってきたのはカイサでした。
店のなかには、すっかり準備できたスープと、
焼きたてのパンの香りが満ちていました。
「あれ、きょうは寒いからなんにもいっしょじゃないの?」と
フェイがいいました。

「えへへ、ちゃんとここにいるよ」
カイサが、かぶっている毛皮のほかほかした帽子を指さしていいました。
「この冬は、ここで越冬することに決めたらしいの」
フェイがカイサの帽子に目を近づけてみると、
バニャーニャハナムグリが一匹、
もこもこのやわらかい毛の間から
ねむそうな顔をのぞかせました。
この国は「ナメナメクジの森」によって
大陸と隔離されているせいか、
昔からバニャーニャだけにいる珍しい生きものがいます。
ピンク色に光るバニャーニャハナムグリもそのひとつ。
カイサは小さな生きものが大好き。
いつも虫といっしょです。
降りつづく雪が川辺に降りつもるころには、
店はジロの予想をこえる数のお客さんで、おおにぎわいになりました。
体の芯からあったまりたいものはトウガラシのスープを、
辛いのが苦手なもの―モーデカイのように―は
インゲン豆やムラサキニンジンのを、
めずらし物好きでお金もちのボデガのようなものたちは夜光貝のチャウダー
―これは「フラミンゴのくちばしのスープ」などと共に
ごくたまにしか手に入らない素材でしたから―を注文しました。
みんなのおなかがいっぱいになり、
バスケットのパンもあらかたなくなったころ、
戸口の鈴が、チリリリーンと鋭い音を立てました。
風が出てきたのでしょうか。
雪が、夜の中から吹きこんできて、
床の上で、さあっと、とけました。
戸口につかまるようにして立っていたのは、
まるで古い人形のようにみえる、
小さなおばあさんでした。
ジロとカイサがかけよって、支えるようにして中に入れると、
おばあさんは、「スープ・・・」
というなり、ばったりと倒れました。
それからの1時間というもの、
おばあさんは4種類のスープを
一杯ずつ、はじめはゆっくりと、
しだいに飲む早さを増して、
そして同じ順番でもう一杯ずつ、
きれいに飲み干し、ゲップをし、
満足そうにため息をつき、言いました。
「こんなおいしいスープを飲んだのは、何百年ぶりかねえ」
そういったおばあさんの目はすっかり元気そうにかがやき、
どこから取り出したのか、
手には2本の黒い編み棒を持っていました。

それをカチカチならしながら、
スカートのひだの間からするすると、
一本の紅バラ色の毛糸を取り出しました。
「まず、今夜ねるとこ」
そういうと、みんながあっけにとられている目の前で、
信じられないようなスピードで、一枚のしきものを編み上げました。
「おつぎはベッド」
そういうと今度は、茶色の糸を引き出して、
体の大きさにピッタリのサイズのベッドを編み上げました。
それはふっかりとやわらかい毛糸でできているのに、
ちゃんと床に立って、みんなをびっくりさせました。
毛糸は時には黄色、時には赤、
というふうに色まで変えながら、
ひだの間から、もうとめどなく出てくるのでした。
それからかけぶとんを編み、
枕を編み、たまげたことには
小さな家まで編み上げて、
外の雪の上に、ふんわり、と置きました。
そして最後にうす茶色の
ふにゃっ、としたものを編んで、肩に乗せました。
するとそれは肩の上で、
こっくりこっくり、いねむりをはじめました。
「ひゃ―、これ、生きてるよぉ!」
指先でさわってみたフェイがおどろいて叫びました。
「これは湯たんぽがわりのカンガルーネズミさ」
おばあさんはそれからジロに向きなおると、
「わたしゃ、1ルーンも持ちあわせがないんだけどね」
といって、ジロに2本の黒い編み棒をさし出しました。
「スープの代金はこれでいいかい?
この編み棒なら、今見たとおり、
心に描いたものを、
そっくりそのまま編むことができるよ」
おばあさんはそういって、
黒い編み棒をジロに手わたすと、
「それじゃ、おやすみ」
といって店から出て行きました。
よく朝、ジロが目をさまして2階の寝室の窓から下をのぞくと、
おばあさんが、ちょうど毛糸の家から出てきたところでした。
ジロが見ていると、おばあさんは目にもとまらない早さで、
きのう編んだすべてのものを
―あの茶色のカンガルーネズミまでも―
スルスルとといて(とかれるそばから糸はまたひだの中に吸いこまれていきました)、
丘のほうに向かってずんずん、歩いていってしまいました。
まるでなにごともなかったかのように、
いちめんの雪が朝日をあびて、
そこには足あとひとつのこりませんでした。
さて、ジロが黒い編み棒で編んだものはなんだったかって?
それは,全長2メートル、
白い舟体に黄色と青の線が入った、ちいさな舟でした。
それはずっとジロの心の中にありましたから、
すみずみまで正確に思い描くことができました。
ジロが毛糸を手にすると、
黒い編み棒は手のなかで勝手に動いて、編みはじめるのです。
もちろん、あのおばあさんのような、
目がまわるようなスピードで編むことはできませんでしたから、
舟が完成するまでには、その冬いっぱいかかりました。
フェイもジロから編み棒をかりて、あのカンガルーネズミを編もうとしました。
しかし、正確に思い描く、というのは案外むずかしいものです。
細かいところがあいまいだったせいか、
なんだか、おかしな生きものができ上がりました。
春の最初の風が、
丘の上から水仙の香りを運んできた朝、
ジロは東の海岸から舟出しました。
黄色と青の線の入った、白い舟で。
舟体に<ジロ号>、とくっきり赤い文字が編みこまれた毛糸の舟で。

「つめれば、二人乗れるかもしれないよ」
フェイがいいました。
「これは、ひとり乗りの舟なんだよ」
とジロがやさしく、しかし、きっぱりといいました。
モーデカイは、心配でなりませんでした。
こんな怪しげな毛糸の舟に乗って、海をわたっていこうなんて。
しかし、誰かが舟出しようとしているときには、止めることはできない、
ということを知っていましたから、
ただ、その大きな手でジロの興奮で冷たくなった小さな手をにぎり、
「気をつけてね」
とだけ言いました。
「オミヤゲ、いっぱい持ってかえるからね」
ジロはそういうと舟に乗りこみ、帆をあげました。
春の気まぐれな風が帆をふくらませて、
ぐいと、ジロ号を海へ押し出しました。
その春の終わりごろ、
モーデカイは国境の町の居酒屋で、
こんなウワサを耳にしました
南の海で、おかしな毛糸の舟に乗った冒険者を見た、と。
ジロはもうすぐ戻ってくるんじゃないか―
モーデカイとフェイとカイサはそんな気がして、
このところ毎日、丘の上の石舞台から、海をながめています。
つづく・・・・・・。
***************************************************
スープ屋のジロ、いきなり1回目で旅に出てしまいましたね・・・・・・。
ところでなんで主人公のひとりジロがスープ屋かっていうと、
それは私がスープがだいすきだから。
スープを飲むと、なんだか心がおちつきます。
あたたかい季節には川辺のテーブルで、
雪降る冬には暖炉のそばで飲むスープって、きっと最高!
なので朝ごはんにはよくスープをつくります。
いちばん好きなのはニンジンとジャガイモの、オレンジ色のポタージュ。
コンソメでニンジンとジャガイモの荒切りを煮て
ミキサーにかけるだけ。
パセリのみじん切りをたっぷりふって。
緑色がきれいなグリーンピースやブロッコリーのスープもよくつくります。
ムラサキニンジンとういのは、バニャーニャにしかないのですが
きっと鮮やかなムラサキ色のスープなんだろうなあと想像しています。
さて次回は、ジロの留守にバニャーニャにとんでもないことが起こります。
毎月1の日は、バニャーニャ更新の日。
また、あそびに来てください。









