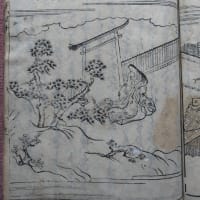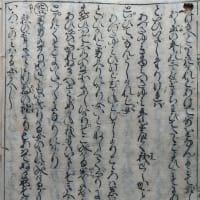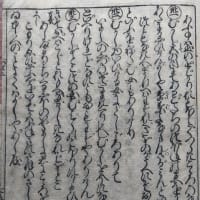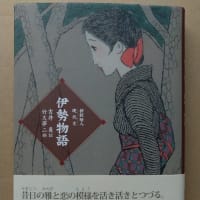あく
た
川
の
だん
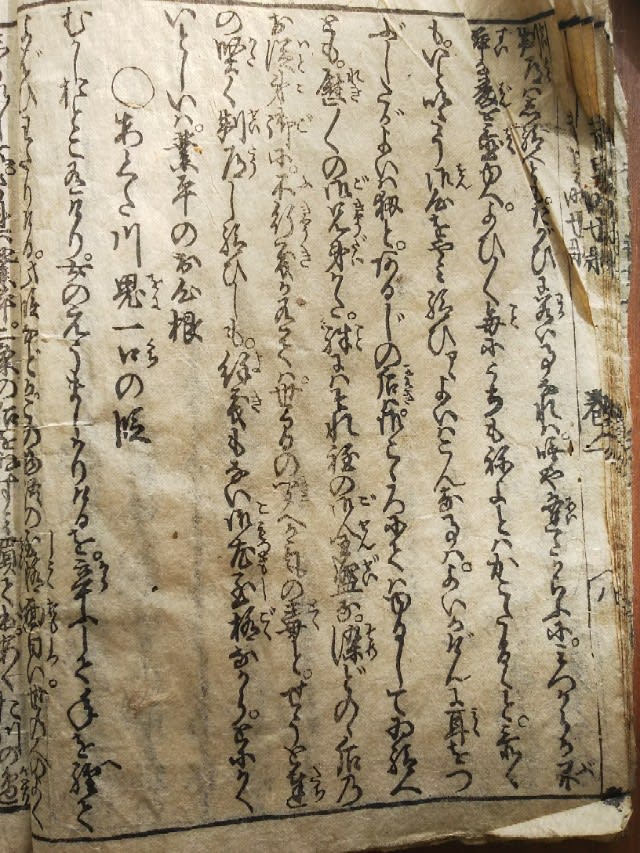
○あくた川鬼一口の段
むかしおとこ有けり。女のえうまじかりけるを辛ふじて年を經て
よばひわたりける。此段などが、この物語の至極面白い、世の人のよく

しられし所。されば業平、二条の后をぬすみ負て出、あくた川の邊
にて、露を何ぞと問れしとは、なま心ある千話ぶみに書なさん、或は
諷又は上瑠璃の道行、いろ/\さま/"\にいひなせし。尤さふも有
さふな事。まづ得がたき君を、年を經てよばひわたり。辛労し
て盗み出て、いと闇い雨の夜、神鳴にも恐れず、戀の奴となり
給ひて、かひ/"\しくも后をば負ふてあくた川迄は来り給ひし
。そのあくた川は、どこの事かもしれねど、それ迄のお二人の有様、
今見るやうにおもはれ、いた/\しうてお笑止。草のうへに置たり
ける、露を何ぞと問れながら、行先多く夜も更にければ、鬼ある
所ともしらで、神鳴はなる、雨は頻にふつて来る。せんかたもなくて
どこぞそこらの、あばらなる倉。人舎のやうなところ、但は人の軒

の下かに、后をばおろし申し、少のをくにをし入れをおとこ弓箭を
負てとあれど、たつた今まで后をばをふてのいたお身なれば
弓箭は有まいけれども、戀の念力、こゝろに弓やなぐゐを負て、
をのれやれあ何ものにても、若もの事もあるならばと、大膽な気に
成給ひて、后をば、はなちはやらじと思召すその躰アゝ一向はやう
夜が明たらと、思ひつゝゐ給ふ内に、鬼はや一口にくひてげり
后はあれなふ、あなやといはせ給へど、神鳴やら雨やらで、業平は聞
付給はず。その内やう/\夜もあけゆくに、見れば出こし女もなし。
南無三宝是までにして、しばらくもねもせぬに、何ものかはつれ
行けん。是はかなしや扨無念やと、蹉跎をして歎き給へどかひなし
しらたまかなにぞと人のとひしとき

つゆとこたへて消なましものを
是は二条の后、お従弟御染殿の后の御方に御奉公でもなく
畢竟いはゞ、お部屋子といふやうなものにていらせ給ひしを、かの
業平も、染殿の后○へは、お心安うなお出入申されしが、いつの隙にか、彼二条
の后の御面影の、さしもめでたくましますをちらと見染、さすが
戀には、氏も位も見かへりがたく、又それ程の賤の夫にてもあらざれば、只
かり初の御たはぶれ、雲にかけはし霞にちよろり、どふやらかふやら
たがひに合点の相ぼれとなり、盗みて負て出ひ給ひけるを、御兄御
堀川の大臣、又その兄の太郎国經、まだ下臈とて殿上人の時とか、さ
れば宵より、雨かみ鳴のはげしき夜なれば、お妹御ながら、染殿の
后の御きげんの程お見舞とて、内へ参り給ふに、いみじうけしからず

泣人の有けるまゝ、是は何じや何事ぞと問せ給へば、お傍衆お腰
元の女中たち、アイ申シ后○がお見えなされず、おゆく衛がしれませ
ぬ。是はまあどふ致しませふと、巣立の白鷺が、親鳥をしたふが
ごとくに、姦しい程泣立るを、お二人の兄御達も、きよつとした顔
つきにて、是はたまらぬそふしては置れまいと、俄に狩衣の袖を
腕まくり、指貫の尻を引からげて、はれやれ是はといひながら
爰かしこと尋ね給ふ。さればとよ業平、一生に跣で、一丁とも
あるかぬお身、殊には后を負給ひて、はか/"\しう得は立退もし給
ず、ついそこらにて、かのふたりの兄御に見付られ、取返されたまひ
し也。さぞ残多ふ思召ふ。露を何ぞと問れ給ひし時、露と答
へて消たらば、今の思ひはせまじき物をと、その業平の思ひの程

をもかへり見給はぬ、戀にはむごき兄御たち、それをかく鬼と
はいふなり。二条の后、まだいとお年若にて、后成もし給はず
只の人にておはしける時の事とかや。
新古今和歌集 第八 哀傷歌
題しらず 在原業平朝臣
白玉か何ぞと人の問ひしとき露とこたへて消なましものを