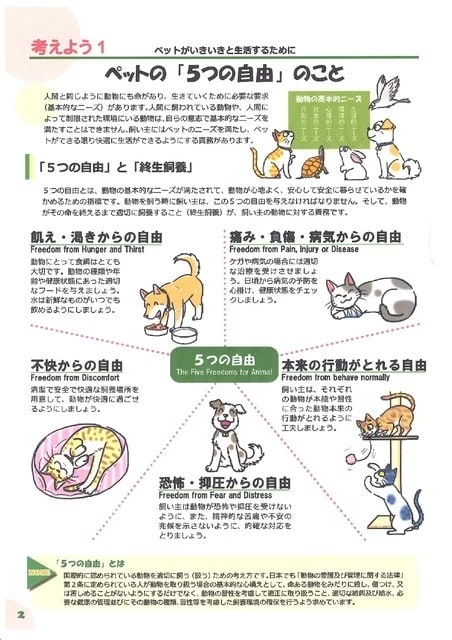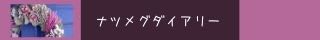今回のテーマは
1.法律から見る動物問題 弁護士 浅野明子氏
2.動物虐待事案の現状と課題 弁護士 細川敦史氏
動物の愛護及び管理に関する法律の目的は…
第一章総則
(目的)
第一条 この法律は、動物虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取り扱い
その他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて
国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の
情操の涵養に資するとともに、
動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に
対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、
もって人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
第一章 総則 (基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、
何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、
または苦しめることのないようにするのみではく、
人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して
適正に取り扱うようにしなければならない。
…とあります。
動物は「物」と言われて憤慨される方もいますが、
定義上のことであり、上の総則第二条にあるように
「命あるもの」と別格になっています。
また、横浜市にも動物の愛護及び管理に関する条例があって
「市の責務」「市民の責務」「飼い主等*の責務」「動物取扱業者の責務」
が明示されています。
*飼い主等=飼い主と実質的に飼い主と同一視されるものを含む
私たちには動物に対する責任、ヒト、および環境に対する責任の両方を
愛護と管理という法律に決められているということです。
動物に関わる問題は、
人が動物に対して行う行為と動物が人に危害等をおよぼす行為がありますが、
愛玩動物では、どちらも人が関わっていますから、
動物が被害者であることが多いように思います。
飼い主である私たちは、動物が被害者にならないように
学び、暮らすことが重要ですし、そうすることで動物と人と共生できる社会に
近づくのではないでしょうか。
・*:..。o♬*゚・*:..。o♬*゚・*:..。o♬*゚・*:..。o♬*゚
今日も暖かい時間にお散歩行ってきました。
速足の時もある。
自由気ままなお散歩です。
におい嗅ぎもバッチリ!
Choco.が必ず歩く土手
リードはなるべく浮かせ気味に持つように気をつけています。
それと、まっすぐ前を向いて歩くとき以外は
少し短めに持って、もう片方の手もリードを軽くつかんでいます。
急に走り出す、回りだすときの安全のためです。
気をつけていれば、それだけChoco.が転ぶ心配が減りますからね。
だからといって、リードは張らないように気をつけています。
ソメイヨシノはもう少し
*今日の午後3回目のワクチン接種してきました。
1,2回目はファイザー、3回目はモデルナでした。
今のところは変化なし。明日はどうでしょうね。
副反応があっても軽く済めばいいのですが…。