
さて、昨日に続いての「イージーリスニング」のウンチクを・・・。
人が音楽を聴いてリラックスするというのは、その音楽(=ジャンル)が好きだ、というのが大前提にある。今回のテーマになっている耳障りでなく優しい雰囲気でそばで鳴っていても気にならないほどの心地よい存在感などが特徴の「ムード音楽」(後のイージーリスニング)には、聴く人の心を優しくくすぐるための音楽的テクニックというものがあることをご存じだろうか。
ただ優しく音量的にフラットな美しいメロディを豪華なオーケストラで奏でただけでは、そこには印象の残らない一過性の美があるだけになる。
この手の音楽の全盛期には、演奏者同士のライバル意識もあっただろうし、ビジネスでもあるわけだから、そこには他者との差別化を図るためのいろいろな工夫があって当然なのだ。
一つは派手なプロモーション。積極的に媒体にも登場することでレコード・セールスを伸ばそうという営業的工夫。
二つには音楽家として曲のアレンジや既存のメロディをどう取り込んで独自のサウンドに染めていくかという音楽的工夫。
三つ目には、その時代時代の空気を読んでヒット作を作っていくというプロデューサー的工夫。
さらには、営業をかける国別にアレンジを変えたり、採用する曲にそのお国柄を反映させたりする工夫。
まぁ、結局のところレコード会社の利益と楽団の存続維持のためとういうのが音楽ビジネスであるから、そのための努力・工夫が最優先されているわけだ。
だけれども僕のような音楽の中身自体に興味がある人間にはやはり二つ目の「音楽的工夫」に迫っていきたくなるのだ。
昨日書き出したこのジャンルの楽団(演奏者)で最も音楽的技術に工夫を見せたのは「ムード音楽」ジャンルにある<マントヴァーニー・オーケストラ>だと思う。
このジャンルの愛好者ならすでによくご存知だろうが、この楽団のストリングス(弦楽器セクション)の創意工夫に満ちたサウンドは一世を風靡したものだ。
具体的なお話の前にまずはこの演奏(サウンド)を聴いていただこう。
誰もが一度は耳にしたことがあるだろう有名な演奏だ。
マントヴァーニー・オーケストラ 「シャルメーヌ」
この曲の構造は単純で、ストリングスの圧倒的に豪華な合奏と木管などのソロのパートが交互に現れる。伴奏となるパートはドラムなどのパーカッションを使わない、古いジャズ的なギターのカッティングが中心のものだ。
マントヴァーニーの最大の特徴は楽器群でいえば「ストリングス」のアンサンブルにある。
極論すればこのストリングス・パート以外はとてもオーソドックスな伝統的手法しか聞きとれない。
それでもマントヴァーニーのどの曲でも必ず姿を見せるストリングスの華麗なサウンドは、他者との
差別化において圧倒的な優位を誇示していた。
あっ、これはマントヴァーニーだ!、とストリングスの部分が出ただけで誰もが気が付く。
これはこの楽団の最大の功績だし、特色であった。
聴いていただいた最初の部分。いきなり「どうだっ!」って感じでこの楽団の唯一ともいえる特色が前面に出てくる。
ヴァイオリンのアンサンブルがまるでエコーやリバーブをかけたように爽やかな響きをもって流れ出てくる。
人呼んで「カスケーディング・ストリングス」と呼ばれる弦楽器のアレンジ法だ。
「カスケード」とは「滝」。「滝」は「滝」でも人工的な滝、というのが本来の意味だが、初期のマントヴァーニのアルバム(英米盤)には「いかなるエコー・マシーンも使っていない」との注意書きがあったほどのこれは弦楽器のアレンジによる魅力的なサウンドなのだ。
「カスケーディング・ストリングス」とは、文字どおり「滝が流れ落ちる」ような弦の響きであり、この楽団の専属アレンジャー:故ロナルド・ビンジの才覚によって生まれた(発明された)ものだ。
マントヴァーニー・オーケストラでは45人のオーケストラの7割を弦楽器とし、バイオリンを4つのパートに分けたそうだ。それぞれがメロディ・ラインを少しずつずらして弾くと、あたかもエコーのような効果が生じ、この響きを楽団のトレード・マークとした。
ネット上でバイオリン・パートを4つに分けたカスケーディング・ストリングスによる「魅惑の宵」の冒頭部の譜面を見つけたのでその実際の音とともに音符のマジックを見てほしい。
 「魅惑の宵」冒頭部(7秒から13秒あたりまで)の恐るべき技!
「魅惑の宵」冒頭部(7秒から13秒あたりまで)の恐るべき技!
「魅惑の宵」
ご覧のように、4つのパートがそれぞれにメロディの一部らしきものをやっているけれども、パート単位で聴くと実際のメロディは出てこない。それは何故かといえば、分散してやっているからで、どう分散しているかというと交互に(パート1~4の)違ったグループに行ったり来たりする。それが一緒になると、他の音が余韻となっているので、エコーのように聴こえる。これを多用したのがロナルド・ビンジのアレンジの秘密というわけだ。
いくつかのパートで弾くと一つのパートでは聞こえてこなかったメロディーがつながって聞こえるというのは<譜面読み大好きの僕>の経験ではチャイコフスキーの「悲愴交響曲」にも例がある。
ロナルド・ビンジのヴァイオリン分奏はこういった聴感上のトリックを使っているのだ。
こういう話になるともう止まらなくなるのが僕の性格なので、この辺でやめておくが、イージーリスニングのような耳に優しい音楽というのは、それなりの演奏や工夫をして生まれている。
今日はマントヴァーニーの一例を使って音楽のトリックの一端を楽しんでもらった。
家でくつろぐ時、たまにはこういう音楽を流してみてはいかがだろうか。
アメリカナイズされたヒップホップなどクソくらえ!と過激なことを静かな音楽を流しながら思う僕だ。
人が音楽を聴いてリラックスするというのは、その音楽(=ジャンル)が好きだ、というのが大前提にある。今回のテーマになっている耳障りでなく優しい雰囲気でそばで鳴っていても気にならないほどの心地よい存在感などが特徴の「ムード音楽」(後のイージーリスニング)には、聴く人の心を優しくくすぐるための音楽的テクニックというものがあることをご存じだろうか。
ただ優しく音量的にフラットな美しいメロディを豪華なオーケストラで奏でただけでは、そこには印象の残らない一過性の美があるだけになる。
この手の音楽の全盛期には、演奏者同士のライバル意識もあっただろうし、ビジネスでもあるわけだから、そこには他者との差別化を図るためのいろいろな工夫があって当然なのだ。
一つは派手なプロモーション。積極的に媒体にも登場することでレコード・セールスを伸ばそうという営業的工夫。
二つには音楽家として曲のアレンジや既存のメロディをどう取り込んで独自のサウンドに染めていくかという音楽的工夫。
三つ目には、その時代時代の空気を読んでヒット作を作っていくというプロデューサー的工夫。
さらには、営業をかける国別にアレンジを変えたり、採用する曲にそのお国柄を反映させたりする工夫。
まぁ、結局のところレコード会社の利益と楽団の存続維持のためとういうのが音楽ビジネスであるから、そのための努力・工夫が最優先されているわけだ。
だけれども僕のような音楽の中身自体に興味がある人間にはやはり二つ目の「音楽的工夫」に迫っていきたくなるのだ。
昨日書き出したこのジャンルの楽団(演奏者)で最も音楽的技術に工夫を見せたのは「ムード音楽」ジャンルにある<マントヴァーニー・オーケストラ>だと思う。
このジャンルの愛好者ならすでによくご存知だろうが、この楽団のストリングス(弦楽器セクション)の創意工夫に満ちたサウンドは一世を風靡したものだ。
具体的なお話の前にまずはこの演奏(サウンド)を聴いていただこう。
誰もが一度は耳にしたことがあるだろう有名な演奏だ。
マントヴァーニー・オーケストラ 「シャルメーヌ」
この曲の構造は単純で、ストリングスの圧倒的に豪華な合奏と木管などのソロのパートが交互に現れる。伴奏となるパートはドラムなどのパーカッションを使わない、古いジャズ的なギターのカッティングが中心のものだ。
マントヴァーニーの最大の特徴は楽器群でいえば「ストリングス」のアンサンブルにある。
極論すればこのストリングス・パート以外はとてもオーソドックスな伝統的手法しか聞きとれない。
それでもマントヴァーニーのどの曲でも必ず姿を見せるストリングスの華麗なサウンドは、他者との
差別化において圧倒的な優位を誇示していた。
あっ、これはマントヴァーニーだ!、とストリングスの部分が出ただけで誰もが気が付く。
これはこの楽団の最大の功績だし、特色であった。
聴いていただいた最初の部分。いきなり「どうだっ!」って感じでこの楽団の唯一ともいえる特色が前面に出てくる。
ヴァイオリンのアンサンブルがまるでエコーやリバーブをかけたように爽やかな響きをもって流れ出てくる。
人呼んで「カスケーディング・ストリングス」と呼ばれる弦楽器のアレンジ法だ。
「カスケード」とは「滝」。「滝」は「滝」でも人工的な滝、というのが本来の意味だが、初期のマントヴァーニのアルバム(英米盤)には「いかなるエコー・マシーンも使っていない」との注意書きがあったほどのこれは弦楽器のアレンジによる魅力的なサウンドなのだ。
「カスケーディング・ストリングス」とは、文字どおり「滝が流れ落ちる」ような弦の響きであり、この楽団の専属アレンジャー:故ロナルド・ビンジの才覚によって生まれた(発明された)ものだ。
マントヴァーニー・オーケストラでは45人のオーケストラの7割を弦楽器とし、バイオリンを4つのパートに分けたそうだ。それぞれがメロディ・ラインを少しずつずらして弾くと、あたかもエコーのような効果が生じ、この響きを楽団のトレード・マークとした。
ネット上でバイオリン・パートを4つに分けたカスケーディング・ストリングスによる「魅惑の宵」の冒頭部の譜面を見つけたのでその実際の音とともに音符のマジックを見てほしい。
 「魅惑の宵」冒頭部(7秒から13秒あたりまで)の恐るべき技!
「魅惑の宵」冒頭部(7秒から13秒あたりまで)の恐るべき技!「魅惑の宵」
ご覧のように、4つのパートがそれぞれにメロディの一部らしきものをやっているけれども、パート単位で聴くと実際のメロディは出てこない。それは何故かといえば、分散してやっているからで、どう分散しているかというと交互に(パート1~4の)違ったグループに行ったり来たりする。それが一緒になると、他の音が余韻となっているので、エコーのように聴こえる。これを多用したのがロナルド・ビンジのアレンジの秘密というわけだ。
いくつかのパートで弾くと一つのパートでは聞こえてこなかったメロディーがつながって聞こえるというのは<譜面読み大好きの僕>の経験ではチャイコフスキーの「悲愴交響曲」にも例がある。
ロナルド・ビンジのヴァイオリン分奏はこういった聴感上のトリックを使っているのだ。
こういう話になるともう止まらなくなるのが僕の性格なので、この辺でやめておくが、イージーリスニングのような耳に優しい音楽というのは、それなりの演奏や工夫をして生まれている。
今日はマントヴァーニーの一例を使って音楽のトリックの一端を楽しんでもらった。
家でくつろぐ時、たまにはこういう音楽を流してみてはいかがだろうか。
アメリカナイズされたヒップホップなどクソくらえ!と過激なことを静かな音楽を流しながら思う僕だ。



















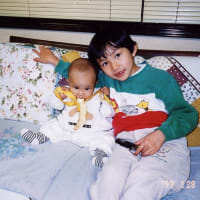
僕らの生きてきた時代って、意外と「イージーリスニング」だったりするんですよね。
僕は「恋は水色」も好きです!
そちらは春の気配がありますか?
こちらは「花粉大盛り」状態に突入です。
それホント?
なんという豪雪。今年はひどいんですね。
気象番組などで耳にはしていたけど、それほどとは・・・驚いたなぁ。
大雪か花粉か・・・と選択を迫られても、う~ん答えが出せないです!
(まぁ、花粉で我慢するか・・・?)
PS.みなさん、このコメントは旭川の方からなんですよ。
春らしい陽気で気持ちいいですね
でも旭川は吹雪なのですね。。
くまじーさん、温かくして過ごしてくださいね。
先週くらいから うちの梅の鉢植えが咲き始めて満開なんです
桜ももうすぐですね!
こんにちは。今年の冬はちょっと寒過ぎて・・・この春めいた空気感に元気が出てきますね。 花粉は大丈夫でしたっけ?
梅の鉢植え、以前にちょっと書いたのですが
http://blog.goo.ne.jp/igakun-bass/e/54307569c87c688b1d4101438a3c4d21
いい香りを毎年振りまいてくれたウチの紅白の梅の鉢は、去年の父の入院~旅立ちの間に全部枯れてしまいました。
僕の管理不行き届きのせいです。
なので今、あのいい香りを間近で楽しめません。残念です。
くまじーさん、ねこっちさんも遠い旭川の風景を想像して書いてくれているようです。
日本は広いです。春を感じ始めた僕らもいれば、風呂場の窓半分まで雪に埋もれている所もある。不公平とすら感じますね。
ねこっちさん、季節の変わり目です。
どうぞご自愛のほどを。