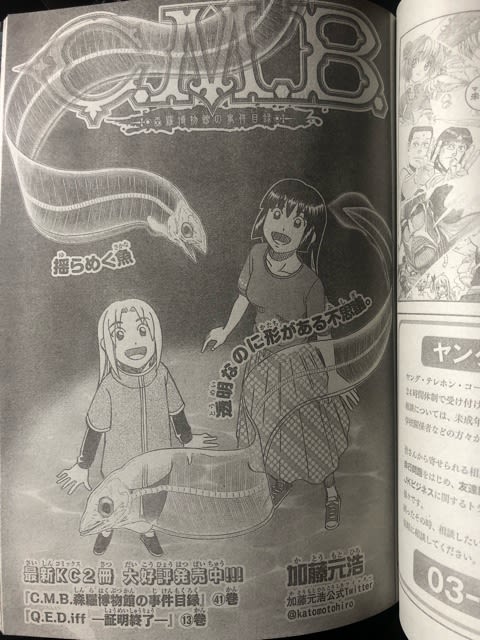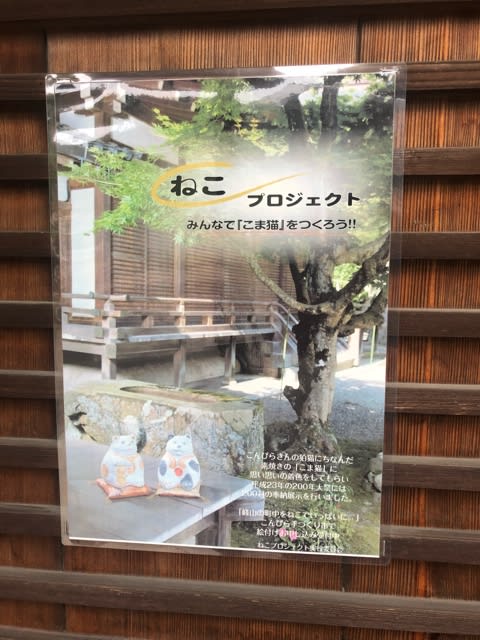●雑誌に載せてもらえない文を書いてます(ToT)
祭「雑」物館
本ブログは、播州から摂津、京都、江戸、韓国、ヨーロッパ、現代から江戸、古代、彫刻・刺繍から、台車、神道から仏教、道教、キリスト教と、記事ごとにテーマがあちこち飛んで行きます。その様相はまさに祭「雑」物館。
民俗学?
でも、その中でも重要視しているのは、台車の記事(播磨版、淡路版)に見られるような祭関係者が知恵を出したり、思いをこめたりしていることについて取り上げたいと思っています。本ブログ管理人は、祭に関係した講演の機会を賜る時は、「民俗学」を専門として語っていますが、民俗学が何なのかはよくわかっていません(ToT) 「民俗学て何?」と聞かれたら「タイコかきながら(担ぎながら)祭の歴史とか文化を考えることやねん」などと答えるのが関の山です。専門家からすると非難轟々な答えかもしれません。現に投稿した論文(もどき)は、書式の不備や推敲が著しく不足していることもあいまり(この時点で読まずに返されても文句は言えないし、読んでくださるだけでも本当にありがたいことです。)、酷評を頂いております(ToT)
●祭関係者の知恵と思いの結晶
ただ、本ブログの柱の一つとなっている屋台やだんじりの構造や担ぎ方などは、「末端」の問題でさして重要でないという指摘も頂いております。しかし、祭関係者にとっては、これほど大切なことはありません。屋台の構造がわかっていなかったり、組み方、担ぎ方の不理解は即怪我につながりますし、存続は不可能となります。また、研究者自身が祭の担い手となる場合は、末端の問題としてすませるわけにはいきません。
屋台やだんじりに関わる庶「民」の知恵とか思いがこもっているところを本ブログでは紹介できればと改めて思っています。ようは、民俗学がこのことを問題にしないのであれば、民俗学かそうでないかというのは、管理人にとってさして重要でないということに最近気づきました。どうせ、雑誌に載せてもらうことのない内容ならば、ここで発信する方がいいという結論に至り、最近はほとんど毎日書いています。
そこで大事なのが「プロトコル」というものだそうです。
●プロトコルて何?おいしいの?
「プロトコル(コンピュータの言葉として知られているみたいです。)」という言葉。博物館に勤務している方にとっては、非常に大切なものだそうです。学芸員資格をもっている管理人は生まれて41年目にして、この言葉を知りました。参考文献は『月刊少年マガジン 2019年10月号』(講談社)所収の「C.M.B 森羅博物館の事件目録」という漫画です。
あらすじはこんなかんじです。
「アメリカのとある美術館で、地球温暖化の展示をしていた。そんなある日、その美術館の学芸員が何者かに襲われる。容疑者として浮上したのは、地球温暖化に疑義を挟む思想の持ち主。大統領も温暖化を否定していると主張している。森羅たちは、この容疑者を犯人だと考えるが、証拠が見つからない。はたして立証できるのか!?」
ここで、美術館は現政権の方針に反する展示を行います。それに対して、暴力的な方法で妨害したこと(どこかで聞いたことある話です)が「プロトコル」を侵されたたいうことになります。
プロトコルというのは、何なのかを主人公の森羅は語っていますが、「自分の考えを分かりやすく伝えるため=表現の自由を行使するための手段と場と手続き」と考えるといいでしょう。伝えるためには相応しい場を用意し、分かりやすく伝えたり心に訴えかける手段をこうじなければなりません。例えば、管理人がインターネットに掲載している文章を印刷して町中に放り投げて配るやり方は迷惑なだけで、きちんとした手段や場、手続き・プロトコルが確立されているとは言えません。
きちんとした手段や場を確立して、表現する人は伝えないといけないし、見る人は自分の考えと違うこともあるかもしれないということもふまえて鑑賞する。このような手続きが必要になります。
月刊「祭」は、論文雑誌に載らない(載せてもらえない、載せて欲しいんです(ToT))けど、祭にとっては面白かったり大切だったりするものだと管理人が考える物事を伝える表現の手段と場と手続き・プロトコルとなります。
●「雑」物館? ゴミの山?
偉そうに本ブログのプロトコルについて能書きをたれたものの、実際に読者のみなさんにとって面白かったり、調べたいことが調べられるブログになっているとは到底言えません。その理由の一つが、アクセスのしにくさです。記事や調べている内容にアクセスしにくい。200を超える記事から目当てのものを探し出すのは、困難を伴います。整理されて陳列されなければガラクタの山と言われても仕方ありません。。
祭が終わったらその点をすこしでも改善できればと思っております。








![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()