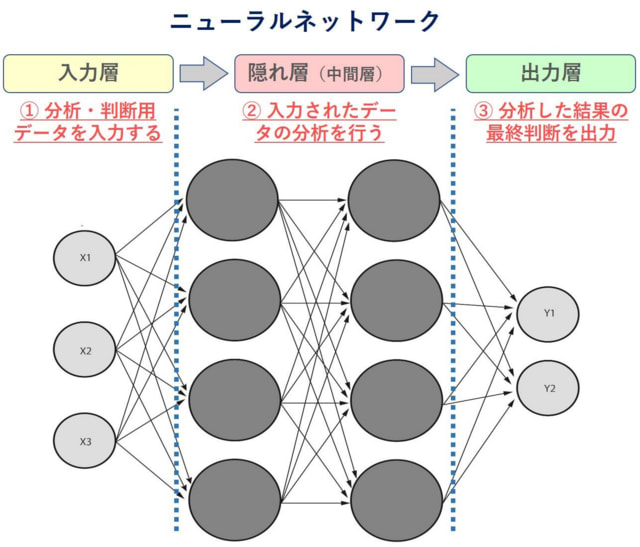はてしない物語と聖書:自己言及のパラドックスについて
ミヒャエル・エンデの「はてしない物語」( 上田 真而子、佐藤 真理子訳、岩波書店)では物語のちょうど中間地点(XI さすらい山の古老)でファンタージェンの出来事を全て記録する古老と王女である幼ごころの君のこんな会話が出て来る。
「あなたとわたくし、そして全ファンタージェンーーーあらゆるものがこの本に記録されているのですか?」 幼ごころの君は尋ねた。
古老は書き、同時に幼ごころの君の耳に古老の答えが聞こえた。
「そうではない。この本こそがファンタージェンであり君でありわたしなのじゃ。」
「では、この本はどこにあるのですか?」
「この本の中に。」 これが古老の書いた答えだった。
よく考えると、この話は矛盾を含んでいる。『この本は、この本の中に(ある)』 と言っているわけだから、自己言及のパラドックスに陥っているのだ。論理学的に考えてみよう。この文章が真ならば、この本はこの空間には存在しないことになり、偽ならばこの空間に存在するのでいくらでも書き換えることができる(=過去の事実を変えることができてしまう)。
このパラドックスは命題「この文章は偽である」と同種である。真ならばこの命題は偽だという事になり、偽ならばこの命題は真ということになる。つまり、真偽の判定ができないので、パラソックスとなる。
実はこのような真偽を判定できないパラドックスは新約聖書(聖書協会共同訳)にも出て来る。
『彼らのうちの一人、預言者自身がこう言っています。「クレタ人は、いつも嘘つき、たちの悪い獣、怠け者の食いしん坊。」』(テトスへの手紙 1:12)
話を簡単にするためにこれを書き換えると「クレタ人は嘘つきだとクレタ人が言った」という命題になる。この命題も真偽判定不能である。
この話を論理学的に記述しようとすると一階の術語論理を用いることになるが、一階の術語論理では記述できない(真偽を判定できない)ケースがある。それを解決する方法の一つが高階の術語論理と呼ばれる理論だが、ここでは詳細については言及しない。
話を はてしない物語 に戻そう。
『この本は、この本の中に(ある)』 という文章のパラドックスを解消にするには、論理学的には高階の術語論理を用いればよい。それが「人の子」という事は、ファンタージェンの世界内で解決できない問題を、別の世界から解決してもらおうという発想であり、実際はてしない物語を読んでいた人間(人の子)バスティアンは問題解決のために本の中に取り込まれてゆく。それがはてしない物語の後半である。
ところで「人の子」という訳は新約聖書でも多数用いられており、そこではキリスト(=救い主)を指しているが、この本ではファンタージェンを救うことができる唯一の人間の子という意味で用いられている。
虚無が広がりつつあるファンタージェンを救うためには幼なごころの君に新しい名前を与える必要がある。ただ、それができるのは人の子(人間)だけだった。
この話は新約聖書ヨハネによる福音書(1:1-5)に起源がある。
『はじめに言(ことば)があった。言は神とともにあった。言は神であった。この言は、初めに神と共にあった。万物は言によって成った。言によらず成ったものは何一つなかった。言の内に成ったものは、命であった。この命は人の光であった。光は闇の中で輝いている。闇は光に勝たなかった。』
実は はてしない物語 には聖書のアナロジーがたくさん使われている。ここで全てを列挙することはできないが、この物語が聖書(特に新約聖書)と強いつながりがある事を示している。
ミヒャエル・エンデの「はてしない物語」( 上田 真而子、佐藤 真理子訳、岩波書店)では物語のちょうど中間地点(XI さすらい山の古老)でファンタージェンの出来事を全て記録する古老と王女である幼ごころの君のこんな会話が出て来る。
「あなたとわたくし、そして全ファンタージェンーーーあらゆるものがこの本に記録されているのですか?」 幼ごころの君は尋ねた。
古老は書き、同時に幼ごころの君の耳に古老の答えが聞こえた。
「そうではない。この本こそがファンタージェンであり君でありわたしなのじゃ。」
「では、この本はどこにあるのですか?」
「この本の中に。」 これが古老の書いた答えだった。
よく考えると、この話は矛盾を含んでいる。『この本は、この本の中に(ある)』 と言っているわけだから、自己言及のパラドックスに陥っているのだ。論理学的に考えてみよう。この文章が真ならば、この本はこの空間には存在しないことになり、偽ならばこの空間に存在するのでいくらでも書き換えることができる(=過去の事実を変えることができてしまう)。
このパラドックスは命題「この文章は偽である」と同種である。真ならばこの命題は偽だという事になり、偽ならばこの命題は真ということになる。つまり、真偽の判定ができないので、パラソックスとなる。
実はこのような真偽を判定できないパラドックスは新約聖書(聖書協会共同訳)にも出て来る。
『彼らのうちの一人、預言者自身がこう言っています。「クレタ人は、いつも嘘つき、たちの悪い獣、怠け者の食いしん坊。」』(テトスへの手紙 1:12)
話を簡単にするためにこれを書き換えると「クレタ人は嘘つきだとクレタ人が言った」という命題になる。この命題も真偽判定不能である。
この話を論理学的に記述しようとすると一階の術語論理を用いることになるが、一階の術語論理では記述できない(真偽を判定できない)ケースがある。それを解決する方法の一つが高階の術語論理と呼ばれる理論だが、ここでは詳細については言及しない。
話を はてしない物語 に戻そう。
『この本は、この本の中に(ある)』 という文章のパラドックスを解消にするには、論理学的には高階の術語論理を用いればよい。それが「人の子」という事は、ファンタージェンの世界内で解決できない問題を、別の世界から解決してもらおうという発想であり、実際はてしない物語を読んでいた人間(人の子)バスティアンは問題解決のために本の中に取り込まれてゆく。それがはてしない物語の後半である。
ところで「人の子」という訳は新約聖書でも多数用いられており、そこではキリスト(=救い主)を指しているが、この本ではファンタージェンを救うことができる唯一の人間の子という意味で用いられている。
虚無が広がりつつあるファンタージェンを救うためには幼なごころの君に新しい名前を与える必要がある。ただ、それができるのは人の子(人間)だけだった。
この話は新約聖書ヨハネによる福音書(1:1-5)に起源がある。
『はじめに言(ことば)があった。言は神とともにあった。言は神であった。この言は、初めに神と共にあった。万物は言によって成った。言によらず成ったものは何一つなかった。言の内に成ったものは、命であった。この命は人の光であった。光は闇の中で輝いている。闇は光に勝たなかった。』
実は はてしない物語 には聖書のアナロジーがたくさん使われている。ここで全てを列挙することはできないが、この物語が聖書(特に新約聖書)と強いつながりがある事を示している。