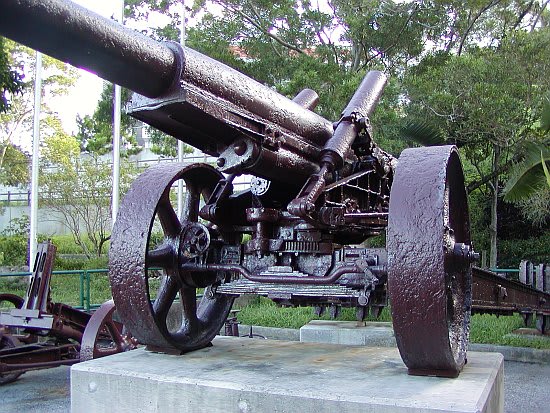南風原町津嘉山にある高津嘉山。標高87メートルの小高い山です。周囲にはサトウキビ畑や住宅地が広がっています。
以前にもブログでご紹介しましたが、いまから約230年前の琉球で、空を飛ぶことを夢見、この山から大空に飛び立った人物がいました。
今回はもう少し詳しくご紹介させていただきます。
琉球王府の花火職人、安里周當(1765-1823)がその人です。人々は周當を「飛び安里」と呼びました。

安里家は代々王府に仕える花火職人の家系で、彼は見事な仕掛け花火で王から褒賞を受けた優秀な技術者であったといいます。
しかしながら時の王府は、空を飛ぶとは人騒がせと、飛行の禁止令を出したそうです。周囲から変人と見られる中、飛び安里はそれでもめげず、飛行機の研究をしました。
安里の羽ばたき飛行機は弓の弾力性を利用して足で翼を上下させる仕組みで、竹、芭蕉布、鳥の羽などで作られていたと伝えられています。沖縄戦で物証が消えてしまった事もあり、詳細は分かっておらず、伝承によるところも多いようです。

高津嘉山のふもとから八合目あたり、頂上に続く階段の右側に飛び安里の碑があります。説明板には安里周當が世界で初めて飛行したこと、周當が琉球王府の花火師だったこと、津嘉山に移り住んだこと、等が記されています。
世界で初めて飛行機を飛ばしたのが飛び安里なのでしょうか?

飛び安里初飛翔のモニュメント。安里周當の頭文字Aをデザインしたということです。

飛び安里が飛び立った高津嘉山から、南風原の街並みを見下ろします。230年前はどんな風景だったのでしょうか。

南風原町役場です。ここの1Fロビーに飛び安里の作った飛行機の1/2スケール模型が展示されています。

「飛び安里」の羽ばたき式飛行機は 翼幅9メートル、全長4.5メートル、全高2メートル、骨組みは竹、翼には芭蕉布と鳥の羽根が貼られていたといいます。
翼の先端から少し内側の梁から、機体の底部にある横棒にロープが4本張られています。横棒を足で前後に動かすことにより羽ばたいたといいます。 こうしてみると、羽ばたき飛行機というより、現在のハングライダーに良く似ています。驚くべき事に、主翼面はゆるやかに湾曲し、揚力を生むような形になっています。
さて、この飛行機、本当に飛んだのでしょうか。
それが、ちゃんと飛んだのです。1999年3月27日、南風原町の町おこしグループ「すきです南風原・夢・未来委員会」が、この飛び安里の飛行機を復元し、町長も見守る中、玉城村前川の丘陵地で15mの飛行に成功したのです。
飛行成功を伝える琉球新報。

ライト兄弟が世界で初めて動力付き飛行機で飛んだのが1903年。
オットー・リリエンタールがハングライダーで飛んだのが1894年。
航空学の父ジョージ・ケイリーのグライダーによる有人飛行が1849年。
世界で初めて空を飛んだとされる岡山の表具師 浮田幸吉(鳥人幸吉)が飛んだのが1785年。
こうしてみると1780年に飛行機を飛ばした飛び安里は、本当に世界で初めて空を飛んだ人間という事になります。
しかしなんとも不思議なのは、人類初飛行という偉業をなしとげた人物が、歴史上に出て来ないということです。ライト兄弟がエンジン付き飛行機で飛んださらに123年前、大空の魅力にとりつかれ、飛行機で大空に舞い上がった人が、この沖縄にいたわけです。
ロマンですねえ。