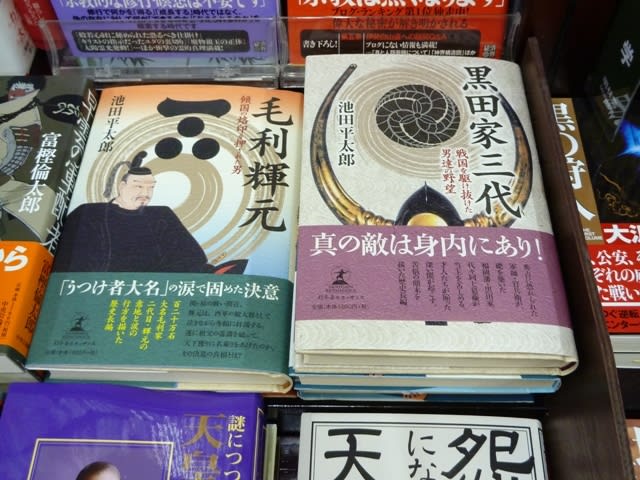渋沢栄一は明治2年(1869年)、29歳のとき、明治政府より出仕命令を受け、大蔵(現財務)官僚となります。
で、その翌々年、大蔵卿(現財務大臣)に就任したのが、薩摩出身の大久保利通。
西郷隆盛、木戸孝允と並んで維新の三傑に数えられる人物ですが、そもそも、三人中、薩摩から二人出ている時点で、大久保が明治草創期に果たした役割の大きさがわかるかと思います。
(本来のバランスを考えれば、薩摩から西郷、長州から木戸なら、もう一人はバランス上、土佐から出るべきで。)
つまり、渋沢が「日本経済」の父だとすれば、大久保は「日本政治」の父だと言えるでしょうか。

(↑大久保利通。見上げ気味に。忖度(笑)。)
ところで、渋沢が主人公の大河ドラマ「青天を衝け」での大久保役は、明らかに、栄一に一本取られてばかりの嫌な権力者・・・でしたが、そうなったのは、渋沢が大久保と反りが合わなかったという背景があるのでしょう。
(でも、大久保はNHKに影響力を持つと言われる麻生太郎・前財務大臣の高祖父。忖度は?(笑)。)
で、渋沢は後年、大久保について、「たいていの人は、いかに見識が抜きんでていても、おおよそ何を思っているのか窺い知ることができるが、大久保侯だけはとうてい測り知ることができなかった。これが何となく不気味で、侯を嫌な人だと感じさせた一因だった」と語っています。
この話は、逆に言えば、渋沢から見れば、ほとんどの上司が、彼の手のひらの上で遊んでいたということで、事実、明治後、彼の親分になる長州の井上馨などはとても心配性の人で、渋沢についたあだ名が「避雷針」だったと。
彼だけに井上の雷が落ちなかったからだとか。
つまり、井上が「あ!」となったときに、渋沢が「ああ、あれなら、そういうときのことを考えてこうしていますよ」と言えば、「おお!君は役に立つ男だなあ」となる。
だから、渋沢がどの上司からも重宝がられたのに対し、大久保だけが例外だったと。

(↑井上馨。だいぶ見上げ気味に(笑)。)
では、大久保の側から見ればどうだったかと言えば、これは、大久保方式と言うよりも薩摩方式なのでしょうが、薩摩人は「こいつは任せるに足る」と思えば、思い切って任せてしまうんですね。
(その好例が、日露戦争時に児玉源太郎総参謀長に一任した薩摩出身・大山巌司令官かと。)
したがって、伊藤博文や大隈重信、岩崎彌太郎のような自信家は、大久保の所へ話を持って行きたがったと。
稟議書を提出すれば、「これだけか」「これだけです」「わかった」で話が済む・・・。
つまり、上司の意図を見抜いて、先回りして用意しておく渋沢と、任せた以上は、いちいち忖度しなくて良いという大久保の、不幸なすれ違いだったと言えるでしょうか。
平太独白
で、その翌々年、大蔵卿(現財務大臣)に就任したのが、薩摩出身の大久保利通。
西郷隆盛、木戸孝允と並んで維新の三傑に数えられる人物ですが、そもそも、三人中、薩摩から二人出ている時点で、大久保が明治草創期に果たした役割の大きさがわかるかと思います。
(本来のバランスを考えれば、薩摩から西郷、長州から木戸なら、もう一人はバランス上、土佐から出るべきで。)
つまり、渋沢が「日本経済」の父だとすれば、大久保は「日本政治」の父だと言えるでしょうか。

(↑大久保利通。見上げ気味に。忖度(笑)。)
ところで、渋沢が主人公の大河ドラマ「青天を衝け」での大久保役は、明らかに、栄一に一本取られてばかりの嫌な権力者・・・でしたが、そうなったのは、渋沢が大久保と反りが合わなかったという背景があるのでしょう。
(でも、大久保はNHKに影響力を持つと言われる麻生太郎・前財務大臣の高祖父。忖度は?(笑)。)
で、渋沢は後年、大久保について、「たいていの人は、いかに見識が抜きんでていても、おおよそ何を思っているのか窺い知ることができるが、大久保侯だけはとうてい測り知ることができなかった。これが何となく不気味で、侯を嫌な人だと感じさせた一因だった」と語っています。
この話は、逆に言えば、渋沢から見れば、ほとんどの上司が、彼の手のひらの上で遊んでいたということで、事実、明治後、彼の親分になる長州の井上馨などはとても心配性の人で、渋沢についたあだ名が「避雷針」だったと。
彼だけに井上の雷が落ちなかったからだとか。
つまり、井上が「あ!」となったときに、渋沢が「ああ、あれなら、そういうときのことを考えてこうしていますよ」と言えば、「おお!君は役に立つ男だなあ」となる。
だから、渋沢がどの上司からも重宝がられたのに対し、大久保だけが例外だったと。

(↑井上馨。だいぶ見上げ気味に(笑)。)
では、大久保の側から見ればどうだったかと言えば、これは、大久保方式と言うよりも薩摩方式なのでしょうが、薩摩人は「こいつは任せるに足る」と思えば、思い切って任せてしまうんですね。
(その好例が、日露戦争時に児玉源太郎総参謀長に一任した薩摩出身・大山巌司令官かと。)
したがって、伊藤博文や大隈重信、岩崎彌太郎のような自信家は、大久保の所へ話を持って行きたがったと。
稟議書を提出すれば、「これだけか」「これだけです」「わかった」で話が済む・・・。
つまり、上司の意図を見抜いて、先回りして用意しておく渋沢と、任せた以上は、いちいち忖度しなくて良いという大久保の、不幸なすれ違いだったと言えるでしょうか。
平太独白