井筒俊彦 「意識と本質―東洋哲学の共時的構造化のために」
人間知性の正しい行使、厳密な思考の展開、事物の誤りない認識のために、「定義」の絶対的必要性をソクラテスが情熱をもって強調して以来、思惟対象あるいは認識対象の「本質」をきわめるということが西洋哲学伝統の主流の一部となって現在に至った。
西洋哲学だけではない。東洋でも(……)「本質」またはそれに類する概念が、言語の意味機能と人間意識の階層的構造と聯関して、著しく重要な役割を果たしていることに我々は気付く。
共時的東洋哲学の初歩的な構造序論
人間意識の様々に異なるあり方が「本質」なるものをどのようなものとして捉えるかを、ここでは特に「本質」の実在性・非実在性の問題を中心として考察してみたい。
われわれの日常意識の働きそのものが、実は大抵の場合、様々な事物事象の「本質」認知の上に成り立っているのだ。
意識をもし表層意識だけに限って考えるなら、意識とは事物事象の「本質」を、コトバの意味機能の指示に従いながら把捉するところに生起する内的状態であると言わなければなるまい。
初期サルトルの「存在」深淵を垣間見る嘔吐的体験
「それが根というものだということは、もはや私の意識には全然なかった。あらゆる語(ことば)は消え失せていた。そしてそれと同時に、事物の意義も、その使い方も、またそれらの事物の表面に人間が引いた弱い符牒(めじるし)) の線も。背を丸め気味に、頭を垂れ、たった独りで私は、まったく生のままのその黒々と節くれ立った、恐ろしい塊りに面と向かって坐っていた」(サルトル)
われわれの日常的世界とは、この第一次的、原初的「本質」認知の過程をいわば省略して―あるいは、それに気づかずに―初めから既に出来上がったものとして見られた存在者の形成する意味分節的存在地平である。
むろん、サルトル的「嘔吐」の場合、あの瞬間に意識の深層が垣間見られることは事実である。もともと言語脱落とか本質脱落とかいうこと自体が、深層意識的事態なのであって、それだから
こそ、「存在」が無分節のままに顕現するのだ。
しかしサルトルあるいは『嘔吐』の主人公は、深層意識の次元に身を据えてはいない。そこから、その立場から、存在世界の実相を視るということは彼にはできない。
それだけの準備ができていないのである。だから絶対無分節の「存在」の前に突然立たされて、彼は狼狽する。
仏教的表現を使っていうなら、世俗諦的意識の働きに慣れ、世俗諦的立場に身を置き、世俗諦的にしかものを見ることのできない人は、たまたま勝義諦的事態に触れることがあっても、そこにただ何か得体の知れない、ぶよぶよした、淫らな裸の塊りしか見ないのである。
勿論、表層意識にも遁げ道はある。他の一切の普通の対象のように、無分節の「存在」を概念化して、一つの対象として取り扱うことだ。……。だが無害にはなるかわり、完全に表層意識の中に取り込まれて死物とかしてしまう。つのり、「存在」の深層意識的真相は全く失われてしまうのだ。
それに反して東洋の精神的伝統では、少なくとも原則的には、人はこのような場合「嘔吐」に追い込まれはしない。絶対無分節の「存在」に直面しても狼狽しないだけの準備が始めから方法的、組織的になされているからだ。
いわゆる東洋の哲人とは、深層意識が拓かれて、そこに身を据えている人である。表層意識の次元に現われる事物、そこに生起する様々の事態を、深層意識の地平において、その見地から眺めることのできる人。表層、深層の両領域にわたる彼の意識の形而上的・形而下的地平には、絶対無分節の次元の「存在」と、千々に分節された「存在」とが同時にありのままに現われている。
常に無欲、以て其の妙を観
常に有欲、以て其の徼を観る
と老子が言うのはそれである。
東洋思想では、どこでもこのような意識ならぬ意識、メタ意識とでもいうべきものを体験的事実として認める。それが東洋哲学一般の根本的な一つの特徴である。
この境位にある意識に現われる「存在」には、どこにも「本質」的区分がない。まさしく言語脱落、「本質」脱落の世界。それを老子は「妙」という言語で表現する。
「本質」によって区劃された事物の充満する世界を、無「本質」の世界を見た人の目が静かに眺めている。
深層意識と表層意識とを二つながら同時に機能させることによって、「存在」の無と有とをいわば二重写しに観ることのできる、こうした東洋的哲人のあり方を僧肇は次のように描き出す。
「聖人空洞其懐、無識無知、然居動用之域、而止無為之境、処有名之内、而宅絶言之境、寂寥虚曠、莫可以形名得、若斯而己矣」(僧肇)
……しかも言語の「本質」喚起作用を超絶したところに住んでいるのであって、その境位はひっそりと静まりかえってものの影すらなく、形象とコトバで捉えられるようなものは一つだにない―およそ、そんな世界に聖人は住んでいるのである、という。(僧肇)
この種の東洋的思惟バターンにおいて、言語の「存在」分節作用が、いかに決定的な位置を占めているかということだ。
いわゆる「本質」は虚構であるという考えに導かざるを得ない。ここに大乗仏教特有の徹底的な本質否定が、本質虚妄説として出現してくる。『般若経』以来、ナーガールジュナ(龍樹)の中観を通って唯識へと展開する大乗仏教の存在論の主流の、これが中枢的テーマをなす空観である。
「一切の言説は仮名にして実なく、ただ妄念に随えるのみ」(『大乗起信論』)
「本質」を通さない存在分節
非「本質」喚起的な言語の使用
シャンカラの不二一元論
イブン・アラビー系の存在一性論
中国的思考の特徴をなす――と本居宣長の考えた――事物に対する抽象的・概念的アブローチに対照的な日本人独特のアブローチとして、宣長は徹底した即物的思考法を説く。
事物のこのような非「本質」的把握の唯一の道として、宣長は「あはれと情の感(うご)く」こと、すなわち深い情的感動の機能を絶対視する。
宣長の「物のあはれをしる」ことを「感動による事物の認識」(吉川幸次郎)とし、それを「存在の本質への接触」として規定した。
二つの違った意味の「本質」
●人が原初的存在解語邂逅において見出すままの事物の、濃密な個体的実在性の結晶点としての「本質」→ものの個的リアリティー→リルケの実在界
●人間の意識の分節機能によって普遍者化され一般者化され、さらには概念化された形でそれらの事物が提示する「本質」→ものの普遍的規定性→リルケの事実界
普遍的「本質」と個体的「本質」
イスラーム哲学の二つの本質
●マーヒーヤ
●フウィーヤ
ものにおけるこのマーヒーヤとフウィーヤとの結合、ないし同時成立を、きわめて独自な詩的、実存的体験の構造のうちに捉えた人物がある。俳人芭蕉がそれだ。
リルケの「意識のピラミッド」 表層→深層
古今的和歌の世界は、一切の事物、事象が、それぞれの普遍的「本質」において定着された世界だ。
王朝文化の雅の生活感情的基底であった「ながめ暮らす心」を、普遍的「本質」消去の手段として、一つの特殊な詩的意識のあり方にまで次第に昇華させた。
だが『新古今』的幽玄追及の雰囲気のさなかで完全に展開しきった形においては、「眺め」の意識とは、むしろ事物の「本質」的規定性を朦朧化して、そこに現成する茫漠たる情趣空間のなかに存在の深みを感得しようとする意識主体的態度ではなかったろうか。
この「眺め」の焦点をぼかした視線の先で、事物はその「本質」的限定を超える。そこに詩的情緒の纏綿があり、存在深層の開顕がある。
ただ、「内をつねに勤めて物に応」じる特別の修練を経た人、すなわち「風雅に情ある人」、の実体験として、ものを前にして突然「……の意識」が消える瞬間があるのだ。
そういう瞬間にだけ、ものの「本情」がちらっと光る。「物の見えたる光」という。(芭蕉)
リルケと芭蕉の本質追及の形
東西の「本質」論
●アリストテレス
●西洋中世哲学→スコラ哲学
●イスラーム
●インド
●中国
●日本の新古今・芭蕉
●リルケ・マラルメ
指示的と喚起的
イスラーム哲学者イブン・アラビーの「有無中道の実在」やスフラワルディの「光の天使」をはじめ。易の六十四卦、密教のマンダラ、ユダヤ教神秘主義カッバーラの「セフィロート」など
古代中国の儒学、特に孔子の正名論、古代インドのニヤーヤ・ヴァイシェーシカ派特有の存在範疇論など
「本質」探究においてマラルメはリルケと対蹠的立場に立つ。
●リルケは、存在者の存在論的具体性を個物の純粋な個体性のうちに認め、それをこそものの真のリアリティと見て、それを彼のいわゆる「意識のピラミッド」の底辺に探った。
●マラルメは、個物の個体性を無化し、無化つくしたところに、「冷酷にきらめく星の光」のように浮かび上がってくる普遍的「本質」の凄まじい形姿だった。
「仏教を知ることなしに、私は虚無(le Néant)に到達した」(マラルメ)
不断に動き変化して一瞬もとどまらぬ経験的事物のざわめき。この偶然性あるいは時間性の支配から存在者を救出することを、マラルメは詩人としての己れの使命とする。
……マラルメの言語は、もはや日常の人々が伝達に使用する言語ではなくて、事物を経験的存在の次元で殺害して永遠の現実性の次元に移し、そこでその物の「本質」を実在的に呼び出す「絶対言語」なのである。
中国宋代の儒者たちの理学
大道は整然と「理」の秩序を貫通して宇宙の窮極的根源に達し、その道に依って、人の意識は静かに一歩一歩深化されていく。意識の深層が完全に拓かれて、ついに意識と、全存在界そのものの唯一絶対の「本質」との窮極的自己同一が自覚されるに至るまで。
「静座」は心内のざわめきを鎮め、同時にそれと相関的に、心外すなわち存在界のざわめきを鎮める修行。
「格物窮理」は、そのようにして次第に鎮まり澄みきった心の全体を挙げて経験的世界の事物を見詰めつつ、それらの事物の「本質」(複数)を一つずつ把握していき、或る段階まで来たとき、この「本質」追及のいわば水平的な進路を、突然、垂直的方向に転じて、一挙に万物の絶対的「本質」(単数)の自覚に到達しようとする「本質」探究の道。
『中庸』巳発とは、意識のゼロ・ポイントから、なんらかの方向に発動した状態における心であり、同時にまた存在のゼロ・ポイントから様々な事物事象として展開した存在界のあり方を指す。
宋儒が、「静座」とは座禅の場合のように心を徒らに空無にしてしまう訓練ではない、むしろ経験的世界の真只中で、心の動そのものの中に心の静を求めようとするのだ、と
強調するのはこのゆえである。
宋学ならびに東洋哲学一般の特徴として先に一言した意識即存在という形而上的体験の事実によって、意識のゼロ・ポイント、すなわち「未発」の極点、が同時にまた全存在界のゼロ・ポイントでもあること、さらに、意識「未発」が意識「巳発」のげんせんであることによって、そのまま全存在界生起の源泉でもあるということである。
格物窮理(程伊川)
経験界にある事物、事象を観察し省察して、それらに内在する先験的「理」を窮め、極め尽くしてその果てに、ついに突如として万物の唯一絶対の「理」に翻入する道を、それは意味する。
儒と禅の相違点→「本質」があるという儒者
「万事、それぞれに必ず本質的に決められた限界というものがある」(『程氏易伝』)→孔子「正名論」から淵源する。
「こうして努力を続けること久しきに及べば、ある時点に至って突如、豁然として貫通するものだ。」(朱子)
●「豁然貫通」(朱子)
●「今日、一件に格り、明日また一件に格る。積習するところ既に多く、然して後、脱然として
自ら貫通するところあり」(程伊川『遺書』)
●「こいねがわくは心を遊ばせて浸熟し、一日、脱然として大寐の醒むるを得るがごとくならん
のみ」(張横渠『張氏全書』)
習熟の度が或るところまで来ると、突然、次元転換が起こる
周子の「一物一太極」
個々の「理」の形而上性を超えて、その彼方に、それらすべてを統合する至極の「理」、すなわち「太極」、の純粋無雑な形而上性を見る。それが「脱然貫通」である。
マラルメにとって、宋儒の「脱然貫通」に相当する体験は、発音された語の音波の振動と化して空しく消えていく経験的事物の消滅に続いて、その「忘却」の向うに、経験的世界の死を背景として、朦朧と立ち昇ってくるそれら事物の永遠の「本質」の、身の毛のよだつような冷酷な姿を見ることだった。
宋学の「理」体系とは、要するに、天地の間に存在するすべての事物はそれぞれ存在すべき根拠があって存在しているのだということ、つまり、事物の一つ一つに普遍的」本質」があるということである。
因果律の支配する世界(アリストテレス)とは、一切の事物がそれぞれ自分の「本質」をもち、自分の「本質」によって規定され、限界付けられ、固定されている世界でなければならない。まさしく宋学の説く「理」体系としての世界である。
だが、この美しい、そして科学的に有効であり得る世界像も、原子論者の呼び名で知られる原初的イスラーム意識の代表者たちの目には、イスラームという宗教の根基そのものにたいして致命的衝撃を加えるものとして映るのであった。なぜならそれは天地万有の創造主、主宰者である神の全能性の否定にほかならないからである。
因果律の世界→偶然性の否定
事物に「本質」があって、それで金縛りになっていたら、奇蹟など起こりようがない。
ムハンマド・アル・ガザーリーの哲学的相対主義→因果律の否定に基づく完全な偶然性の哲学である。
かくてアザリーは後世のイギリス経験論的哲学者ヒュームと同じ立場に赴く。
ガザーリーとアリストテレスの対立は、要するに世界を「本質」のない事物の偶然的集積と見るか、それとも「本質」によつて固定された事物の整然たるロゴス的体系と見るか、の違いに帰
「時の人、この一株の花を見ること夢のごとくに相似たり」南泉普願
サーンキヤの三徳
❶純質❷激質❸闇質
禅ではよく「心を擬する」という表現を使う。心を擬する、とは意識のエネルギーをある一定の方向に向かって緊張させ、その先端に一つの対象を認知すること。
「心を擬する」ことこそ見性、すなわち「至道」、への最大の障礙である。
『楞伽経』の意識三相説
❶真相❷業相❸転相
「本質」は「言語アラヤシキ」の意味的「種子」の現勢化した姿である……
禅の実在体験そのもの
トーマス・マートンの禅理解→静的
プロティノス的一者観照→エクスタティックな恍惚の追想的形象→静的
禅→ダイナミック
少なくとも第一義的、第一次的には、禅は全体的に、一つのダイナミックな認識論的・存在論
吉州青原惟信禅師
「山を見るに是れ山、……山を見るに是れ山にあらず、……山を見るに祇だ是れ山」
分節→無分節→分節
「唯だ妄念に依って差別あり。もし妄念を離るれば唯だ一真如なり」(法蔵『妄尽還源論』)
無門慧開禅師
「箇の熱鉄丸を呑了するが如くに」(『無門関』)
「本質」で固めてしまわない限り、分節はものを凝結させないのである。内部に凝結点を持たないものは四方八方に向かって己を開いて流動する。
「粘綴無き一道の清流」(黄檗)
風穴の禅機は「掣電の如く」一瞬、走ったのだ
長憶江南三月裏
鷓鴣啼処百花香
(無門禅師)
元来、「本質」とは存在の限界付け、すなわち存在の部分的、断片的、あるいは局所的、限定を意味する。存在界を一つの全体と見て、これを現実と呼ぶ場合、その全体的現実のこの部分、あの部分を他から切り離して、局所的にこれに意識の焦点を絞り、その特殊部分を一個の独立したものとして立てる。この部分的存在凝固の中心的拠点をなすのが、「本質」である。
或庵(わくあん)の「胡子無鬚」(達磨に鬚がない)
だが、突然、日常的意識の活躍のさ中で、ふと、現実的事物との結合を離れ、事実性から遊離したイマージュがどこからともなく現われてきて、意識一面を奇妙な色に染めてしまうことがある。何らかの刺激で意識が興奮し、あるいは逆に弛緩した時に、人は屡々それを経験する。
ただ、本来、深層意識で機能すべきこれらの、事物性から遊離したイマージュが、それを組織的に取り扱うことのできない常識的人間の日常意識に割り込んでくると、異常現象となり、往々にして病的現象になるのだ。職業的(あるいは天才的)シャーマンやタントラの達人のように、深層意識の超現実的次元を方法的に拓いた人たちだけが、この種のイマージュを正しく活用する術を心得ている。
(続く)
人間知性の正しい行使、厳密な思考の展開、事物の誤りない認識のために、「定義」の絶対的必要性をソクラテスが情熱をもって強調して以来、思惟対象あるいは認識対象の「本質」をきわめるということが西洋哲学伝統の主流の一部となって現在に至った。
西洋哲学だけではない。東洋でも(……)「本質」またはそれに類する概念が、言語の意味機能と人間意識の階層的構造と聯関して、著しく重要な役割を果たしていることに我々は気付く。
共時的東洋哲学の初歩的な構造序論
人間意識の様々に異なるあり方が「本質」なるものをどのようなものとして捉えるかを、ここでは特に「本質」の実在性・非実在性の問題を中心として考察してみたい。
われわれの日常意識の働きそのものが、実は大抵の場合、様々な事物事象の「本質」認知の上に成り立っているのだ。
意識をもし表層意識だけに限って考えるなら、意識とは事物事象の「本質」を、コトバの意味機能の指示に従いながら把捉するところに生起する内的状態であると言わなければなるまい。
初期サルトルの「存在」深淵を垣間見る嘔吐的体験
「それが根というものだということは、もはや私の意識には全然なかった。あらゆる語(ことば)は消え失せていた。そしてそれと同時に、事物の意義も、その使い方も、またそれらの事物の表面に人間が引いた弱い符牒(めじるし)) の線も。背を丸め気味に、頭を垂れ、たった独りで私は、まったく生のままのその黒々と節くれ立った、恐ろしい塊りに面と向かって坐っていた」(サルトル)
われわれの日常的世界とは、この第一次的、原初的「本質」認知の過程をいわば省略して―あるいは、それに気づかずに―初めから既に出来上がったものとして見られた存在者の形成する意味分節的存在地平である。
むろん、サルトル的「嘔吐」の場合、あの瞬間に意識の深層が垣間見られることは事実である。もともと言語脱落とか本質脱落とかいうこと自体が、深層意識的事態なのであって、それだから
こそ、「存在」が無分節のままに顕現するのだ。
しかしサルトルあるいは『嘔吐』の主人公は、深層意識の次元に身を据えてはいない。そこから、その立場から、存在世界の実相を視るということは彼にはできない。
それだけの準備ができていないのである。だから絶対無分節の「存在」の前に突然立たされて、彼は狼狽する。
仏教的表現を使っていうなら、世俗諦的意識の働きに慣れ、世俗諦的立場に身を置き、世俗諦的にしかものを見ることのできない人は、たまたま勝義諦的事態に触れることがあっても、そこにただ何か得体の知れない、ぶよぶよした、淫らな裸の塊りしか見ないのである。
勿論、表層意識にも遁げ道はある。他の一切の普通の対象のように、無分節の「存在」を概念化して、一つの対象として取り扱うことだ。……。だが無害にはなるかわり、完全に表層意識の中に取り込まれて死物とかしてしまう。つのり、「存在」の深層意識的真相は全く失われてしまうのだ。
それに反して東洋の精神的伝統では、少なくとも原則的には、人はこのような場合「嘔吐」に追い込まれはしない。絶対無分節の「存在」に直面しても狼狽しないだけの準備が始めから方法的、組織的になされているからだ。
いわゆる東洋の哲人とは、深層意識が拓かれて、そこに身を据えている人である。表層意識の次元に現われる事物、そこに生起する様々の事態を、深層意識の地平において、その見地から眺めることのできる人。表層、深層の両領域にわたる彼の意識の形而上的・形而下的地平には、絶対無分節の次元の「存在」と、千々に分節された「存在」とが同時にありのままに現われている。
常に無欲、以て其の妙を観
常に有欲、以て其の徼を観る
と老子が言うのはそれである。
東洋思想では、どこでもこのような意識ならぬ意識、メタ意識とでもいうべきものを体験的事実として認める。それが東洋哲学一般の根本的な一つの特徴である。
この境位にある意識に現われる「存在」には、どこにも「本質」的区分がない。まさしく言語脱落、「本質」脱落の世界。それを老子は「妙」という言語で表現する。
「本質」によって区劃された事物の充満する世界を、無「本質」の世界を見た人の目が静かに眺めている。
深層意識と表層意識とを二つながら同時に機能させることによって、「存在」の無と有とをいわば二重写しに観ることのできる、こうした東洋的哲人のあり方を僧肇は次のように描き出す。
「聖人空洞其懐、無識無知、然居動用之域、而止無為之境、処有名之内、而宅絶言之境、寂寥虚曠、莫可以形名得、若斯而己矣」(僧肇)
……しかも言語の「本質」喚起作用を超絶したところに住んでいるのであって、その境位はひっそりと静まりかえってものの影すらなく、形象とコトバで捉えられるようなものは一つだにない―およそ、そんな世界に聖人は住んでいるのである、という。(僧肇)
この種の東洋的思惟バターンにおいて、言語の「存在」分節作用が、いかに決定的な位置を占めているかということだ。
いわゆる「本質」は虚構であるという考えに導かざるを得ない。ここに大乗仏教特有の徹底的な本質否定が、本質虚妄説として出現してくる。『般若経』以来、ナーガールジュナ(龍樹)の中観を通って唯識へと展開する大乗仏教の存在論の主流の、これが中枢的テーマをなす空観である。
「一切の言説は仮名にして実なく、ただ妄念に随えるのみ」(『大乗起信論』)
「本質」を通さない存在分節
非「本質」喚起的な言語の使用
シャンカラの不二一元論
イブン・アラビー系の存在一性論
中国的思考の特徴をなす――と本居宣長の考えた――事物に対する抽象的・概念的アブローチに対照的な日本人独特のアブローチとして、宣長は徹底した即物的思考法を説く。
事物のこのような非「本質」的把握の唯一の道として、宣長は「あはれと情の感(うご)く」こと、すなわち深い情的感動の機能を絶対視する。
宣長の「物のあはれをしる」ことを「感動による事物の認識」(吉川幸次郎)とし、それを「存在の本質への接触」として規定した。
二つの違った意味の「本質」
●人が原初的存在解語邂逅において見出すままの事物の、濃密な個体的実在性の結晶点としての「本質」→ものの個的リアリティー→リルケの実在界
●人間の意識の分節機能によって普遍者化され一般者化され、さらには概念化された形でそれらの事物が提示する「本質」→ものの普遍的規定性→リルケの事実界
普遍的「本質」と個体的「本質」
イスラーム哲学の二つの本質
●マーヒーヤ
●フウィーヤ
ものにおけるこのマーヒーヤとフウィーヤとの結合、ないし同時成立を、きわめて独自な詩的、実存的体験の構造のうちに捉えた人物がある。俳人芭蕉がそれだ。
リルケの「意識のピラミッド」 表層→深層
古今的和歌の世界は、一切の事物、事象が、それぞれの普遍的「本質」において定着された世界だ。
王朝文化の雅の生活感情的基底であった「ながめ暮らす心」を、普遍的「本質」消去の手段として、一つの特殊な詩的意識のあり方にまで次第に昇華させた。
だが『新古今』的幽玄追及の雰囲気のさなかで完全に展開しきった形においては、「眺め」の意識とは、むしろ事物の「本質」的規定性を朦朧化して、そこに現成する茫漠たる情趣空間のなかに存在の深みを感得しようとする意識主体的態度ではなかったろうか。
この「眺め」の焦点をぼかした視線の先で、事物はその「本質」的限定を超える。そこに詩的情緒の纏綿があり、存在深層の開顕がある。
ただ、「内をつねに勤めて物に応」じる特別の修練を経た人、すなわち「風雅に情ある人」、の実体験として、ものを前にして突然「……の意識」が消える瞬間があるのだ。
そういう瞬間にだけ、ものの「本情」がちらっと光る。「物の見えたる光」という。(芭蕉)
リルケと芭蕉の本質追及の形
東西の「本質」論
●アリストテレス
●西洋中世哲学→スコラ哲学
●イスラーム
●インド
●中国
●日本の新古今・芭蕉
●リルケ・マラルメ
指示的と喚起的
イスラーム哲学者イブン・アラビーの「有無中道の実在」やスフラワルディの「光の天使」をはじめ。易の六十四卦、密教のマンダラ、ユダヤ教神秘主義カッバーラの「セフィロート」など
古代中国の儒学、特に孔子の正名論、古代インドのニヤーヤ・ヴァイシェーシカ派特有の存在範疇論など
「本質」探究においてマラルメはリルケと対蹠的立場に立つ。
●リルケは、存在者の存在論的具体性を個物の純粋な個体性のうちに認め、それをこそものの真のリアリティと見て、それを彼のいわゆる「意識のピラミッド」の底辺に探った。
●マラルメは、個物の個体性を無化し、無化つくしたところに、「冷酷にきらめく星の光」のように浮かび上がってくる普遍的「本質」の凄まじい形姿だった。
「仏教を知ることなしに、私は虚無(le Néant)に到達した」(マラルメ)
不断に動き変化して一瞬もとどまらぬ経験的事物のざわめき。この偶然性あるいは時間性の支配から存在者を救出することを、マラルメは詩人としての己れの使命とする。
……マラルメの言語は、もはや日常の人々が伝達に使用する言語ではなくて、事物を経験的存在の次元で殺害して永遠の現実性の次元に移し、そこでその物の「本質」を実在的に呼び出す「絶対言語」なのである。
中国宋代の儒者たちの理学
大道は整然と「理」の秩序を貫通して宇宙の窮極的根源に達し、その道に依って、人の意識は静かに一歩一歩深化されていく。意識の深層が完全に拓かれて、ついに意識と、全存在界そのものの唯一絶対の「本質」との窮極的自己同一が自覚されるに至るまで。
「静座」は心内のざわめきを鎮め、同時にそれと相関的に、心外すなわち存在界のざわめきを鎮める修行。
「格物窮理」は、そのようにして次第に鎮まり澄みきった心の全体を挙げて経験的世界の事物を見詰めつつ、それらの事物の「本質」(複数)を一つずつ把握していき、或る段階まで来たとき、この「本質」追及のいわば水平的な進路を、突然、垂直的方向に転じて、一挙に万物の絶対的「本質」(単数)の自覚に到達しようとする「本質」探究の道。
『中庸』巳発とは、意識のゼロ・ポイントから、なんらかの方向に発動した状態における心であり、同時にまた存在のゼロ・ポイントから様々な事物事象として展開した存在界のあり方を指す。
宋儒が、「静座」とは座禅の場合のように心を徒らに空無にしてしまう訓練ではない、むしろ経験的世界の真只中で、心の動そのものの中に心の静を求めようとするのだ、と
強調するのはこのゆえである。
宋学ならびに東洋哲学一般の特徴として先に一言した意識即存在という形而上的体験の事実によって、意識のゼロ・ポイント、すなわち「未発」の極点、が同時にまた全存在界のゼロ・ポイントでもあること、さらに、意識「未発」が意識「巳発」のげんせんであることによって、そのまま全存在界生起の源泉でもあるということである。
格物窮理(程伊川)
経験界にある事物、事象を観察し省察して、それらに内在する先験的「理」を窮め、極め尽くしてその果てに、ついに突如として万物の唯一絶対の「理」に翻入する道を、それは意味する。
儒と禅の相違点→「本質」があるという儒者
「万事、それぞれに必ず本質的に決められた限界というものがある」(『程氏易伝』)→孔子「正名論」から淵源する。
「こうして努力を続けること久しきに及べば、ある時点に至って突如、豁然として貫通するものだ。」(朱子)
●「豁然貫通」(朱子)
●「今日、一件に格り、明日また一件に格る。積習するところ既に多く、然して後、脱然として
自ら貫通するところあり」(程伊川『遺書』)
●「こいねがわくは心を遊ばせて浸熟し、一日、脱然として大寐の醒むるを得るがごとくならん
のみ」(張横渠『張氏全書』)
習熟の度が或るところまで来ると、突然、次元転換が起こる
周子の「一物一太極」
個々の「理」の形而上性を超えて、その彼方に、それらすべてを統合する至極の「理」、すなわち「太極」、の純粋無雑な形而上性を見る。それが「脱然貫通」である。
マラルメにとって、宋儒の「脱然貫通」に相当する体験は、発音された語の音波の振動と化して空しく消えていく経験的事物の消滅に続いて、その「忘却」の向うに、経験的世界の死を背景として、朦朧と立ち昇ってくるそれら事物の永遠の「本質」の、身の毛のよだつような冷酷な姿を見ることだった。
宋学の「理」体系とは、要するに、天地の間に存在するすべての事物はそれぞれ存在すべき根拠があって存在しているのだということ、つまり、事物の一つ一つに普遍的」本質」があるということである。
因果律の支配する世界(アリストテレス)とは、一切の事物がそれぞれ自分の「本質」をもち、自分の「本質」によって規定され、限界付けられ、固定されている世界でなければならない。まさしく宋学の説く「理」体系としての世界である。
だが、この美しい、そして科学的に有効であり得る世界像も、原子論者の呼び名で知られる原初的イスラーム意識の代表者たちの目には、イスラームという宗教の根基そのものにたいして致命的衝撃を加えるものとして映るのであった。なぜならそれは天地万有の創造主、主宰者である神の全能性の否定にほかならないからである。
因果律の世界→偶然性の否定
事物に「本質」があって、それで金縛りになっていたら、奇蹟など起こりようがない。
ムハンマド・アル・ガザーリーの哲学的相対主義→因果律の否定に基づく完全な偶然性の哲学である。
かくてアザリーは後世のイギリス経験論的哲学者ヒュームと同じ立場に赴く。
ガザーリーとアリストテレスの対立は、要するに世界を「本質」のない事物の偶然的集積と見るか、それとも「本質」によつて固定された事物の整然たるロゴス的体系と見るか、の違いに帰
「時の人、この一株の花を見ること夢のごとくに相似たり」南泉普願
サーンキヤの三徳
❶純質❷激質❸闇質
禅ではよく「心を擬する」という表現を使う。心を擬する、とは意識のエネルギーをある一定の方向に向かって緊張させ、その先端に一つの対象を認知すること。
「心を擬する」ことこそ見性、すなわち「至道」、への最大の障礙である。
『楞伽経』の意識三相説
❶真相❷業相❸転相
「本質」は「言語アラヤシキ」の意味的「種子」の現勢化した姿である……
禅の実在体験そのもの
トーマス・マートンの禅理解→静的
プロティノス的一者観照→エクスタティックな恍惚の追想的形象→静的
禅→ダイナミック
少なくとも第一義的、第一次的には、禅は全体的に、一つのダイナミックな認識論的・存在論
吉州青原惟信禅師
「山を見るに是れ山、……山を見るに是れ山にあらず、……山を見るに祇だ是れ山」
分節→無分節→分節
「唯だ妄念に依って差別あり。もし妄念を離るれば唯だ一真如なり」(法蔵『妄尽還源論』)
無門慧開禅師
「箇の熱鉄丸を呑了するが如くに」(『無門関』)
「本質」で固めてしまわない限り、分節はものを凝結させないのである。内部に凝結点を持たないものは四方八方に向かって己を開いて流動する。
「粘綴無き一道の清流」(黄檗)
風穴の禅機は「掣電の如く」一瞬、走ったのだ
長憶江南三月裏
鷓鴣啼処百花香
(無門禅師)
元来、「本質」とは存在の限界付け、すなわち存在の部分的、断片的、あるいは局所的、限定を意味する。存在界を一つの全体と見て、これを現実と呼ぶ場合、その全体的現実のこの部分、あの部分を他から切り離して、局所的にこれに意識の焦点を絞り、その特殊部分を一個の独立したものとして立てる。この部分的存在凝固の中心的拠点をなすのが、「本質」である。
或庵(わくあん)の「胡子無鬚」(達磨に鬚がない)
だが、突然、日常的意識の活躍のさ中で、ふと、現実的事物との結合を離れ、事実性から遊離したイマージュがどこからともなく現われてきて、意識一面を奇妙な色に染めてしまうことがある。何らかの刺激で意識が興奮し、あるいは逆に弛緩した時に、人は屡々それを経験する。
ただ、本来、深層意識で機能すべきこれらの、事物性から遊離したイマージュが、それを組織的に取り扱うことのできない常識的人間の日常意識に割り込んでくると、異常現象となり、往々にして病的現象になるのだ。職業的(あるいは天才的)シャーマンやタントラの達人のように、深層意識の超現実的次元を方法的に拓いた人たちだけが、この種のイマージュを正しく活用する術を心得ている。
(続く)













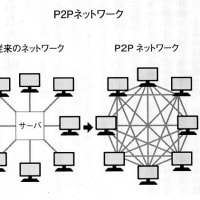
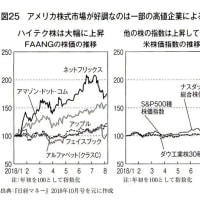

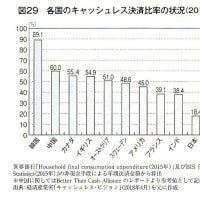
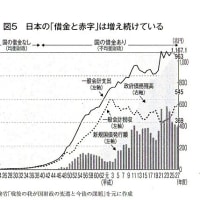

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます