Ⅰ 古代劇場をめぐる風景と現代の<状況>について
科学の「没価値性」と人間へのはね返り
以下におきまして私は、哲学にとって避けることのできないそのような課題に対する、私なりのささやかな参加を行なうつもりになりまして、いま哲学が指向すべき世界観はどのようなものかということの、見取り図だけでもスケッチすることに努めたいと思います。
Ⅱ 近代自然科学と、二元論的下絵の定着
近代自然科学の根本想定
世界の基礎には物質(物)があって、その物質――あるいは物質の構成要素――が瞬間瞬間にさまざまの配置を形づくりながら全空間を通じて拡がっているということ、このことを、世界・自然における窮極的な事実とみなして前提するところの世界観であります。
そういう物質はそれ自体としては、センスレス、感覚がなく、ヴァリューレス、価値がなく、パーバスレス、目的をもたない。世界・自然の出来事は、そのような性格の物質あるいはその構成要素の、場所的な運動として記述されるべきであるという立場であります。
ホワイトヘッド=物質を基本とした機械論=シンプル・ロケィションの観念=実体と属性のカテゴリー
シンプル・ロケィション=単純な局在化が可能であるという考え
世界・自然のなかに窮極的に実在するものを求めるとすると、それは、それらさまざまの知覚的な性質を支えまたは担う何ものか(基体)でなければならないという考え方です。そういうさまざまの性質の担い手、支え手となる何ものか(実体・基体)が実在的なものとしてあって、それの緒属性をわれわれは知覚するのであり、またそれを主語としてさまざまの性質を述語づけるのだ、ということです。
「生物というシステムはその特性からいっても、その機能からいっても、いっさいの弁証法的記述に抵抗するものである。それは根底からデカルト的であってヘーゲル的でない。生物の細胞はまさしく機械なのである」(ジャック・モノー『偶然と必然』)
二元論的下絵
科学の偉大な成功により、「物」の世界と「心」の世界が、相互に独立なものとして、世界観の下絵として描かれることになります。
この新たな用語法によって、「没価値的」であることと「客観的」であることが同義となり、また、認識の主体とか自由意志とか価値とかいったものを優先的に立てようとする試みは、すべて「主観的」な立場であり「主観主義」であると呼ばなければならないことになりました。
別の言葉でいうと、古典力学を範とする自然科学が想定してきた上述のような「客観的実在の世界」の観念が、抜きがたく人々の心中に植えつけられているということであります。
Ⅲ いくつかの基本的問題点
1 事実と価値
2 物質と生命
3 「物」と知覚
4 部分と全体
まさにそのような相互排除性を原理・出発点として、二つの世界が設定されているからです。
価値や道徳や倫理の問題は厳密な知識苦となりえないという、価値・倫理の「非知識性」の主張が行われることになり……
このようにして、物質の世界と生命の世界との乖離・分裂という問題に対する分子生物学の挑戦は、逆にかえって、問題の設定のされ方そのものに由来する原理的な困難を、いっそうよく明るみに出す結果になったと申せましょう。
科学のやり方を局部照明にたとえた(ヴァイゼッカー)
科学の知見がそういう「切り取り」主義と局部照明によって得られた成果であるとすれば、個々の科学的な知見を全部あわせてみても、そのまま世界全体についての真実の知見になるというわけのものではないし、全体としての世界像に関わる哲学が、個別科学の総和に解消されるということもありえないわけであります。
そもそもそういう見方(科学的見方)が世界の記述・描写として誤っている、つまり世界のあり方のありのままの正確な記述・描写になっていないからだと考えなければなりません。
Ⅳ 歴史的=原理的遡源
実態と属性のカテゴリー分けでありますが、これが人間の思想の歴史のうちに初めて明確な形を与えられて登場したのは、アリストテレスの哲学においてでありました。この実体と属性との原理的な区別は、日常語の構文における主語(S)と述語(P)の区別と密接に対応し結びついています。
「SはPである」
「Pで表される属性的なものが、Sで表される実体に依存して存在する」
このうち、「SはPである」という命題の通常の場合、実体はつねに主語(S)の位置を占め、けっして他のものの述語(P)となることはないし、他方、属性はつねに述語(P)として語られ、けっして主語(S)の位置に来ることはありません。
属性のほうはそれ自身で独立に存在することができず、実体に依存してはじめて存在しうるのだという、存在のうえでの依存関係の事実と、正確に対応することになります。
「主語・述語=実体・属性」
実体と属性との区別それ自体を推し進め徹底化すると、すでに見られたように、属性としてのさまざまの性質と、その担い手(基体)である実体との剥離となり、実体(基体)そのものはいっさいの性質(価値的な性質も含めて)から独立した、いかなる術語的規定にも染まらない無垢でニュートラルな何ものかである。
Ⅴ 哲学的世界観の方向性と諸条件
しかし、そこに仕組まれた概念の枠組に無条件にのめり込むことに対して、抵抗し拒否するということであります。
すなわち、主語=実体(基体)に言及することなく、もっぱら端的に、それぞれの知覚像ないし知覚的性状が現われることだけを述べるような記述方式であります。そのような記述方式として考えられるのは、「場の描写」的な記述方式であります。
もっと切実な経験の場面では、われわれはただ、「美しい花!」とだけ言うでしょう。それは端的に、「美しい花」というひとつの知覚像がそこに現われて、我々に訴えかけてきているという事態であり、けっして、主語となる「この花」という物(基体)がまずあって、それに「美しい」という述語的性質が所属しているというような事態ではありません。
……「実体(基体)・属性」という解釈と直結しがちな「主語・述語」の語法に代えて、右のような意味での場の描写的な記述を、最も基本的な記述方式として据えたいと思います。
Ⅵ プラトンの哲学について
プシューケーこそが万有のいちばん元のものであるとみなすプラトンの立場は、後にも見られるように、一度確立されたこの物体・物質(ソーマ)の観念を徹底的に再吟味して、これをふたたび「動きつつある成り行きの過程」(『ソピステス』)へと解消し還元しつくす作業によって裏打ちされているということです。
Ⅶ アリストテレスの哲学と〈エネルゲイア>の思想
個別科学におけるこの「部分切り取り」主義についての彼の明確な発言(『形而上学』)
それは、彼がエネルゲイア(現実性)の概念に託している思想であります。
人間がたんに運動する物体ではないとすれば、人間が人間として行うほんとうの行為・行動とは、これとは根本的に異なった――つまり、本質的に効率や能率の観念が入り込む余地のまったくないような――あり方のものでなければならないはずだと、彼は考えます。そしてそのようなあり方を、〈エネルゲイア〉(活動、現実活動)と呼んだのでした。
〈キーネーシス〉が文字通り物体の運動へと原理上還元されるのに対して、〈エネルゲイア〉とは魂・心・精神(あるいは、生命)の活動にほかならないことを告げています。
〈エネルゲイア〉とはプシュケーの活動であり、〈キーネーシス〉とはソーマの運動であること。
その世界観・自然観とは、まさしく「物があって、その物が、時間・空間の中で、動く」ということを世界・自然における最も基本的な事態と見て、世界の〈客観的〉で真実のあり方はもっぱら物とその構成要素の時間・空間内の運動を精密に記述することによってとらえられるとみなす立場に立つものだったからです。
〈近代化〉とも呼ばれる全体としてのこうした動き(キーネーシス)の一象徴であるところの、あらゆる領域における器具・機械の進歩と高性能化ということは、その単純化――もっぱら一つの機能だけを強力に果たすこと――によって特徴づけられます。これは、世界観の局面において先に見られたような、全体の中の一部分だけへの認識の注意集中ということと対応するものとはいえないでしょうか。
そこに仕組まれている「運動の論理」に無条件にのめりこむこと――そして効率主義・能率主義を決定的な支配原理とすること――は、結局は、われわれ自身の生と行為のあり方を根源的に物の運動へと変質させることにほかなりませんでした。
常識がもっている概念的枠組
Ⅷ むすび
「運動の論理」を基本とする世界観=科学的世界観
客観的とは、……、「価値的な観点からの判断を一切排除した」という意味です。
われわれの哲学的経験の自律性を新たに獲得するということ
*平成三〇年六月二日抜粋終了。
*科学の知見が局所照明であるがゆえに、謙虚さが最も重要な資質となるのだが、なかなか人間はそおしえないから問題が発生するのだろう。
*この本は一九八〇年に出版されている。抜粋者の履歴(左記の一行)に照らせば、当時出逢っていたら面白い化学反応があったかもしれない。
昭和五十六年 (1981)小説『述語は永遠に・・・・・・』400字詰め原稿用紙六三六枚脱稿
*「ひかり」に飛び乗って、男は術語の呪縛にうめきつつ連想過多症におちいるというのが筋立てであった。(『述語は永遠に・・・・・・』)
*今はただ再経験を静かに繰り返すよすがとする。













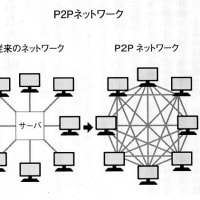
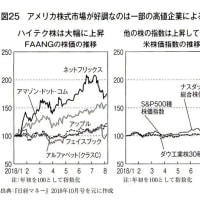

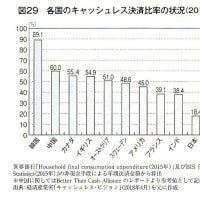
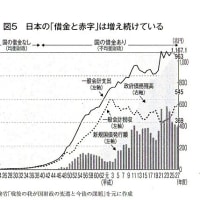

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます