こうした事例では、ふつう、前世らしきものの記憶の形態に二通りある。まず第一は、〈イメージ記憶〉である。……。こうした記憶は、もう一方の、〈行動的記憶〉と呼んでいるものとは異なっている。
前世から来世へ持ち越す可能性のある(イメージ記憶および行動的記憶以外の)記憶としては、識閾下認知的記憶もある。〈行動的記憶〉という言葉は、習慣をはじめ、一個の人間に見られる多少なりとも自動的な行動を指しているが、それに対して〈識閾下認知的記憶〉とは、実際に保持していながら、身に付けた覚えのない知識のことである。
大多数は、五歳から八歳までの間に前世の話をしなくなるが、もっと早い時期にやめる子どももあれば、もつと後まで続ける者もある。
前世の記憶を持つ子どもがはじめてその話をするのは、二歳から五歳までの間がほとんどである。
前世の記憶を喪失するのは、言葉が急速に発達し、それに伴って視覚的イメージが失われる時期と一致する。
死後の思念には、私たちになじみ深い覚醒時の世界よりも、はるかに多くのイメージが入り込んでいるかもしれない。言葉があまり介在しない(言葉による制約も少ない)だろうからである。その点、死後の思念は、幼児や夢を見ている人間の思考形態と似ているかもしれない。
「死者にとってふつうの伝達手段は、生者にとって〈超常的〉なのである」 ハンス・ドリーシュ
肉体のない世界にも法則があるかもしれないが、この世のものとは違うであろう。時間の流れも異なるであろうし、空間も異質かもしれない。誰かのことを思うだけで、あたかも〝今〟が
〝ここ〟と同義であるかのように、次の瞬間にはその人の目の前にいることになるのかもしれないのである。
もしこの世が(キーツの言うように)「魂を造る世」であるなら、私たちは自分自身の魂を作っているのである。
前世を記憶しているという子どもたちの研究を通じて私は、実際に生まれ変わった子供が一部にいることを確信したけれども、それと同時に、生まれ変わりという現象についてはまだほとんどわかっていないということも思い知らされたのである。
*平成二十九年九月十六日抜粋終了。










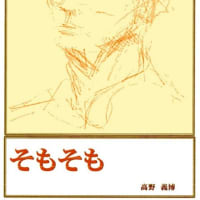

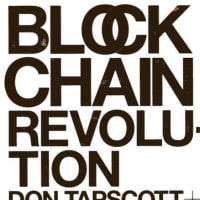
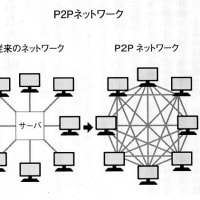
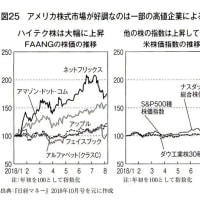
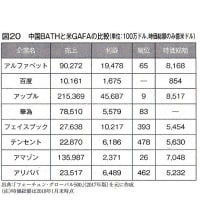
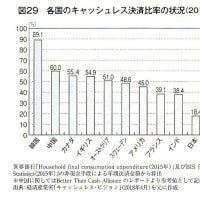
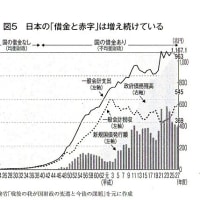
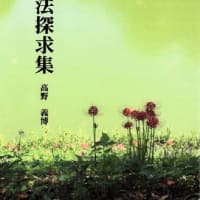
分厚いだけで、内容空疎です。
こめんとありがとう。