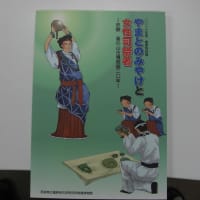本日、橿原考古学研究所の講堂で講座を二つ受講してきました。
1つは「2.3世紀の金属器生産」、もう1つは「考古資料から見た海外交渉~楽浪土城からホケノ山古墳まで~」というもの。
その会場に、なんと幻の「親魏倭王」印が持ち込まれていたのです。
その印は言うまでもなく、中国三国時代の魏から邪馬台国の卑弥呼に贈られたものですから、これが出てくれば邪馬台国論争が大きく前進?
ということなんでしょうが、もちろんこれは偽物です。
なにやら、江戸時代の藤貞幹(とうていかん)の「好古日録」という書物に載っているものから復元したようです。その「好古日録」に載っていた親魏倭王の印は出自がかなり怪しいそうです。
「2.3世紀の金属器生産」の講義は、近畿地方の弥生時代は、唐古・鍵遺跡や大阪の東奈良遺跡などの大規模集落で青銅器が生産され始めましたが、弥生時代後期になるとやがて小規模の集落で小規模に作られていたらしいです。
鉄器の生産があることがわかるのは纒向遺跡になってからということだったかな? ちょっとあやふやです。
いずれにしても、鉄器生産技術は未熟なものだったようです。
「考古資料から見た海外交渉~楽浪土城からホケノ山古墳まで~」の講義は、弥生時代の遺跡から朝鮮半島の土器が出る場所は限定的で、近畿地方では、楽浪系の土器は全く出ていないとのこと。他方伊都国や奴国ではたくさん出ているとのこと。
いずれにしても、土器の出土状況からすると弥生時代には、地域の海洋民のした交易と国同士の外交とが不分明な時代だったらしい。
近畿で、奈良盆地に半島南部の形式の土器が多数出土するようになったのは5世紀以降とのこと。
纒向遺跡にあるホケノ山古墳から鏡が二面ほど出ているけど、二つの内1つは早くとも3世紀の中頃以降のものだから、ホケノ山古墳の築造もそれ以降ですとのこと。
以上。
今回の二つの講座の大きな目的は、「あんまりマスコミに踊らされてはいけません。」という事だったように思います。
ホケノ山古墳といえば、卑弥呼の墓ではないかといわれている箸墓古墳に先立つ古墳ですから、卑弥呼が死んだのが3世紀中頃なので、箸墓を3世紀中頃に持ってくるためにはホケノ山古墳を3世紀前半に持ってこないといけないわけです。
それを意識して、ホケノ山古墳の築造時期を3世紀初頭ないし前半とする説やそれを裏付ける発見がマスコミで大いに取り上げられますよね。
それに警告を発しているみたいです。「もっと落ち着いて。そんなに簡単に邪馬台国がどこにあったかわかりませんよ。」ということでしょう。
邪馬台国がどこにあったか、私はどこでもよいと思っているのですが、どこにあったかを決めるのは文献と考古学資料であってマスコミじゃないですからね~。
マスコミに踊らされてはいけませんというのはそのとおりなんでしょうね。 でも、すごい発見が新聞に載ると心が躍ってしまいますけどね(笑)
わたしも俗物ですから。
1つは「2.3世紀の金属器生産」、もう1つは「考古資料から見た海外交渉~楽浪土城からホケノ山古墳まで~」というもの。
その会場に、なんと幻の「親魏倭王」印が持ち込まれていたのです。
その印は言うまでもなく、中国三国時代の魏から邪馬台国の卑弥呼に贈られたものですから、これが出てくれば邪馬台国論争が大きく前進?
ということなんでしょうが、もちろんこれは偽物です。
なにやら、江戸時代の藤貞幹(とうていかん)の「好古日録」という書物に載っているものから復元したようです。その「好古日録」に載っていた親魏倭王の印は出自がかなり怪しいそうです。
「2.3世紀の金属器生産」の講義は、近畿地方の弥生時代は、唐古・鍵遺跡や大阪の東奈良遺跡などの大規模集落で青銅器が生産され始めましたが、弥生時代後期になるとやがて小規模の集落で小規模に作られていたらしいです。
鉄器の生産があることがわかるのは纒向遺跡になってからということだったかな? ちょっとあやふやです。
いずれにしても、鉄器生産技術は未熟なものだったようです。
「考古資料から見た海外交渉~楽浪土城からホケノ山古墳まで~」の講義は、弥生時代の遺跡から朝鮮半島の土器が出る場所は限定的で、近畿地方では、楽浪系の土器は全く出ていないとのこと。他方伊都国や奴国ではたくさん出ているとのこと。
いずれにしても、土器の出土状況からすると弥生時代には、地域の海洋民のした交易と国同士の外交とが不分明な時代だったらしい。
近畿で、奈良盆地に半島南部の形式の土器が多数出土するようになったのは5世紀以降とのこと。
纒向遺跡にあるホケノ山古墳から鏡が二面ほど出ているけど、二つの内1つは早くとも3世紀の中頃以降のものだから、ホケノ山古墳の築造もそれ以降ですとのこと。
以上。
今回の二つの講座の大きな目的は、「あんまりマスコミに踊らされてはいけません。」という事だったように思います。
ホケノ山古墳といえば、卑弥呼の墓ではないかといわれている箸墓古墳に先立つ古墳ですから、卑弥呼が死んだのが3世紀中頃なので、箸墓を3世紀中頃に持ってくるためにはホケノ山古墳を3世紀前半に持ってこないといけないわけです。
それを意識して、ホケノ山古墳の築造時期を3世紀初頭ないし前半とする説やそれを裏付ける発見がマスコミで大いに取り上げられますよね。
それに警告を発しているみたいです。「もっと落ち着いて。そんなに簡単に邪馬台国がどこにあったかわかりませんよ。」ということでしょう。
邪馬台国がどこにあったか、私はどこでもよいと思っているのですが、どこにあったかを決めるのは文献と考古学資料であってマスコミじゃないですからね~。
マスコミに踊らされてはいけませんというのはそのとおりなんでしょうね。 でも、すごい発見が新聞に載ると心が躍ってしまいますけどね(笑)
わたしも俗物ですから。