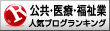ニッセイ基礎研究所のレポートに「ケアマネジメントにおける業務プロセスの測定と評価」というレポートが掲載されていた。副題に「介護報酬体系の理論的構築に向けて」とある。レポート者は山村学園短期大学専任講師(発表当時)村田 久氏とニッセイ基礎研究所の社会研究部門副主任研究員(発表当時)である阿部崇氏の共著となっている。
レポートは業務プロセスを構造的に把握して適正な報酬体系を理論的に構築することを目的に行われた。
「身体機能面に特化した認定調査から導かれる要介護度では、多様な在宅サービスを組み合わせ利用者の生活を総合的に支援することをサービス内容とするケアマネジメントの業務負荷等を適切に評価しきることは困難」と、つまり介護度と居宅介護支援にかかる業務量は比例せず、介護度によって介護支援費を設定している介護報酬は妥当でないという指摘である。レポートでは統計的学術的に論じているがこれは私が経験的実証的に昨年6月に「達人ケアマネ」誌上で述べた介護度と手間数とは関係ないという論旨と合致する。
この認識に立ったうえでレポートは「質の高いケアマネジメントは、独立性を確保する高水準の単価でもなく、業務負荷を軽減するための担当利用者基準に縮減でもなく、ケアマネジメントの業務プロセスの構造的把握に基づく適正な『介護報酬体系』に支えられた“ケアマネジャーの納得感”によってもたらされる」と結論している。つまりケアマネジャーが行った自分の業務に対して納得できる報酬を得たときに質の高いケアマネジメントが行われると言っている。
この趣旨は私がケアプラン作成の自己負担に対して結果評価型報酬体系の導入を提唱した本年2月の介護保険情報で発表した論文と同じ結論に結び付く。ただ阿部氏とは自己負担を巡る視点は異なる。
このようなレポートが2006年4月の改定を前に出されていたことに驚く。私の無知を恥じるばかりである。
レポートは業務プロセスを構造的に把握して適正な報酬体系を理論的に構築することを目的に行われた。
「身体機能面に特化した認定調査から導かれる要介護度では、多様な在宅サービスを組み合わせ利用者の生活を総合的に支援することをサービス内容とするケアマネジメントの業務負荷等を適切に評価しきることは困難」と、つまり介護度と居宅介護支援にかかる業務量は比例せず、介護度によって介護支援費を設定している介護報酬は妥当でないという指摘である。レポートでは統計的学術的に論じているがこれは私が経験的実証的に昨年6月に「達人ケアマネ」誌上で述べた介護度と手間数とは関係ないという論旨と合致する。
この認識に立ったうえでレポートは「質の高いケアマネジメントは、独立性を確保する高水準の単価でもなく、業務負荷を軽減するための担当利用者基準に縮減でもなく、ケアマネジメントの業務プロセスの構造的把握に基づく適正な『介護報酬体系』に支えられた“ケアマネジャーの納得感”によってもたらされる」と結論している。つまりケアマネジャーが行った自分の業務に対して納得できる報酬を得たときに質の高いケアマネジメントが行われると言っている。
この趣旨は私がケアプラン作成の自己負担に対して結果評価型報酬体系の導入を提唱した本年2月の介護保険情報で発表した論文と同じ結論に結び付く。ただ阿部氏とは自己負担を巡る視点は異なる。
このようなレポートが2006年4月の改定を前に出されていたことに驚く。私の無知を恥じるばかりである。