チリ・サンティアゴで開催されている国際地理学会に参加中です。学会の前に,北方のコピアポ市周辺を回る巡検に参加しました。その際に,3.11の津波が地球の裏側まで到達し,被害が生じた場所を訪れました。場所は Puerto Viejo という海岸の集落で,コピアポ市の北西にあります。

砂礫層の台地が削られてできた湾入部に,たくさんの家屋があります。大半は常住の家ではなく,夏季に海に滞在する人たちの別荘で,ベニヤなどを組み合わせて建てられています。土地の所有ははっきりしておらず,違法建築なのですが,地域の習慣もあり,強引に撤去したりはしないそうです。

台地の縁辺から集落を見たところです。

チリの海岸部は日本と同様に津波の危険が高いので,台地の上には津波の際に逃げるべき場所を示すサインがありました。大きな津波が来れば Puerto Viejo の集落は壊滅すると思われますが,今回,日本の沖から到達した津波は,幸いにも水深が小さく(現地の研究者によると1 m未満),それほど大きな被害は出ませんでした。

しかし海岸に最も近い家は流されたり破損したりしました。写真の左側中央に見える高床式の家は無事でしたが,その周囲の家は土台だけになっています。

手前の家は高床の部分が全て流され,杭だけが残りました。背後には,杭と床だけが残った家や,流されなかったが杭が大きく傾いた家が見えます。

高床式ではない建物も流されたことが,残っているシャワー室の土台からわかります。東北の津波被災地でも,風呂の床が残っている場所が多かったことを思い出しました。

壊された家の瓦礫。ここでも東北の被災地を思い出しました。

半壊した家。脇の車が今回被災したものかは不明です。時間的にみて錆びすぎている感じですが,海岸なので非常に早く錆びた,あるいは元から塗装が悪かった可能性もあります。

被災地の脇で地元の大学の先生や行政の方に話を聞きました。日本から津波が来ることはわかっていて避難を呼びかけたので,集落には当時誰もおらず,人的な被害はなかったとのことです。1960年に三陸を襲ったチリ津波とは異なる状況です。波高が小さかったことも幸いでした。

その後,海岸沿いのレストランで昼食となりました。海の幸が出ましたが,3.11の津波は,この地域のホタテなどの養殖に大きな被害をもたらしたと説明がありました。特にレストランの店員は,「俺たちが養殖していたものは全部ダメになった」と言っていました。
東北の3.11被災地を見た後に,地球の裏側の被災地を見たことは重要な経験になりました。チリの人たちとも,同じ自然災害の脅威がある国の住民として,心を共有できたように感じました。
Long, long way to go.
But what are miles.
Across the ocean.
(Long Long Journey/ Enya)










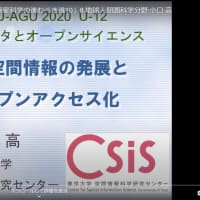
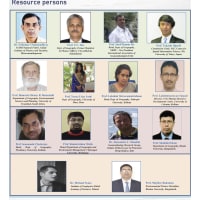
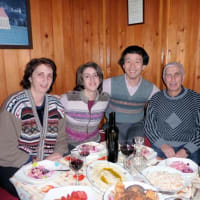







これは津波が来たらひとたまりもなく呑み込まれてさらわれてしまうでしょうね…。
何をしている人たちがどういう理由で住居を建てたのか。
コキンボ、バルパライソと今日のU+1F4FBでも聞こえてきますが大地震でここはどうなったのかU+2049U+FE0F
また今後ともよろしくお願いいたします。
貴重な記事,ありがとうございました。大変興味深く拝見いたしました。
それで私のブログで記事を紹介(リンク)してもよろしいでしょうか?
私は,すっかり海外学会へ参加する機会がなくなってしまい,寂しい思いをしています。またIGUに参加したいなとは考えてはいるのですが...。