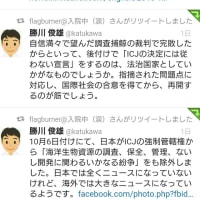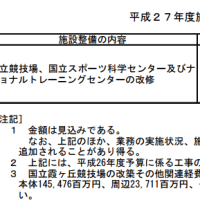今回はリハビリみたいなモン(謎)
去年3月、国際司法裁判所(ICC)は日本の南極海「調査捕鯨」を違法と判断し、去年分の南極海「調査捕鯨」は中止となった。
しかし、日本政府は全然さっぱり反省するどころか懲りずに南極海「調査捕鯨」を再開した。
というかしてしまった。
・南極海へ、調査船が出航=2年ぶり捕鯨再開-山口県下関(2015年12月1日 時事ドットコム)
一体全体どうなってるのか、と日本政府を問い詰めたくなるこの話。
以下、2015年12月1日分時事ドットコム『南極海~』を全文(略)
---- 以下引用 ----
南極海での調査捕鯨再開に向けた船団の一部が1日、下関港(山口県下関市)から出航した。
反捕鯨国の提訴を受けた昨年3月の国際司法裁判所(ICJ)の中止命令を踏まえ、日本は昨年度の南極海調査を目視にとどめていた。
今回は対象や目的を絞り込んだ新たな捕鯨計画に基づき、捕獲を伴う調査を約2年ぶりに再開する。
下関港から出航したのは「勇新丸」と「第二勇新丸」の2隻。
今後は航路の途中で母船の「日新丸」(8145トン)などと合流し、計4隻の調査船団(乗組員計160人)が今月下旬から南極海での活動を始める予定。
クロミンククジラ333頭を捕獲するなどして生態を詳しく調べる。
(2015/12/01-12:00)
---- 引用以上 ----
今回の「調査捕鯨」の根拠となった計画に対しては、実の所国際捕鯨委員会(IWC)の科学委員会で厳しい批判を受けてるんだよな。
この辺は、真田 康弘(Yasuhiro SANADA)氏による↓の解説を参照(手抜き)。
・日本の新調査捕鯨計画(NEWREP-A)とIWC科学委員会報告(2015年8月1日 ika-net.jp)
上の記事によると、科学委員会の見解は、日本政府が提出した「調査捕鯨」計画は「科学的」かどうかについて評価や検証不十分である、という。
どこかの誰かは、この計画について「科学的」と言い張ったが、これのどこが「科学的」なのやら・・・。
それでも日本政府は南極海「調査捕鯨」再開に踏み切った裏で、それなりの下準備をしていた模様。
日本政府は、今年10月、海洋資源に関する法的紛争に関して国際司法裁判所の訴訟に応じない、という宣言を国連に出していたのよね。
・捕鯨訴訟
専門裁判所で 政府宣言、国際司法裁に応じず(2015年10月29日 mainichi.jp;web魚拓)
その宣言の根拠が笑うに笑えないシロモノなのだが・・・。
参考までに、2015年10月29日分mainichi.jp『捕鯨訴訟~』を全文(略)
---- 以下引用 ----
クジラや魚など海洋生物資源に関する争いについて、日本政府が国際司法裁判所(ICJ)の訴訟には応じないとする宣言を国連に出したことが外務省への取材で分かった。日本は南極海の調査捕鯨を巡るICJの訴訟で昨年3月に敗訴している。
外務省は「ICJの判事は必ずしも海洋生物資源の専門家ではない」として、今後は国際海洋法裁判所などで争う方針だ。
外務省によると、ICJの訴訟は訴訟で争うことについて当事国同士の合意がないと成立しない。
一方、国際紛争の平和的解決を重視する立場から、国連加盟国中、豪州など72カ国は事前の同意がなくても訴訟に応じることを意味する「強制管轄受諾宣言」をしている。
宣言国同士の訴訟に適用され、日本も1958年に宣言した。
この宣言を巡り、日本政府は10月6日付で「海洋生物資源の調査、保存、管理または開発に関する国際的な紛争には応じない」と内容を修正した。
南極海の調査捕鯨を巡っては、捕鯨に反対する豪州が差し止めを求めてICJに提訴。
ICJは昨年3月、調査捕鯨は国際捕鯨取締条約が例外的に認めた「科学調査」と言えないと判断し、調査捕鯨の中止を命じた。
日本政府は調査捕鯨計画を見直さざるを得なくなり、今年度から捕獲頭数を減らした新計画を実施する。
外務省は「科学者が審理に参加できる規定がある国連海洋法条約上の紛争解決手続きを用いるのが適当」とし、国際海洋法裁判所や仲裁裁判所で争う方針を示す。
捕鯨問題に詳しい石井 敦・東北大准教授(国際政治学)は「日本は国際法を重視すると言ってきたのに、その立場を自らないがしろにする行為で、国益に反する」と話した。
一方、水産庁OBで捕鯨交渉に携わった経験がある小松 正之・東京財団上席研究員は「小手先の議論で、ICJを避けても勝てる保証はない。日本がどういう形で調査捕鯨計画と商業捕鯨を実施するのかを明確に示す方が重要だ」と指摘した。
【一條 優太】
---- 引用以上 ----
科学者(・・・)が審理に参加できる国際海洋法裁判所などで争ったとしても、「調査捕鯨」が「科学的」なんて認められる保証はどこにもないのに・・・。
この辺りに関しては、オーストラリアABCにおける真田氏のコメントが一番参考になるか。
・Japan resumes whaling in Southern Ocean, skirting International Court of Justice ban(2015年12月1日 abc.net.au)
ちうわけで、2015年12月1日 abc.net.au『Japan resumes whaling~』からその部分を(略)
---- 以下引用 ----
(中略)
But Japanese academic Yasuhiro Sanada said that too may prove to be illegal.
"I doubt Japan would win if Australia or other countries took legal action based on this. Japan is on very hazardous ground," he said.
Mr Sanada said his country had to face the truth — that scientific whaling is a fabrication. To date the program has produced 666 research papers but only two have ever been peer-reviewed.
"The research is poor," Mr Sanada said.
"They don't have to catch and kill anymore, research can be done by non lethal methods."
(以下略)
---- 引用以上 ----
「調査捕鯨」は「科学的」、という思い込みを捨て去ることはできないんだろうか?
去年3月、国際司法裁判所(ICC)は日本の南極海「調査捕鯨」を違法と判断し、去年分の南極海「調査捕鯨」は中止となった。
しかし、日本政府は全然さっぱり反省するどころか懲りずに南極海「調査捕鯨」を再開した。
というかしてしまった。
・南極海へ、調査船が出航=2年ぶり捕鯨再開-山口県下関(2015年12月1日 時事ドットコム)
一体全体どうなってるのか、と日本政府を問い詰めたくなるこの話。
以下、2015年12月1日分時事ドットコム『南極海~』を全文(略)
---- 以下引用 ----
南極海での調査捕鯨再開に向けた船団の一部が1日、下関港(山口県下関市)から出航した。
反捕鯨国の提訴を受けた昨年3月の国際司法裁判所(ICJ)の中止命令を踏まえ、日本は昨年度の南極海調査を目視にとどめていた。
今回は対象や目的を絞り込んだ新たな捕鯨計画に基づき、捕獲を伴う調査を約2年ぶりに再開する。
下関港から出航したのは「勇新丸」と「第二勇新丸」の2隻。
今後は航路の途中で母船の「日新丸」(8145トン)などと合流し、計4隻の調査船団(乗組員計160人)が今月下旬から南極海での活動を始める予定。
クロミンククジラ333頭を捕獲するなどして生態を詳しく調べる。
(2015/12/01-12:00)
---- 引用以上 ----
今回の「調査捕鯨」の根拠となった計画に対しては、実の所国際捕鯨委員会(IWC)の科学委員会で厳しい批判を受けてるんだよな。
この辺は、真田 康弘(Yasuhiro SANADA)氏による↓の解説を参照(手抜き)。
・日本の新調査捕鯨計画(NEWREP-A)とIWC科学委員会報告(2015年8月1日 ika-net.jp)
上の記事によると、科学委員会の見解は、日本政府が提出した「調査捕鯨」計画は「科学的」かどうかについて評価や検証不十分である、という。
どこかの誰かは、この計画について「科学的」と言い張ったが、これのどこが「科学的」なのやら・・・。
それでも日本政府は南極海「調査捕鯨」再開に踏み切った裏で、それなりの下準備をしていた模様。
日本政府は、今年10月、海洋資源に関する法的紛争に関して国際司法裁判所の訴訟に応じない、という宣言を国連に出していたのよね。
・捕鯨訴訟
専門裁判所で 政府宣言、国際司法裁に応じず(2015年10月29日 mainichi.jp;web魚拓)
その宣言の根拠が笑うに笑えないシロモノなのだが・・・。
参考までに、2015年10月29日分mainichi.jp『捕鯨訴訟~』を全文(略)
---- 以下引用 ----
クジラや魚など海洋生物資源に関する争いについて、日本政府が国際司法裁判所(ICJ)の訴訟には応じないとする宣言を国連に出したことが外務省への取材で分かった。日本は南極海の調査捕鯨を巡るICJの訴訟で昨年3月に敗訴している。
外務省は「ICJの判事は必ずしも海洋生物資源の専門家ではない」として、今後は国際海洋法裁判所などで争う方針だ。
外務省によると、ICJの訴訟は訴訟で争うことについて当事国同士の合意がないと成立しない。
一方、国際紛争の平和的解決を重視する立場から、国連加盟国中、豪州など72カ国は事前の同意がなくても訴訟に応じることを意味する「強制管轄受諾宣言」をしている。
宣言国同士の訴訟に適用され、日本も1958年に宣言した。
この宣言を巡り、日本政府は10月6日付で「海洋生物資源の調査、保存、管理または開発に関する国際的な紛争には応じない」と内容を修正した。
南極海の調査捕鯨を巡っては、捕鯨に反対する豪州が差し止めを求めてICJに提訴。
ICJは昨年3月、調査捕鯨は国際捕鯨取締条約が例外的に認めた「科学調査」と言えないと判断し、調査捕鯨の中止を命じた。
日本政府は調査捕鯨計画を見直さざるを得なくなり、今年度から捕獲頭数を減らした新計画を実施する。
外務省は「科学者が審理に参加できる規定がある国連海洋法条約上の紛争解決手続きを用いるのが適当」とし、国際海洋法裁判所や仲裁裁判所で争う方針を示す。
捕鯨問題に詳しい石井 敦・東北大准教授(国際政治学)は「日本は国際法を重視すると言ってきたのに、その立場を自らないがしろにする行為で、国益に反する」と話した。
一方、水産庁OBで捕鯨交渉に携わった経験がある小松 正之・東京財団上席研究員は「小手先の議論で、ICJを避けても勝てる保証はない。日本がどういう形で調査捕鯨計画と商業捕鯨を実施するのかを明確に示す方が重要だ」と指摘した。
【一條 優太】
---- 引用以上 ----
科学者(・・・)が審理に参加できる国際海洋法裁判所などで争ったとしても、「調査捕鯨」が「科学的」なんて認められる保証はどこにもないのに・・・。
この辺りに関しては、オーストラリアABCにおける真田氏のコメントが一番参考になるか。
・Japan resumes whaling in Southern Ocean, skirting International Court of Justice ban(2015年12月1日 abc.net.au)
ちうわけで、2015年12月1日 abc.net.au『Japan resumes whaling~』からその部分を(略)
---- 以下引用 ----
(中略)
But Japanese academic Yasuhiro Sanada said that too may prove to be illegal.
"I doubt Japan would win if Australia or other countries took legal action based on this. Japan is on very hazardous ground," he said.
Mr Sanada said his country had to face the truth — that scientific whaling is a fabrication. To date the program has produced 666 research papers but only two have ever been peer-reviewed.
"The research is poor," Mr Sanada said.
"They don't have to catch and kill anymore, research can be done by non lethal methods."
(以下略)
---- 引用以上 ----
「調査捕鯨」は「科学的」、という思い込みを捨て去ることはできないんだろうか?