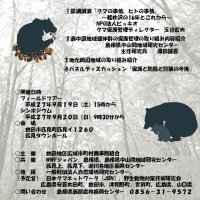11/9の当ブログの記事、
「七日市小学校の森林教室に行ってきました。」で報告したとおり、
七日市小学校では、10/29(月)に、
間伐材を使った木工体験等の森林教室を行いました。
これに続けて、「子ども達に、是非林業の作業体験を!」という
担任のM先生の御要望に応え、
第2弾として、11/26(月)に“間伐体験”を企画しています。
メイン担当者は、引き続きU先輩で、“サブ”として私も付いていきます。
11/21(水)は、その準備で、
吉賀町内のヒノキ林に行ってきましたので、報告します。
間伐体験を行う36年生ヒノキ林です(写真1)。

写真1 ヒノキ林内の地面から空を見上げたところ
植えられてから無間伐の超過密林分です。
空がほとんど見えません。
当日は、子ども達に間伐を手鋸で交代でやってもらうつもりです。
チルホールやロープ等の牽引具も使用しますが、
あまりにも込み合った林分であるため、
このままでは、伐倒しても100%“かかり木”になります。
そこで、選定した間伐木の中から、
あらかじめ子ども達に伐倒してもらう木を選び、
その木を倒すのに邪魔になる木を伐ることにしました。
U先輩が、伐倒作業をしています(写真2)。

写真2 ヒノキの伐倒(受け口作成)をするU先輩
U先輩が、かかり木をフェリングレバー(木回し)で、
処理しようとしています(写真3)。

写真3 フェリングレバーでかかり木処理を試みるU先輩
注意事項
(フェリングレバーは、体の外側に向けて押す使い方がより安全です。
誤った使い方は、死亡災害等、重篤な災害を招く可能性もあります。
専門家の指導を受けて、安全な使い方をして下さい。
関連して、記事の最後にコメントを投稿していますので、
参考にして下さい。)
ところが、このヒノキ、しっかりと枝が絡んでおり、
少々、動かしても全く倒れる気配がなく、
結局、チルホールを使用し、
2人で協力して安全に処理しました。
私も久し振りにチェンソーのハンドルを握り、
チルホールやフェリングレバーの使い方の実習ができました。
子ども達よりも私たちの方が勉強になったかもしれません(笑)。
投稿者 島根県西部農林振興センター益田事務所林業普及グループ
主任林業普及員 大場寛文
~清流高津川、山の緑に映える柿色の瓦屋根の町並み~
なつかしの国石見(いわみ)
「七日市小学校の森林教室に行ってきました。」で報告したとおり、
七日市小学校では、10/29(月)に、
間伐材を使った木工体験等の森林教室を行いました。
これに続けて、「子ども達に、是非林業の作業体験を!」という
担任のM先生の御要望に応え、
第2弾として、11/26(月)に“間伐体験”を企画しています。
メイン担当者は、引き続きU先輩で、“サブ”として私も付いていきます。
11/21(水)は、その準備で、
吉賀町内のヒノキ林に行ってきましたので、報告します。
間伐体験を行う36年生ヒノキ林です(写真1)。

写真1 ヒノキ林内の地面から空を見上げたところ
植えられてから無間伐の超過密林分です。
空がほとんど見えません。
当日は、子ども達に間伐を手鋸で交代でやってもらうつもりです。
チルホールやロープ等の牽引具も使用しますが、
あまりにも込み合った林分であるため、
このままでは、伐倒しても100%“かかり木”になります。
そこで、選定した間伐木の中から、
あらかじめ子ども達に伐倒してもらう木を選び、
その木を倒すのに邪魔になる木を伐ることにしました。
U先輩が、伐倒作業をしています(写真2)。

写真2 ヒノキの伐倒(受け口作成)をするU先輩
U先輩が、かかり木をフェリングレバー(木回し)で、
処理しようとしています(写真3)。

写真3 フェリングレバーでかかり木処理を試みるU先輩
注意事項
(フェリングレバーは、体の外側に向けて押す使い方がより安全です。
誤った使い方は、死亡災害等、重篤な災害を招く可能性もあります。
専門家の指導を受けて、安全な使い方をして下さい。
関連して、記事の最後にコメントを投稿していますので、
参考にして下さい。)
ところが、このヒノキ、しっかりと枝が絡んでおり、
少々、動かしても全く倒れる気配がなく、
結局、チルホールを使用し、
2人で協力して安全に処理しました。
私も久し振りにチェンソーのハンドルを握り、
チルホールやフェリングレバーの使い方の実習ができました。
子ども達よりも私たちの方が勉強になったかもしれません(笑)。
投稿者 島根県西部農林振興センター益田事務所林業普及グループ
主任林業普及員 大場寛文
~清流高津川、山の緑に映える柿色の瓦屋根の町並み~
なつかしの国石見(いわみ)