東京に来て蕎麦屋の多さには驚いた。
広島で「そば」といえばお好み焼きにいれる中華麺に近いやきそば用のやつのこと。
店舗も蕎麦屋よりうどん屋の方が多いと思う。
そばにしますか、うどんにしますかと聞かれるときは、間違いなく関西ではうどん、関東ではそばを注文する。
蕎麦屋さんにはいまだに謎が一杯。
最初の疑問は、暖簾や看板。
どう見ても意味不明の文字が書かれている。
き○む”?
なんだか解からないけど、そんな文字が書いてあったらそこは蕎麦屋。
そのうち、「きそば」と読むんだよと教えられた。
いったいあれがどうやったら「きそば」と読めるんだろう。
最初は疑問に思ったのだが、そのうちおいしけりゃいいや。
と。忘れ去っていた。
丼の話と、やっぱり切っても切れない存在の蕎麦屋。
最近の丼シリーズで、どんな丼があるのかと街を歩きながら、蕎麦屋の陳列をいろいろ覗いてみてた。
蕎麦ねえ。
好きな蕎麦屋さんはあるけど、、、
「ざるそば」と「もりそば」の違いも解からなかった私が蕎麦を語ることは出来ない。
ちなみに今の認識はのりが上にかっているかいないかだと思っている。
↑
そうだよね?違う?
そう、第二の疑問はそばのメニュー。
暖かいそばなら
かけ (具なし soba in plain soup)
きつね(あげ deep-fried soy bean curd)
たぬき(てんかす tempra flakes)
月見 (たまご a raw egg on top which resembles a full moon )
おかめ(かまぼこ他)
天ぷら(海老の天ぷら)
鴨南蛮(合鴨 duck and green onion )
といった上に乗る具材で名称が分かれるから解かりやすい。
冷となるとそうはいかない。
もり(汁につけて食べる。海苔なし plain soba )
ざる(竹ザルに盛り付けられたもの。海苔あり the same as above but with thin strips of dried seaweed )
せいろ(蒸篭:せいろに盛り付けられたもの)
ぶっかけ(汁がかかっている)
冷たい蕎麦が食べたいと考えただけで、微妙に差異はあるが、提供の仕方だけ違う種類のメニューが並ぶ。
第3の疑問は食べ方。
最初は蕎麦だけで風味を味わうとか、
↑
鼻で嗅ぐ「スメル」ではなく、喉で味わう「フレーバー」なのだそう。
つゆも先っちょにちょっとだけしかつけちゃダメだとか。
音を立ててずずずっと吸うとか。
3回以上噛んではだめだとか。
先に冷を食べて、後で温を食べるべしとか。
一気に流し込む類の食べ物の割には、なにかと奥深い食べ物なのである。
第4の疑問は締め。
最初に出てきたときは三々九度でもするのかと思った赤茶けた四角い急須のようなもの。
そう、そば湯。
冷やしを食べた後のつけ汁にそば湯を入れ、薄めて飲むのだけれど、どんな味が正しい味なのか誰も教えてくれない。
あれを飲むためにつけ汁は少し残しておく必要があるのかとか。
その道の達人がつくったそば湯を飲んだことがないから、どのぐらい薄めたらいいのかが解からない。
などなど、今だにちゃんとした蕎麦屋に入ると緊張する。
今回のそば番外編。そばのとーしろーが書いたもの。
そんなこたぁあたりめーだよって。
江戸っ子の皆さん笑ってくださいな。
でもね。
これって知ってました?
例の暖簾/看板に書かれた「き○む”」なる文字
たしかに発音は「きそば」で正しい。
だがしかーし。
「生蕎麦」を崩したものではなく、万葉仮名で「幾楚者」を字母にした変体仮名なんですってよ。奥さん。
さあ、勉強しよう。
・万葉仮名:漢字を崩してかなを表したもの。現在かな文字の47字より沢山あった。
・字母:崩すもとの漢字。
・変体仮名:それまで47文字以上あった「かな」が、明治時代に一音一字に決められた。その際に、外れてしまった「かな」。⇔正体。変態ではない。
さあ、今日は蕎麦屋にてコネタで乾杯と行きますか。
広島で「そば」といえばお好み焼きにいれる中華麺に近いやきそば用のやつのこと。
店舗も蕎麦屋よりうどん屋の方が多いと思う。
そばにしますか、うどんにしますかと聞かれるときは、間違いなく関西ではうどん、関東ではそばを注文する。
蕎麦屋さんにはいまだに謎が一杯。
最初の疑問は、暖簾や看板。
どう見ても意味不明の文字が書かれている。
き○む”?
なんだか解からないけど、そんな文字が書いてあったらそこは蕎麦屋。
そのうち、「きそば」と読むんだよと教えられた。
いったいあれがどうやったら「きそば」と読めるんだろう。
最初は疑問に思ったのだが、そのうちおいしけりゃいいや。
と。忘れ去っていた。
丼の話と、やっぱり切っても切れない存在の蕎麦屋。
最近の丼シリーズで、どんな丼があるのかと街を歩きながら、蕎麦屋の陳列をいろいろ覗いてみてた。
蕎麦ねえ。
好きな蕎麦屋さんはあるけど、、、
「ざるそば」と「もりそば」の違いも解からなかった私が蕎麦を語ることは出来ない。
ちなみに今の認識はのりが上にかっているかいないかだと思っている。
↑
そうだよね?違う?
そう、第二の疑問はそばのメニュー。
暖かいそばなら
かけ (具なし soba in plain soup)
きつね(あげ deep-fried soy bean curd)
たぬき(てんかす tempra flakes)
月見 (たまご a raw egg on top which resembles a full moon )
おかめ(かまぼこ他)
天ぷら(海老の天ぷら)
鴨南蛮(合鴨 duck and green onion )
といった上に乗る具材で名称が分かれるから解かりやすい。
冷となるとそうはいかない。
もり(汁につけて食べる。海苔なし plain soba )
ざる(竹ザルに盛り付けられたもの。海苔あり the same as above but with thin strips of dried seaweed )
せいろ(蒸篭:せいろに盛り付けられたもの)
ぶっかけ(汁がかかっている)
冷たい蕎麦が食べたいと考えただけで、微妙に差異はあるが、提供の仕方だけ違う種類のメニューが並ぶ。
第3の疑問は食べ方。
最初は蕎麦だけで風味を味わうとか、
↑
鼻で嗅ぐ「スメル」ではなく、喉で味わう「フレーバー」なのだそう。
つゆも先っちょにちょっとだけしかつけちゃダメだとか。
音を立ててずずずっと吸うとか。
3回以上噛んではだめだとか。
先に冷を食べて、後で温を食べるべしとか。
一気に流し込む類の食べ物の割には、なにかと奥深い食べ物なのである。
第4の疑問は締め。
最初に出てきたときは三々九度でもするのかと思った赤茶けた四角い急須のようなもの。
そう、そば湯。
冷やしを食べた後のつけ汁にそば湯を入れ、薄めて飲むのだけれど、どんな味が正しい味なのか誰も教えてくれない。
あれを飲むためにつけ汁は少し残しておく必要があるのかとか。
その道の達人がつくったそば湯を飲んだことがないから、どのぐらい薄めたらいいのかが解からない。
などなど、今だにちゃんとした蕎麦屋に入ると緊張する。
今回のそば番外編。そばのとーしろーが書いたもの。
そんなこたぁあたりめーだよって。
江戸っ子の皆さん笑ってくださいな。
でもね。
これって知ってました?
例の暖簾/看板に書かれた「き○む”」なる文字
たしかに発音は「きそば」で正しい。
だがしかーし。
「生蕎麦」を崩したものではなく、万葉仮名で「幾楚者」を字母にした変体仮名なんですってよ。奥さん。
さあ、勉強しよう。
・万葉仮名:漢字を崩してかなを表したもの。現在かな文字の47字より沢山あった。
・字母:崩すもとの漢字。
・変体仮名:それまで47文字以上あった「かな」が、明治時代に一音一字に決められた。その際に、外れてしまった「かな」。⇔正体。変態ではない。
さあ、今日は蕎麦屋にてコネタで乾杯と行きますか。












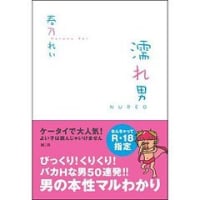




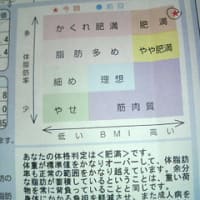
確かにきれいな水と良質のそばができる地方においしい蕎麦があるかも。
そういえば、島根の出雲そば好きだったな。
生のうずらの卵をつゆにいれるんです。
私は田舎蕎麦とよばれる濃い灰色の蕎麦のほうが食べた気がします。