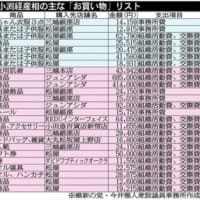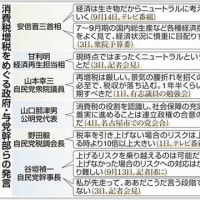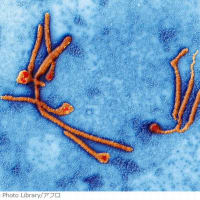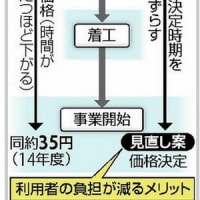2012年9月13日(木)08:05
(産経新聞)
 約1300万人が暮らす首都・東京。その防災力向上のため、12日公表された東京都地域防災計画の修正素案では、東日本大震災で得られた教訓を踏まえ、被災者の立場で、きめ細やかな対策を盛り込んだ。
約1300万人が暮らす首都・東京。その防災力向上のため、12日公表された東京都地域防災計画の修正素案では、東日本大震災で得られた教訓を踏まえ、被災者の立場で、きめ細やかな対策を盛り込んだ。
▼近隣県に火葬要請
東日本大震災の被災地では、犠牲者の遺体数が火葬場の処理能力を大きく上回り、都が火葬を支援する事態にもなった。
被災地では遺族の了解を得た上でいったん土葬し、後に火葬する「仮埋葬」も行われたが、現在の日本の火葬率はほぼ100%で、土葬に抵抗感を持つ遺族も少なくない。尊厳を守りながらどう弔うか。震災直後に直面する大きな課題だ。
防災計画では、都内での火葬が困難な場合、近隣県に対し広域火葬の応援協力を要請。葬祭関係事業者と連携し、速やかにひつぎや火葬場を確保するとした。
遺体搬送車両には、交通規制を行っている道路でも通行可能な「緊急通行車両」標章を交付するなど具体的な対策も盛り込んだ。
▼マンホールトイレ
発災後、避難所などでは衛生環境が悪化する恐れもある。トイレの確保は防疫対策の観点からも重要だ。
防災計画では、これまで避難者100人当たり1基としていた災害用トイレの数を75人当たり1基と改め、トイレが設置できるマンホールを拡充することも盛り込んだ。水道管が被害を受ければ、水洗トイレが使えなくなるからだ。
首都直下地震が起きれば、鉄道の運休などで自宅に戻れなくなる「帰宅困難者」が大量に発生する。都交通局は帰宅困難者対策のため、10月下旬までに都営地下鉄全101駅に簡易トイレ1万個と携帯トイレ4万個を追加配備する。
▼課題は最終処分場
東日本大震災では焼却施設のない自治体でがれきの処理が大きく遅れた。広域処理の動きも広がっているものの、焼却後の灰や不燃物を埋め立てる最終処分場は十分ではなく、新たな課題になっている。
都の防災計画では、がれきの一時集積場所や最終処分場の確保が必要と強調。がれき処理を実施する区市町村に、不足することが予想される運搬車や資機材の備えを求めた。また、道路が寸断され、ごみ収集車による回収が滞れば、ごみの山が各所にできて悪臭を放つほか、ハエなどが大量発生することも予想され、感染症の懸念も生じる。
このため、保健所や区市町村は被災地や避難所での感染症発生状況の把握に努める。病気が蔓延(まんえん)する恐れがあるときは消毒やねずみ、昆虫の駆除を実施するなどの手順を明確化した。
都の防災担当者は「被災者の視点に立って計画を抜本的に見直した」と話す。
● 都の防災計画 火災 特区、道路整備…「木密」対策カギ gooニュース2012年9月13日(木)08:05
(産経新聞)
 東京都が地域防災計画修正素案に掲げた減災目標の実現には、「木造密集(木密)地域対策」が欠かせない。環状7号線やJR山手線など主要交通網沿いに広がる同地域は、大規模火災を引き起こし、倒壊すれば救出や物流が停滞、被害拡大につながりかねないからだ。
東京都が地域防災計画修正素案に掲げた減災目標の実現には、「木造密集(木密)地域対策」が欠かせない。環状7号線やJR山手線など主要交通網沿いに広がる同地域は、大規模火災を引き起こし、倒壊すれば救出や物流が停滞、被害拡大につながりかねないからだ。
都は木密地域解消の切り札として「不燃化特区制度」を創設。すでに、品川区など都内11区内の計12地区が申請した。特区では木造からの建て替えに対し一定以上の耐火・耐震性能を求める代わりに助成金を増額し、税金の減免措置などの優遇策を時限的に講じる。
特区とは別に、都は燃え広がりやすい密集状態を解消するため、延焼を遮断する効果が高く、さらに緊急通行路の役割も果たすことになる都市計画道路を指定する制度も設けた。指定道路計画では、新設や拡幅のための用地買収で立ち退きを迫られる人に対し、住居を優先的に確保するなどの施策をとる考えだ。
都はこうした対策で、住宅の耐震化率を平成27年度までに90%、32年度までに95%▽街の燃えにくさを示す「不燃領域率」を32年度までに70%▽主要都市計画道路の整備率を32年度までに100%-とする目標を立てた。実現できれば、4月に見直した首都直下地震での新被害想定で約4100人と見込まれた火災による死者を約2千人に、火災での全壊・焼失棟数を約18万8千棟から約9万6千棟に、それぞれ減少させる-との道筋を描く。
ただ、道のりは簡単ではない。住居建て替えや引っ越しなど、個人の財産や生活に直結する問題となる。ある区の担当者は「動機付けはできるが強制はできず、最終的には住民自身に『やらなければ』と思ってもらうしかない」と話している。
● 都の防災計画 津波 水門強化で確実閉鎖 gooニュース2012年9月13日(木)08:05
(産経新聞)
 東京都の地域防災計画修正素案では、従来は高潮が中心だった水防対策で、東日本大震災を教訓として、津波への備えも大きく取り上げた。
東京都の地域防災計画修正素案では、従来は高潮が中心だった水防対策で、東日本大震災を教訓として、津波への備えも大きく取り上げた。
都による首都直下地震での津波被害想定では東京湾岸で最大2・6メートル、島嶼(とうしょ)部で22・4メートルが、国の南海トラフ巨大地震想定では島嶼部に30メートル以上が押し寄せるとされた。
都は隅田川沿いの江東、墨田各区など23区東部に広がる「海抜ゼロメートル地帯」を中心に堤防や水門の耐震化を進めているが、万一、水門が機能しなければ、最大約2500棟が全半壊し、逃げ遅れによる被害が出ることもありえる。
このため、水門を遠隔監視する高潮対策センターを2つに増設。通信網も多重化しバックアップすることで確実に閉鎖する。新想定に合わせ、今年度中に新たな耐震整備計画もまとめる。
島嶼部については南海トラフ巨大地震想定も踏まえ、都は浸水予測調査を早期に実施。具体的対策の基礎となる町村でのハザードマップ(災害予測地図)作成をサポートする。
津波の際、各自治体は防災無線などで一刻も早い避難を呼びかけることになる。緊急時の情報伝達に万全を期すとともに、防災教育が奏功し東日本大震災の津波にもほとんどの子供が無事だった岩手県釜石市の「釜石の奇跡」の例も踏まえ、学校での実践的訓練を充実させる。