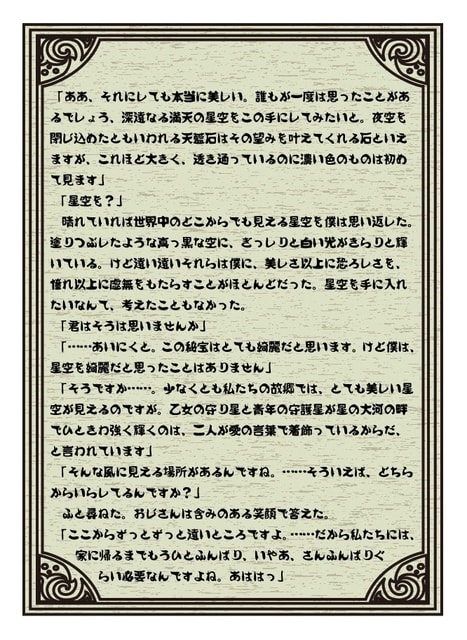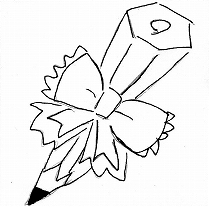1日1枚画像を作成して投稿するつもりのブログ、改め、一日一つの雑学を報告するつもりのブログ。
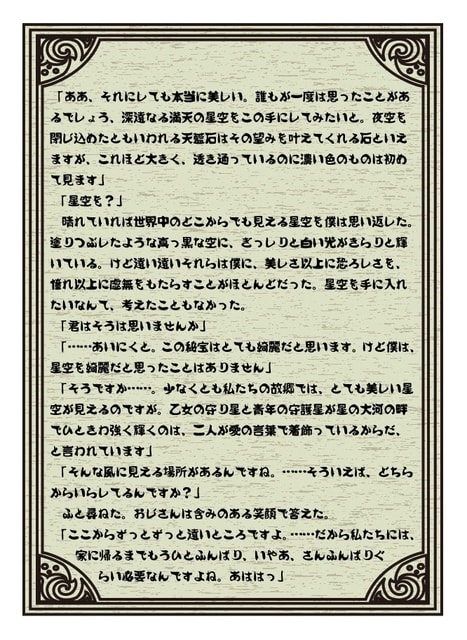
本文詳細↓
「ああ、それにしても本当に美しい。誰もが一度は思ったことがあるでしょう、深遠なる満天の星空をこの手にしてみたいと。夜空を閉じ込めたともいわれる天藍石はその望みを叶えてくれる石といえますが、これほど大きく、透き通っているのに濃い色のものは初めて見ます」
「星空を?」
晴れていれば世界中のどこからでも見える星空を僕は思い返した。塗りつぶしたような真っ黒な空に、ぎっしりと白い光がきらりと輝いている。けど遠い遠いそれらは僕に、美しさ以上に恐ろしさを、憧れ以上に虚無をもたらすことがほとんどだった。星空を手に入れたいなんて、考えたこともなかった。
「君はそうは思いませんか」
「……あいにくと。この秘宝はとても綺麗だと思います。けど僕は、星空を綺麗だと思ったことはありません」
「そうですか……。少なくとも私たちの故郷では、とても美しい星空が見えるのですが。乙女の守り星と青年の守護星が星の大河の畔でひときわ強く輝くのは、二人が愛の言葉で着飾っているからだ、と言われています」
「そんな風に見える場所があるんですね。……そういえば、どちらからいらしてるんですか?」
ふと尋ねた。おじさんは含みのある笑顔で答えた。
「ここからずっとずっと遠いところですよ。……だから私たちには、家に帰るまでもうひとふんばり、いやあ、さんふんばりぐらい必要なんですよね。あははっ」

本文詳細↓
「大丈夫かい、凄い音がしたけど」
「ど、どうにか……。あとアダム、うるさい。……それより、これは?」
「これが竜(ドラゴン)ですよ。そして、この像が握るコレこそが旧き時代の青き天藍石……『聖宮(テメノス)の秘宝』です」
部屋の中には、大きく尖った耳がついた鰐の頭と蜥蜴の体と先が分かれた蛇の尾と二対の蝙蝠の羽を持つ生き物の大きな像が鎮座しているだけだった。床に立てば見上げるほどなんだろうけど、上下逆転している僕からすると幸いというか、目線に竜の顔があった。その、もの言わぬはずのオパールの瞳が僕らを探るように見てくるように感じて、僕は慌てて視線をさらに上へやった。
ナイフほどの鉤爪に守られるように、竜の左手に金を散らした瑠璃色の宝石があった。
おじさんが少し触ると、あっけないほど簡単にころりと手の中に収まった。
「罠とかがあるかと思ってたんですけど……」
「そうですね。けど、こう考えることもできます。ここまで辿り着けるほどの知力、武力、財力を持つ者なら秘宝を渡してもかまわない、と。本当に誰にも渡したくないなら、竜自身が番人となればいいわけですし」
知力は言わずもがな。99階の探索中、おじさんたちに助けてもらわなければ死にかけたことが何度あったか。そういう事態を乗り越えるだけの武力。長期間巨大な迷宮に挑むための装備を揃える財力。全て持ち合わせるものはごくわずかだと思えば、なるほど一理ある。

本文詳細↓
おじさんが拳大ほどの石を光の中へ投げ入れた。石はとぷんっと重たげな音ともに、小さな波紋を浮かべて沈んでいった。
「異界というのは、世界のどこでもない場所です。中に飲み込まれたら最後、五体満足、精神正常なままでいられるかどうか分かりません。なので、特に注意してくださいね」
僕も上着の胸ボケットの中に入っているアダムも、神妙な顔で頷いた。足裏の感触、手元の感覚に集中したいからか、下へ向かう間会話はそれ以上なかった。
だからか、光から響く音がよく聞こえた。
闇夜を照らすたき火の爆ぜる音。
夕日が地平に消えていく静かな揺らぎの音。
燦然と輝く太陽と笑顔がはじけるときの音。
荘厳なる森の中を抜ける安らぐ風の音。
煌めく青海の雄大な波の音。
大いなる悠久の藍空(そら)が奏でる神秘の音。
茜さす地で紡がれる希いと望みの歌物語の音。
まるで世界が管絃楽(オーケストラ)を組んで、この世の美しい音たちを聞かせてくれている夢を見た気分だった。
最下層、つまり塔の最上階の部屋へ到着した。中はひたすら暗く透(とお)く、空気はどことなく冷たかった。床に手をかけ、天井まで飛び下りた。そこまでの距離ではなかったんだけど、丸天井だったせいで僕は足を滑らせて盛大に尻餅をついた。
「もっと華麗に着地せんか! 我を落とす気か!」

本文詳細↓
「見取り図を見るかぎり、内部は天辺に小部屋とそこへ繋がる螺旋階段があるだけのようですね」
「でも建物が逆さになってるってことは、上へ上がるための階段を下へ下りていかなきゃならないってことですよね? 想像するだけでこんがらがるんですが」
「大丈夫ですよ。考えるから分からなくなるんです。一歩一歩足場を確かめて下りていけばいけます」
「おぬし、意外と脳筋というか、色々物理的よな」
「残念ながら、思考と行動を両立できるほど器用ではなくて」
おじさんが苦笑したとき、「うおぉ!?」という声とともに梯子の一番上で作業していた天狗が落ちてきた。
「大丈夫ですか!? 何がありました?」
幸い、空中でバランスを立て直してなんとか着陸できたので、その人に大きな怪我はなかった。
「すいやせん、ちょっと目が回っちまって……。あれはそう、異界、のような気持ち悪さを感じやした」
「異界……。では、気休めかもしれませんが命綱も結びましょう」
腰にしっかりと縄をくくり付けて、僕はおじさんのあとに続いて中を覗き込んだ。
そして絶句した。
部屋を形作るための、あるはずの壁がなかった。ただ虹よりも濃い極彩色の光が渦を巻いていた。その中を下へまっすぐに貫いている硬質な黒い螺旋階段の方が異様に見えるほどだった。

本文詳細↓
山歩きに不慣れな僕が足を滑らせたり、大型獣に遭遇してアダムが喰われかけたり、色々あった100階の探索も4日目の昼を迎えた。
「おお、あの大岩を見よトルル。まるでこんがりと焼けた肉のようではないかっ。もっと近くへ寄れ!」
たしかに、全体が色褪せた薄い茶色であることや雨風に削られた筋なんかは、焼けた分厚い肉のように見えた。何気なく反対側へ回ろうとして大岩の影から出た瞬間、僕はギョッとして立ち止まった。
巨大な四角錐の石の建造物が、逆さになって地面に突き刺さっていた。
「ふむ。これはもしや、探していた100階ではないか? 早う奴らを呼んでこねばな」
肉に似た大岩に興奮していたはずのアダムが、落ち着き払ってそんなことを言った。
「……アダム。まさか知っていたのか?」
「さて、なんのことだ」
これも話す気はないらしい。僕は首を振るとおじさんたちを呼びに行った。色々確かめてみて、これが100階に違いないと分かると、僕は何故か胴上げされた。
「でかした坊主! お宝は目前だ、気合い入れろ!」
『おー!』
部下の人たちのほうがテンションが高かった。
入口の扉は僕たちの遥か頭上、三階建ての家の屋根ぐらいの高さにあり、今は錆ついた扉を動かそうと彼らにがんばってもらっていた。