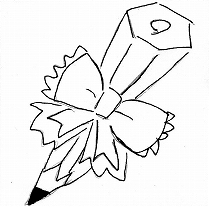本文詳細↓
まるで、しゃべりすぎたと慌て恥じるように。
「世界と歴史から名を捨てられた我が一族、か……」
人だけが忘れてしまった世界の名と生まれ。
女の子の言葉が、ナイトウォーカーが残したあの言葉と重なった。もう少し話をしてみたくて足を前へ出そうとした瞬間、アダムに思いっきり殴られた。
「まるでヘタクソなファンタジーのようなことを言う奴であったな。あんな世迷い言など忘れてしまえ。それより祭じゃ、祭! 肉と娘たちが我を待っておる!」
僕の女の子を追いかけたい、という気持ちが通るはずもなく、僕は後ろ髪引かれる思いで再び大通りの流れに身を投じた。
一通り街を観光して回り、お腹がはち切れるぐらいいっぱいになった頃には、永世礼賛の舞台もいよいよ終幕へと向かっていた。
――それはつまり、夕暮れが近づいてきているということ。今日の夕暮れは、一瞬空が燃えているのかと錯覚するほどだった。音もなく静かに、ただ勢いばかり強く、雲を溶かして空を焼きつくすかと。そう思ってしまうほどに、空は朱かった。
そういえば、毎年この時期の王都は不思議なくらいに晴れるという噂を聞いたことがある。800年間、ただの一度も雨天になったことはないとか。まあ人に天気を決める力なんてあるはずもないし、あくまで噂だけど。
そのとき、突然横のほうで悲鳴と何かが倒れ壊れるような音がした。