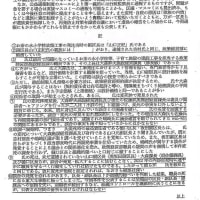音は。そこに介在したか、余りにも昔の事で…今となっては、もう思い出せない。
もう数十年前の事だ。私は一人列車に乗っていた。
山肌の斜面を走るレールの上で、何を思う訳でも無く最初から…私はここに居た。
何の気無しに辺りを見回してみても、私以外の者の姿は見えない。ボックス席の向かいには客は居らず、南に面した窓からは、少しばかりの後ろと前(まえ)が見て取れるだけで、この車両の外(ほか)は解らない。
見えるのは、この中と、左に見えて来る前(さき)ばかりで、代わり映えの無い景色を、いつからか、私はずっと眺めている気がした。
列車は緑の中を抜けていた。山肌と木々の間に挟まれて、いったい今は…どこだろう。いつになったら、着くのだろう。ぼんやりと、そんな事を考えていた。
そうして、どれ位そこに居たのだろう。緑の稜線が切れる時が遂に来た。
溢れん力が突如として現れた。それは永く穏やかに慣らされた目には、余りに濃密な色だった。水平線も地平線も空の境さえも、色が全てを圧倒した。
底が覗けない程の黄色、どこまでも不透明な黄色が遥か広がる。前の前まで埋め尽くす鮮やかな、黄色い水を湛えた、それは河だった。
光は黄金(こがね)だけを跳ね返し、外(そと)の景色を消し去った。どこまでも全てが黄色に覆われて。
私は窓に全てを奪われた。時間も距離も消え去った世界の中で、私は二つの目になっていた。
そうして、果てしなく続く光の中で。やがて一つの色が浮かび上がった。
染まる事の無い光、白、それは真っ白な水瓶だった。
彼方の白は、やがて水瓶には不釣り合いな大きさと、それを解らせる。
そこでは女達が洗濯をしていた。瓶の三分の一の程の身丈か。袖を、長い裾を膝の上までたくし上げ、笑い合い互いに、自らの持ち物を黄色に濯いでいた。
黄色は洗う足も着物も、濃いその中に見え隠れさせるだけで何も、白も、染め様とはしていない。
何故だろう、何もかも圧倒する程なのに。染めようとしない色。
何故だろう、何もかも圧倒する程なのに。それに染まらない色。
私は、そんな思いに捕われた。
いつしか女達は消えていた。
力は増々大きくなって、近づく私は再び二つの色に奪われて行く。
そうして、白い瓶は、既に輪郭を失って、ただの円い光の様に、河の中に浮かんで、
黄色と白の境界線だけに溶けて…
「この色、この色はっ!」
いつの間にか向かいの席にいた私は、思わず列車を止めていた。
胸が騒ぐ。手を当てる。鼓動が聞こえる。
あの色は?
あの色は、温かいのだろうか、冷たいのだろうか。
あの色は?
オレンジの鮮やかな香りが、味がするのだろうか。
それとも?
それとも?
開けた扉から斜面を見下ろして。深く息を吸い込んで。
「確かめるのよ」
列車を止めた私は、そしてその黄色い河の中へ降りて行った。
列車も線路も消えていた。
「わたしはどんなにおいだろう」
そして今、私は泳いでいる。東の空を泳いでいる。
2009.8.31 ?(猫目寝子)
もう数十年前の事だ。私は一人列車に乗っていた。
山肌の斜面を走るレールの上で、何を思う訳でも無く最初から…私はここに居た。
何の気無しに辺りを見回してみても、私以外の者の姿は見えない。ボックス席の向かいには客は居らず、南に面した窓からは、少しばかりの後ろと前(まえ)が見て取れるだけで、この車両の外(ほか)は解らない。
見えるのは、この中と、左に見えて来る前(さき)ばかりで、代わり映えの無い景色を、いつからか、私はずっと眺めている気がした。
列車は緑の中を抜けていた。山肌と木々の間に挟まれて、いったい今は…どこだろう。いつになったら、着くのだろう。ぼんやりと、そんな事を考えていた。
そうして、どれ位そこに居たのだろう。緑の稜線が切れる時が遂に来た。
溢れん力が突如として現れた。それは永く穏やかに慣らされた目には、余りに濃密な色だった。水平線も地平線も空の境さえも、色が全てを圧倒した。
底が覗けない程の黄色、どこまでも不透明な黄色が遥か広がる。前の前まで埋め尽くす鮮やかな、黄色い水を湛えた、それは河だった。
光は黄金(こがね)だけを跳ね返し、外(そと)の景色を消し去った。どこまでも全てが黄色に覆われて。
私は窓に全てを奪われた。時間も距離も消え去った世界の中で、私は二つの目になっていた。
そうして、果てしなく続く光の中で。やがて一つの色が浮かび上がった。
染まる事の無い光、白、それは真っ白な水瓶だった。
彼方の白は、やがて水瓶には不釣り合いな大きさと、それを解らせる。
そこでは女達が洗濯をしていた。瓶の三分の一の程の身丈か。袖を、長い裾を膝の上までたくし上げ、笑い合い互いに、自らの持ち物を黄色に濯いでいた。
黄色は洗う足も着物も、濃いその中に見え隠れさせるだけで何も、白も、染め様とはしていない。
何故だろう、何もかも圧倒する程なのに。染めようとしない色。
何故だろう、何もかも圧倒する程なのに。それに染まらない色。
私は、そんな思いに捕われた。
いつしか女達は消えていた。
力は増々大きくなって、近づく私は再び二つの色に奪われて行く。
そうして、白い瓶は、既に輪郭を失って、ただの円い光の様に、河の中に浮かんで、
黄色と白の境界線だけに溶けて…
「この色、この色はっ!」
いつの間にか向かいの席にいた私は、思わず列車を止めていた。
胸が騒ぐ。手を当てる。鼓動が聞こえる。
あの色は?
あの色は、温かいのだろうか、冷たいのだろうか。
あの色は?
オレンジの鮮やかな香りが、味がするのだろうか。
それとも?
それとも?
開けた扉から斜面を見下ろして。深く息を吸い込んで。
「確かめるのよ」
列車を止めた私は、そしてその黄色い河の中へ降りて行った。
列車も線路も消えていた。
「わたしはどんなにおいだろう」
そして今、私は泳いでいる。東の空を泳いでいる。
2009.8.31 ?(猫目寝子)