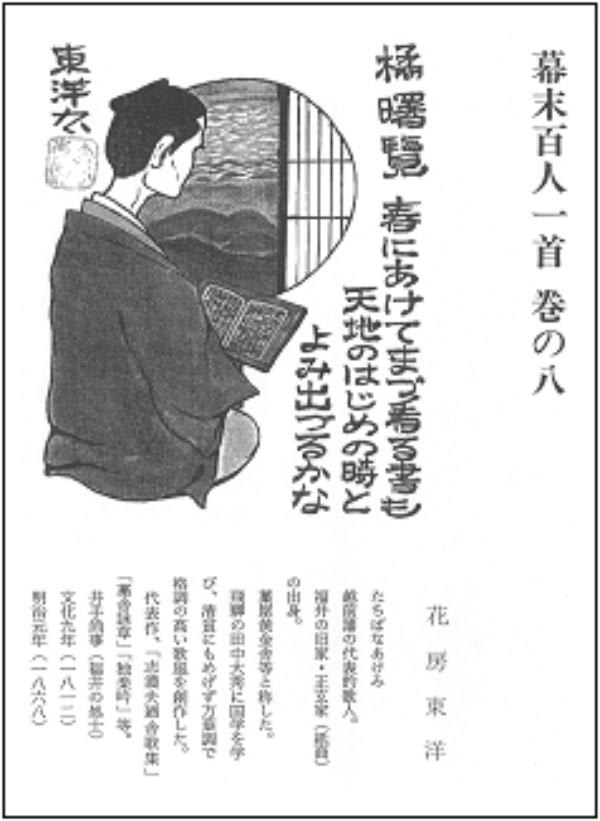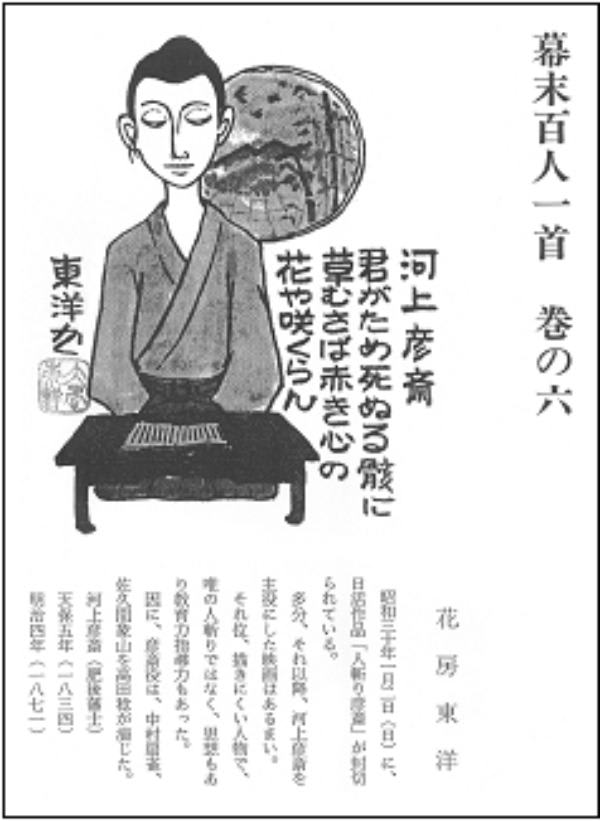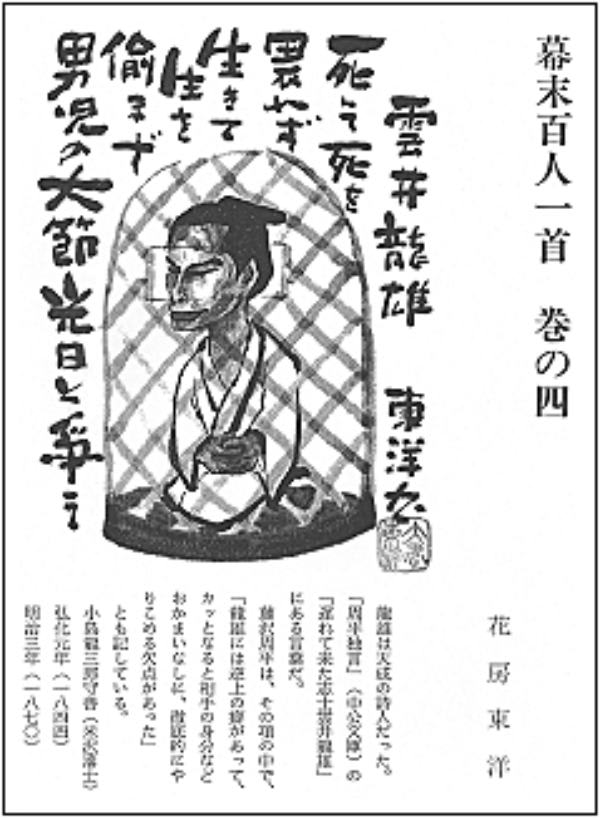平成四年七月一日発行 平成四年度版「岐阜の人権」
民族主義に人権はない─正確にいえば、日本民主主義の中に近代自由主義を前提とする人権思想を見出すことはできない。しかしながら、人権を敵対視するものではない。むしろ、人権概念を明確なものにし、これを保障することが日本民族主義の理念、すなわち日本建国の理念を完全たらしめるものだと考える。
すでに、明治維新草創の際、このような見解に立っての法理論が展開されている。伊藤博文が、帝国憲法第二章(臣民権利義務)を説述するその冒頭に、
「臣民の権利及ビ義務ヲ掲グ蓋祖宗ノ政ハ専ラ臣民ヲ愛重シテ名クルニ大寶ヲ以テシタリ」(憲法義解)
として、建国の理念に人権の根拠を求めたことは、そのあらわれである。
さりとて、人権概念の確立とその法的保障に際して、常に欧米の近代自由主義思想に依拠しなければならないという考えは容認できない。なるほど、人権という概念が欧米の近代的法思想に由来するものである以上、その理念と技術から学ぶべきものは少なくないであろう。しかし、徒な欧米法思想への追随は、その文化的相違の故に国民に人権の本質を理解せしめる妨げとなるであろう。のみならず、今日の人権論は、その母国欧米においてすら人権の氾濫による社会的混乱を招く要因となっているように思われる。
したがって以下は、欧米の近代自由主義思想を基底に持つ人権論の問題点、および我が国にそのような人権論を持ち込むことの問題点を指摘し、その上で日本民族主義の立脚する伝統文化および建国の理念からみて、人権の意義が如何なる形で国民に保障されるべきかを考えてみたい。
近代自由主義的人権論の問題点
世界人権宣言、あるいは多くの自由主義国の憲法にみられる人権は、
「人間が人間であるというそれだけの理由に基づき、各個人に保障される前国家的絶対的権利」と説明されている。日本国憲法における人権規定も同様に解釈されている。
周知のごとく、この人権概念は近代個人主義を前提とする。そして、この個人主義は原始論的社会観に立ち、「人が他者に関与されることなく自らの生を生きること」が人間の本質であるとの立場をとる。
古来、我が民族は有機論的自然観・社会観に立ち、人間存在をして「生かされて生きる存在」と理解してきた。これは単なる観念でなく、厳然たる事実である。我々は天然自然の恵みを得て成長する。我々は縁を得て、人々と接し、この人々の助けを得て自らの生活を営む。まさに我々「生かされて生きる」存在者として、自然との和、国家全体の和、地域社会の和、家庭の和、その他あらゆる人間関係において「和」を重んずることが求められている。我が国が「大和」と称された所以である。
日本民族主義は、このような「生かされて生きる」という何人も否定できぬ事実認識を尊重する。故に、個としての人間存在に至上の価値を認め、これに他のなにものにも勝る「前国家的な絶対的権利」を認めるという論理は、事実に反するものとして同意することはできない。
のみならず、現代の自由主義的法学において主張されている無限定な「人間理性の法則」、ないしカントのいう定言命法すら否定する「人間の自律的自己形成能力」を前提として人権論には本質的な欠陥がある。つとに、ヴァージニア権利章典は、
「およそ自由なる政治を、あるいは自由の享受を、人民に確保するにはひとり正義、中庸、節制、簡素および廉潔を固守し、人権の根本的諸原則をしばしば想起すること以外に方法はない」
と断言したが、今日これを意識している人間が何人いるだろうか。「理性の法則」あるいは「人間の自律的自己形成能力」を根拠とした人権論の下で、人権が健全な形で行使されているといえようか。家庭の崩壊、教育現場の混乱、残虐非道な犯罪の多発、過度のミーイズムによる人間的紐帯の喪失、自然の破壊等々、この種の人権論は人間を悲惨な状況の下に追いやっているといえよう。「人間理性の法則」あるいは「人間の自律的自己形成能力」を論拠とした人権論は、幸福追求という大前提にもかかわらず、逆の結果を招きつつある。
これは、当然予想された結果なのである。論証を割愛して結果のみを述べよう。近代人権論、これはそれぞれの社会に存した既成の道徳規範に守られて権利と義務の整合性を得、健全たり得た。ところが無限定な理性の名によって、この道徳規範が否定されるとき、前述のヴァージニア権利章典のいうがごとき訓告は無視され、権利のみが無限定に主張され、人権は権利と義務の整合性を失う。これが、混乱せる社会現象を招来した主たる原因である。であれば、日本民族主義以前の問題としても、このような人権論は到底認めることはできない。
建国の理念の現代的意義
「舊来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クベシ」
(五箇条の御誓文)
日本民族主義は、頑な保守主義ではない。時代の推移に適合することの必要性は当然に認める。ただし、その本質を見失うことはない。その本質とは何か。建国の理念である。日本民族主義は、国家統治の原点を建国の理念に求めつつ、その理念の実現に最も相応しき道を時代に則して模索する。
では、その建国の理念とはなにか。
「苟も民に利有らば何ぞ聖の造に妨はむ」
神武天皇橿原遷都の詔が、日本民族の理念、日本建国の理念を端的に表している。我が国が近代国家として生まれ変わる時にも、この理念が忘れられることはなかった。
「今般朝政一新の時に膺り、天下億兆、一人もその処を得ざるときは、みな朕が罪ならば、今日の事こと、朕自身骨を労し、心志を苦しめ、艱難の先に立ち、古い列祖の尽くさせ給いし蹤を履み、治蹟を勤めてこそ、始めて、天職を奉じて億兆の君たる所に背かざるべし」(明治元年三月一四日 明治天皇御沙汰書)
国民の福利、国民おのもおのもに「其の処を得さしめる」こと、これが国家統治論としての我が国の建国の理念である。
では、「其の処を得さしめる」とは何か。そもそも、「生かされて生きる」ことに価値を認める。したがって、ここでは、存在者が自らの存在価値を全うすることの意義を認める。桜花は桜花として開花し、然るのち、その務めを終える。これを以て、桜花はその存在価値を十全たらしめる。人また然り。人として生まれ、そのもてる力を充分に養い、これを発揮してはじめてその存在価値を全うする。だとすれば、国民各自に対して、自らの能力を充分に発揮せしめる場が与えられなければなるまい。
また、古来、我が民族は天然自然に畏敬の念をもち、この恵みに感謝して生きることを精神生活の中核としてきた。政治の理念、国家統治の理念もここにその起源をもつ。伝統的「祭政一致」に見られる「祭」は、自然に対する感謝のあらわれである。ここでは自然の恵みが祈られた。したがって、祭政一致の原則の下では、「政」はこの祈りを現実生活の場で実現生活の場で実現するもの、自然の恵みをあまねくするものでなければならない。あたかも、太陽の恵みに貴賎の別なきがごとく。であれば、政治において不当の差別のゆるされるべき道理はない。
なるほど、我が国の歴史を観るとき、我々は門地その他による差別的処遇があったことを知る。しかし観念的という観点からみるとき、不当な差別は「舊来ノ陋習」として否定されるべきである。もしこれが許されるならば、国民各自をして、その存在価値を十全たらしめることは不可能となるであろう。因みに、伊藤博文は、帝国憲法十九条(文武官就任の平等)を説述するに際し、
「維新ノ後陋習ヲ一洗シテ門閥ノ弊ヲ除キ」
と説く。
さらに、「一視同仁」もまた、社会弱者の救済を求める建国の理念であった。戦前における一連の昭和維新運動は、まさにこの建国の理念と乖離した現実との戦いであった。遠くは仁徳天皇治世の教訓が歴史的に国家統合の模範として語り継がれてきた事実に、また前述の明治天皇御沙汰書における「天下億兆、一人も其の処を得ざる時は─」なる言葉に、我が国における「一視同仁」の理念性が明らかに読みとれる。
建国の理念と憲法
さて、以上のごとき建国の理念の実現に、人権保障の法的技術は、極めて有効に機能するものと解される。その意味で、日本民族主義は、憲法による人権保障に賛同する。しかし、既に述べたごとく、其の法理と保障形態は近代人権論のそれとは異なったものとなる。
では日本民族主義の自然観・人間観に立脚してなされる憲法的人権論は如何なるものとなるであろうか。以下、人権論の基本的原理、人権の内容、および人権保障の限界に分けて述べてみよう。
〈基本的原理〉
前述したごとく、有機体的社会観に立つ日本民族主義の下では、欧米の近代個人主義的人権論、あるいは前国家的権利論は否定される。また、人権は相対化され、その絶対性も認められない。
日本民族主義は、「生かされて生きる」即ち「共存共栄」の価値原理に基づき、人権は「共存共栄」という目的を以て、国家・社会が個々の国民に保障したものと解する。この保障を法的に裏付けるものが、憲法上の権利章典ないしは人権規定である。
〈人権の内容〉
日本民族主義に立つ憲法の下においても、近代自由主義の憲法の多くによって保障されてきた自由権、平等権、社会権、国務請求権等の殆どの人権が保障の対象となるべきだろう。けだし、国民各自に対して、これらの権利を保障することが、建国の理念の実現、また「共存共栄」の価値実現に有効に機能するものと解されるからである。参政権についても、これと同様に国民各自に「其の処を得さしめる」為には、国民意思を基調とする政治(広義の民主政治)が、現代社会において最も有効なものと解されるからである。
〈人権保障の限界〉
日本民族主義に立つ憲法の下で保障される人権に対して、「法律留保主義」がとられるべきか否かが問題となる。この問題に関しては、前述した人権の基本的原理を想起してもらいたい。思うに、人権保障の契機は国民各自の「存在価値」を十全たらしめることであった。一方、社会的、国家的には、社会公共の福利が今一つの大きな価値として措定される。したがって、人権の限界は、社会公共の福利に反せざること、ここに求められよう。この場合に限って、人権は法律により制限されるべきものと解される。個々の具体的事例に際しては、判断者の恣意を避ける為にも、限界確定利益衡量の手法が望ましいと思われる。
なお、ここにいう「社会公共の福利」には、国家の存続と安全保障、社会秩序の維持が当然に含まれる。さらに人権の濫用を防止する為に、伝統的文化・道徳の維持が必要である。そのことは歴史が我々に教える所である。したがって、必要があれば、伝統的文化・道徳は、憲法そのものによって保護されるべきである。のみならず、伝統的文化・道徳を忘れるとき、日本民族主義は民族としてのアイデンティティを失い、国家存続の基盤すら失うことになろう。この意味では、伝統的文化・道徳は国家存続の為の大前提であり、これなくして、事実上の人権保障はあり得ない。世界的事実に照らしてみても、亡国の民が人権を享受した事例はない。
以上、日本民族主義と人権について述べた。現在のところ、日本民族主義に人権論は極めて少ない。
したがって、本論において「日本民族主義は─」という主語の下で述べた見解も、筆者自身の個人的見解である。にもかかわらず「日本民族主義は─」として述べたのは、現代社会における日本民族主義という立場からする時、そのように考えることが正しいと信じたからである。また、許容範囲内で、近代法学にも多くを学んだ。けだし、良き知恵は、洋の東西、時代の古今を問わず学ぶべきものと考えたからである。無論、以上述べた所は、極めて粗削りなものである。それ故、本論に対して多くの非難が予想される。しかしその非難は筆者の望むところである。これらの非難を得て日本民族主義の立場からする人権論をより確たるものにしてゆきたい。
民族主義に人権はない─正確にいえば、日本民主主義の中に近代自由主義を前提とする人権思想を見出すことはできない。しかしながら、人権を敵対視するものではない。むしろ、人権概念を明確なものにし、これを保障することが日本民族主義の理念、すなわち日本建国の理念を完全たらしめるものだと考える。
すでに、明治維新草創の際、このような見解に立っての法理論が展開されている。伊藤博文が、帝国憲法第二章(臣民権利義務)を説述するその冒頭に、
「臣民の権利及ビ義務ヲ掲グ蓋祖宗ノ政ハ専ラ臣民ヲ愛重シテ名クルニ大寶ヲ以テシタリ」(憲法義解)
として、建国の理念に人権の根拠を求めたことは、そのあらわれである。
さりとて、人権概念の確立とその法的保障に際して、常に欧米の近代自由主義思想に依拠しなければならないという考えは容認できない。なるほど、人権という概念が欧米の近代的法思想に由来するものである以上、その理念と技術から学ぶべきものは少なくないであろう。しかし、徒な欧米法思想への追随は、その文化的相違の故に国民に人権の本質を理解せしめる妨げとなるであろう。のみならず、今日の人権論は、その母国欧米においてすら人権の氾濫による社会的混乱を招く要因となっているように思われる。
したがって以下は、欧米の近代自由主義思想を基底に持つ人権論の問題点、および我が国にそのような人権論を持ち込むことの問題点を指摘し、その上で日本民族主義の立脚する伝統文化および建国の理念からみて、人権の意義が如何なる形で国民に保障されるべきかを考えてみたい。
近代自由主義的人権論の問題点
世界人権宣言、あるいは多くの自由主義国の憲法にみられる人権は、
「人間が人間であるというそれだけの理由に基づき、各個人に保障される前国家的絶対的権利」と説明されている。日本国憲法における人権規定も同様に解釈されている。
周知のごとく、この人権概念は近代個人主義を前提とする。そして、この個人主義は原始論的社会観に立ち、「人が他者に関与されることなく自らの生を生きること」が人間の本質であるとの立場をとる。
古来、我が民族は有機論的自然観・社会観に立ち、人間存在をして「生かされて生きる存在」と理解してきた。これは単なる観念でなく、厳然たる事実である。我々は天然自然の恵みを得て成長する。我々は縁を得て、人々と接し、この人々の助けを得て自らの生活を営む。まさに我々「生かされて生きる」存在者として、自然との和、国家全体の和、地域社会の和、家庭の和、その他あらゆる人間関係において「和」を重んずることが求められている。我が国が「大和」と称された所以である。
日本民族主義は、このような「生かされて生きる」という何人も否定できぬ事実認識を尊重する。故に、個としての人間存在に至上の価値を認め、これに他のなにものにも勝る「前国家的な絶対的権利」を認めるという論理は、事実に反するものとして同意することはできない。
のみならず、現代の自由主義的法学において主張されている無限定な「人間理性の法則」、ないしカントのいう定言命法すら否定する「人間の自律的自己形成能力」を前提として人権論には本質的な欠陥がある。つとに、ヴァージニア権利章典は、
「およそ自由なる政治を、あるいは自由の享受を、人民に確保するにはひとり正義、中庸、節制、簡素および廉潔を固守し、人権の根本的諸原則をしばしば想起すること以外に方法はない」
と断言したが、今日これを意識している人間が何人いるだろうか。「理性の法則」あるいは「人間の自律的自己形成能力」を根拠とした人権論の下で、人権が健全な形で行使されているといえようか。家庭の崩壊、教育現場の混乱、残虐非道な犯罪の多発、過度のミーイズムによる人間的紐帯の喪失、自然の破壊等々、この種の人権論は人間を悲惨な状況の下に追いやっているといえよう。「人間理性の法則」あるいは「人間の自律的自己形成能力」を論拠とした人権論は、幸福追求という大前提にもかかわらず、逆の結果を招きつつある。
これは、当然予想された結果なのである。論証を割愛して結果のみを述べよう。近代人権論、これはそれぞれの社会に存した既成の道徳規範に守られて権利と義務の整合性を得、健全たり得た。ところが無限定な理性の名によって、この道徳規範が否定されるとき、前述のヴァージニア権利章典のいうがごとき訓告は無視され、権利のみが無限定に主張され、人権は権利と義務の整合性を失う。これが、混乱せる社会現象を招来した主たる原因である。であれば、日本民族主義以前の問題としても、このような人権論は到底認めることはできない。
建国の理念の現代的意義
「舊来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クベシ」
(五箇条の御誓文)
日本民族主義は、頑な保守主義ではない。時代の推移に適合することの必要性は当然に認める。ただし、その本質を見失うことはない。その本質とは何か。建国の理念である。日本民族主義は、国家統治の原点を建国の理念に求めつつ、その理念の実現に最も相応しき道を時代に則して模索する。
では、その建国の理念とはなにか。
「苟も民に利有らば何ぞ聖の造に妨はむ」
神武天皇橿原遷都の詔が、日本民族の理念、日本建国の理念を端的に表している。我が国が近代国家として生まれ変わる時にも、この理念が忘れられることはなかった。
「今般朝政一新の時に膺り、天下億兆、一人もその処を得ざるときは、みな朕が罪ならば、今日の事こと、朕自身骨を労し、心志を苦しめ、艱難の先に立ち、古い列祖の尽くさせ給いし蹤を履み、治蹟を勤めてこそ、始めて、天職を奉じて億兆の君たる所に背かざるべし」(明治元年三月一四日 明治天皇御沙汰書)
国民の福利、国民おのもおのもに「其の処を得さしめる」こと、これが国家統治論としての我が国の建国の理念である。
では、「其の処を得さしめる」とは何か。そもそも、「生かされて生きる」ことに価値を認める。したがって、ここでは、存在者が自らの存在価値を全うすることの意義を認める。桜花は桜花として開花し、然るのち、その務めを終える。これを以て、桜花はその存在価値を十全たらしめる。人また然り。人として生まれ、そのもてる力を充分に養い、これを発揮してはじめてその存在価値を全うする。だとすれば、国民各自に対して、自らの能力を充分に発揮せしめる場が与えられなければなるまい。
また、古来、我が民族は天然自然に畏敬の念をもち、この恵みに感謝して生きることを精神生活の中核としてきた。政治の理念、国家統治の理念もここにその起源をもつ。伝統的「祭政一致」に見られる「祭」は、自然に対する感謝のあらわれである。ここでは自然の恵みが祈られた。したがって、祭政一致の原則の下では、「政」はこの祈りを現実生活の場で実現生活の場で実現するもの、自然の恵みをあまねくするものでなければならない。あたかも、太陽の恵みに貴賎の別なきがごとく。であれば、政治において不当の差別のゆるされるべき道理はない。
なるほど、我が国の歴史を観るとき、我々は門地その他による差別的処遇があったことを知る。しかし観念的という観点からみるとき、不当な差別は「舊来ノ陋習」として否定されるべきである。もしこれが許されるならば、国民各自をして、その存在価値を十全たらしめることは不可能となるであろう。因みに、伊藤博文は、帝国憲法十九条(文武官就任の平等)を説述するに際し、
「維新ノ後陋習ヲ一洗シテ門閥ノ弊ヲ除キ」
と説く。
さらに、「一視同仁」もまた、社会弱者の救済を求める建国の理念であった。戦前における一連の昭和維新運動は、まさにこの建国の理念と乖離した現実との戦いであった。遠くは仁徳天皇治世の教訓が歴史的に国家統合の模範として語り継がれてきた事実に、また前述の明治天皇御沙汰書における「天下億兆、一人も其の処を得ざる時は─」なる言葉に、我が国における「一視同仁」の理念性が明らかに読みとれる。
建国の理念と憲法
さて、以上のごとき建国の理念の実現に、人権保障の法的技術は、極めて有効に機能するものと解される。その意味で、日本民族主義は、憲法による人権保障に賛同する。しかし、既に述べたごとく、其の法理と保障形態は近代人権論のそれとは異なったものとなる。
では日本民族主義の自然観・人間観に立脚してなされる憲法的人権論は如何なるものとなるであろうか。以下、人権論の基本的原理、人権の内容、および人権保障の限界に分けて述べてみよう。
〈基本的原理〉
前述したごとく、有機体的社会観に立つ日本民族主義の下では、欧米の近代個人主義的人権論、あるいは前国家的権利論は否定される。また、人権は相対化され、その絶対性も認められない。
日本民族主義は、「生かされて生きる」即ち「共存共栄」の価値原理に基づき、人権は「共存共栄」という目的を以て、国家・社会が個々の国民に保障したものと解する。この保障を法的に裏付けるものが、憲法上の権利章典ないしは人権規定である。
〈人権の内容〉
日本民族主義に立つ憲法の下においても、近代自由主義の憲法の多くによって保障されてきた自由権、平等権、社会権、国務請求権等の殆どの人権が保障の対象となるべきだろう。けだし、国民各自に対して、これらの権利を保障することが、建国の理念の実現、また「共存共栄」の価値実現に有効に機能するものと解されるからである。参政権についても、これと同様に国民各自に「其の処を得さしめる」為には、国民意思を基調とする政治(広義の民主政治)が、現代社会において最も有効なものと解されるからである。
〈人権保障の限界〉
日本民族主義に立つ憲法の下で保障される人権に対して、「法律留保主義」がとられるべきか否かが問題となる。この問題に関しては、前述した人権の基本的原理を想起してもらいたい。思うに、人権保障の契機は国民各自の「存在価値」を十全たらしめることであった。一方、社会的、国家的には、社会公共の福利が今一つの大きな価値として措定される。したがって、人権の限界は、社会公共の福利に反せざること、ここに求められよう。この場合に限って、人権は法律により制限されるべきものと解される。個々の具体的事例に際しては、判断者の恣意を避ける為にも、限界確定利益衡量の手法が望ましいと思われる。
なお、ここにいう「社会公共の福利」には、国家の存続と安全保障、社会秩序の維持が当然に含まれる。さらに人権の濫用を防止する為に、伝統的文化・道徳の維持が必要である。そのことは歴史が我々に教える所である。したがって、必要があれば、伝統的文化・道徳は、憲法そのものによって保護されるべきである。のみならず、伝統的文化・道徳を忘れるとき、日本民族主義は民族としてのアイデンティティを失い、国家存続の基盤すら失うことになろう。この意味では、伝統的文化・道徳は国家存続の為の大前提であり、これなくして、事実上の人権保障はあり得ない。世界的事実に照らしてみても、亡国の民が人権を享受した事例はない。
以上、日本民族主義と人権について述べた。現在のところ、日本民族主義に人権論は極めて少ない。
したがって、本論において「日本民族主義は─」という主語の下で述べた見解も、筆者自身の個人的見解である。にもかかわらず「日本民族主義は─」として述べたのは、現代社会における日本民族主義という立場からする時、そのように考えることが正しいと信じたからである。また、許容範囲内で、近代法学にも多くを学んだ。けだし、良き知恵は、洋の東西、時代の古今を問わず学ぶべきものと考えたからである。無論、以上述べた所は、極めて粗削りなものである。それ故、本論に対して多くの非難が予想される。しかしその非難は筆者の望むところである。これらの非難を得て日本民族主義の立場からする人権論をより確たるものにしてゆきたい。
「司法を裁く、逆シンポジウム」に参加して
昭和五五年六月二〇日発行 月刊「燕雀」昭和55年6月号より
世間では、私のことを「右翼」という。自分ではそのつもりはないのだが、私の言動や交友関係をみて、人はそうよぶのであろう。私も無理に否定するほどのこともないから、言われるがままにしている。
そんな「右翼」の私のもとに「左翼」から一通の手紙が届いた。
ある運動の呼びかけであった。
その運動とは、東大裁判を担当している山根二郎という弁護士が日弁連から懲戒処分をうけた事件に対し大島渚・野坂昭如・竹中労の三氏が中心となって、その処分の不当性を訴え、日弁連に抗議するといった一種の反権力闘争である。
私は平素より、反体制である筈の左翼の人達が、民主主義や憲法を擁護する立場をとっていることに矛盾を感じていたので、
「反権力闘争大いに結構。但し、反体制・反権力を標榜するものが、体制側の憲法に依拠するような闘争方法をとることは納得できない。戦略・戦術的に分からないわけではないが、自分としては、体質が合わない」
として「非賛同」という返事を出しておいた。
話は少し横道にそれるが、私は以前「物質万能の戦後体制の打倒」を訴えるため、米・英・ソ大使館、政財界首脳邸、朝日新聞等を襲撃することを計画、志半ばにおいて逮捕されたことがあった。これを「国民前衛隊事件」というのだが、この際、「法」が体制の「法」として機能する限り法廷闘争など無意義であるとし「弁護人不要、弁論無用、黙して罪に服するのみ」という裁判姿勢を貫き徹した。これは何も豪傑を気取り、肩肘を張っている訳ではない。
故・井上孚麿氏の言葉を借りるなら、
「人生は複雑であり、法を守るだけでは、忠義の道を貫き得ぬ場合がないとも限らない。そう思いつめたものが非合法の道をとるのは、止むを得ぬ。だが世の常の道を進まず、法を犯してまでも忠の道を断じて進む者は、自らはっきりとおのれの違法を認めて、」ということになる。
もっとも「弁護人不要」というのは、裁判運営上困るというので、やむをえず、国選弁護人を依頼したところ、共産党の弁護士が担当することになった。共産党の人に弁護してもらうのも一興だわい、と楽しみにしていたら、弁護士の方から「右翼の弁護はしたくない」と拒否されてしまった。
以上のような私自身の法体制に対する見解もあって「山根懲戒処分に抗議する運動」には賛同しかねたのである。「非賛同」の返事を出したところ、この運動の実質的な推進者である竹中労氏から「あなたの意見は非常にユニークだ。今度のシンポジウムで、ぜひ発言してくれないか」という要請があった。私の意見といっても、賛否以前の問題だから発言しても、何の問題提起にもならないし、シンポジウムの進行意図にもそわないと思うので辞退したのだが、旧知の畏友である一水会の鈴木邦男氏からも再三すすめられて、ついに承諾してしまった。
時は5月17日、所は東京麹町・東条会舘大ホール、
「司法を裁く・逆シンポジウム」は開催された。見世物小屋のロクロ首でもみるような好奇な目差しを一斉に浴びた発言者の私は、前記した意見を述べたあと、次のようなことを付け加えて、しめくくった。
「私は、右翼や左翼といった弁別意識は全くありません。ただ、真摯に〝反体制〟や〝反権力〟を唱えるのなら、まず、現体制の中にドップリとつかりこんで、その恩恵を蒙っている、このダンナ衆との訣別、そして現行憲法を破棄し、幻の戦後民主主義から脱却していただきたい。そこからこそ、本物の反体制・反権力闘争が生まれるのではないか、と確信します。半ばあきらめに近い期待をもって、皆様方にお願いする次第です」
この後、引き続き記念講演に移ったが、その講師は羽仁五郎ダンナであった。
これからは余談。
私がこの集まりに参加して驚いたのは、シンポジウムが終わったあとの豪華な懇親パーティーと賛同者の多彩な顔ぶれであった。
パーティーの方は、特に豪華というほどでもない、右でいえばいわゆる総会屋右翼の類いがよくやる立食形式のものだったが、いずれにせよ、私のような〝ルンペン右翼〟を驚かせるには充分なものだった。
それより、驚いたのは賛同者の顔ぶれの方である。因みに、賛同者名をザッと上げると、青島幸男、荒畑寒村、石垣綾子、いずみたく、いいだもも、伊丹十三、一圓一億、井上清、猪野健治、色川大吉、今村昌平、岩井章、梅原正紀、永六輔、小田切秀雄、小中陽太郎、岡本喜八、大野明男、木下半治、黒柳明、サトウサンペイ、新藤兼人、宗左近、千代丸健二、戸浦六宏、土本典昭、東郷健、中山千夏、中村武志、仁木悦子、二谷英明、平尾昌晃、深沢七郎、本多勝一、南博、無着成恭、結城昌治、山下耕作、吉川勇一、吉行淳之介、湯川れい子、米倉斉加年、美輪明宏、渡辺美佐子…と書き出せばキリがない。これらの中に〝ダンナ〟が何人いるのかなとチェックをしていくと面白い。
さらにおどろいたのは、二次会で行ったスナックで大島渚氏が「蒙古放浪歌」や「青年日本の歌」を唄ったことである。勿論、これは「右翼」である私に対する氏のサービス精神がなせる業なのであろうが、その歌のメロディ・歌詞を寸分の狂いなく歌いこなす歌唱力、そして、その鷹揚な態度に感服した。テレビや人伝に知る氏はきわめて教条的で神経質な印象があり、生理的に嫌悪感さえ抱いていたのだが、氏への認識を改めなければいけないナ、と思ったりした。
反面、こんなことですぐに感激するようだから、世間から「右翼」といわれるんだろうナ、と考えもしたのである。
昭和五五年六月二〇日発行 月刊「燕雀」昭和55年6月号より
世間では、私のことを「右翼」という。自分ではそのつもりはないのだが、私の言動や交友関係をみて、人はそうよぶのであろう。私も無理に否定するほどのこともないから、言われるがままにしている。
そんな「右翼」の私のもとに「左翼」から一通の手紙が届いた。
ある運動の呼びかけであった。
その運動とは、東大裁判を担当している山根二郎という弁護士が日弁連から懲戒処分をうけた事件に対し大島渚・野坂昭如・竹中労の三氏が中心となって、その処分の不当性を訴え、日弁連に抗議するといった一種の反権力闘争である。
私は平素より、反体制である筈の左翼の人達が、民主主義や憲法を擁護する立場をとっていることに矛盾を感じていたので、
「反権力闘争大いに結構。但し、反体制・反権力を標榜するものが、体制側の憲法に依拠するような闘争方法をとることは納得できない。戦略・戦術的に分からないわけではないが、自分としては、体質が合わない」
として「非賛同」という返事を出しておいた。
話は少し横道にそれるが、私は以前「物質万能の戦後体制の打倒」を訴えるため、米・英・ソ大使館、政財界首脳邸、朝日新聞等を襲撃することを計画、志半ばにおいて逮捕されたことがあった。これを「国民前衛隊事件」というのだが、この際、「法」が体制の「法」として機能する限り法廷闘争など無意義であるとし「弁護人不要、弁論無用、黙して罪に服するのみ」という裁判姿勢を貫き徹した。これは何も豪傑を気取り、肩肘を張っている訳ではない。
故・井上孚麿氏の言葉を借りるなら、
「人生は複雑であり、法を守るだけでは、忠義の道を貫き得ぬ場合がないとも限らない。そう思いつめたものが非合法の道をとるのは、止むを得ぬ。だが世の常の道を進まず、法を犯してまでも忠の道を断じて進む者は、自らはっきりとおのれの違法を認めて、」ということになる。
もっとも「弁護人不要」というのは、裁判運営上困るというので、やむをえず、国選弁護人を依頼したところ、共産党の弁護士が担当することになった。共産党の人に弁護してもらうのも一興だわい、と楽しみにしていたら、弁護士の方から「右翼の弁護はしたくない」と拒否されてしまった。
以上のような私自身の法体制に対する見解もあって「山根懲戒処分に抗議する運動」には賛同しかねたのである。「非賛同」の返事を出したところ、この運動の実質的な推進者である竹中労氏から「あなたの意見は非常にユニークだ。今度のシンポジウムで、ぜひ発言してくれないか」という要請があった。私の意見といっても、賛否以前の問題だから発言しても、何の問題提起にもならないし、シンポジウムの進行意図にもそわないと思うので辞退したのだが、旧知の畏友である一水会の鈴木邦男氏からも再三すすめられて、ついに承諾してしまった。
時は5月17日、所は東京麹町・東条会舘大ホール、
「司法を裁く・逆シンポジウム」は開催された。見世物小屋のロクロ首でもみるような好奇な目差しを一斉に浴びた発言者の私は、前記した意見を述べたあと、次のようなことを付け加えて、しめくくった。
「私は、右翼や左翼といった弁別意識は全くありません。ただ、真摯に〝反体制〟や〝反権力〟を唱えるのなら、まず、現体制の中にドップリとつかりこんで、その恩恵を蒙っている、このダンナ衆との訣別、そして現行憲法を破棄し、幻の戦後民主主義から脱却していただきたい。そこからこそ、本物の反体制・反権力闘争が生まれるのではないか、と確信します。半ばあきらめに近い期待をもって、皆様方にお願いする次第です」
この後、引き続き記念講演に移ったが、その講師は羽仁五郎ダンナであった。
これからは余談。
私がこの集まりに参加して驚いたのは、シンポジウムが終わったあとの豪華な懇親パーティーと賛同者の多彩な顔ぶれであった。
パーティーの方は、特に豪華というほどでもない、右でいえばいわゆる総会屋右翼の類いがよくやる立食形式のものだったが、いずれにせよ、私のような〝ルンペン右翼〟を驚かせるには充分なものだった。
それより、驚いたのは賛同者の顔ぶれの方である。因みに、賛同者名をザッと上げると、青島幸男、荒畑寒村、石垣綾子、いずみたく、いいだもも、伊丹十三、一圓一億、井上清、猪野健治、色川大吉、今村昌平、岩井章、梅原正紀、永六輔、小田切秀雄、小中陽太郎、岡本喜八、大野明男、木下半治、黒柳明、サトウサンペイ、新藤兼人、宗左近、千代丸健二、戸浦六宏、土本典昭、東郷健、中山千夏、中村武志、仁木悦子、二谷英明、平尾昌晃、深沢七郎、本多勝一、南博、無着成恭、結城昌治、山下耕作、吉川勇一、吉行淳之介、湯川れい子、米倉斉加年、美輪明宏、渡辺美佐子…と書き出せばキリがない。これらの中に〝ダンナ〟が何人いるのかなとチェックをしていくと面白い。
さらにおどろいたのは、二次会で行ったスナックで大島渚氏が「蒙古放浪歌」や「青年日本の歌」を唄ったことである。勿論、これは「右翼」である私に対する氏のサービス精神がなせる業なのであろうが、その歌のメロディ・歌詞を寸分の狂いなく歌いこなす歌唱力、そして、その鷹揚な態度に感服した。テレビや人伝に知る氏はきわめて教条的で神経質な印象があり、生理的に嫌悪感さえ抱いていたのだが、氏への認識を改めなければいけないナ、と思ったりした。
反面、こんなことですぐに感激するようだから、世間から「右翼」といわれるんだろうナ、と考えもしたのである。
平成九年六月一日発行 「すぐに役立つ実用マレー語会話辞典」より
琉球の古い民謡の中に「マタハリヌ・チンタラ・カヌサマヨ」というのがあるが、この意味を地元の古老に尋ねても「ただの合いの手で特別の意味はない」と答える。ところがこれは紛れもないマレー語である。「マタハリ」とは「太陽」、「チンタ」は「愛する」それに「ラ」という強調語が付いて「強く愛する」という意味である。最後の「カヌサマ」は大和言葉の「神様」の訛りである。琉球には、民謡の例を挙げるまでもなく、マレー文化に共通するものが多々ある。マレーとの関連は琉球ばかりでなく、日本本土においても見られる。「阿蘇山」や「富士山」がマレー語だと言うと、信じて貰えるだろうか。
遥かなる昔、丸太舟に帆を掛けて原始マレー人が沖合の漁撈に出た。黒潮と偏西風に押し流されて台湾、琉球そして日本列島の南端・日向海岸へと流れ着いた。そこで煙たなびく高千穂の峰を見て「あっ煙だ!」と叫んだ。(マレー語で〝煙〟のことを〝アソップ〟という)以後「煙の山」(アソップ→アソ→阿蘇)と呼ぶようになった。更に土佐海岸、紀伊半島、渥美半島と流れ、秀麗の富士山を仰ぎ見て「素晴らしい!」と褒め讃えた。(マレー古語で〝素晴らしい〟又は〝褒める〟ことを〝フジー〟という)これが「素晴らしい山」(フジー→フジ→富士)となった。
「名も知らぬ遠き島より流れ寄る椰子の実一つ」と渥美半島・伊良湖畔において島崎藤村が詠ったように、南方にしかない椰子の実が日本列島に無数に流れ着いている。南方に生棲した原始マレー人も椰子の実と同様、黒潮と偏西風に乗って流れ着いたのであろう。
日本民族文化の根源は「稲作文化」である。それ故に、我々先祖は我が国を「豊葦原瑞穂の国」と称した。しかし、稲作は通説にあるような中国大陸から渡来したものではない。大陸文化が日本民族の文化形成に多大な影響を及ぼしたことは否めないが、大陸文化が本格的に、日本へ渡来したのは奈良朝期以降のことである。この時期の日本では、既に稲作が根付いていた。また、北方中国において現在まで水田稲作は皆無に近い。従って、日本文化の根源が稲作文化である限り、大陸文化が日本文化のオリジナルではなく、南方民族の漂流移動によって到達・伝承された黒潮文化(稲作文化)が日本民族文化のオリジナルであると考えるのが自然である。故に、古事記や日本書紀に書かれているように南方民族が流れ着いた日向海岸や高千穂の峰が日本民族発祥の地とされているのである。
以上は、小生の手前定規な推論ではない。本協会顧問であった故ラジャー・ダト・ノンチク長老が福田赳夫元首相から聴かれた説である。その福田元首相も山下奉文、今村均両将軍から聴かれたとのことである。このように、両将軍はアジアと日本との歴史的な関わりを調査された上で、アジアに民族独立の貴重な種を蒔かれたのである。昨今の円高をはじめとする経済状況の中、企業の海外進出がブームだが、その前に、同じ根をもつアジアの人々の言語・文化・宗教・習慣など諸々の事般を調査研究し、理解して、その地に適応した実践が重要不可欠ではなかろうか。
琉球の古い民謡の中に「マタハリヌ・チンタラ・カヌサマヨ」というのがあるが、この意味を地元の古老に尋ねても「ただの合いの手で特別の意味はない」と答える。ところがこれは紛れもないマレー語である。「マタハリ」とは「太陽」、「チンタ」は「愛する」それに「ラ」という強調語が付いて「強く愛する」という意味である。最後の「カヌサマ」は大和言葉の「神様」の訛りである。琉球には、民謡の例を挙げるまでもなく、マレー文化に共通するものが多々ある。マレーとの関連は琉球ばかりでなく、日本本土においても見られる。「阿蘇山」や「富士山」がマレー語だと言うと、信じて貰えるだろうか。
遥かなる昔、丸太舟に帆を掛けて原始マレー人が沖合の漁撈に出た。黒潮と偏西風に押し流されて台湾、琉球そして日本列島の南端・日向海岸へと流れ着いた。そこで煙たなびく高千穂の峰を見て「あっ煙だ!」と叫んだ。(マレー語で〝煙〟のことを〝アソップ〟という)以後「煙の山」(アソップ→アソ→阿蘇)と呼ぶようになった。更に土佐海岸、紀伊半島、渥美半島と流れ、秀麗の富士山を仰ぎ見て「素晴らしい!」と褒め讃えた。(マレー古語で〝素晴らしい〟又は〝褒める〟ことを〝フジー〟という)これが「素晴らしい山」(フジー→フジ→富士)となった。
「名も知らぬ遠き島より流れ寄る椰子の実一つ」と渥美半島・伊良湖畔において島崎藤村が詠ったように、南方にしかない椰子の実が日本列島に無数に流れ着いている。南方に生棲した原始マレー人も椰子の実と同様、黒潮と偏西風に乗って流れ着いたのであろう。
日本民族文化の根源は「稲作文化」である。それ故に、我々先祖は我が国を「豊葦原瑞穂の国」と称した。しかし、稲作は通説にあるような中国大陸から渡来したものではない。大陸文化が日本民族の文化形成に多大な影響を及ぼしたことは否めないが、大陸文化が本格的に、日本へ渡来したのは奈良朝期以降のことである。この時期の日本では、既に稲作が根付いていた。また、北方中国において現在まで水田稲作は皆無に近い。従って、日本文化の根源が稲作文化である限り、大陸文化が日本文化のオリジナルではなく、南方民族の漂流移動によって到達・伝承された黒潮文化(稲作文化)が日本民族文化のオリジナルであると考えるのが自然である。故に、古事記や日本書紀に書かれているように南方民族が流れ着いた日向海岸や高千穂の峰が日本民族発祥の地とされているのである。
以上は、小生の手前定規な推論ではない。本協会顧問であった故ラジャー・ダト・ノンチク長老が福田赳夫元首相から聴かれた説である。その福田元首相も山下奉文、今村均両将軍から聴かれたとのことである。このように、両将軍はアジアと日本との歴史的な関わりを調査された上で、アジアに民族独立の貴重な種を蒔かれたのである。昨今の円高をはじめとする経済状況の中、企業の海外進出がブームだが、その前に、同じ根をもつアジアの人々の言語・文化・宗教・習慣など諸々の事般を調査研究し、理解して、その地に適応した実践が重要不可欠ではなかろうか。