
「国母陛下の御瑞夢」
以前(「団塊の世代雑感(9-1)」)にちょっと紹介したように、龍馬が
日露開戦前夜に美子皇后(昭憲皇太后)の夢枕に現れた(明治37年2月6日夜)
ことが、吉兆つまり瑞祥であるとされて新聞に記事が載って(4月13日付
『時事新報』)話題となります。
2月6日は、日本がロシアに対して国交断絶の最終通告をした日であり、
東郷平八郎率いる連合艦隊が、旅順口方面にあるロシア太平洋艦隊を撃滅
すべく佐世保軍港を進発した日でもありました。つまり、宣戦布告(2月
10日)に先立って戦意高揚のために仕組まれたものであることは確かなの
です。(これは弱気になっていた明治天皇のためですが。)
なぜ二月余りも経ってから『時事新報』に記事が載ったのかと云いますと、
直前の4月4日の閣議において、講和方針が打ち出され、有利な講和条件
を引き出すためにはバルチック艦隊との海戦に勝利することが不可欠と
されたからです。また、記事が掲載された4月13日は、前月27日の第二
回旅順港口閉塞作戦において、指揮官のひとり海軍少佐広瀬武夫が、
その乗船福井丸が自爆沈没する前に敵水雷が命中し水没しはじめたため、
端艇で本船を離れようとしたときに敵弾が頭部に命中し、身体ごと海中
に吹き飛ばされた、その葬儀の日でもあったからです。広瀬を軍神と
して祭上げたことをも考え合わせると、目的が戦意高揚にあったこと
は明白なのです。
そして、その年の11月に寺田屋伊助によって『国母陛下の御瑞夢 附大和魂』
と題する小冊子が宮内省御用書肆吉川弘文館から定価六銭で発行されます。
内容は、文部省検定による高等小学校の教員と児童用および尋常小学校の
教員用の唱歌の教科書。
「瑞夢」は逓信大臣大浦兼武による造語で、奇瑞な夢、つまり不思議な目
出度い徴(しるし)の意です。大浦がわざわざ寺田屋へ赴いた(5月6日)と
いうのも、この仕掛けをするためだと思えます。
ここに掲載した写真は、その小冊子(奥付も含めて10頁)の2、3頁目です。
実は、この歌に龍馬暗殺に関する暗号文が隠されているのです。このことは
未だ誰も気付いていません。皆さんへの新年のお年玉。
以前(「団塊の世代雑感(114-4)」で)貶した加治将一先生の暗号文とは
違って、こちらは正真正銘の暗号文(と僕は確信しています)。でもその解き明
かした内容は割愛させてね。
誰です、大きな熨斗袋の中身を覗いたら、小銭しか入っていなかった、なんて
云うのは。
ブログトップへ戻る
辰年の発見



















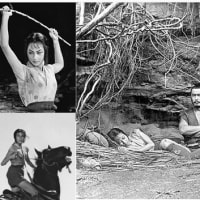
僕が住まいするマンション(と云うのもおこがましいコンドミニアムですが)
の管理組合のゴタゴタに何だかんだと煩わされることになって、あれやこれや
で時間を取られて、観たい映画を見に行くどころか、読書すらも儘ならず、
伊藤勉くんとの同期会の打ち合わせもズルズルと遅れております。
そんな状態でもテレビや新聞を見る時間はあって、今朝テレ朝で興味深い
ことが取り上げられていました。
「モーニングバード」と云う番組の中の「定数減か給料か、議員が身を切る
べきはどっち?」というもので、現在消費税等の増税で国民に負担を強いる
議論がなされていますが、それなら優遇されている公務員や国会議員も自ら
の身を削るべきではないかと世論の突き上げにあって、公務員の給料の1割
近くの削減は見込まれているものの、国会議員の方は定数削減で各党の思惑
が何だかんだと働いて中々結論がでない状況にあります。
この番組で問題としたのは、定数削減で良いのか、歳費を削減すべきでは
ないのか、という本質的な視点。
そもそも議員定数が決められたのは明治時代のことで、当時は10万人ほど
で構成されていた「郡」から一人を選出していました。ところが現在は27
万人から一人が選出されている計算になるそうで、G7の他の国と比べても
多すぎるということではないようです。
であれば、歳費(議員一人当たり5600万円!)を削減すれば良いと思う
のですが、各党の地盤・看板・かばんが揃った主だった面々は、議員定数
を減らそうが我が身に影響は無いとして、定数削減の方が歳費削減より、より
効果的であると、もっともらしくのたまっている。
本当にそうなのかしらん。歳費の削減額次第では定数削減より捻出できる
金額は増えそうだけど。
それに、定数を削減したなら、前述したような世襲議員ばかりが幅を利かせて、
貧乏人から議員になる道はか細いものになるもの。
それと、党利党略が絡んだ定数削減案は、どっちつかずの中途半端なものに
なって、国民の代表者としての議員選出といった根本をくつがえすものとなり
かねません。
こういったことについて国民がどのような意識を持っているかアンケートを
とって調査したそうです。それ(100人)によると、
定数削減に賛成 38人
歳費削減に賛成 31人
両方削減に賛成 21人
その他 10人
だったそうです。
議員に費やす税金は、上記歳費だけでなく、議員のための宿舎やJRの無料パス
など付随する費用が沢山あるので、それに議員の中にはまともな活動もせずに
のうのうと暮らす不埒な輩もいて、そういった輩を篩にかける意味合いからも
定数削減はそれなりに必要だと思えます。(僕個人の意見としては「両方削減、
ただし歳費削減の方に重点を置いて」です。)
最早封印された感のある最低保障年金制度ですが、月額7万円ものバラマキが
行われたなら、目的税とされている消費税が将来7.1%引き上げられるのは
必至。
加えて、現行の厚生年金受給標準よりも殆どのひと(生涯平均年収が約380
万円を超えているひと)が年金額が減ることになります。
増税で負担が増える上に、多くのひとの年金が減るような案が国民の納得を得
られる筈がありません。
誤った問の答えを求めるよりも、正しい問を発することが大切。無年金者の
将来を憂うるのであれば、どうすれば年金加入者を、その受給金額を、増やす
ことができるのかを真剣に論じるべきです。
週刊新潮の今週号に「辰年の発見」という小さなコラムが載っている
のですが、それによると、松坂屋の創業者である伊藤次郎左衛門祐民
の名古屋市にある「揚輝荘」と云う別荘、その別荘の敷地の中に「白
雲橋」(はくうんばし)と云う屋根付きの橋があって、その屋根の天井
に、縦横約2メートルの墨絵の龍が描かれてあるそうで(祐民自身の
手になるものらしい)、今年は辰年ですから、その絵を年賀状に使うた
めに、関係者が写真を撮ろうとして、あちこちの角度から眺めている
うちに、その龍の頭の部分が「冠をかぶった女性の顔」に見えてきた
そうです。そのコラムでは「人を驚かせることが好きだった祐民の隠し
絵の可能性も」なんて書いてあるので、早速ネットで検索。
その結果見つけた写真をこのコメントの親記事「つぶやきの部屋16」
の下の方に載せました。1、2枚目の全容から、3枚目が入口で、橋
を渡っていくと、4枚目の絵の描かれた天井のところに。そして5枚
目が天井に書かれた龍の絵の頭の部分です。
口とヒゲの辺りに注目!
右横から見てみて、ほら、紅白で美川憲一だか小林幸子だかが被って
いたでしょ、こんな冠。その冠の下に女性だか男性だか分かりません
が、凛々しい横顔が。
写真が小さくて分かり難いのですが、3枚目の入り口のところに張り
紙があるでしょ。「入れません」と書いてあるのです。
平成19年10月20日から、揚輝荘は一般公開されるようになった
のですが、残念ながら白雲橋は特別なイベント(橋の上を舞台にして
音楽や踊りなどが催される)を除いて利用されることは無いとのこと。
京都の修学院離宮にある「千歳橋」(ちとせばし)を真似たといわれて
いて、両端の切石の石垣に架けられた木造橋の屋根は緑釉和瓦だそう
で、名古屋市の有形文化財に指定されています。
揚輝荘は、北側にある北庭園(6,500㎡)と南側にある南庭園(2,700
㎡)とから成っているのですが、白雲橋は北庭園にあります。
北庭園が京都の修学院離宮の地割を模しているとのことですから、
白雲橋が千歳橋を真似たのは確か。(ただし、千歳橋の屋根は一部
銅葺の茅葺。)
大正7年(1918)に造られたと云いますから、伊藤次郎左衛門祐民(すけ
たみ)が、40歳のときにこの絵も描き上げたことになります。
不惑とは云え、何か秘密が潜んでいそうですが、残念ながら直に絵を
拝める機会はなさそうですし、祐民を巡るレコの存在も今となっては
知る由もありません。
それにしても、大金持ちのやることなすこと、豪勢なもんですなー。
今日の朝日新聞の「天声人語」は、昨日死刑が確定した
光市の母子殺害事件について書かれてあります。
その中で気になった表現が使われているのです。
それは「当時少年だった被告(30)の死刑が固まった。」と
ある箇所です。
「固まる」は「確実になる」の意であり、「確定する」とは
その意味が異なり、「当選確実」のように、若干ながらも
不確定な意味合いを含む言葉です。
また、一面に掲載された当該裁判の判決記事の「おことわり」
には、「最高裁判決で死刑が確定する見通しとなったことを
受け、実名での報道に切り替えます。」としてあるのに、
後段では「事件当時は少年でも、死刑が確定する場合、原則
として実名で報道する方針を決めています。」と矛盾するよう
な表現をとっています。
実名で報道しているのですから、確定したと認めている筈なの
ですが、人権派を気取る朝日新聞の体質(購読者も人権左派が
多い)が「固まる」であるとか「見通しとなった」とかの表現
をとることになったのでしょう。
天の発する声は、どっちつかずのものでは無い筈。
社会の木鐸としての矜持があるのなら、どっちつかずの態度を
とらずに堂々と論陣を張ればよいのです。
僕個人の今回の判決に対する意見は、当然の帰結と思っています。
大衆と称せられる人々の意見も同様だと考えています。
被告を擁護する人は、「生育環境」とか「犯行時の年齢」とか
をその理由として取り上げますが、前者の人々の大半は残虐な
犯行など起こしはしません。そのようなことを理由とするので
あれば、そういった人々を犯罪予備軍として暗に差別すること
になり兼ねません。後者の年齢についてもその理由にはなりま
せん。18歳になっていれば、少年法の適用外です。
これは犯罪に限らず、例えば公序良俗に反する行為にも厳粛に
適用されます。18歳未満と線引きしたのは、更生の可能性が
高いとされているからですが、報道を通じて知らされる被告の
態度にはその可能性は全くと云ってよいほど感じることができ
ません。友人に出した手紙の内容などを見ると、再犯の可能性
すら嗅ぎ取ることができます。
連続射殺魔事件の永山の方が更生という面では、多分にその可
能性があったと思います。
ですから更生とは切り離して、また被害者の人数ばかりでなく、
その時の犯行が情状酌量の余地があるか否かで、死刑の判決が
下されたものと考えています。(四人が二人であっても死刑に
なったと思います。なぜなら被害者には何の落ち度もないから
です。強盗殺人、それも偶発的なものでなく計画的なものなの
ですから当然の帰結です。)
今回の判決は、年齢だとか人数がとか、そういった数での線引
きでは無く、犯行そのものに焦点が当てられたという点で、望
ましい方向への第一歩を踏んだものとして評価しています。
それにしても、天の声を伝え語るという輩には、常に怪しい何
かが付き纏うようで。
今週、昭和邦画のメッカ「神保町シアター」で二本観てきました。
一本は「こつまなんきん」(1960,S35,松竹京都)、もう一本は「女殺し油地獄」
(1957,S32,東宝)。
「こつまなんきん」は、今東光の同名の原作を映画化したもので、題名がどう
いう意味なのか知らずに、主演が瑳峨三智子と云うことで足を運んだのですが、
映画の中で「色は黒くて小振りだけど、味の良いカボチャ」のことを云うのだ
と、それが転じて「小粒で味の良い女性」のことを指す言葉だと知りました。
瑳峨三智子が色黒で小粒だとは思えませんが、男好きのする主人公を妖艶に
演じています。なんだかんだあって、最後は男に頼らない女となることを宣言
して終わるのですが、グラマラスな姿態をふんだんに拝めるからかどうなのか
分かりませんが、札止めになった(全席が埋まった)のは初めての体験です。
この映画のときは25歳。まだ顔をいじる前のちょっとあどけなさの残る
可愛らしい顔立ちですが、1962年に岡田眞澄と婚約(結婚には至らず)した
ことが契機になったのでしょうか、「裸体」(1962)では顔が変わっています。
「女殺し油地獄」は、近松門左衛門の人形浄瑠璃「女殺油地獄」が原作で、何本
も映画化されていますが、観てきたものは河内屋与兵衛を二代目中村扇雀(現三代
目鴈治郎)、与兵衛に殺される豊島屋の女房お吉を新珠三千代が演じたもの。
よくできた作品ですが、上記と違って1/3ほどしか席は埋まりませんでした。
裸が無いから?女性が主役じゃ無いから?う~む、分からん。
この映画、子供の頃に一度観たことがあるのです。桶から流れ出た油の中で、二人
が殺し殺される凄惨なシーンが繰り広げられるのですが、これが強烈に印象に残
っていたようで、もっと長いこと組んず解れつしていたように記憶していたのです。
でも実際はそうではなかった。記憶って面白い。
話は変わって、BS255「日本映画専門チャネル」が3月1日から4日の深夜
まで無料放送されます。
明日3日の9:00~11:00には近松ものの「近松物語」(長谷川一夫、香川京子)が、
そして今晩の日本アカデミー賞の最優秀作品賞にノミネートされている「最後の
忠臣蔵」(役所広司、桜庭ななみ)が4日の13:00~16:00に放映されます。
どちらも良い作品です。お見逃しなく。
シリーズが少し続くかも知れないので、こちらに移動。
TVに続いて、豊かさや憧れの象徴であった三種の神器のひとつ、
冷蔵庫について。
三種の神器がマスコミによって喧伝されたのは1950年代後半、つま
り我が家に白黒テレビが遣って来た頃のことですが、我が家には
その頃氷冷蔵庫があって、電気冷蔵庫が遣って来たのはずっと後の
こと。
「懐かしの昭和」にある写真のものは上下二段ですから、上に氷を
入れても下の部分に食べ物を入れておけるので何とかなるのでしょ
うが、我が家のは一段だけのものであったように記憶しています。
氷を入れると、それこそ食物を入れるスペースは無いということに
なりますから記憶違いかも知れないのですが。
当時は氷屋さんが自転車にリヤカーを牽いて、筵で覆った氷を
運んできてくれて、家の前で鋸で適当な大きさに切って売って
くれました。
もっとも当時は、西瓜を冷やすくらいでしか使用せず、その必要性
を殆ど感じることの無かった代物でした。ですから、世の中に普及
した順も白黒TVが最も早くて、冷蔵庫が最も遅かったと云います。
「ALWAYS三丁目の夕日」では、確かシュークリームを冷蔵庫に
保存していて、それを食べて食中りするシーンがあったように
思うのですが(電源を入れていなかったのだったかな?)、我が家
ではケーキなんて滅多に口にできるものではありませんでしたし。
アメリカのホームドラマのように大きな電気冷蔵庫に沢山の食品を
保存しておくような生活をしていなかったので、我が家に遣って来
たのは1965年、高校2年生のとき。
日立製で、霜取りは自動ではなくてボタンを押して行う必要があり、
そのときの水が冷蔵庫の下に置いた受け皿に溜まるというものでし
た。
この初代の電気冷蔵庫、二代目を購入するときに、伯母(母の姉)に
引き取ってもらってからも(サブとして)使われていましたから、
30年もの長きに亘って故障することもなく働き続けてくれたこと
になります。流石、モーターの日立!
伯母が亡くなって、伯父も体が不自由になって名古屋へ引っ越し
ていったものですから、そのときに冷蔵庫も処分されてしまいま
した。そうでなかったら、その後もまだまだ働いてくれたのでは
ないかしらん。
その冷蔵庫が来た当初は、今から考えると随分と小振りであったに
もかかわらず、保存しておくものなど殆どなくて、夏場に西瓜の他、
ジュース類を冷やしておくくらいでした。でも学校から帰ってくる
と冷たく冷えたファンタオレンジやグレープがあると思うと、家に
向かう足取りも随分と違ったものです。
「フーテンの寅」のようなタイトルの付け方になりましたが、
シリーズ化すると、こういったところが面倒。
三種の神器の残りひとつ、電気洗濯機は別の機会に回すとして、
今回は月刊誌『少年』について。
「懐かしの昭和」には、鉄人28号の漫画本の写真が載ってい
ますが、この「鉄人28号」(横山光輝)が連載されていたのが、
月刊誌『少年』でした。
ネットで調べたところ、「鉄人28号」が『少年』に登場した
のは昭和31年(1956)7月号からだそうです。僕が小学校2年
生のときです。
僕は、よくは覚えていないのですが、たしか「鉄人28号」は
初回から読んでいた記憶がありますので、その頃から梅屋敷駅
の横っちょにあった小さな本屋へ毎月息急き切って駆け付けて
いたことになります。
『少年』には「鉄人28号」の他に「鉄腕アトム」(手塚治虫)、
「矢車剣之助」(堀江卓)、といった僕の好きな漫画が連載されて
いたので、少年月刊誌には他に『冒険王』、『ぼくら』などが
ありましたが、小遣いの関係もあって、一冊選ぶなら迷わず
『少年』、となります。
当時の少年月刊誌には付録が付いていたのですが、中でも『少年』
のそれは分厚くて、こちらの方が楽しみであったりしたものです。
大体がつるつるの面に彩色が施された厚手のボール紙の紙模型で、
戦艦、空母、戦車、ジェット機などの男の子に人気のある戦争もの
が多かったように記憶しています。
中には「少年探偵手帳」なるものがあって、昭和34(1959)年9月
号のものを僕も持っていたように思います。これもネットで調べた
ところ、以下のような内容であったそうですが、忍術云々のこと
が書かれてあったことは朧気ながら覚えています。
・きみも名探偵になれる
・犯人はだれ?
・暗号の作りかた
・忍術はあったか
・秘密インキの作りかた
など35項目。
このような付録が付いていたのは、挿絵付の「怪人二十面相」を始
めとした少年探偵団シリーズが連載されていたからで、少年探偵団
バッジ(BDバッジ)もこの付録の手帳を通じて手に入れた(\25)よう
に思います。
景品にも何度か応募して、鉄腕アトムの首振り人形が当りました。
円形の赤く塗った木製の台の上に身体の前で腕を組んですっくと立
ったもので、高さは30cm近くあったように思います。
頭は彩色した鋳物で出来ていて丈夫でしたが、赤いブーツも含めて
胴体は石膏の詰まったセルロイド製ですから、結局はそこがひび割
れて石膏が零れ落ちて、到頭壊れてしまいました。
この人形、数が出ていない筈ですから、大切に保管していたら、今
ならかなり高額で取引されたように思うのです。まっこと残念!
『少年』は、昭和43年(1968)3月まで続いたようですが、既に
『少年サンデー』、『少年マガジン』(ともに昭和34年3月創刊)
といった週刊の漫画雑誌が出ていたことや、その前後に精巧な縮尺
プラモデルが出始めていたこと、更にはTVの影響もあって、その
魅力も失われたのでしょう。
僕も、昭和34年(1959)1月号から始まった「ナガシマくん」(わち
さんぺい)は読んでいたけど、昭和36年(1961)7月号からの「サス
ケ」(白土三平)はその記憶が殆ど無いので、小学5年生か6年生の
初めくらいには購読を止めたのではないかしらん。
少年期の懐かしい思い出です。
「懐かしの昭和」に載っている写真では、牛乳瓶が写っていますから、
僕らの卒業後の給食メニューですね。
昭和33年(1958)に文部省から「学校給食用牛乳取扱要領」が出て、
脱脂粉乳が牛乳に変わったとのことですが、我らの小学校というか
大田区というか東京都というか、どこでどうなったのか分かりません
が、対応が少し遅れたようです。
アルマイトのトレイにアルマイトの食器が、軽くて耐久性に優れている
という理由から使用されていたわけですが、なぜか引っ掻き傷が付きや
すい。
午後の授業があったときに、給食が出たように記憶しているので、5年生
から出たのかしらん。
正午のチャイムが鳴ると、教室に据え付けてあったスピーカーから音楽
だか何だかの放送が流れている中、給食当番が配膳をして回るのですが、
食器は自分で用意していたように思います。
給食当番の記憶が薄れているけど、エプロンや三角巾などを使っていた
のかしらん。もしそうだったら、僕も当番にはなっているわけで、その
姿を今想像すると顔が赤くなる。
洗濯はどうしていたのだろう?持参していたのかな?記憶にない!
オカズが一品、そして脱脂粉乳とかカレー汁とかが付いてくる、といった
極めて粗末なもの。
当時の僕は、肉類、魚類が苦手、というか食わず嫌いで、カレー汁のとき
は皆は喜んでいたけど、僕は食べ残す。鯨の竜田揚げなんて、血管がその
まま残っていたりするものだから、それを見ただけで、これまた残す。
僕が至福と感じたのは、揚げたコッペパンに甘く煮込んだ金時豆、そして
脱脂粉乳、この組み合わせ。皆が少ししかよそわないので、たくさん余って
いた脱脂粉乳をおかわりして飲んでいましたね。蛋白質、カルシウム、乳糖
などが多く、栄養価も高いので、動物性蛋白質を補ってもくれて、華奢な
がらも今日の僕を形作ってくれた有り難い飲み物でした。
脱脂粉乳は、当時のアメリカが、過剰に余っていたものをユニセフからの
援助物資を装って在庫処分したようですが、パンの原料の小麦粉と抱き
合わせ(輸出)といったアメリカの思惑もあったのでしょう。
コッペパンは、今は済生病院となっていますが、そこにあった平林製パンが
卸していました。裏手というか向かって右手の奥まったところに製パン所が
あって、出来たてのあの独特の香ばしい匂いが辺りに漂っていたものです。
子供の頃、\10円の、わらじのような大きなコッペパンに、近くのコロッケ屋
で買った\5のコロッケを挿んで頬張ったものです。
グローブだか手だかの形をしたクリームパン、三つの丸い形をした三色パン、
練りチョコの詰まったロールパン、三角形の黒い蒸しパン、円錐形の甘食も
美味しかった。どれもこれも最早思い出の中だけの味覚。
アンパンやジャムパンもあったでしょうが、小倉パンとかメロンパンだとか
になると、これまた不明瞭。
なぜかと言うと八中では、調理室が無く、造ろうとしても場所も適当な
ところが無いし、造ったところで、団塊の世代がぎっしり詰め込まれた、
2千数百人にも及ぶ給食を賄うのは大変だったのでしょう。それで、これ
また不明瞭な記憶ですが、2年生の途中からだったか、パンと牛乳とを
朝申し込んで、当然料金は前払いで、給食代わりとするようになったの
です(それまでは弁当持参)。
このときのパンの種類とゴッチャになっているのです。
ちなみに高校のときも同じだったので、尚更混同に輪をかけることに。
今だと\4,000くらいになりますが、それが割高なのかどうかも分かりません
が、さほどの負担と感じていなかったようですから、一月20回もあったか
どうかも当時の時間割がこれまたハッキリせず何とも云えないのですが、
1食当りで換算すると妥当なものだったのだと思います。
それなのに、昨今では義務教育だからという理由で給食費の支払いを拒否
している保護者がいるとか。(義務教育の「義務」は「権利」と対のもので、
何人も教育を受ける権利があり、その保護者は教育を受けさせる義務を負う、
つまりその一環としての給食も保護者にとってはその費用を負う義務がある
わけなんですけどね。)
保護者にも給食当番があって、母も駆り出されたことがあったそうです。
どのようなことをしたのか、この稿を起こすに当ってあれこれ聞いてみたの
ですが、もう半世紀以上も前のことですし、何度もやったことでも無いと
云うことで、不確かこの上ないのですが、バケツのような食缶(バケツと
異なるのは、これまたアルマイト製で、蓋が付いていること)に脱脂粉乳と
かを、そして木箱?にコッペパンとかを、それぞれ人数分入れることだった
らしい。4、5人来ていたといいますから、1クラス分だけを担当したの
でしょう。後始末をした記憶が無いと云うことですから、これだけのために
当番が割り当てられていたらしい。
今はどうなっているのか全くもって不明ですが、保護者の給食当番だけは
なさそうに思います。そんな義務なんぞ負ってはいません、なんてがなり
立てるモンスターペアレントが蔓延っていますからね。
現在の大森第一小学校には、ランチルームと称する立派な食堂があって、
デザートも付くホテルの昼食と見紛うような献立。
それでも食物アレルギーだとかうるさいことがあって、栄養士も調理人も
配膳係も給食当番も、それぞれに面倒なんだろうな、と。
過保護もモンスターも存在しなかったあの頃の方が、たとえ僕のような偏食
児童がいたにせよ本人はさほどの不満を感じていなかっただろうし、幸せな
時代だったのかも。
隣家の染井吉野がぽつりぽつりとほころび始めました。今年の開花予想は
「平年並み、又は平年よりも遅め」だそうですが、春先の気温に左右される
と云いますから、例年よりもやや遅めになっているのでしょう。
我らが母校の校章には、花弁が5枚の桜花がデザインされていますが、それ
が染井吉野かどうかまでは定かではありません。
その五弁の美しい形状からして染井吉野のように思うのですが、樹齢が短
いということもあり、どうなんでしょうか。
なお、校章は大正9年4月1日に制定されたそうです。
そろそろあちこちで入学式が催されますが、咲き誇る中でのものとはなりそ
うにありません。
僕らの入学式のときはどんなだったのだろう、ちっとも覚えておりません。
学校の入学式はマチマチですが、入社式は殆どが今日。僕のときには、小雨
そぼ降る中、行われたと記憶しています。
赤坂の本社ビルには、当時四百有余もの新入社員を収容できる会場を用意する
ことが出来ず、本社ビルから大分離れたところ(隣の千代田区)にある砂防会館
で挙行されました。
銀製の社章を襟に付けたときの喜びは今も鮮明に記憶に残っています。
さて、ここからが本題。
新入社員として、出社前のおまじないは「ハトが豆くってパッ」。
研修期間が3ヶ月ほどもありましたから、学生気分の延長なのですが、それ
でも心構えとして身だしなみにはやはり気を使います。
そこでおまじない。
「ハ」・「ト」・「が」…と、一つひとつ口にしながら背広のポケットなどを
弄る。「ハ」はハンカチ、「ト」は腕時計、「が」はがま口(つまり財布)、「ま」
は万年筆(要するに筆記具)、「め」は名刺入れ、「く」はクシ、「て」は手帳、
「パ」はパス(つまり定期券)と、胸や腰や腕を叩いたり眺めたりして確かめて
からいざ出陣となるわけです。
学生気分の延長とは云え、遅刻は許されません。
当時の研修所は東京と大阪に分かれていて、東京は茅場町の山種証券ビルの何階
かを借用していました。そこまで京浜急行、山手線、地下鉄千代田線と乗り継い
で9時までに駆け込むのですが、その慌ただしい出勤前、後でハトが豆鉄砲を
食ったようなことにならないよう、日課として呪文を唱える。
今でも忙しいときには、忘れ物をすることは滅多に無いのですが、時間的に余裕
があると却って何かを忘れたりします。呪文はとうに唱えなくなりましたが、
習い性はしっかり染み付いているようで。