
「物理学校」(漱石つながりで)
この写真は、明治39年(1906)9月29日、牛込区神楽町2丁目24番地の地に、
木造2階建てとして新築された東京物理学校の校舎を、その後身である東京理科大学
が、というより東京物理学校の卒業生の一人二村氏からの建設費寄贈によって、平成
3年(1991)に、創立110周年を記念して復元されたものです。
復元といっても、設計図が残っていたわけではなく、当時の写真を頼りに、それこ
そ手探りで造ったそうです。当時の総面積は226坪(約746㎡)で、器具、設備
を合わせて総工費38,192円(現在だと、約5億1000万円)だったとのこと
ですが、それらと比べてどうだったのでしょうか。
復元された建物は、東京理科大学が運営する「東京理科大学近代科学資料館」として、
神楽坂校舎の左手横道を入って行ったところにあり、東京物理学校から引き継がれた
書物や機器等が展示されています。それに館長は、TVでもお馴染みの数学者秋山 仁。
興味のある方は、以下のURLで。
http://www.sut.ac.jp/info/setubi/museum/
さて、漱石の『坊ちゃん』。
両親に死に別れた坊ちゃんですが、商業学校を卒業して九州の支店に勤務することに
なった兄が、家屋敷から家財道具の一切合財を売り払って、そのうちから600円を
手渡して自由に使えというので、
“六百円を三に割って一年に二百円宛使えば三年間は勉強が出来る。三年間一生懸命に
やれば何か出来る。夫からどこの学校へ這入ろうと考えたが、学問は生来どれもこれも
好きでない。ことに語学とか文学とか云うものは真平御免だ。新体詩などと来ては二十
行あるうちで一行も分らない。どうせ嫌なものなら何をやっても同じ事だと思ったが、
幸い物理学校の前を通り掛ったら生徒募集の広告が出て居たから、何も縁だと思って規
則書をもらってすぐ入学の手続をして仕舞った。今考えると是も親譲りの無鉄砲から起
った失策だ。
三年間まあ人並に勉強はしたが別段たちのいい方でもないから、席順はいつでも下から
勘定する方が便利であった。然し不思議なもので、三年立ったらとうとう卒業して仕舞
った。自分でも可笑しいと思ったが苦情を云う訳もないから大人しく卒業して置いた。”
とあります。
ちなみに、僕が持っている『坊ちゃん』(新潮文庫)は、昭和37年4月30日四十三刷
(定価50円)とありますから、中学生のときに読んだようです。
でも、その物理学校が5年後に入学した大学の前身であったことを知ったのは、入学時
に貰った小冊子「学園生活」を見てから。
大体が、大学選びに迷っていたときに、仲の良かった級友が見ていた学校案内を覗き込
んで、僕も受けてみようと思ったくらいですから、無鉄砲と云う点では、坊ちゃんとは
五十歩百歩。
その「学園生活」の中に、
“東京物理学校の神楽坂移転は、今まで学校のなかった場所だけに、周囲にいろいろの
逸話を残した。夏目漱石の『坊ちゃん』の主人公は、東京物理学校の門前を通りかかって、
ついふらふらと入学してしまう。この小説の発表は明治39年で、牛込に住む漱石は建
築中の本校の門前をたびたび通ったので、それを「坊ちゃん」のなかで使ったのだろう。”
とあります。
漱石は『坊ちゃん』を1週間ほどで書き上げていますが、果して坊ちゃんはこの白亜の
校舎の前を通りかかって入学したのでしょうか?
詳しくは、コメント欄で。



















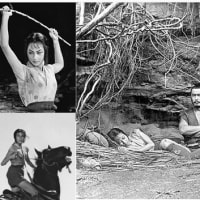
結論から云うと、坊ちゃんが入学したのは、写真にある白亜のしゃれた校舎では
ないと。なぜなら、『坊ちゃん』が最初に掲載されたのは雑誌『ホトトギス』で、
それは明治39年の4月号。
物理学校が牛込区神楽町2丁目24番地に校舎敷地約394坪(約1300㎡)を
購入したのは、前年の11月のことで、竣工が翌年9月ですから、3月~4月は、
未だ工事半ば。
その工事現場を漱石が通りかかって、坊ちゃんを物理学校卒業生にする着想を得
たという可能性は極めて低いと思います。なぜなら、漱石が、小石川区(文京区)
西片町10から神楽坂に近い牛込区早稲田南町に移ってきたのは、明治40年9月
のこと。それに『坊ちゃん』執筆当時は、神楽坂からは大分離れた駒込千駄木町
に居を構えていたのですから。
構想を温めていたからこそ、1週間といった短期間で書き上げることができたの
だと思いますし、実際、漱石と物理学校の係わりは、それよりずっと以前にあっ
たのです。
その辺りのことをこれから見て行くことにしましょう。
文藝春秋社から刊行された『この国のかたち』(全6巻)という本があります。
司馬遼太郎が1986年から1996年にかけて雑誌「文藝春秋」の巻頭随筆欄に
連載してきたものを、6巻に分けている。第1巻は1986~1987年のものが
収録されてあって、1990年3月25日に第1刷が出版され、第6巻は1996年分
が収録されていて、第1刷は1996年9月10日に出ている。一定の枚数がたま
ると、そのつど本になったことが分かる。
その第3巻(1990~1991、1992.5.25第1刷)の中に「文明の配電盤」と題する
ものがあって、以下のように記されています。
“まことに明治初年、西欧文明受容器の日本は一個の内燃機関だった。
その配電盤にあたるものが、東京帝国大学(以下、東京大学)で、意識して
そのようにつくられた。いまでもこの大学に権威の残像が残っているのは、
そのせいである。(中略)
神田には江戸時代から文武の私塾が密集していて、明治後、いっそうふえた。
そのうちのいくつかが、こんにちでは総合大学、もしくは単科大学になって
いる。
これは、明治の配電盤と関係がるのではないか。
幕府の洋学機関開成所は神田一ツ橋におかれ、それが明治後、東京大学に
発展した。やがて本郷台にうつるこの大学は、明治初年は右の神田一ツ橋
から出発した。神田はいわば地元だった。
自然、国力を傾けてつくられたこの巨大な配電盤は、地元の神田の私学に、
いわば漏電するようにして、"新文明"をこぼした。
そのなかで高貴ともいうべき例がある。神田に設けられた私学の一つ東京
物理学校(こんにちの東京理科大学)のことである。
明治初年、東京大学の理工系を出た人達には、国家のカネによって学問を
さずかったということで、恩恵を感ずる人が多かったらしい。
とくに明治十二年(一八七九年)前後の理学部物理学科の卒業生にその意識
がつよかった。
かれら二十一人は、同盟を結び、報恩のために一私学を興そうと申しあわせた。
ただし、金がないために当初は他の学校の校舎を間借りした。さらには、夜学
にした。
明治十四年における東京物理学校の出発である。
資金はすべて"配電盤"である右の学部の卒業生たちの拠金によった。かれらは
維持同盟を結び、その規約のなかで、
「会員は三十円を寄付すべし」
という項目を設けた。当時、下級官吏が月に十数円をとればいいほうだったから、
この額は安くなかった。ただ、月賦もゆるした。月賦の場合、一円以上は納よ、
とある。むろん寄付の見返りはなく、まったく無償そのものであった。
もっとも、理学部卒業生は官庁などに就職していて、すくなくとも四十円はとって
いたから、月々一円を割くことは、過重とはいえなかった。(中略)
物理学の教授や研究には、実験用機械など膨大なカネが要る。それらは当時東京
大学しか所有しておらず、維持同盟のひとたちの毎月一円以上の拠金でなりたって
いる東京物理学校にあっては、そんなものを買う金はなかった。
この事情を東京大学理学部はよく理解した。
そこで、日中、大学がそれらを使用すると、夕方から物理学校へそれらを大学の
使丁が運搬したという。このことは、毎日、数年もつづけられた。官物が私的に
つかわれることはゆるされることではないのだが、あえて大学はこの便法をとった。
配電盤が、国家の将来のために志をもって漏電していたのである。(後略)”
明治14年(1881)9月11日に、日本で最初の私立理学学校として誕生したときの名称は、
東京物理学講習所でした。その校舎は自前のものでなく、東京府麹町区飯田町4丁目
1番地(現在の千代田区九段下)の稚松(わかまつ)小学校の教室を夜間だけ間借りすると
いうものでした。
最初は、物理学だけでしたが、翌年9月からは算術、代数、幾何の三教科をも教授
するようになりました。椅子や机のサイズは小学生用の小さなものだし、電燈が普及
していなかったこともあり、石油ランプを使用しての授業ですから、さぞかし苦労
したものと思います。
東京物理学校と改称するのは、明治16年9月のこと。このときには自前の校舎があり
ました。前年の9月頃だと思えるのですが、神田区小川小路三丁目九番地に建坪30坪の
教室と小使い室をつけただけの小さな校舎を建てたのです。もちろん創立に加わった
21名の先生たちの拠出金でです。
この地に校舎を構えるまで、稚松小学校から神田区錦町の大蔵省簿記講習所へ移り
(明治14年暮れ)、さらに本郷区元町2丁目の進文舎に転居(明治15年)しています。
司馬先生の「神田の地」とあるのは、この自前の校舎での東京物理学校としての出発
を指します。
でもこの校舎、明治17年(1884)9月15日の台風により倒壊してしまうのです。
それでまた、あちこちでの間借りを余儀なくされます。
明治17年9月、麹町区九段坂下牛ヶ淵にある共立統計学校を間借り。
明治19年9月、神田区駿河台淡路町の成立学舎に移転。
そして、明治19年11月、神田小川町1番地の仏文会校舎を借りるようになります。
それも又借り。持ち主は、東京法学校(法政大学の前身)で、左右対称のレンガ建て平屋
の右半分を東京法学校が使用し、左半分を仏語学校である仏文会が借りて使用していた
のですが、仏文会の方は昼間だけの授業であったことから、夜間は物理学校が借りること
にしたのです。
この建物、明治10年代初期に建てられた缶工場だったものを東京法学校が購入して使っ
ていたもので、窓が少なく室内は暗かったと云います。また内部は相当荒廃していたの
で、生徒たちはトンネル学校とか北極学校と呼ぶようになったそうです。北極点ではそれ
以上北が無いので「北ない極み」、つまり「汚い極み」という意味です。
明治22年から数学の教師を勤めた野口保興という人が、回顧譚として、「小川町ノ
校舎如キ婉然罐工場ノ感アリテ教場ノ傍ニ便所ガアツテ講義スルトキナド随分臭イ思
ヒヲナシマシタ」と語っている。
そのような校舎でも、物理学校にとっては大金だったのでしょうけど、2,200円(現在
だと5,000万円位)で購入します。明治21年12月のことでした。
東京法学校の移転に伴い、購入話が出たようですが、全棟を購入したわけではなくて、それ
まで使用していた左半分だけ。(右半分は、活版工場に売却された。)
建物の真ん中に廊下があって、その両側に区切った教室があったようで、その面積は合わせて
105.5坪。そこにかなりの数の生徒(明治20年の入学者237、21年の入学者は520)
が学んでいたので、かなりのすし詰め状態であったわけです。
で、これを解消すべく、明治30年2月の入学生からは昼夜のクラスに分けられるように
なりますが、校舎の方は明治28年に物理実験室を増築したぐらいで、明治39年神楽坂に
移るまで殆ど手入がなされない有様でした。
明治30年9月にガス灯が取り付けられるまでは、石油ランプを吊るしての勉学。電気照明
になったのは、神楽坂の校舎になってからのこと。
神田区駿河台南甲賀町(現千代田区神田駿河台一丁目)の校舎に毎週(講師として)通っていま
した。そして、この校舎と物理学校は距離にして400mほどしか離れていませんでした。
漱石が『坊ちゃん』の舞台となった愛媛県尋常中学校教諭(明治28年4月赴任)をたった1年
で辞めて、明治29年4月に赴任した熊本の第五高等中学校の当時の校長は、司馬先生の云う
「維持同盟を結んだ」16名の一人である桜井房記。
最初の創設メンバー21名のうち、2名は中退者であった(理学士でなかった)ため、維持同盟
参加を辞退。あとの2名はいずれも肺結核で病没。
桜井は、漱石が明治33年に英国留学を国から命じられたとき、心配する漱石の相談に乗ってや
ります。桜井が英国と仏国にかって留学した経験があったからです。
さらに、漱石の小石川区西片町の家の近所に住んでいて、漱石と昵懇の中であったのが、やはり
維持同盟メンバーの一人、中村恭平。中村は、『坊ちゃん』が世に出るころ、東大助教授の他に
学生監を兼務していて、東大総長の山川健次郎(「八重の桜」にも出てくる人物です。初め白虎隊
に組み入れられたものの、15歳であったため幼少組に格下げとなって、籠城して戦いました。)
の秘書役でもあったことから、明治大学だけでなく東大文学部英文科の講師も務めていた漱石と
親交を結ぶようになったのだろうと思います。
もう一つ、漱石を触発したエピソードとしては、漱石と同じ名前の小倉金之助が挙げられます。
小倉は、『坊ちゃん』が書かれた前年の明治38年に物理学校を卒業し、直後に東京帝国大学
理科大学化学選科に入学したものの、悪性の風邪に罹り療養のために、中退して故郷山形に帰郷
せざるを得なくなります。小倉は、後(大正5年)に、東北帝国大学から理学博士号を授与され
るほどですから、その英才を惜しむ話が漱石の耳にも入った可能性があります。
以上から、愛媛県尋常中学校(松山中学校)教諭時代のことを小説に使おうとしたした漱石は、
『吾輩は猫である』と同様に自虐趣味を存分に発揮して、自身を赤シャツに譬えて、主人公に
物理学校卒の坊ちゃんを配したのだと思うのです。
そのためには、当時の物理学校のことを一通り情報収集しておく必要がある。で、神田小川町1番地
の物理学校に何度か立ち寄ることがあった筈なのです。(工事中の牛込区神楽町2丁目24番地へ
行っても誰もいませんからね。)
ですから、“幸い物理学校の前を通り掛ったら生徒募集の広告が出て居た”とあるのは、赤レンガ
の小川町校舎のこと。それに、坊ちゃんが、そのときに下宿していたのは“しばらく前途のつく迄
神田の小川町に下宿していた。”、“俺は四畳半の安下宿に籠って”、“此三年間は四畳半に蟄居
して”とあるように、神田小川町。
つまり、物理学校の近所に下宿していたことにしてあるのです。それならいつも通って目にしている
物理学校に生徒募集広告が貼り出してあって、それが目に留まった、というシチュエーションも納得
の行くものになります。
の話が出てきますので、漱石自身が赴任した明治28年4月と同じ設定にしてありますから、同年
2月17日になります。
そうだとすると、明治25年に入学したことになりますが、その年の物理学校入学者は707名、
それが明治28年の卒業生となると、たったの34名になるのですから、小説にあるように、
“三年間まあ人並に勉強はしたが別段たちのいい方でもないから、席順はいつでも下から勘定する
方が便利であった。然し不思議なもので、三年立ったとうとう卒業して仕舞った。”
というほど進級、卒業は簡単なものでは無かったのです。つまり坊ちゃんは成績優秀だった。
ちなみに、物理学校は、明治24年に規則を改正し、修業年数をそれまでの二年から、二年半
として五学期制をとっています。ですから入学したのは明治25年の9月になる勘定です。
(生徒募集は夏の暑い盛りに貼り出してあったことになります。)
坊ちゃんが“六百円を三に割って一年に二百円宛使えば三年間は勉強が出来る。”と云っている
のも、600円は現在だと約800万円ですから、1年あたり260万円強で考えているわけで、
授業料五学期すべてで27円(現在だと35万円ほど)の出費と、四畳半の安下宿の部屋代と、
あとは食費等ぐらいですから、十分やって行けたのです。
だから、
“卒業してから八日目に校長が呼びに来たから、何か用だろうと思って、出掛けて行ったら、四国
辺りのある中学で数学の教師が入る。月給は四十円だが、行ってはどうだと云う相談である。”
と教師の口、それも40円(現在だと、50万円以上の初任給と云うことになります)。
漱石自身は、校長の月俸が60円だと云うのに、80円だったのですが。
先述の「学園生活」にある
“牛込に住む漱石は建築中の本校の門前をたびたび通ったので、それを『坊ちゃん』のなかで使った
のだろう。”
は眉唾ものでしたが、
“東京物理学校の神楽坂移転は、今まで学校のなかった場所だけに、周囲にいろいろの逸話を残した。”
とあるのは本当。
啄木の明治41年10月29日の日記に「北原君の新居を訪ふ。吉井君が先に行ってゐた。二階の
書斎の前に物理学校の白い建物。瓦斯がついて窓という窓が蒼白い。それはそれは気持ちのよい色だ。
そして物理の講義の声が、琴や三味線と共に聞える。・・・」とありますが、北原君というのは詩人
北原白秋のことで、白秋が物理学校裏に引っ越してきたのは啄木が訪れた少し前のこと。
白秋の目にも物理学校は奇異に映ったのでしょう。詩集『東京景物詩及其他』(明治四十三年三月)で
「物理学校裏」と題する奇っ怪な詩を発表しています。
やたら長いし、全部書くと読む方も頭が痛くなるので、一部だけ紹介します。
“C2H2O2N2+NaOH=CH4+Na2CO3……
蒼白い白熱瓦斯の情調(ムウド)が曇硝子を透して流れる。
角窓のそのひとつの内部(インテリオル)に
光のない青いメタンの焔が燃えているらしい。
肺病院の如(やう)な東京物理学校の淡(うす)い青灰色(せいくわいしょく)の壁に
いつしかあるかなきかの月光がしたたる。”
うーむ、これだけでも頭が痛くなる。
えっ、いままで読んできて頭が痛くなったって?
兆しも無いのに例年より早い梅雨入り宣言がなされ、梅雨らしくない日々が続き、
その実感もわかないうちに例年より2週間も早い梅雨明け宣言となりました。
さて、『坊ちゃん』では、仕入れた情報の扱いに齟齬があったようで、小説の舞台と
なった明治28年と、それが執筆・発表された明治39年とが、漱石の中でごっちゃ
になっています。
坊ちゃんは、物理学校を卒業して直ぐに、中学校教師の口が掛かりますが、教員検定
の試験を受けずとも、卒業と同時にその資格(無免許教員ですが)が与えられるよう
になるのは、明治33年3月の「教員免許令」が発令されてからです。
そこには「文部大臣ノ定ムル所ニ依リ免許状ヲ有セサル者ヲ以ツテ教員に充ツルコ
トヲ得」といった但し書きがあった。
先に挙げた小倉金之助(明治38年卒業)も、その著書『数学者の回想』の中で
「世間に信用のある優良な卒業生を出そうというので、試験は相当に厳格でありま
した。維持員先生の中には文部省の中等教育検定試験委員がかなり沢山おったので
あります。そういうことから、おのずから中等教員を志願するものが多くなりまし
た。」とある。
坊ちゃんは、数学教師山嵐と一緒に教頭赤シャツと図画教師野だいこをやっつけて、
学校に郵便で辞表を送って、東京にとっとと帰ってきてしまって、“其後ある人の
周旋で街鉄の技手になった。”とあります。
その“其後ある人の周旋で街鉄の技手になった。”とあるのが、漱石の今一つの齟齬
で、街鉄つまり東京市街鉄道株式会社が設立されたのは、明治36年のことなので、
“その後”といっても、坊ちゃんは8年近くもプータローということになってしまい
ます。
それに続いて、“月給は二十五円で、家賃は六円だ。清は玄関付きの家でなくっても
至極満足の様子であったが、気の毒な事に今年の二月肺炎に罹って死んで仕舞った。”
とありますが、街鉄は、『坊ちゃん』が『ホトトギス』に掲載されたその年に、東京
電車鉄道・東京電気鉄道と合併して東京鉄道株式会社となってしまうので、清が亡く
なった二月には、街鉄そのものも無くなってしまっているのです。もっとも預言者な
らぬ漱石にそこまで求めるのは酷ですが。
それから、「技手」ですが、先に引いた司馬遼太郎の「文明の配電盤」には、
“当時、官庁の技術畑に、技師と技手(まぎらわしいために"ぎて"ともいった)の区別
があった。
技師は、西洋の工学技術を身につけた人で、具体的には明治中期までは東京大学の
理工系の出身者にして官庁に奉職している人のことをいった。ついでながら、明治
三十一年の「技術官俸給令」では"技師は奏任とし、技手は判任とす"とあり、まこと
におもおもしい。
技師は高等官であり、高等官とは、旧幕府の制度でいうと、将軍に御目見得できる
身分のことで、旗本がそうであった。
おなじ幕臣でも御家人は御目見得できないから、明治の判任官にあたる。”
とあります。ですから、25円(現在だと31万円ほど)は、妥当な線です。
さて、その後の物理学校ですが、大正12年(1923)9月1日午前11時58分、伊豆大島、
相模湾を震源として発生した関東大震災でも、神楽坂の校舎は、実験室の戸棚が倒れて
器具類が壊れり、教室の中の机や椅子がひっくり返ったりはしましたが、たいした被害を
受けませんでした。
昭和に入って、物理学校は神楽坂の校舎周辺の土地を次々と購入し、総校地は1200坪
(約3960㎡)にもなります。当初の3倍にもなったわけです。が、やはり狭い。
狭いながらも、昭和12年10月18日に鉄筋コンクリート4階建て(一部5階建て)、
延べ面積2291坪(約7560㎡)、総工費およそ38万円(約2億円)の校舎を新築
します。
僕が入学したとき(昭和42年)には、学部・学科が新設されるたびにそうなったのでしょう
けど、校舎が付足し付たしのような形で建てられていましたが、昭和12年に建てられた
校舎は、旧1号館として、そっくりそのまま残されていました。
昭和20年5月25日の東京大空襲の戦災では周りは被害を受けたのに、校舎は石炭庫を
焼いただけで、その殆どが無事であった。
そこには階段教室(1階)があり、教養課程のときには利用しました。それから学生課とか
生協(いずれも地下1階)もあったので、とくに生協はよく利用しました。それと当時1万
円という高額な実習費を支払ったコンピュータルームもありましたね。
そういったところに出入りしていたわけですが、ともに1回こっきりしか行かなかったところ
がありました。それは図書館と屋上。
どちらも迷路のようなところを通って辿り着いたのですが、なぜに屋上かというと、そこに
知る人ぞ知る小さな社があったからです。
その名も、誰が名付けたか、「落第神社」。実際は、御真影や教育勅語謄本などを奉安する
ための奉安殿なのですが、物理学校は進級が難しかったので、こぞって落第しないようにと
祈願した。にもかかわらず、落第する学生が多かったから、そのように呼ばれたそうです。
僕は、願掛けも何もしなかったけど、
“然し不思議なもので、四年経ったらとうとう卒業して仕舞った。自分でも可笑しいと思った
が苦情を云う訳もないから大人しく卒業して置いた。”
と相成りました。
各種学校から始まり、大正6年(1917)3月26日に専門学校となり、昭和24年2月21日に
東京理科大学として認可され、昭和24年4月、学制改革により、新制大学に移行して現在に
至ります。
昭和26年3月10日が、物理学校最後の卒業式となった。偶然にも通算100回目。
そして、3月31日、物理学校の幕が下ろされた。
戦後のベビーブーム(僕ら団塊世代です)が大学に進学するようになると、猫の額のような
神楽坂キャンパスでは手狭なので、あちらこちらにキャンパスが分散して造られるように
なります。
昭和42年には千葉県に野田キャンパス、昭和62年には北海道に長万部キャンパス、平成
5年には埼玉県に久喜キャンパス。
そして、今年、擦った揉んだの挙句、神楽坂キャンパスの一部が葛飾キャンパスへ移転。
当初、神楽坂に高い高いビルを建てようと計画したのですが、新宿区の条例がそれを許さず、
代りに当時の理事長が葛飾区への移転計画をぶち上げたのですが、神楽坂を聖地と考えてか、
飲み食いできる旨くて安い店が沢山あるからか、その辺りの事情は詳らかではありませんが、
教員の中から反対の声が上がったのです。
でも、これまでその歴史を見てお分かりのように、「容器より中身」が学校の理念。
どこだろうと、どんな建物だろうと一向にかまわないのです。要は学生が第一。その勉学を
支え伸ばす教師と設備とが整っていればよいのです。その意味では、葛飾キャンパスへの移
転は評価できるものだと僕は思っています。
それにしても、都心では
「灯を消せば 涼しき星や 窓に入る」(漱石)
とはならないですね。ここ何十年も彦星と織姫の逢瀬を見たことがありません。
させて頂くと、
戦後のベビーブームの世代(僕ら団塊世代です)が大学に進学するようになると、猫の額の
ような神楽坂キャンパスでは手狭なので、昭和42年に千葉県に野田キャンパスが造られ
ます。
それから、新しい学部ができる度に、昭和62年には北海道に長万部キャンパス(基礎工学
部)、平成5年には埼玉県に久喜キャンパス(経営学部)が造られます。
それから実験等の設備を整えようとすると、神楽坂は上に伸ばすしか手が無く、高い高い
ビルを建てようと計画したのですが、新宿区の条例がそれを許さず、代りに当時の理事長が
葛飾区への移転計画をぶち上げたのですが、神楽坂を聖地と考えてか、飲み食いできる旨く
て安い店が沢山あるからか、その辺りの事情は詳らかではありませんが、教員の中から反対
の声が上がったのです。
擦った揉んだの挙句、今年、神楽坂キャンパスの一部が葛飾キャンパスへ移転したのですが、
これまでその歴史を見てお分かりのように、「容器より中身」が明治14年以来の学校の理
念・伝統。
どこだろうと、どんな建物だろうと一向にかまわないのです。要は学生が第一。その勉学を
支え伸ばす教師と実験等の設備とが整っていればよいのです。その意味では、必要な設備の
整った葛飾キャンパスへの移転は評価できるものだと僕は思っています。
ここ何十年も彦星と織姫の逢瀬を見たことがありません。
とも書きましたが、一昨日の飲み会で、Kくんが、これを読んでそのようなことを云ったの
かどうか定かではありませせんが、1年経って相見えることができた彦星のようなことを云
ってのけたので、(アルコールの回った)君は、彦星どころか梅ぼしさ、テカテカ光り輝い
ているから1億何千万年に1回、近くを通り過ぎるだけのハゲー彗星かも知れないな、と云
ってやろうと思ったのですが…、江戸っ子じゃない僕には、そんな啖呵を切ることなんぞ
できゃせんぞな、もし。
なんと読むかって?
「いりやまず」と読みます。漢字変換でも「いりやまず」と入力して変換キーを
押すと、「不入斗」が出てきます。
『ことばの歳時記』(金田一春彦)によると、
“これは「不入計」と書くべきもの、ここのあがりは税金に計算しないという有
難い土地だったのが、「計」の字の草字体が「斗」と書きあやまられ、今の「不入斗」
が出来てしまったという。”
とありますが、「計」の草書体は、ひらがなの「け」(基になった?)に近いので、
どう見誤れば、「斗」(草書体でもその形にさほどの違いは無い)になるのかしらん。
それに、ネットで調べてみたところ、語源には諸説あって、「不入計」の漢字誤読に、
「不入計」(いりよまず)の読みが訛って「いりやまず」となった説もあれば、
「昔は海岸地帯で土地は塩分のため田畑は殆ど収穫を上げることが出来ず、為政者が
耕作奨励の意味を持って貢税免除を宣言して不入斗村と称したと云われています。」
もあれば、「不入斗」を「いりやまぜ」と呼ぶ地名があることから、元は「入山瀬」
とか「入山津」とかであって、谷口集落を表すものであると云う説もあるし、
さらには、神社の領地であったために討ち入る事が禁じられていた「不入討」説なん
てものもある。
要するにいずれが正しいのか分からないのですが、ネットの住人が調べた興味深い
ものもあります。
それによると、「不入斗」では、
・千葉県市原市の「不入斗村」
・同県富津市の「不入斗村」
・同県富山町(現南房総市)の「不入斗村」
・東京都大田区の「不入斗村」
・神奈川県横須賀市の「不入斗村」
・静岡県袋井市の「不入斗村」(これだけが「いりやまぜ」と読む)
があり、さらに「入山瀬」や「入山津」だと、
・千葉県長生村の「入山須村」(現在の地名は入山津)
・神奈川県平塚市の上入山瀬村、下入山瀬村
・静岡県富士市の入山瀬村
・静岡県大東町(現掛川市)の入山瀬村
があり、
それらの場所を地図上に配置してみたところ、駿河から上総にかけて海岸線を結ぶもの
であることを発見したそうです。つまり、「入り組んだ山の瀬が連なるリアス式の海岸
地形を示す、入山瀬説」ではないかと。
でも、リアス式では無いと思うし、海岸線を結ぶということでは、「土地は塩分のため
田畑は殆ど収穫を上げることが出来ず、為政者が耕作奨励の意味を持って貢税免除を
宣言して不入斗村と称した」という方が理に適っているように思うのですよね。
した中にも東京都大田区の「不入斗村」とあります。
現在の地図には見当たらないので、調べてみたところ、昭和2年(1927)の口絵によ
ると、北に大井村、南に大森村、東に東京湾、西に新井宿村に囲まれた地域になり
ます。
現住所だと、不入斗村の字「八幡、潮田」が大森本町一丁目、大森北二、三丁目。
字「谷沢、谷中、川添」が大森北三~六丁目、字「中」が大森北一、三、四丁目、
字「高田、堀後、根岸の一部」が大森北一~四丁目となっているそうです。
その口絵が当時の状態を表したものかというと、そうではなくて、
・1889年(明治22年)5月1日 - 町村制の施行に伴い、不入斗村、新井宿村が合併して
入新井村が発足。
・1919年(大正8年)8月1日 - 入新井村が町制施行して入新井町となる。大字名は、
旧不入斗村が入新井、新井宿村が新井宿となる。
とありますから、明治22年以前の状態を口絵にしたものであることが分かります。
「不入斗」の名は、大正8年を境にして、地図から消滅してしまったわけですが、現在
でも平和島近辺にある公園や会社に、わずかではあっても、その名を留めています。
僕ら大森第一小学校を母校とする面々は、大半が旧大森村に住まいしていたことになる
のですが、さらに江戸の昔には、西大森村、東大森村、北大森村とに分かれていたそう
です。そしてそれらが明治5年(1872)に合併して大森村になったとあります。
嘉永6年(1853)の黒船来航で沿岸警備の必要に迫られた幕府が築いた台場の一つは、
僕らが写生に行ったことのある、旧大森ガス会社(現「ジャックニコラスゴルフセンター
大森」大森東3丁目28-1)の所にあったので、東大森村だったのでしょう。小学校
のある所もね。
この稿を興すきっかけとなった『ことばの歳時記』の項は、7月16日付の「そうめん」
と題するもので、
“ソウメンは漢字では素麺と書かれる。ソメンがソーメンとのびたのかと思うと、さに
あらず、もとこれは「索麺」と書いた。それをそそっかしい人がいて、「索」を「素」と
書きまちがえたのが起こりだそうだ。”
“宮中の古い儀式のことなどに詳しい人を「有識」と書いてユウソクと読むが、「職を
持つ」では意味がない。これは「有識」と書くべきものをやはり字をあやまったもの
という。”
“文字を知らない人のことを「目に一丁字(いっていじ)ない」というが、この「丁」は
元来片仮名のケを書いたもので「箇」の省画、一箇の字も知らないの意味だったが、
いつか「一丁字」と書かれるようになった。”
広辞苑によると、「一丁字」とは、「丁」は「个(か)」の古い書体を誤読したもの
(「个」は「箇」に同じ)で、一つの文字のこと。
と、それぞれの語源を正すものとして、「不入斗」も採り上げているわけです。
ともあれ、
ソメンでも、のびたソーメンでも、どっちでも良いから、素麺が食べたーい!
「日盛りや つるつる啜る 白き涼」(鈍末)
今日の午後、以下の記事がネットに掲載されていました。(そのまま引用)
“菅元首相が安倍首相を提訴 原発事故めぐり「メルマガで中傷記事」
民主党の菅直人元首相は16日、国会内で記者会見し、東京電力福島第1原発事故をめぐり、
安倍晋三首相が「菅総理の海水注入指示はでっち上げ」と題したメールマガジンを配信し、
現在もネット上で掲載しているのは名誉毀損(きそん)だとして、安倍首相に対し、該当する
メールマガジンの削除と謝罪を求め提訴したことを発表した。
安倍首相のメールマガジンは平成23年5月20日付配信。首相は「東電はマニュアル通り淡水
が切れた後、海水を注入しようと考えており、実行した。しかし、やっと始まった海水注入を
止めたのは、何と菅総理その人だった」と記載。その上で「海水注入を菅総理の英断とのウソを
側近は新聞・テレビにばらまいた」としている。
菅氏は「内容は全くの虚偽の情報に基づく。私の名誉を著しく傷つける中傷記事だ」と述べた。”
「つぶやきの部屋13」の中の「団塊の世代雑感(104)」「同(105)」と、安倍首相のメル
マガとはちょっと違うところがあるのですが、いずれにせよメルトダウンにビビった菅元首相が
注水を止めさせたことだけは確か。
またもや民主党の得意技「ブーメラン」(「ブーメラン」って、やぶへびのことですが)で終わるの
でしょうね。
これで確実に「カン」に「ア」の冠詞が付く。不逞菅氏が、ね。
♪ブーメラン ブーメラン ブーメラン ブーメラン
きっとあなたは 戻って来るだろう
カリッと音がするほど 小指をかんで
痛いでしょう 痛いでしょう
忘れないでしょう
そんなこといったあなたの後姿が
もうやがて見えなくなる 見えなくなる