
「物理学校」(漱石つながりで)
この写真は、明治39年(1906)9月29日、牛込区神楽町2丁目24番地の地に、
木造2階建てとして新築された東京物理学校の校舎を、その後身である東京理科大学
が、というより東京物理学校の卒業生の一人二村氏からの建設費寄贈によって、平成
3年(1991)に、創立110周年を記念して復元されたものです。
復元といっても、設計図が残っていたわけではなく、当時の写真を頼りに、それこ
そ手探りで造ったそうです。当時の総面積は226坪(約746㎡)で、器具、設備
を合わせて総工費38,192円(現在だと、約5億1000万円)だったとのこと
ですが、それらと比べてどうだったのでしょうか。
復元された建物は、東京理科大学が運営する「東京理科大学近代科学資料館」として、
神楽坂校舎の左手横道を入って行ったところにあり、東京物理学校から引き継がれた
書物や機器等が展示されています。それに館長は、TVでもお馴染みの数学者秋山 仁。
興味のある方は、以下のURLで。
http://www.sut.ac.jp/info/setubi/museum/
さて、漱石の『坊ちゃん』。
両親に死に別れた坊ちゃんですが、商業学校を卒業して九州の支店に勤務することに
なった兄が、家屋敷から家財道具の一切合財を売り払って、そのうちから600円を
手渡して自由に使えというので、
“六百円を三に割って一年に二百円宛使えば三年間は勉強が出来る。三年間一生懸命に
やれば何か出来る。夫からどこの学校へ這入ろうと考えたが、学問は生来どれもこれも
好きでない。ことに語学とか文学とか云うものは真平御免だ。新体詩などと来ては二十
行あるうちで一行も分らない。どうせ嫌なものなら何をやっても同じ事だと思ったが、
幸い物理学校の前を通り掛ったら生徒募集の広告が出て居たから、何も縁だと思って規
則書をもらってすぐ入学の手続をして仕舞った。今考えると是も親譲りの無鉄砲から起
った失策だ。
三年間まあ人並に勉強はしたが別段たちのいい方でもないから、席順はいつでも下から
勘定する方が便利であった。然し不思議なもので、三年立ったらとうとう卒業して仕舞
った。自分でも可笑しいと思ったが苦情を云う訳もないから大人しく卒業して置いた。”
とあります。
ちなみに、僕が持っている『坊ちゃん』(新潮文庫)は、昭和37年4月30日四十三刷
(定価50円)とありますから、中学生のときに読んだようです。
でも、その物理学校が5年後に入学した大学の前身であったことを知ったのは、入学時
に貰った小冊子「学園生活」を見てから。
大体が、大学選びに迷っていたときに、仲の良かった級友が見ていた学校案内を覗き込
んで、僕も受けてみようと思ったくらいですから、無鉄砲と云う点では、坊ちゃんとは
五十歩百歩。
その「学園生活」の中に、
“東京物理学校の神楽坂移転は、今まで学校のなかった場所だけに、周囲にいろいろの
逸話を残した。夏目漱石の『坊ちゃん』の主人公は、東京物理学校の門前を通りかかって、
ついふらふらと入学してしまう。この小説の発表は明治39年で、牛込に住む漱石は建
築中の本校の門前をたびたび通ったので、それを「坊ちゃん」のなかで使ったのだろう。”
とあります。
漱石は『坊ちゃん』を1週間ほどで書き上げていますが、果して坊ちゃんはこの白亜の
校舎の前を通りかかって入学したのでしょうか?
詳しくは、コメント欄で。



















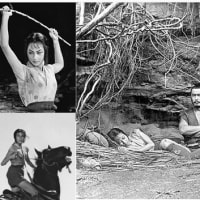
明日、9月7日は、二十四節気では白露(はくろ)に当たります。
それまでの処暑(8/23~9/6、暑さが止み、新涼が間近い日)と秋分(9/23~)
に挟まれたこの期間は、朝夕涼しくなり、草木の葉に宿る露が白く光ると
いう意から白露と名付けられました。夏の終わりを感じさせる美しい言葉
ですね。
9月7日は、白露に当たると云いましたが、正確には「白露の初候」であって、
この日から秋分前日までの16日間が白露になります。
古代中国で考案されたと云う七十二候(しちじゅうにこう)では、二十四節気
をさらに三等分して、それぞれ初候、次候、末候としています。
今年は16日間あるので、次候が6日間となっています。
また、白露の初候は、殆どが9/7か9/8のどちらかですが、2088、2092、2096年
は9/6になるとのこと。
僕のところに掛かっているカレンダーは、「天気のことば」と表題のあるもので、
そこには
“日本には天気を表す言葉が数多にあり、その数は、千にもおよぶといわれて
います。それは、四季が豊かに移ろう日本の、そして、古くから自然との対話
を積み重ね、花鳥風月を身近なものとして愛でてきた、日本人ならではの財産
といえるでしょう。毎日その存在を感じながらも、意識することのない天気の
名前。(以下略)”
とあるように、いずれの日にもそれぞれの名前が与えられています。
例えば、
9月7日(白露の初候)は、「草露白(くさのつゆしろし)」(草に降りた露が白く
光る)。
9月12日(白露の次候)は、「鶺鴒鳴(せきれいなく)」(せきれいが鳴き始める)。
9月18日(白露の末候)は、「玄鳥去(つばめさる)」(燕が南へ帰って行く)。
毎日挙げると大変なので初候と次候との間のものだけを採り上げますと、
9月8日は、「金風(きんぷう)」(秋に吹く風。西風。※五行説では、金は秋や西
を表す)。
9月9日は、「山風(やまじ)」(夏から秋にかけ、山から吹き下ろす風)。
9月10日は、「野分(のわき)」(二百十日頃に草木を分けながら吹く暴風)。
9月11日は、「雨喜(あめよろこび)」(旱天〈かんてん〉の後に降る、恵みの雨。
待ち望んだ雨)。
という具合です。
言葉の一つひとつが美しい響きを持っているだけでなく、その連なりが移ろい
行く季節を的確に表している。
白露も、「しらつゆ」と読んで、露を美的に表現する。日本人って素敵だよね。
「白露や 芋の畠の 天の川」(子規)
て、現代史家の秦郁彦氏曰く。
“終戦直後の東京裁判で、中国の国民政府は軍人の死傷者は320万人だったと明らかに
した。(中略)共産党体制になると、(中略)うなぎ上りに増えていきました”
挙げ句、1995年には、江沢民国家主席(当時)が3500万人という荒唐無稽な数字を発表
したという。
“その後、3500万人のうち死者は1100万人だとしましたが、いずれにしても学説的に
まったく根拠のない数字。さらに、中国に次いで死者が多いとされたのがフィリピン
です。この国が公にしている死者は100万人。被害の最も多い2つの国を足しても、中
沢史観の数字には遠く及ばないのです”
中沢史観とあるのは、原作者中沢啓治の歴史観のこと。
「日本が三光作戦という殺しつくし奪いつくし焼きつくす…」に対して、京都大学の
中西輝政名誉教授曰く。
“戦後、これらの話は中国が、日本軍の極悪非道ぶりを国際的にアピールするために
プロパガンダとして流布させたものです。だいたい「三光」という言葉は日本語では
ありません。中国語で「光」は「~しつくす」という徹底的な行為を表します。70年代
になって、中国から輸入された言葉ですから、あの時代のゲンが話すのはナンセンス”
そして、なぜに後半部分になると、中国によるプロパガンダを鵜呑みにしたような作風
に変わってしまったのか、という本質的な解明が時系列でなされています。
・連載がスタートしたのは『週刊少年ジャンプ』で、1973年6月のこと。
・しかし、1年半後には、オイルショック(紙不足から紙面削減)の煽りを食って、
打ち切りとなる。
・半年後、朝日新聞の社会部の記者の紹介で『市民』(無党派革新層向けの月刊誌)に
掲載。
・しかし、『市民』は1年で廃刊。
・1977年から『文化評論』(日本共産党系論壇誌)に掲載。
・しかし、『文化評論』での連載は、1980年3月に突然の打ち切り。
・2年後、『教育評論』(日教組の機関誌)で連載を再開。この時期に問題となった
第10巻がまとめられた。
単に原爆被害者としての憤りから始まった連載が、それぞれの団体の思想的影響を多分
に受けて、作風が変わっていった。最後は、日教組の主張する反天皇制、自虐史観と
いった、それこそ学習指導要領にある「天皇陛下に敬愛と理解を深めること」に反する
内容にまでなってしまったのですから、教育委員会としての判断に誤りはなかったので
す。それを表現の自由と云うすり替えで、朝日新聞は世論形成し、正義を捻じ曲げた。
日清、日露では慎重な政府を焚きつけて開戦に踏み切らせ、いずれも勝利であったので
得意満面であったものが、大東亜戦争でも同様であったのに、敗戦するや手のひらを返す
ようにして反日的言動を行う朝日新聞。本来なら反米であってしかるべきものが、反日
として矛先ならぬペン先を変える。まさに中国や韓国の反日政策の裏にある拗けた感情
と同じ。
「はだしのゲン」の作者も、純な動機が拗けた磁界によって捻じ曲げられて、意図した
ものとは違った作品になってしまって、さぞや草葉の陰(2012年12月歿、享年73歳)で
無念な思いをしていることでしょう。
昨年12月17日のこと。
それが、終戦記念日の翌日(8/16)に地元紙に「『はだしのゲン』描写過激 松江の
全小中学校「閉架」に」として大々的に報じられるや、例によって、朝日新聞が
大騒ぎ。
8月19日には、「『はだしのゲン、自由に読ませて』電子署名2日で6千人」、
8月20日には、「はだしのゲン、鳥取でも閲覧制限 図書館の事務室に移す」、
そして同日の社説で、「閲覧制限はすぐ撤回を」とやった。
ネットで呼びかけて集めたのは本人確認ができる電子署名ではなく、単なるネット
署名。つまり、ツイッターやフェイスブックを通じてのもの。しかも呼びかけたの
が、松江とは縁もゆかりもない堺市北区の学童保育指導員、樋口徹(55)という人。
何か怪しいよね。全てがうまい具合に連動している。リベラルという仮面を被った
左がかった人たちの常套手段。
で、8月26日、松江市教育委員会落城。閲覧制限を撤回。何とも情けない。
でも、「学校の自主性に任せることになったため、(自由に読める)開架式にしていた
学校では元の運用に戻るとみられる。」と曖昧さが残るため、今もって最初に挙げた
ような投稿を採り上げて(?)、ネチネチと圧力を加える。
で、これからがちょっとは溜飲が下がる記事の紹介。
それは週刊新潮の今週号にある「反戦だから子供でも残虐シーンOKという『はだしの
ゲン』応援団」という特集記事。そこから、朝日等のまやかしを暴く部分を抜粋して
みることにします。
「はだしのゲン」で描かれてあることが真実であり、それを知ることは子どもの
時こそ必要である、と云っているわけです。
後者では、「子供」と「子ども」が混ざっていて、穿った見方をすれば、前者と
別人であることを強調するために、文体だけでなく表現も変えたけど、替え忘れた
ところが残ってしまった(「市教委」という表現も実に怪しいのですが)、という
ことも考えられる投稿ですが、これも松江市の教育委員会が閲覧制限を設けたそも
そもの切っ掛けを、戦争の悲劇という一般化にすり替えることで煙幕を張り、知る
権利は子どもにあり、その及ぼす影響は親の責任に帰する、という極めていい加減
なもの。学校に責任があると声高に叫ぶモンスターペアレンツを見て育った子ども
とは、とても思えませんね。
では、松江市の教育委員会が何を問題にしたのか、ですが。
もともとは、昨年8月のこと。市内に住む男性からの市議会への陳情があって、市
議会で審議の結果、不採択になったものの、教育委員会に丸投げされたのです。
その陳情というのは“子供に間違った歴史認識を植えつけるので、小中学校から
撤去すべし”というもので、教育委員会では単行本全10巻を読んで、後半部分に
子供の発達上、悪影響を及ぼす描写があり、一部のみの閲覧制限にすると、検閲
になりかねないために、全部を閲覧制限としたそうです。
それが、どの部分かと云うと、
最後の第10巻にある、中学の卒業式で国歌斉唱を先生から告げられたとき、ゲンが
「なんできらいな天皇をほめたたえる歌を歌わんといけんのんじゃ 天皇は戦争犯罪
者じゃ 天皇陛下のためだと言う名目で日本軍は、中国、朝鮮、アジアの各国で約三
千万人以上の人を残酷に殺してきとるんじゃ」と先生に食って掛かるシーンがあり、
さらに「アジア人の首をおもしろ半分に切り落としたり、妊婦の腹を切りさいて中の
赤ん坊をひっぱり出したり、女性の性器の中に一升ビンがどれだけ入るかたたきこ
んで骨盤をくだいて殺したり」として、それらの残虐な描写がなされています。
さらに「わしゃ日本が三光作戦という殺しつくし奪いつくし焼きつくすことでありと
あらゆる残酷なことを同じアジア人にやっていた事実を知ったときはヘドが出たわい」
と云い捨てる、こういったところに問題があると云うわけです。
「あらゆる残酷なことを同じアジア人にやっていた事実を知ったときはヘドが出
たわい」とあるのは、おかしいですよね。ゲンの卒業式は、終戦直後の筈ですか
ら、この後に述べるような中国の反日政策によるでっち上げは未だ無かったので、
有り得ません。
今朝の朝日でも勝利の美酒を舌なめずりするかのごとき意見を、それも
いつものように市民の声を借りて、披露していた。
一つは、「声」欄で、「子どもも戦争の真実は分かる」と題して
“(前略)小学生が「グロ!」と興味本位の読み方をしていたそうですが、大事な
のは、子どもが成長すれば分かると信じ、ありのままを伝えることです。
約30年前、私の子どもと広島平和記念資料館を訪ねました。やけどをして放浪
する子どもの人形など、目をそむけたくなるような展示がありましたが、真実を
知ることは子どもの時こそ必要だ、と痛感しました。感じ方は、子どもによって
違いはあるでしょう。でも、自分と同じくらいの年齢の子どもがどのように生き、
死んでいったかを伝えることは年長者の務めだと思います。(後略)”
(東京、主婦69歳)というもの。
今一つは、「若い世代」欄で、「ゲンの世界 私たち引き継ごう」と題して
“松江市教育委員会が「はだしのゲン」の閲覧制限を撤回したという。「子供の
教育にふさわしくない描写がある」という教育委員会の主張は正しかったのか。
確かに、感じやすい性格で激しい場面を見るとトラウマになってしまう子なら、
読まない方が良いということもあるのかもしれない。しかし、大丈夫な子が多い
だろうし、「ゲン」で戦争の悲劇を知って良かったという子もたくさんいるだろ
う。
親が子供に「ゲン」を読むのを禁止するのは良いと思う。自分の子供の性格を
知っているからだ。だが、市教委のような権力を持つ組織が一律に閲覧を制限す
るのは、権力の行使を軽くみすぎており、あってはならないことだ。
戦争を直接知っている方々が減っている。私たちの世代が戦争に関する本を読
み、戦争の惨禍を伝えていかないといけない。とりわけ、ゲンが生きた世界は、
私たちぐらいの子どもたちが経験したもので、貴重なのだと思う。”
(東京、女子高生15歳)というもの。
昨日、観てきました。
「少年H」と、どちらにするか迷っていたのですが、週刊新潮(夏季特大号)の
「Cinema Selection 夏休み映画24本チェック」では、「終戦の…」の方がわず
かに評価が高かったこと、それと以下の紹介文に惹かれたからかも。
“昭和天皇の戦争犯罪を調査したフェラーズ准将の実話をベースに、人間の尊厳、
正義、そして悲恋を描きこむ。「敗戦国・日本」像に一石を投じる。”
キャッチコピーは、さらに魅惑的で、
“1945年8月、太平洋戦争終結。終戦直後の日本で、マッカーサーが命じた極秘
捜査とは?日本の運命を決めた、知られざるドラマが今、明かされる”
さらに同誌のコラム「福田和也の世間の値打ち」でも、タイミングよく、“主役以外
は絶品だった『終戦のエンペラー』”なんて書いてある。
東条英機役の火野正平、昭和天皇役の片岡孝太郎、関屋貞三郎(元宮内次官であった
貴族院議員)役の夏八木勲は手放しで誉めちぎっていますが、近衛文麿役の中村雅俊
と木戸幸一役の伊武雅刀はちょっと手厳しい。主人公のフェラーズ准将役のマシュー・
フォックスに対しては“知的な佇まいがあって、まさに適役。もっとも、准将として
は、やや若すぎるような気もしますが…。”とありますが、マッカーサー役のトミー・
リー・ジョーンズに対しては“薹(とう)が立っているというか、どう見てもフケ過ぎ
ですね。十歳くらい、余計にフケている。何よりも、缶コーヒーのコマーシャルに出
ている人に、マッカーサーを演じさせるのは、ちょっと無理があるんじゃないか、と
思わざるを得ない。”とボロクソ。コマーシャルまで持ち出して難癖を付ける福田氏は、
何があったのか知らないけど、余程彼が嫌いらしい。
火野正平、東条英機に似ているといえば似ているかも知れないけど、ちょっとの
場面しか出て来ないし、それに一言も発しなかったような…。
以上は実在の人物で、フェラーズ准将と恋仲であったアヤ(初音映莉子)、その叔父
である鹿島大将(西田敏行)とその妻(桃井かおり)は架空の人物。
でも、モデルとなった女性はいたようで、河井道というひと。でも、東京で二人が
初めて会った大正11(1922)年4月は、フェラーズ26歳に対して、道は44歳。
映画でアヤが米国留学から帰国し、女学校の教師であったように、道も米国留学を
終えて女子英学塾(現在の津田塾大学)の教師となっています。(ただし、昭和4
(1929)年4月には恵泉女学園を創設しています。)
道は、キリスト教徒ではありましたが、玉音放送を聞いたときを回顧して、
“この未曾有の国家的危機に際して、…「大道を誤り、信義を世界に失う如き」を戒め
よという天皇の父親らしい戒めに対して、国民は孝心を明らかにして従順に従った
のであった。天皇に対する代々の忠誠心は、塵や埃のように一吹の風にあえなく散っ
てしまいはしない。”
と自伝に書き残していますし、来日してから3週間も経った9月23日にフェラーズが
道との再会で、フェラーズが「天皇を処刑することになったとしたなら、あなたは
どう思うか」と聞いたときに、道は「日本人はそのような事態を決して受け入れな
いでしょう。もし陛下の身にそういうことが起これば、私がいの一番に死にます。
…もし、陛下が殺されるようなことがあったら、血なまぐさい反乱が起きるに違い
ありません。」と答えたそうです。
映画では、この道の役どころを恋人アヤとその叔父鹿島大将にさせているように思
えます。
物語は、8月30日に最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥とその副官フェラーズ
が、専用機バターン号で厚木飛行場に到着したときから始まり、9月27日に昭和天皇
が赤坂のアメリカ大使館へマッカーサーを訪問するまでの約1ヶ月間における天皇
の戦争責任の有無についてのフェラーズの調査(証拠集め)を主軸にしたものです
が、映画ではハッキリさせていないのですが、黒でない証拠を集めることを任務と
していたようです。
実際、フェラーズは日本に到着するや、河井道の消息を求め、上述したように、道
の意見を求めています。
このことは『陛下をお救いなさいませ 河井道とボナー・フェラーズ』(岡本嗣郎、
ホーム社、2002年刊)に詳述されています。そしてこの本がこの映画の原作にな
っています。
アメリカ本国でも、天皇を平和の象徴として利用することがトルーマン大統領以下
明確な政策となっていて、そのことはマッカーサーにも伝えられていますからね。
フェラーズは、その後、アイゼンハワーに睨まれたらしく、大佐に降格されています。
マッカーサーは、その後、大統領選に打って出るも、共和党候補にすらなれず、朝鮮
戦争では核兵器使用を主張したことや、命令無視で北上したことから中華人民共和国
の参戦を招いたとして、トルーマンによって更迭されてしまいます。
1951年4月19日、退任演説を行ったときに、最後に述べたのが有名な「老兵は死なず、
ただ消え去るのみ」。
1952年にレミントンランド社(武器から髭剃り用カミソリまで幅広く扱っていた)の
会長に収まります。
同社は、世界初の軍用コンピュータENIACをもとに、これまた世界初の商用コンピュー
タUNIVACを取り扱っていましたので、日本の自衛隊にUNIVACが納入された経緯には
そのような背景があったからでしょう。
僕の入った会社は、三井物産とレミントンランド社との合弁会社でしたので、新人研
修、というより入社前研修として、2月の寒いときに、富士の裾野で2泊3日の自衛隊
体験入学をさせられたのも、その関係から。
結構ハードで、物見遊山とは対極のもの。前年までは3泊4日だったそうです。お蔭
で脱走せずに済みました。
閑話休題。
アメリカの映画なので、字幕。(日本語を話しているときは英訳した字幕。)
原題は「Emperor」。(こちらの方が好い。「終戦の」は限定的に過ぎる。)
主な撮影は、ニュージーランドで行なわれたそうで、CGでは無いセットの荒廃とし
た終戦直後の東京が生々しく再現されています。それと、日本国内の撮影としては、
皇居敷地内での撮影を映画としては初めて行っていて、なかなかに厳かなものがあり
ます。
そういった時代の空気は上手く表現できていると思いますが、調査を縦糸に、恋情を
横糸にして紡ぎだす模様がボケてしまっているのが、ちょっとばかし残念。
それでも僕は、睡魔に襲われることもなく、最後までしっかり観ました。で、及第点
をあげてもいいかな。
今朝の天声人語。
“明治の落語界の大看板だった三遊亭円朝は「牡丹灯籠」などの
怪談ものを自作した。(中略)
▼ところで、幽霊とお化けは、似ているようで違うらしい。お化け
はたいてい決まった所に現れて、誰彼なしにおどかす。片や幽霊は、
うらむ相手を狙って出る。民俗学の柳田国男が「妖怪談義」で述べて
いる▼さらに、幽霊は丑三つの鐘が鳴るような深夜に登場する。お
化けは時刻にこだわらない。(後略)”
「幽霊や 朝日に出るは 気味悪し(わろし)」(鈍末)
今日、8月13日は、お盆の入り(迎え盆)。
ご先祖様を、盆提灯と麻幹(おがら。麻の皮をはいだ茎)を焚いて、
その道しるべとし、迎え入れるのですが、僕のところも子供の頃は
そのような真似事をしていましたが、今はオハギを頂くくらいしか
その名残をとどめていません。オハギも14日にお供えするしきた
りですが、今日に前倒ししてしまいました。もちろんお八つに頂き
もしました。
位牌の前に、茄子で作った牛と胡瓜で作った馬を供え、ご先祖様を
お迎えするときには馬を、16日(お盆の明け。送り盆)の夜には
牛を、それぞれ使って、ひと時でも長く滞在してほしいという願い。
僕は、四国は高松の生まれですが、2歳くらいのときに東京に出て
きたので、そんな風習があるとは知らなかったのですが、成人して
から初めて故郷にある先祖の墓に参ったときに、盆燈籠というもの
を目にしました。
もともとは浄土真宗本願寺派の門徒が安芸地方(広島県)で広めた
ものが讃岐にも伝わったようですが、本来のもの(赤・青・黄などの
色紙を貼って作ったもの)とは違っていて、真っ白な紙で作られた
ものが沢山風に舞っていました。
新盆の霊には、白い紙の盆燈籠を供えるところもあるようですが、
菩提寺の墓と云う墓が新盆であろう筈がなく、その変遷は不明で
すが、とにかく一面に白い盆燈籠が翻っていました。
盆と燈籠といえば、三遊亭円朝の怪談話「牡丹燈籠」。
僕は、日本三大怪談(あとの二つは「四谷怪談」と「番町皿屋敷」)の
中でもこの「牡丹燈篭」が一番怖い。
何故かと云うと、1968年6月15日に公開された、山本薩夫監督の「牡丹
燈籠」の所為。本郷功次郎演じる新三郎の長屋を訪ねる赤座美代子
演じるお露と大塚道子演じる下女お米が牡丹燈籠を提げてスーッと
滑るようにして歩く(?)ところが実に怖い。ほんと、巧みな演出。
今、思い出しただけでも、お、お、おとろしゃ(香川県の方言)。
「怪談の 後更(うしろふけ)行く 夜寒哉」(召波)
註)黒柳召波(しょうは)は、与謝蕪村に師事した江戸中期の俳人。
ところで、お化けと幽霊の違いって分かります?
柳田国男の『妖怪談義』によると、
・お化けが出没する場所が決まっているのに対して、幽霊の方は足が
ないにもかかわらず風のようにどこへでも出張して行く。
・お化けはだれかれの見境なしに「バー!」とおどかして喜んでいるが、
幽霊の方は特定の人だけをつけねらって他には心を向けない。
・幽霊は丑三つの鐘が陰にこもってものすごくというような刻限にかぎ
って戸をたたいたり、屏風の背後にひそんだりするが、お化けの方は
特にそういうめんどうな時間を定めることもない。
だから、トイレの花子さんも口裂け女もお化け。古色蒼然とした館に住
みついているのもお化け。でも最近は、至る所に出没するお化けもいる
ようで。お、お、おとろしゃ。
今朝の朝日新聞の天声人語もまさにこれ。
これまでは内閣法制局が、集団的自衛権の解釈見直しを断固として
撥ね付けていたときには、やれ「法の番人だ」なんだらかんだらと褒
めちぎっていたのに、なにやら雲行きが怪しくなってきたら、
“そもそも法制局はいわば助言機関であり、内閣の一組織にすぎな
い。これまでの憲法解釈を最終的に決めてきたのは歴代内閣、多く
は自民党政権である。”
なんてことをのたまう。
であるならば、
“法制局は一貫して憲法9条の下ではできないとしてきた。”
そしてそれを覆すのは
“無理筋だろう。長年、9条の意味はこうですと言ってきたが、やっぱ
りそれは違っていました、実はこういう意味でした…。こんな気まぐれ
な言い分が通るなら、日本は法治国家なのかと疑われる”
と云い切るのなら、大船に乗ったようにしていればよいのに、と思
うのですが、安倍首相が内閣法制局長に集団的自衛権見直しに積
極的な人を充てようとすると、慣例ではない外部(外務省出身)から
の人事だといちゃもんを付ける。あれっ、いつもエスカレーター人事
に苦言を呈してきたのはどこの新聞社だっけ?
そして、
“それを変える先頭に、一つの役所を、一人の個人を立たせよう。そ
んな考えなら、姑息のそしりをの免れまい。”
なんて、それこそ姑息な言葉で結んでいる。
子供じみた天声人語氏に、大人の意見を教えてあげるね。(以下は
週刊新潮今週号の特集「『安倍総理』舵を切って『集団的自衛権』入門」
に拠る)
内閣法制局が、集団的自衛権について「権利はあるが、行使できない」
との政府見解として示したのが1981年のこと。
国連憲章では、個別的自衛権のみならず集団的自衛権も認めている
のですが、憲法9条2項(戦力の保持を禁止)によって、自国を守るため
の必要最小限度の武力は戦力とは見做さないものの、他国を守るよ
うな武力行使は憲法で容認される自衛権を超えるため、戦力と見做す、
としているからです。
しかし、今年に入ってからの中国の領海侵犯やレーダー照射事件など
から、危機感を募らせた安倍首相が、第一次安倍内閣(2006年9月~07
年9月)のときの「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」にお
ける、当時国際法局長であった小松一郎氏(現駐仏大使)の仕事ぶりを
見て、それが今回の抜擢人事に繋がったとあります。
その小松氏がまとめた報告書では、集団的自衛権の行使を容認すべき
以下の「4類型」(概要)が示されていました。
第1類型は、公海で共同訓練中に米国艦船が攻撃された場合、日本も
反撃できるようにする。
第2類型は、日本の上空を通過して、米国へ向けられた弾道ミサイル
を(そう予想できた場合ですが)迎撃できるようにする。
第3類型は、他国での人道復興支援などの場において、他の部隊(友軍)
が攻撃を受けたときに、それを援けるための反撃ができるようにする。
第4類型は、給油や整備などの後方支援活動ができるようにする。
上記より踏み込んだ報告書が年内にもまとめられて、来年の通常国会で
政府解釈を示して、国家安全保障基本法が提出される見込みのようです。
で、ここからが大人としての見解。
“内閣法制局に詳しい明治大学政経学部の西川伸一教授はこんな意見。
「新長官が国会答弁で新解釈を述べれば、『変わった』ということには
なる。が、法制局にすれば、今までの解釈の積み重ねが全て否定されて
しまうので、幹部がそれを許すとも思えません。従って、実際に解釈
変更が可能かどうかは未知数です」”
天声人語氏も含めて、朝日が、そんなにヒステリックにならずとも、中々に
難しい問題なんですよ。
僕ら国民としては、朝日のように感情的に煽って「臭いものに蓋をする」の
ではなく、政府としての見解とそれに対しての様々な意見が公開される
方が有り難いのですよ。
それをワーワーと騒いで、国民の目をそらし、耳を塞ぎ、口を挟ませない。
御用学者の意見や、国民の「声」として、自分らに都合の良い意見だけを
採り上げる。
今日の「声」でも、こんなのばかり。
・「戦争前後を経験 改憲は悪夢だ」(86歳、無職、男性)
・「声に出して孫と憲法を読む」(78歳、無職、女性)
・「麻生発言 批判報道に驚いた」(37歳、無職、男性)
最後のは、朝日が麻生の発言を非難したことに対して、朝日の捏造
だと批判する人々が多いことから、朝日を擁護する発言です。
こういったご都合主義は、既に大方から看破されているのですが、懲りな
いのですね。
今朝の天声人語では「法匪」(ほうひ。法律を絶対視して人を損なう役人
や法律家をののしっていう語)という言葉を使って、内閣法務局を貶すよう
なことをやっていますが、朝日さん、あなたの護憲についてもそう云える
のではないですか?
あーあー、のんびりと本を読むつもりだったのに…。
暑さがぶり返し、蝉しぐれの中、暦では秋の訪れを告げています。
毎度お馴染み『ことばの歳時記』では、9日の項に「立秋のころ」
と題して、ちょっと面白いことが書いてあります。
“ある風流人のところに、暑さの中を訪れた客が、茶室に通され、
汗をぬぐいながら、ふと床の間の掛け字に目をやると「夕有風立秋」
と書いてある。「良い句ですな。夕方ごろ吹く風に秋の気配を感じる、
というのは今ごろにピタリですよ」と、お世辞半分にほめると、主人
は微笑して、「いやあ、これはユーアルフーリッシュと読んで、おバカ
さんね、ということなんです」と答えた。”
「掛け字」というのは、文字を書いた掛物(掛軸)のこと。
金田一先生は、音読みと訓読みがあるから、このような言葉遊びが
できるけど、英語では、同じ字をまるっきりちがう発音で読むことは
できないから、こんな風流(?)は通じない、とおっしゃっているけど、
音で違った意味にとらえるという遊びはあるようで。(以下は、週刊
新潮の先週号「世界は数字でできている!―贋作『若草物語』ほか
数字ジョーク」by野口悠紀雄から)
その一、エイミーが小さいころの話。「9という数字は可哀そう」と泣く
エイミーにジョーがどうして泣いているのか理由を尋ねると、エイミー
は「だって、今日、学校で数字を習ったの。7、8、9と」。
エイミーは“Because, seven ate nine.”(だって、7が9を食べちゃた
んだもの)と云ったのですけどね。
その二、英語が上手自慢のドイツ人夫婦がイギリスを旅行中のこと。
レストランでキールを注文した。「キールを2杯ください」。ウェイターが
「ドライですか?」と尋ねるので、慌てて云ったのが“Nein! zwei.”。
「キール」は、白ワインにクレーム・ド・カシスを加えたカクテル。
ドイツ語では1、2、3は「eins(アインス)、zwei(ツバイ)、drei(ドライ)」。
「3杯ですか?」と聞かれたと思っちゃった。
その三、アメリカでの話。英語が苦手な婦人が電話で「ピザを2枚配達
してください」と注文したところ、「数字が間違っています」と返ってきた
ので、「では、3枚ください」と。
あちゃらでは、電話の掛け間違いには、“You have the wrong number.”と
返事するのですよね。いったいこの婦人は何枚ピザを注文するはめになっ
たのかしらん。
少しは暑さも忘れて楽しめました?
ではもっと寒くなるものを。
おらが畑で芋掘ってたら、ゲージンが来てよ、その掘った芋を指差すもん
だから、「堀った芋いじるな」と云ったんだ。そしたら、人差し指を口に
あてて「シー」というような仕草をするだろ、おら、腹立ったけどゲージン
だから仕方ねーと思って、しばらく黙って芋掘ってた。一時間も経っただ
ろうか、後ろを振り向くとまだそこにつっ立てるじゃねーか。だから又
「掘った芋いじるな」と云ったんだ。そしたら今度はVサインを出しや
がった。
そのゲージンが腕時計を見てたところを見てたのにね。
おー寒。
もしも…であったならば、が論述されているのですが、その末尾に「太平洋
戦争終結の遺産」として次の記述があります。
“広島・長崎に投下された原爆が日本を降伏させた決定的な一撃であるという
神話をアメリカ人は信じている。このストーリーによると、原爆投下の決定は、
戦争が継続されていれば犠牲になったであろうアメリカ兵のみならず、日本国
民の命も救ったのだとされる。この神話はトルーマンの決定を正当化し、アメ
リカ人のなかにある後ろめたい意識を取り除く役割を果してきた。(中略)
トルーマンは生前、たえず原爆投下の決定の問題を取り上げて、自分自身で
創作した虚構を信じながら、この決定を最後まで執拗に擁護した。トルーマン
がたえず自己の決定を正当化しようと試みたこと自体、原爆投下の決定が、死
を迎えるまで彼を苛んでいたことを示している。(中略)”
先に挙げた原爆投下に対して抗議した日本政府も戦争法規に違反する非人道
的行為を行っていますが、
“こうした行為にたいして日本人が負わねばならない道徳的責任をもって、日
本政府が原爆投下に抗議することはもってのほかであるとする議論は成り立た
ない。倫理的責任は相対的なものではなく、絶対的な価値だからである。”
昨年は、平和式典ににトールマンの孫が出席して話題になりましたが、今年は、
「もうひとつのアメリカ史」というドキュメンタリーの中で「日本への原爆投下の
主たる目的はソ連への牽制であり、軍事的な必要性はなかった」と主張してい
る米映画監督のオリバー・ストーンが参列するそうです。
とまれ、どこかの国のように騒ぎ立てず、静謐の中で祈る。二度と同じ過ちを
犯さないようにと。
その意味で、思い出に残す「記念」の文字よりも、「祈念」の方が相応しいよう
にも思えます。
広島上空に達し、リトルボーイが投下されたのが午前8時15分(日本時間)。
リトルボーイは標的の太田川をまたぐ相生橋から550フィート外れた島病
院の中庭の1,900フィート上空で爆発。その威力は12,500トンの
TNT(トリニトロトルエン)と同等であり、爆発点の温度は華氏5,400°
に達し、爆心地から半マイル以内にいた人々の内臓を一瞬のうちに蒸発させ
たため、丸焦げの塊となって幾千も道路に、歩道に、橋の上に転がっていた
と云います。銀行の大理石の石段の上にその影だけを残した男性もいました。
爆風による火災は、市内76,000戸の家屋のうち、70,000戸を舐
め尽し、35万人の人口のうち、2万人の軍人と11万人の無辜の市民が即
死し、その直後に降った黒い雨などによる原爆症で亡くなったひとも含める
と、1945年末までに14万人が死亡しました。
原爆による長崎の死者は、3万5千人から4万人に達したとのこと。
以上は、『暗闘』(長谷川毅著、中央公論社)に拠るものです。
同書は、日本の降伏が原爆投下によるだけでなく、むしろ日本が戦争終結の
仲介役として頼りにしていたソ連が、日ソ中立条約を破って参戦したことに
あることを、様々な史料に基づいて、客観的に論じたものです。
著者があとがきで述べているように、日本の大学を卒業してからアメリカの
大学でロシア史の博士号を取得し、アメリカ国籍を得て、アメリカの大学で
ロシア史を教えているといった特殊な経歴から、太平洋戦争をアメリカ、ソ連、
そして日本の三者の視点に立って検証を試みたものです。(600ページにも
及ぶ大著であり、第10回司馬遼太郎賞、第7回読売・吉野作造賞を受賞し
ています。)
横浜、小倉が標的とされ、新潟を代替候補とする決定がなされます。28日
の会議では、その優先順位が京都、広島、新潟と決まるのですが、その後に
京都は候補地から除外されます。京都が除外されなかったならば、このよう
な無慈悲な行為が日本人に遺恨の念を植えつけ、その結果、日本人はアメリ
カよりもソ連になびく可能性があり、長い占領政策に支障があるとの判断か
らです。
初めは、ポツダム宣言は、アメリカ軍による日本本土上陸の前に日本に対し
て降伏を呼びかける最後通牒として考えられていたのですが、原爆の完成
によって、降伏しなければ「速やかにして徹底的な破壊」をもたらすための
アリバイといった性格のものに変わります。
そのため日本が到底呑むことのできないポツダム宣言(国体つまり天皇の扱
いが不透明)を最後通牒としてつきつけて(7月26日)、日本がこれを黙殺
するや、それを拒否したものと見做し、原爆投下を正当化するのです。
7月31日、リトルボーイの準備が完了したものの、日本を襲った台風のた
め、延期され、8月6日のその日を迎えます。
リトルボーイを搭載したエノラ・ゲイを含め、7機のB29がその任務に当
てられていました。うち3機は、気象観測機として広島、小倉、長崎に飛行
(広島の天候次第で、小倉、長崎に落とす予定だった)し、2機は、エノラ・
ゲイの護衛機、他の1機は、科学専門のジャーナリストとカメラマンを載せ
た観察の任務を帯びたものでした。このことからも、原爆投下の目的が、早
期の戦争終結を隠れ蓑とした、原爆の威力の実証にあったことが分かるの
ですが。
日本政府は、8月9日の長崎への二発目の原爆(ファットマン)投下の
直後(10日)、スイス政府を通じてアメリカ政府に対して次の抗議声明
を送っています。
「米国が今回使用したる本件爆弾は、その性能の無差別性かつ残虐性
において、従来かかる性能を有するが故に使用を禁止せられおる毒ガ
スその他の兵器を遥かに凌駕しをれり…。いまや新奇にして、かつ従
来のいかなる兵器、投射物にも比し得ざる無差別性残虐性を有する本
件爆弾を使用せるは人類文化にたいする新たなる罪悪なり。帝国政府
はここに自らの名において、且つ又全人類及び文明の名において米国
政府を糾弾すると共に即時かかる非人道的兵器の使用を放棄すべきこ
とを厳重に要求す」
もちろんトルーマンは無視しました。
アメリカは、日本が降伏しなければ、11月1日までに順次完成すること
になっていた7発の原爆を、8月中に第3、9月始めに第4として主要都
市に落とすことまで考えていました。
の間で交わされたヤルタ条約において、その最終日に、ルーズベルトがスター
リンとの非公式の会談の場で持ち出したのが、ソ連の対日戦への参加の条件と
して満州と南サハリン(樺太の南半分。日露戦争の結果、日本に割譲)とクリ
ール(千島列島。明治8年5月7日に日本とロシア帝国との間で結ばれた千島・
樺太交換条約で日本の領土となった)をソ連に引き渡すという密約。
安政2年(1855)の日露和親条約(千島列島の択捉島以南は日本に、ウル
ップ島以北はロシアに属することが確認され、樺太は両国の所領とされ
た)を持ち出すまでもなく、北方4島(歯舞、色丹、国後、択捉)は古来
より日本固有の領土ですが、1955年6月から開始された日ソ交渉で
日本側が、歯舞と色丹は北海道の一部であり、サンフランシスコ講和条
約(1951年9月調印、翌年4月28日発効し占領が終結。ソ連は条約に署名しな
かった)で放棄した千島列島に歯舞と色丹は含まれず、国後と択捉はいかな
る外国の主権下にもない日本固有の領土であると主張したのに対して、
ソ連側は、歯舞と色丹の返還には応じるとしたものの、国後と択捉につ
いては国際協定その他により解決済みであると主張し、その後の交渉も
ままならず現在に至っています。
サンフランシスコ講和条約においては、領土処理として、朝鮮の独立承認、
台湾と澎湖諸島、千島列島、南樺太、新南群島に対する日本の一切の権利、
権原および請求権を放棄するとされており、旧ソ連および現ロシアが主張
する国際協定はこのことを指し、その他云々というのはヤルタ密約のこと
を云っているのだと思います。国後島と択捉島は南千島であることから、
千島列島に属するものとして返還対象では無いとするものですが、上記に
あるように、権利等を放棄したのは数々の戦果として手に入れたものに限
られています。したがって、南樺太と交換したのは国後島と択捉島より北
にあるウルップ島以北の千島諸島であって、それらが対象になるのは分か
りますが、国後と択捉は対象外とすべきものです。
スターリンは、北海道の北半分をも掠め取ろうとしていましたから、国後
と択捉が略奪であることは百も承知。
日本を降伏させるためにソ連の参戦を求めていたのですが、原爆の完成に
より、アメリカはそのことを必ずしも望まなくなります。むしろ、ソ連が
アジアで影響力を増大させることに懸念を抱いていました。
トルーマンは、ソ連の参戦前に原爆を投下して日本を無条件降伏させよう
とし、スターリンも後(7月24日)に原爆完成の情報を得て、当初の予定
を早めて、日本が降伏する前に参戦し、ヤルタの密約で決めた分け前にあ
ずかろうとします。(当初は8月15日を予定していたのですが、8月9日
に前倒しします。)
広島にリトルボーイと称する原爆が落とされてから、今日で68年が経過
したことになりますが、そのときから人類は未来永劫忘却されることの無
い、重い十字架を負ったことになります。
1941年12月7日(ハワイ現地時間)の日本による真珠湾奇襲攻撃に
より、太平洋戦争の幕が切って落とされたのですが、アメリカは翌年、直
ちにマンハッタン計画と称する原爆開発計画に着手します。
そして、1944年9月、イギリスのチャーチル首相がルーズベルト大統領
を訪問したときに、原爆完成の暁には、日本が降伏するまで原爆を繰り
返し使用するという警告をした後に、日本に対して使用する旨の合意が両
者の間でなされます。
同年12月の報告によって、1945年8月1日までに鉄砲型爆弾としての
原爆(リトルボーイ)が完成し、もうひとつの内発的爆弾である原爆(ファット
マン)の実験が7月に行われることをルーズベルトは知ります。
しかしルーズベルトは、原爆の完成を見ることなく、その数か月前(4月12
日)に息を引き取ります。そして副大統領であったトルーマンが大統領と
なり、その意志を引継ぐことになります。
原爆実験の成功は、当初の予想よりも早く、トルーマン、チャーチル、そ
してソ連のスターリンの三巨頭によるポツダム会談(45年7月17日~
8月2日)の最初の会議(17日午後5時~7時前)が終了し、その後の
宴会も終わったときに、電報を受取り、翌日の朝にそれをトルーマンに伝
えます。
電報の内容は「医者は小さな男の子が大きな兄と同様に元気であること
を熱狂的に確信して帰ってきた。男の子の目の光はここからハイホール
ドまで識別することができ、男の子の泣き声はここから私の農場まで聞
くことができた」というもので、小さな男の子が「リトルボーイ」、大きな兄
が「ファットマン」、医者とあるのは、マンハッタン計画の責任者である
グローヴス将軍のことであり、トリニティでの実験ではロングアイランド
のハイホールドまで爆発の閃光が届き、農場とあるのはペンタゴンから
5マイルの場所で、そこまで爆発音が届いたという実験成功の報告です。
あくまで秘密事項であり、このような暗号電文とする必要があったので
すが、そのため、直ぐにトルーマンに知らせに行ったところ、その場が
騒がしかったことや、トルーマンの周りに多くの客人がいたことから、
翌日朝の報告となったのです。
言、というよりも火遊びをしてはしゃいでいる子供じみた姿を露呈してい
るのだけど、どうなんだろ。国益を極めて損じているとしか思えないので
すが。(他紙や他のテレビ局では殆ど問題視していないのにね。)
記憶に新しいけど、昨夏のロンドン五輪における日韓戦において、竹島の
領有を主張するプラカードを掲げて、FIFA(国際サッカー連盟)から
処分を受けた韓国。
そこでは、当の選手のみならず韓国サッカー協会への戒告も含まれていた
(再発した場合には規律委員会がさらに厳しい処分を科すと警告もしていた)
にもかかわらず、またまた先の(6/28)のサッカー東アジア杯においても、
「歴史を忘却した民族に未来はない」と書かれた巨大横断幕を掲げて、い
とも簡単にその戒告を無視する蛮行に出た。
そのことに対して日本が東アジアサッカー連盟に抗議文を提出するや、日
本のサポーターが個人的に旭日旗を振ったにもかかわらず、その行為が件の
横断幕を掲げることに繋がったのだと、そして韓国人にとっては旭日旗は
ナチスの「ハーケンクロイツ」と似た悪感情を与える日本軍国主義の象徴
であり、「より深刻な政治行為と見なされる」と開き直って、東アジアサッ
カー連盟に書簡を送ったのですが、FIFAでは旭日旗については問題な
しとしているのです。
東アジアサッカー連盟は、FIFAの直属組織で、事務局は東京文京区の
日本サッカー協会ビルにある。
この韓国の子供じみた言掛りに対して、これまた子供じみた朝日がなにも
反論しないのは、どうしたわけ?
だって、朝日新聞の社旗、旭日旗なんですよね。いくら「朝」の字が左が
かったところにあるからと言い訳しても、旭日旗であることに変わりは無
いわけで、旭日旗の本来の意味をしっかり社説等で堂々と述べれば良いのに、
そうはしない。
旭日旗の歴史は古く、民間での祝い事などの際にめでたさを強調するた
めに用いられてきたと云います。
そして明治維新後、兵部省において全国各藩統合の旗として、日章の背
景に光線を伴った意匠、いわゆる旭日旗が、1870年(明治3年)5月15日
の太政官布告第355号で「陸軍御國旗」として初めて考案されました。
しかし、戦後は、太陽光線が四方八方に雲なく広がる意匠が「天晴れ」と
して景気が良いとされ、祝事やスポーツの試合などで使用されています。
「ハーケンクロイツ」は、第二次世界大戦の発端となった、悪しき印象を
遺したものですが、旭日旗はそのようなものではなく、明治の御代におい
ては、西南の役などの内乱で使用された他、日清、日露を戦って当時の朝
鮮半島を中国やロシアの属国・植民地となることを防いだ日本人の流血の
象徴でもあるのです。
日韓併合において、今の韓国の繁栄の礎を築いた背景に翩翻と翻っていた
のが旭日旗でした。
大東亜戦争においても、その大義のもと、日本兵として戦った朝鮮人民の
御旗となったのが旭日旗です。
そのような旭日旗に唾する韓国。恩に仇する韓国。一方的に李承晩ライン
を引いて、竹島を盗み取った韓国。盗難品である仏像を返還しない韓国。
朝日新聞も同様に縁起の良いデザインとして使用している筈ですが、その
ような韓国に対して、何らの反論もしないのは何故?
以前、朝日は、政教分離というごくまっとうな創価学会批判を繰り広げて
いたのですが、聖教新聞の印刷という話が持ち込まれるや、それがピッタリ
と止んでしまったことがありました。(今もそれが続いています。)
朝日を「ちょうにち」と読んで、朝日の偏向に満ちた報道を批判するひとが
いますが、中国に対する報道特権などを考え合わせると、そういった国から
の何らかの見返りが、その報道を歪ませているのかと、勘繰りたくもなり
ます。
「新聞の 文字で黒ずむ 旭日旗」(鈍末)
“ぎょっとした。麻生副総理が7月29日、ある会で改憲に触れて、こう述べたと
いう。「気づいたら、ワイマール憲法がナチス憲法に変わっていた。誰も気づかない
で変わった。あの手口に学んだらどうか」。”
と、都合の良いところだけを抜書きして、とんでもないことを考えている奴だ、と
悪く印象づけようとしています。
“同僚記者の取材と麻生事務所に確認した結果をあわせ以下紹介する。
▼麻生氏はまずナチスがどうやって独裁権力を獲得したかを語った。それは先進的
なワイマール憲法の下でドイツ国民が選択したことだ、と。いかに憲法がよくても、
そうしたことは起こるのだ、と。
▼次に、日本の改憲は騒々しい環境のなかで決めてほしくないと強調した。それから
冒頭の言葉を口にした。素直に聞けば、粛々と民主主義を破壊したナチスのやり方を
見習え、ということになってしまう”
どうして「素直に聞けば」になるのだろ。恣意的に曲解しているとしか言いようがない
のだけどね。これも朝日得意のミスリードテクニック。
“▼氏は「民主主義を否定するつもりはまったくない」と続けた。としても、憲法は
いつの間にか変わっているくらいがいいという見解にうなずくことは到底できない”
これに至っては、日本語の読解力も無い人物が「天声人語」を執筆していることを自
ら認めているようなもので、恥ずかしくないのかしらん。(当然、百も承知の上で
特技を発揮しているだけなのですが。)
“▼ヒトラー政権は当時の議会の機能不全に乗じて躍り出た。対抗勢力を弾圧し、全権
委任法とも授権法とも呼ばれる法律を作って、やりたい放題を可能にした。麻生氏の
言うナチス憲法とはこのことか。そして戦争、ユダヤ人大虐殺へと至る”
ここにもレトリックが巧みに仕組まれています。上述した曲解によって、麻生(自民党)
は、ナチス憲法成立に至る過程をまねて、与党の数の力によるやりたい放題でもって、
憲法を変える、そんなことをすれば戦争になって、やがてはナチスのようなことになる、
といった論法を読者に刷り込もうとしているのです。
“巨大な罪を犯した権力集団を、ここで引き合いに出す発想が理解できない。熱狂の中
での改憲は危うい、冷静で落ち着いた論議をすべきだという考えなら、わかる。なぜ
これほど不穏当な表現をしなければならないのか。”
あれ?日本に対しては、南京大虐殺とか、とんでもない数の慰安婦の強制連行とか、な
んらの客観的証拠を示すこともなく、引き合いに出しているのはどこの新聞社でしたっけ。
それに分かり易い譬えとしてナチスの例は、朝日の曲解でなければ、理解できることで
すけどね。ちっとも不穏当な表現でないし。朝日の曲解が不穏当そのものなんだけど。
“言葉の軽さに驚く。”
と結んでいるのですが、天声人語氏、あなたこそそうなのではありませんか?
ゆっくり本を読もうと思ってムシしていたのだけど、夕刊を読んで、どうにも腹のムシが
おさまらない。で、ムシ下しで獅子身中のムシ(アサヒムシ)を排泄したわけです。
アサヒムシって実在するのですよ、ぎょっとした?
アサヒムシ:原生動物門肉質虫亜門軸足綱放散虫目アストロロンケ科。体長0.2~0.3㎜。
1個の細胞の中心部に等長の20本の骨針が放射状に集合している。細胞は
球形で2部から成り、内部に1個の核と黄色の共生藻類を多数含み、外部
の細胞質は各骨針に沿って自由に伸縮し、仮足となって餌をとる。
プランクトンの一種で、日本各地の沿岸に普通に分布する。
朝日新聞が、麻生の舌足らずな発言の揚げ足を取って、またもや国際紛争の
種を撒き散らそうとしたのが、以下のもの(そのまま全文を引用)。
“護憲と叫んでいれば平和が来ると思っているのは大間違いだし、改憲でき
ても『世の中すべて円満に』と、全然違う。改憲は単なる手段だ。目的は国家
の安全と安寧と国土、我々の生命、財産の保全、国家の誇り。狂騒、狂乱の
中で決めてほしくない。
ヒトラーは民主主義によって、議会で多数を握って出てきた。ワイマール憲法
という当時欧州で最も進んだ憲法下にヒトラーが出てきた。常に、憲法はよく
てもそういうことはありうる。
今回の憲法の話も狂騒のなかでやってほしくない。”
と、どんなに理想的な憲法と思えるものであってもヒトラーの様な例があるの
で、憲法の改正は慎重に取り組むべきであるとごく当たり前のことを述べてい
るに過ぎない。
“靖国神社も静かに参拝すべきだ。お国のために命を投げだしてくれた人に敬
意と感謝の念を払わない方がおかしい。いつからか騒ぎになった。騒がれたら
中国も騒がざるをえない。韓国も騒ぎますよ。だから静かにやろうや、と。”
朝日にとっちゃ、耳が痛い話。靖国神社参拝や慰安婦、さらには南京大虐殺な
んて問題をでっちあげ、火をつけ煽った張本人ですからね。
そして、鬼の首でも取ったようにして、問題視したのが次の発言。
“憲法はある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わって
いたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口に学んだらどうかね。
わーわー騒がないで。本当にみんないい憲法と、みんな納得してあの憲法変わっ
ているからね。”
麻生が云いたかったのは、熱狂、騒乱の中では、どんなに素晴らしい憲法であっ
ても、国民がその良し悪しを冷静に判断する暇もなく、改悪されてしまうこと
がある。その例がナチスだ。そのことを反面教師として学ぶ必要がある。
“わーわー騒がないで。”と句点にしていますが、実際は次の発言と繋がってい
て、議論が盛んになされることもなく、ナチスの憲法は皆が納得の上で決められ
ている、と悪しき事例として取り上げているのは、改憲派の麻生の発言であれば
、しかも次の発言があるのだから、そのように解釈するのが自明の理。
“ぼくは民主主義を否定するつもりはまったくありませんが、私どもは重ねて
いいますが、喧噪のなかで決めてほしくない。”
国民の多数決で決める民主主義を否定するつもりは全くない。しかし、熱に浮か
された民衆による決定のようなことにならないように、自民党は熟議を重ねて国
民に信を問いたい。
それを朝日は、自己の都合の良いように翻訳して、米国のユダヤ人権団体「サイモン・
ウィーゼンタール・センター」や韓国、中国に流したのです。そして、それらから
批判するコメントを得たとして、夕刊の1面で、「麻生氏、ナチス発言撤回」と
大見出しで記事を掲載しています。
そこで麻生は“(発言が)私の真意と異なり誤解を招いたことは遺憾だ。憲法改正
については落ち着いて議論することが極めて重要だと考えている。この点を強調
する趣旨で、喧騒にまぎれて十分な国民的理解、議論のないまま進んでしまった
悪しき例としてあげた。私がナチスやワイマール憲法にかかわる経緯について極め
て否定的にとらえていることは、全体の流れをみていただいたらはっきりしている。”
と、僕が朝日の朝刊を読んで、上記のように感じたことと同じことを述べています。
また、夕刊には朝日の電話インタビューに対して、サイモン・ウィーゼンタール・
センターの副代表が、
“21世紀の民主主義にナチスの手口をもたらし、憧れを呼び起こそうというのは
まったく理解できなかった。”
と回答したことが掲載されているのですが、語るに落ちるとはまさにこのことで、
朝日がミスリードしていたことがバレテしまいました。
初めて買った活字だらけ(挿絵が何点かあったような気がします)の本のタイトルが、
表題のようなものであったと思うのですが。
それでネットで調べてみたところ、『マゼランの世界一周』(あかね書房、少年少女世界
ノンフィクション全集第8巻)という本が昭和36年に出版されているのですが、全集
では無かったように記憶していますし、第一、小学校の高学年の頃のことですから、
別の本なのでしょう。(でも、内容は同じかも知れません。)
マゼランは、アメリカ大陸を発見したコロンブスに比べてマイナーな存在ですし、男子
の間で人気のあったジュール・ヴェルヌの『十五少年漂流記』、『海底二万里』、『八十日
間世界一周』などと比べると随分と地味なものであったのですが、何故この本を選んだ
かと云うと、切羽詰まっていて、いつも月刊誌『少年』を買いに行っていた本屋には
あれこれ選べるだけのものが置いていなかったから。
切羽詰まっていたのは、夏休みも終わりに近づいていて、宿題に読書感想文という
厄介な代物があったから。
当然のことながら、読み易いものということで「少年少女なんだらかんだら」と云う類
の本の中から選んだのだと思うのですが、内容はもとよりマゼランそのものに対する
興味もへったくれも無いわけで、少ない中からも何故選んだかというと、その表紙絵
(と挿絵)が気に入ったから。
斜め読みしたので、今ではどのような伝記ものであったのか全く覚えていません。
そんなことでまともな感想文なんぞ書ける筈もなく、はてさてどのような感想文を書
いて提出したのやら。小学校に保管されているのであれば読んでみたい(冷汗かいて、
少しは身体も冷えるかも)。
同じころ読んだ(?)ものに『イワンのバカ』がありました。何故「?」を付けているかと
云うと、マンガ本だったから。
原作は、トルストイですから、活字で読んだのなら、左程印象に残らなかったと思うの
ですが、そのマンガは大変良くできていて(もっとも原作を読んでいませんし、どこまで
原作に忠実であったか分からないのですが)、トルストイの教条主義的な臭みが消し
去られていて、親しみの湧く道徳的なものに昇華されていました。
これだったら、感想文も少しはましなものが書けたように思うのですが、そうしなかった
のは、子供心にも「読書」という範疇に含めることに抵抗があったからだと思います。
も一度、この手に取って読んでみたいと常々思っているのですが、半世紀以上昔の、
それも非耐久消費財ですから、「バカ云わんの」との声が返ってきそうです。
ちなみに、マゼランが艦隊を率いてスペインのセビリアを出帆したのは1519年8月10日
のこと。そして世界一周の航海を終えて帰国したのは、1522年9月6日。
出航時に約270人いた乗組員がわずか18人になっていたというのですから、いかに
厳しい3年間であったかが分かるというもの。
マゼラン自身も1521年4月27日、マクタン島(フィリピン諸島の一つ)での現地人との戦で
戦死しています。
したがって、厳密に云うと、マゼランは世界一周をしていないことになります。
で、世界一周達成者にマゼランは、まぜられん。
昨日、観に行ってきました。
本来ならば、2011年4月2日から横浜美術館で開催される筈であったのですが、東日本大震災
が直前に発災したため、延期となっていたものです。
愛知県美術館(4/26~6/23)を皮切りに、横浜美術館(7/6~9/16)、神戸市立博物館(9/28~
12/8)と順繰りに、ロシアのプーシキン美術館所蔵の中から選りすぐりの66点が、フランス
絵画300年(17世紀~20世紀)の足跡を辿ることができるようにと、以下のように4ブロック
に分けて展示されます。
プーシキン美術館は、ロシアの首都モスクワの中心地に位置し、サンクトペテルブルクの
エルミタージュ美術館とならんで、世界的な西洋絵画コレクションを誇る国立美術館です。
1912年、「モスクワ大学附属アレクサンドル3世美術館」として開館し、ロシア革命を機に
「モスクワ美術館」と名を変え、さらに文豪アレクサンドル・プーシキンの没後100年を記念
して、1937年に現在の名称に改められました。
絵画、版画、彫刻など67万点を超す収蔵作品は、古代エジプトから近代にいたるヨーロッ
パ美術の流れを幅広く概観できるその多様性が特徴です。なかでも、印象派からマティス、
ピカソまで、屈指の名品を揃えたフランス近代絵画のコレクション(700点を超す)は極め
て高い水準を誇ります。
第1章 17-18世紀 古典主義、ロココ―(22点)
第2章 19世紀前半 新古典主義、ロマン主義、自然主義―(14点)
第3章 19世紀後半 印象主義、ポスト印象主義―(19点)
第4章 20世紀 フォーヴィズム、キュビスム、エコール・ド・パリ―(11点)
点数が少ないのと、日本人に馴染み深い印象派、後期印象派の作品がもう少し充実していれ
ばなと、少々残念な思いはしますが、それでも内容は中々のものです。
目に留まったものを何点か紹介すると、
第1章では、17世紀古典主義の巨匠プッサンの「アモリびとを打ち破るヨシュア」、18世紀ロココ
萌芽期のジャン=パティスト・サンテールの「蝋燭の前の少女」。
第2章では、裸の少女が中の水が流れ落ちる水瓶を左肩にかついでいる「泉」で有名な新古典
主義の巨匠ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングルの「聖杯の前の聖母」、本展で初めて
知ったロマン主義の画家ウジェーヌ・フロマンタンの「ナイルの渡し船を待ちながら」、穏や
かな風景を得意にしたジャン=バティスト・カミーユ・コローには珍しいタッチの「突風」、
自然主義を代表する画家ジャン=フランソワ・ミレーの「薪を集める女たち」。
第3章では、本展目玉のピエール=オーギュスト・ルノワールの「ジャンヌ・サマリーの肖像」。
ジャンヌ・サマリーは、コメディ=フランセーズの花形女優で、1870年代後半のルノワール
のお気に入りのモデル。ルノワールは彼女の肖像画を何枚も描いていますが、この絵のジャ
ンヌは20歳。ジャンヌは後に富豪の息子と結婚し、3女をもうけましたが、1890年に腸チフス
のため、33歳でこの世を去ります。
パステル画を得意とし踊子の絵の多いエドガー・ドガの「バレエの稽古」、本人は否定していま
すが、明らかに浮世絵の影響を多分に受けているポール・セザンヌの「パイプをくわえた男」。
同じく浮世絵の影響を多分に受けて平面的な装飾美術を目指したフィンセント・ファン・ゴッホ
の「医師レーの肖像」とポール・ゴーギャンの「彼女の名はヴァイルマティといった」。
ゴッホの「医師レーの肖像」ですが、「つぶやきの部屋15」の中の「団塊の世代雑感(121)」
でちょっと触れた、“人に贈った絵(「医師フェリックス・レイの肖像」1889年作)が、鶏小屋の穴
を塞ぐのに使われていた”というその絵です。
アルルでゴーギャンと共同生活をしていたゴッホは、いさかいがもとで自身の耳を切り、神経
症の発作を起こして入院しますが、そこで診療にあたった見習い医師がフェリックス・レイ。
ゴッホが感謝を込めて描いた肖像画を贈られたレイは気に入らず、鶏小屋の穴を塞ぐのに使い、
そしてゴッホが亡くなると、パリの画商に売り払ってしまったのです。
モーリス・ドニの「緑の浜辺、ぺロス=ギレック」も造形・色彩の素敵な作品です。
第4章では、アンリ・マティスの「カラー、アイリス、ミモザ」、アンリ・ルソーの「詩人に霊感を与える
ミューズ」。
アンリ・ルソーの「詩人に霊感を与えるミューズ」ですが、詩人とはギヨーム・アポリネールで、
ミューズとは画家のマリー・ローランサン。その恋人たちの姿、ずんぐりとして描かれているの
ですよね(ルソーは、アポリネールの顔や手を採寸しながら描いたといいますが)。
ふたりの手前に描かれている赤い花、詩人の花とされるバラではなく、ニオイアラセイトウだっ
たためか、バラに描きなおした別作品がバーゼル市立美術館にあるそうです。ほんと、ルソー
って面白い。
僕の好きな画家モイーズ・キスリングの「少女の顔」(国吉康雄が絶対に影響を受けていると思え
る色使い)。僕の隣で観ていた二人連れの若い女性は、気持ち悪い絵とかなんとか悪態を吐いて
いたけど、醜は美学においては感性の論題なんだよね。彼女らにかかったら、国吉の絵もけちょん
けちょんなんだろうね。
観に行くタイミングを計っていたのですが、幸いにも昨日は最高気温が東京で30°、横浜で29°で
したので、強い日差しではありましたが、身体的には比較的楽でした。先週夏休みをとった人が多
いだろうし、学校が夏休みに入ったとは云え、子供が美術館に足を運ぶなんてことは、絵日記の材
料に事欠くようになってからだろうし、今が谷間なんだろうと思うのですが、ゆっくり見て回ること
ができました。
僕は、音声ガイドは利用しない主義ですが、水谷豊(杉下右京の口調)の音声ガイド(使用料\500)
付きならじっくり見学ができる筈です。僕のように、観て回るだけなら、1時間余りで済みます。
横浜美術館のURL
http://www.yaf.or.jp/yma/index.php
“この日にウナギを食べると夏負けしないと言われ、おかげでウナギ屋は大繁盛する。(中略)
もっとも、とくに土用のウシの日が知られているのは、江戸時代のウナギ屋さんの商策
によるものだったらしく、平賀源内が看板を頼まれて「今日は丑」と書いたのが評判に
なったという話がある。
なぜとくにウシの日ときめたのか不明だが、地方にはウシ年生まれの人はウナギを食べ
るなという習俗もあったというから、なにかウシとウナギを関係づけた民俗があったの
かもしれない。東京でいう蒲焼を関西ではマムシという。毒ヘビの蝮とまちがえて驚い
たという人もあるが、こちらは「真蒸し」の意味だ。”(同上7月22日の項より)
諸説あるようですが、平賀源内説が有力です。
その説というのは、
丑の日に「う」の付くものを食べると夏負けしないという民間伝承があったらしく、うどん、
うり、梅干しが食されていたのですが、「う」のつくうなぎは夏場は(冬眠に備えて身に養分
を蓄える晩秋から初冬にかけての時期が旬で、夏のうなぎは味がおちるとは云え、やはり
脂っこいから避けられたのでしょう)さっぱり売れない。そこで鰻屋は、平賀源内のところ
に相談しに行ったところ、源内は「本日丑の日」と書いて店先に貼り出すよう勧めた。
エレキテルが有名な源内ですが、本草学(薬物学)者でもあり医者でもあったので、夏バテ
解消にうなぎが効果的であることを承知していたのでしょう。でも源内の非凡なところは、
キャッチコピーで、忘れられていた「うなぎ」に目を向けさせたこと。
源内先生のお墨付きなら、ということで店は大繁盛。これを見た他の鰻屋もこぞって真似を
した。
そして、ならいとして定着して現在に至るというわけです。
ところが僕は、あなごは好きなのに、うなぎが嫌い。
随分と昔のことですが、群馬にある三洋電機の工場へ何人かと連れだって訪問したときに、
昼食にと招待してくれたのが有名な鰻屋だったみたいで、二段重ねのうな重がでてきました。
僕は鰻と鰻に挟まれたタレのしみ込んだご飯を、蓋で隠すようにして、吸い物と漬物で食べて
帰ってきたのですが、三洋電機の方、鰻屋、そして贄となったうなぎには本当に申し訳ない
ことをしたと、今も思い出す度に胸がチクチクチクと疼きます。
「土用凪 『う』欠けたるだけ 清々し」(鈍末)
今日、7月19日は、土用の入りで、8月7日の立秋までが土用の期間となります。
暑中見舞いは、この期間に出すのがならわし。
でも土用って何?
その答えは、
“昔の中国人は、一切の物事を木・火・土・金・水の五つに分けることを思いつき、
たとえば、当時知られてた遊星が五つあったので、木星・火星・土星・金星・水星
と呼んだ。(中略)
ところで、「四季」というものにこの木・火・土・金・水をあてはめようとすると、
春は木、夏は火、秋は金、冬は水と割り当てて、どうも土だけがあまってしまう。
そこで春・夏・秋・冬からその終わりの部分を十八日ずつ削り、それを集めて土の
用とした。これが土用のはじまりで、四季にあるゆえんである。それが、春・秋・
冬の土用は影が薄くなって、土用干し・土用波。すべて土用といえば夏の土用をさ
すことになった。”(『ことばの歳時記』7月20日の項より)
便宜上、1年を360日として5等分すると72日となり、それをさらに4等分する
と18日となるので、それを「土」用として、各季節の尻尾にくっ付けたわけです。
平気法(中国で明の時代まで行われた暦法)だと、1年間を24等分して二十四節気
を定めていたので、土用は必ず18日間と定まっていたのですが、現在では太陽の黄
経によって1年を二十四節気に区分する定気法が使われていますので、土用の入りも
期間も年によって異なります。
2011年は、土用の入りが7月20日、期間が19日。
2012年は、土用の入りが7月19日、期間が19日。
2013年は、土用の入りが7月19日、期間が19日。
2014年は、土用の入りが7月20日、期間が18日。
夏の土用の場合、19日間になる確率が82%、18日間が18%だそうです。
じゃあ土用の丑の日って何?
これも古代中国で考え出されたもので、十干(甲、乙、丙、…)と十二支(子、丑、寅、…)
とを組み合わせて60(10×12の最少公倍数)の周期で暦を表し、その丑に当たる日のこと。
ですから、昨年が7月27日の1回(入りの19日が巳であったため)しかなかったのに、
今年は同じ入り日であっても(戌であったため)7月22日と8月3日(二の丑)と2回あり
ます。
つまり、今年はうなぎを2回も食べることができるわけです。
昨日、有楽町のスバル座で観てきました。
スバル座は、全席が自由席で、入れ替え制では無いので、開始から1時間ほど経ったところから
見始めて、最初から筋がつながるところまで見て館を後にしました。
エンディングにテーマ曲「幸先坂」(さいさきざか)が流れるのですが、主演の真木よう子の歌、
へたなことへたなこと。
それが休憩時間にも延々と流れるので、映画の内容そのもののごとく辛い辛い。
物語は、現在、遠い昔、近い昔がシャッフルされているので、途中から見るとかなり戸惑う。
だって「ごく普通に見える夫婦。だがふたりは残酷な事件の被害者と加害者だった―。」がキャッチ
コピーだもの。複雑なんですよ、人間関係というより、人間という生き物、それも男女の愛情の
ギャップが。
「私が死んで、あなたがしあわせになるなら、私は絶対死にたくない」
「あなたが死んで、あなたの苦しみがなくなるのなら、私は決してあなたを死なせない」
「だから私は死にもしないし、あなたの前から消えない。だって、私がいなくなれば、私は、あなた
を許したことになってしまうから」
こんなセリフが真木よう子の口を借りて出てくる。
原作は、『悪人』と同じ吉田修一の原作(同名小説)ですが、どっちも原作は読まずに、映画だけを
みた感想に過ぎないので的外れなところがあるかも知れませんが、神とその殉教者との間の愛の
関係に見えるのです。特に「さよなら渓谷」にその感が強く、上記のセリフはその象徴であるように
思います。
真木よう子は、完成した映画を見た人々が漏らす感想に、男女の違いを強く感じたようで、映画の
「その後の進展」(一緒に不幸になる約束をした相手を残し、真木よう子は「さよなら」という文字
を託す)について“男性と女性で意見が真っぷたつに分かれるんですよ。男性は、2人の関係に対し
「希望」を持っているんですよね。吉田修一さんも驚かれていたそうです”と明かし、“演じた本人
はそういう男性の希望とは正反対の感情を持って演じたんですけどね”と、いたずらっぽい笑みを
浮かべたそうです。
原作本のキャッチコピーが「あの夏に、終わりはない」ですから、あの夏、つまりレイプが起きた
あの事件、そのことに対する贖罪は未来永劫やってこないという僕の見立てもまんざらでも無いよう
です。
この映画、第35回モスクワ映画祭のコンペティション部門で審査員特別賞を受賞しましたが、神
と常に向き合っているお国柄であるゆえの高評価であったように思います。そのような慣わしの無い
日本において、二人の愛のあり方に共感することは難しいように思えますが。
モスクワ映画祭は、カンヌ、ベルリン、ヴェネチアと並ぶ世界四大映画祭のひとつで、審査員特別
賞は最優秀作品賞に次ぐ賞。
精神的だけでなく、肉体的にも組んず解れつの場面が頻繁に出てくるのですが、真木よう子は、それ
こそ体当たりで演じています。結構きつかったからなのか、役作りでなのか、よくは分かりませんが、
随分と痩せ細った姿も。でもバストだけは…。
でも何故「さよなら渓谷」なんだろ。渓谷って、深い山と山との谷間のことでしょ。
ニーチェの「おまえが長く深淵を覗くならば、深淵もまた等しくおまえを見返すのだ」と関係して
いるのかしらん。
深淵は、浮かび上れない苦しい境遇、絶体絶命の心境を譬える言葉であり、ニーチェが云わんと
したところは、心の闇に通常と異なるものがあると気付いた人間が、自分がその闇に陥らないため、
他のひとが陥らないため、さらには陥ったひとを救い出すために、その心の闇をもっと深く知ろう
と思うほどに、気付けばその異常なものに慣れてしまい、いつのまのか自分自身に影響を及ぼして
いる。だから、生半可な気持ちで行ってはならない、という戒め。
「さよなら」は、別離の言葉でなくて、再会を期す言葉。永久ループ。「終わりはない」のです。
今日の午後、以下の記事がネットに掲載されていました。(そのまま引用)
“菅元首相が安倍首相を提訴 原発事故めぐり「メルマガで中傷記事」
民主党の菅直人元首相は16日、国会内で記者会見し、東京電力福島第1原発事故をめぐり、
安倍晋三首相が「菅総理の海水注入指示はでっち上げ」と題したメールマガジンを配信し、
現在もネット上で掲載しているのは名誉毀損(きそん)だとして、安倍首相に対し、該当する
メールマガジンの削除と謝罪を求め提訴したことを発表した。
安倍首相のメールマガジンは平成23年5月20日付配信。首相は「東電はマニュアル通り淡水
が切れた後、海水を注入しようと考えており、実行した。しかし、やっと始まった海水注入を
止めたのは、何と菅総理その人だった」と記載。その上で「海水注入を菅総理の英断とのウソを
側近は新聞・テレビにばらまいた」としている。
菅氏は「内容は全くの虚偽の情報に基づく。私の名誉を著しく傷つける中傷記事だ」と述べた。”
「つぶやきの部屋13」の中の「団塊の世代雑感(104)」「同(105)」と、安倍首相のメル
マガとはちょっと違うところがあるのですが、いずれにせよメルトダウンにビビった菅元首相が
注水を止めさせたことだけは確か。
またもや民主党の得意技「ブーメラン」(「ブーメラン」って、やぶへびのことですが)で終わるの
でしょうね。
これで確実に「カン」に「ア」の冠詞が付く。不逞菅氏が、ね。
♪ブーメラン ブーメラン ブーメラン ブーメラン
きっとあなたは 戻って来るだろう
カリッと音がするほど 小指をかんで
痛いでしょう 痛いでしょう
忘れないでしょう
そんなこといったあなたの後姿が
もうやがて見えなくなる 見えなくなる
した中にも東京都大田区の「不入斗村」とあります。
現在の地図には見当たらないので、調べてみたところ、昭和2年(1927)の口絵によ
ると、北に大井村、南に大森村、東に東京湾、西に新井宿村に囲まれた地域になり
ます。
現住所だと、不入斗村の字「八幡、潮田」が大森本町一丁目、大森北二、三丁目。
字「谷沢、谷中、川添」が大森北三~六丁目、字「中」が大森北一、三、四丁目、
字「高田、堀後、根岸の一部」が大森北一~四丁目となっているそうです。
その口絵が当時の状態を表したものかというと、そうではなくて、
・1889年(明治22年)5月1日 - 町村制の施行に伴い、不入斗村、新井宿村が合併して
入新井村が発足。
・1919年(大正8年)8月1日 - 入新井村が町制施行して入新井町となる。大字名は、
旧不入斗村が入新井、新井宿村が新井宿となる。
とありますから、明治22年以前の状態を口絵にしたものであることが分かります。
「不入斗」の名は、大正8年を境にして、地図から消滅してしまったわけですが、現在
でも平和島近辺にある公園や会社に、わずかではあっても、その名を留めています。
僕ら大森第一小学校を母校とする面々は、大半が旧大森村に住まいしていたことになる
のですが、さらに江戸の昔には、西大森村、東大森村、北大森村とに分かれていたそう
です。そしてそれらが明治5年(1872)に合併して大森村になったとあります。
嘉永6年(1853)の黒船来航で沿岸警備の必要に迫られた幕府が築いた台場の一つは、
僕らが写生に行ったことのある、旧大森ガス会社(現「ジャックニコラスゴルフセンター
大森」大森東3丁目28-1)の所にあったので、東大森村だったのでしょう。小学校
のある所もね。
この稿を興すきっかけとなった『ことばの歳時記』の項は、7月16日付の「そうめん」
と題するもので、
“ソウメンは漢字では素麺と書かれる。ソメンがソーメンとのびたのかと思うと、さに
あらず、もとこれは「索麺」と書いた。それをそそっかしい人がいて、「索」を「素」と
書きまちがえたのが起こりだそうだ。”
“宮中の古い儀式のことなどに詳しい人を「有識」と書いてユウソクと読むが、「職を
持つ」では意味がない。これは「有識」と書くべきものをやはり字をあやまったもの
という。”
“文字を知らない人のことを「目に一丁字(いっていじ)ない」というが、この「丁」は
元来片仮名のケを書いたもので「箇」の省画、一箇の字も知らないの意味だったが、
いつか「一丁字」と書かれるようになった。”
広辞苑によると、「一丁字」とは、「丁」は「个(か)」の古い書体を誤読したもの
(「个」は「箇」に同じ)で、一つの文字のこと。
と、それぞれの語源を正すものとして、「不入斗」も採り上げているわけです。
ともあれ、
ソメンでも、のびたソーメンでも、どっちでも良いから、素麺が食べたーい!
「日盛りや つるつる啜る 白き涼」(鈍末)
なんと読むかって?
「いりやまず」と読みます。漢字変換でも「いりやまず」と入力して変換キーを
押すと、「不入斗」が出てきます。
『ことばの歳時記』(金田一春彦)によると、
“これは「不入計」と書くべきもの、ここのあがりは税金に計算しないという有
難い土地だったのが、「計」の字の草字体が「斗」と書きあやまられ、今の「不入斗」
が出来てしまったという。”
とありますが、「計」の草書体は、ひらがなの「け」(基になった?)に近いので、
どう見誤れば、「斗」(草書体でもその形にさほどの違いは無い)になるのかしらん。
それに、ネットで調べてみたところ、語源には諸説あって、「不入計」の漢字誤読に、
「不入計」(いりよまず)の読みが訛って「いりやまず」となった説もあれば、
「昔は海岸地帯で土地は塩分のため田畑は殆ど収穫を上げることが出来ず、為政者が
耕作奨励の意味を持って貢税免除を宣言して不入斗村と称したと云われています。」
もあれば、「不入斗」を「いりやまぜ」と呼ぶ地名があることから、元は「入山瀬」
とか「入山津」とかであって、谷口集落を表すものであると云う説もあるし、
さらには、神社の領地であったために討ち入る事が禁じられていた「不入討」説なん
てものもある。
要するにいずれが正しいのか分からないのですが、ネットの住人が調べた興味深い
ものもあります。
それによると、「不入斗」では、
・千葉県市原市の「不入斗村」
・同県富津市の「不入斗村」
・同県富山町(現南房総市)の「不入斗村」
・東京都大田区の「不入斗村」
・神奈川県横須賀市の「不入斗村」
・静岡県袋井市の「不入斗村」(これだけが「いりやまぜ」と読む)
があり、さらに「入山瀬」や「入山津」だと、
・千葉県長生村の「入山須村」(現在の地名は入山津)
・神奈川県平塚市の上入山瀬村、下入山瀬村
・静岡県富士市の入山瀬村
・静岡県大東町(現掛川市)の入山瀬村
があり、
それらの場所を地図上に配置してみたところ、駿河から上総にかけて海岸線を結ぶもの
であることを発見したそうです。つまり、「入り組んだ山の瀬が連なるリアス式の海岸
地形を示す、入山瀬説」ではないかと。
でも、リアス式では無いと思うし、海岸線を結ぶということでは、「土地は塩分のため
田畑は殆ど収穫を上げることが出来ず、為政者が耕作奨励の意味を持って貢税免除を
宣言して不入斗村と称した」という方が理に適っているように思うのですよね。
させて頂くと、
戦後のベビーブームの世代(僕ら団塊世代です)が大学に進学するようになると、猫の額の
ような神楽坂キャンパスでは手狭なので、昭和42年に千葉県に野田キャンパスが造られ
ます。
それから、新しい学部ができる度に、昭和62年には北海道に長万部キャンパス(基礎工学
部)、平成5年には埼玉県に久喜キャンパス(経営学部)が造られます。
それから実験等の設備を整えようとすると、神楽坂は上に伸ばすしか手が無く、高い高い
ビルを建てようと計画したのですが、新宿区の条例がそれを許さず、代りに当時の理事長が
葛飾区への移転計画をぶち上げたのですが、神楽坂を聖地と考えてか、飲み食いできる旨く
て安い店が沢山あるからか、その辺りの事情は詳らかではありませんが、教員の中から反対
の声が上がったのです。
擦った揉んだの挙句、今年、神楽坂キャンパスの一部が葛飾キャンパスへ移転したのですが、
これまでその歴史を見てお分かりのように、「容器より中身」が明治14年以来の学校の理
念・伝統。
どこだろうと、どんな建物だろうと一向にかまわないのです。要は学生が第一。その勉学を
支え伸ばす教師と実験等の設備とが整っていればよいのです。その意味では、必要な設備の
整った葛飾キャンパスへの移転は評価できるものだと僕は思っています。
ここ何十年も彦星と織姫の逢瀬を見たことがありません。
とも書きましたが、一昨日の飲み会で、Kくんが、これを読んでそのようなことを云ったの
かどうか定かではありませせんが、1年経って相見えることができた彦星のようなことを云
ってのけたので、(アルコールの回った)君は、彦星どころか梅ぼしさ、テカテカ光り輝い
ているから1億何千万年に1回、近くを通り過ぎるだけのハゲー彗星かも知れないな、と云
ってやろうと思ったのですが…、江戸っ子じゃない僕には、そんな啖呵を切ることなんぞ
できゃせんぞな、もし。
さて、その後の物理学校ですが、大正12年(1923)9月1日午前11時58分、伊豆大島、
相模湾を震源として発生した関東大震災でも、神楽坂の校舎は、実験室の戸棚が倒れて
器具類が壊れり、教室の中の机や椅子がひっくり返ったりはしましたが、たいした被害を
受けませんでした。
昭和に入って、物理学校は神楽坂の校舎周辺の土地を次々と購入し、総校地は1200坪
(約3960㎡)にもなります。当初の3倍にもなったわけです。が、やはり狭い。
狭いながらも、昭和12年10月18日に鉄筋コンクリート4階建て(一部5階建て)、
延べ面積2291坪(約7560㎡)、総工費およそ38万円(約2億円)の校舎を新築
します。
僕が入学したとき(昭和42年)には、学部・学科が新設されるたびにそうなったのでしょう
けど、校舎が付足し付たしのような形で建てられていましたが、昭和12年に建てられた
校舎は、旧1号館として、そっくりそのまま残されていました。
昭和20年5月25日の東京大空襲の戦災では周りは被害を受けたのに、校舎は石炭庫を
焼いただけで、その殆どが無事であった。
そこには階段教室(1階)があり、教養課程のときには利用しました。それから学生課とか
生協(いずれも地下1階)もあったので、とくに生協はよく利用しました。それと当時1万
円という高額な実習費を支払ったコンピュータルームもありましたね。
そういったところに出入りしていたわけですが、ともに1回こっきりしか行かなかったところ
がありました。それは図書館と屋上。
どちらも迷路のようなところを通って辿り着いたのですが、なぜに屋上かというと、そこに
知る人ぞ知る小さな社があったからです。
その名も、誰が名付けたか、「落第神社」。実際は、御真影や教育勅語謄本などを奉安する
ための奉安殿なのですが、物理学校は進級が難しかったので、こぞって落第しないようにと
祈願した。にもかかわらず、落第する学生が多かったから、そのように呼ばれたそうです。
僕は、願掛けも何もしなかったけど、
“然し不思議なもので、四年経ったらとうとう卒業して仕舞った。自分でも可笑しいと思った
が苦情を云う訳もないから大人しく卒業して置いた。”
と相成りました。
各種学校から始まり、大正6年(1917)3月26日に専門学校となり、昭和24年2月21日に
東京理科大学として認可され、昭和24年4月、学制改革により、新制大学に移行して現在に
至ります。
昭和26年3月10日が、物理学校最後の卒業式となった。偶然にも通算100回目。
そして、3月31日、物理学校の幕が下ろされた。
戦後のベビーブーム(僕ら団塊世代です)が大学に進学するようになると、猫の額のような
神楽坂キャンパスでは手狭なので、あちらこちらにキャンパスが分散して造られるように
なります。
昭和42年には千葉県に野田キャンパス、昭和62年には北海道に長万部キャンパス、平成
5年には埼玉県に久喜キャンパス。
そして、今年、擦った揉んだの挙句、神楽坂キャンパスの一部が葛飾キャンパスへ移転。
当初、神楽坂に高い高いビルを建てようと計画したのですが、新宿区の条例がそれを許さず、
代りに当時の理事長が葛飾区への移転計画をぶち上げたのですが、神楽坂を聖地と考えてか、
飲み食いできる旨くて安い店が沢山あるからか、その辺りの事情は詳らかではありませんが、
教員の中から反対の声が上がったのです。
でも、これまでその歴史を見てお分かりのように、「容器より中身」が学校の理念。
どこだろうと、どんな建物だろうと一向にかまわないのです。要は学生が第一。その勉学を
支え伸ばす教師と設備とが整っていればよいのです。その意味では、葛飾キャンパスへの移
転は評価できるものだと僕は思っています。
それにしても、都心では
「灯を消せば 涼しき星や 窓に入る」(漱石)
とはならないですね。ここ何十年も彦星と織姫の逢瀬を見たことがありません。
兆しも無いのに例年より早い梅雨入り宣言がなされ、梅雨らしくない日々が続き、
その実感もわかないうちに例年より2週間も早い梅雨明け宣言となりました。
さて、『坊ちゃん』では、仕入れた情報の扱いに齟齬があったようで、小説の舞台と
なった明治28年と、それが執筆・発表された明治39年とが、漱石の中でごっちゃ
になっています。
坊ちゃんは、物理学校を卒業して直ぐに、中学校教師の口が掛かりますが、教員検定
の試験を受けずとも、卒業と同時にその資格(無免許教員ですが)が与えられるよう
になるのは、明治33年3月の「教員免許令」が発令されてからです。
そこには「文部大臣ノ定ムル所ニ依リ免許状ヲ有セサル者ヲ以ツテ教員に充ツルコ
トヲ得」といった但し書きがあった。
先に挙げた小倉金之助(明治38年卒業)も、その著書『数学者の回想』の中で
「世間に信用のある優良な卒業生を出そうというので、試験は相当に厳格でありま
した。維持員先生の中には文部省の中等教育検定試験委員がかなり沢山おったので
あります。そういうことから、おのずから中等教員を志願するものが多くなりまし
た。」とある。
坊ちゃんは、数学教師山嵐と一緒に教頭赤シャツと図画教師野だいこをやっつけて、
学校に郵便で辞表を送って、東京にとっとと帰ってきてしまって、“其後ある人の
周旋で街鉄の技手になった。”とあります。
その“其後ある人の周旋で街鉄の技手になった。”とあるのが、漱石の今一つの齟齬
で、街鉄つまり東京市街鉄道株式会社が設立されたのは、明治36年のことなので、
“その後”といっても、坊ちゃんは8年近くもプータローということになってしまい
ます。
それに続いて、“月給は二十五円で、家賃は六円だ。清は玄関付きの家でなくっても
至極満足の様子であったが、気の毒な事に今年の二月肺炎に罹って死んで仕舞った。”
とありますが、街鉄は、『坊ちゃん』が『ホトトギス』に掲載されたその年に、東京
電車鉄道・東京電気鉄道と合併して東京鉄道株式会社となってしまうので、清が亡く
なった二月には、街鉄そのものも無くなってしまっているのです。もっとも預言者な
らぬ漱石にそこまで求めるのは酷ですが。
それから、「技手」ですが、先に引いた司馬遼太郎の「文明の配電盤」には、
“当時、官庁の技術畑に、技師と技手(まぎらわしいために"ぎて"ともいった)の区別
があった。
技師は、西洋の工学技術を身につけた人で、具体的には明治中期までは東京大学の
理工系の出身者にして官庁に奉職している人のことをいった。ついでながら、明治
三十一年の「技術官俸給令」では"技師は奏任とし、技手は判任とす"とあり、まこと
におもおもしい。
技師は高等官であり、高等官とは、旧幕府の制度でいうと、将軍に御目見得できる
身分のことで、旗本がそうであった。
おなじ幕臣でも御家人は御目見得できないから、明治の判任官にあたる。”
とあります。ですから、25円(現在だと31万円ほど)は、妥当な線です。
の話が出てきますので、漱石自身が赴任した明治28年4月と同じ設定にしてありますから、同年
2月17日になります。
そうだとすると、明治25年に入学したことになりますが、その年の物理学校入学者は707名、
それが明治28年の卒業生となると、たったの34名になるのですから、小説にあるように、
“三年間まあ人並に勉強はしたが別段たちのいい方でもないから、席順はいつでも下から勘定する
方が便利であった。然し不思議なもので、三年立ったとうとう卒業して仕舞った。”
というほど進級、卒業は簡単なものでは無かったのです。つまり坊ちゃんは成績優秀だった。
ちなみに、物理学校は、明治24年に規則を改正し、修業年数をそれまでの二年から、二年半
として五学期制をとっています。ですから入学したのは明治25年の9月になる勘定です。
(生徒募集は夏の暑い盛りに貼り出してあったことになります。)
坊ちゃんが“六百円を三に割って一年に二百円宛使えば三年間は勉強が出来る。”と云っている
のも、600円は現在だと約800万円ですから、1年あたり260万円強で考えているわけで、
授業料五学期すべてで27円(現在だと35万円ほど)の出費と、四畳半の安下宿の部屋代と、
あとは食費等ぐらいですから、十分やって行けたのです。
だから、
“卒業してから八日目に校長が呼びに来たから、何か用だろうと思って、出掛けて行ったら、四国
辺りのある中学で数学の教師が入る。月給は四十円だが、行ってはどうだと云う相談である。”
と教師の口、それも40円(現在だと、50万円以上の初任給と云うことになります)。
漱石自身は、校長の月俸が60円だと云うのに、80円だったのですが。
先述の「学園生活」にある
“牛込に住む漱石は建築中の本校の門前をたびたび通ったので、それを『坊ちゃん』のなかで使った
のだろう。”
は眉唾ものでしたが、
“東京物理学校の神楽坂移転は、今まで学校のなかった場所だけに、周囲にいろいろの逸話を残した。”
とあるのは本当。
啄木の明治41年10月29日の日記に「北原君の新居を訪ふ。吉井君が先に行ってゐた。二階の
書斎の前に物理学校の白い建物。瓦斯がついて窓という窓が蒼白い。それはそれは気持ちのよい色だ。
そして物理の講義の声が、琴や三味線と共に聞える。・・・」とありますが、北原君というのは詩人
北原白秋のことで、白秋が物理学校裏に引っ越してきたのは啄木が訪れた少し前のこと。
白秋の目にも物理学校は奇異に映ったのでしょう。詩集『東京景物詩及其他』(明治四十三年三月)で
「物理学校裏」と題する奇っ怪な詩を発表しています。
やたら長いし、全部書くと読む方も頭が痛くなるので、一部だけ紹介します。
“C2H2O2N2+NaOH=CH4+Na2CO3……
蒼白い白熱瓦斯の情調(ムウド)が曇硝子を透して流れる。
角窓のそのひとつの内部(インテリオル)に
光のない青いメタンの焔が燃えているらしい。
肺病院の如(やう)な東京物理学校の淡(うす)い青灰色(せいくわいしょく)の壁に
いつしかあるかなきかの月光がしたたる。”
うーむ、これだけでも頭が痛くなる。
えっ、いままで読んできて頭が痛くなったって?
神田区駿河台南甲賀町(現千代田区神田駿河台一丁目)の校舎に毎週(講師として)通っていま
した。そして、この校舎と物理学校は距離にして400mほどしか離れていませんでした。
漱石が『坊ちゃん』の舞台となった愛媛県尋常中学校教諭(明治28年4月赴任)をたった1年
で辞めて、明治29年4月に赴任した熊本の第五高等中学校の当時の校長は、司馬先生の云う
「維持同盟を結んだ」16名の一人である桜井房記。
最初の創設メンバー21名のうち、2名は中退者であった(理学士でなかった)ため、維持同盟
参加を辞退。あとの2名はいずれも肺結核で病没。
桜井は、漱石が明治33年に英国留学を国から命じられたとき、心配する漱石の相談に乗ってや
ります。桜井が英国と仏国にかって留学した経験があったからです。
さらに、漱石の小石川区西片町の家の近所に住んでいて、漱石と昵懇の中であったのが、やはり
維持同盟メンバーの一人、中村恭平。中村は、『坊ちゃん』が世に出るころ、東大助教授の他に
学生監を兼務していて、東大総長の山川健次郎(「八重の桜」にも出てくる人物です。初め白虎隊
に組み入れられたものの、15歳であったため幼少組に格下げとなって、籠城して戦いました。)
の秘書役でもあったことから、明治大学だけでなく東大文学部英文科の講師も務めていた漱石と
親交を結ぶようになったのだろうと思います。
もう一つ、漱石を触発したエピソードとしては、漱石と同じ名前の小倉金之助が挙げられます。
小倉は、『坊ちゃん』が書かれた前年の明治38年に物理学校を卒業し、直後に東京帝国大学
理科大学化学選科に入学したものの、悪性の風邪に罹り療養のために、中退して故郷山形に帰郷
せざるを得なくなります。小倉は、後(大正5年)に、東北帝国大学から理学博士号を授与され
るほどですから、その英才を惜しむ話が漱石の耳にも入った可能性があります。
以上から、愛媛県尋常中学校(松山中学校)教諭時代のことを小説に使おうとしたした漱石は、
『吾輩は猫である』と同様に自虐趣味を存分に発揮して、自身を赤シャツに譬えて、主人公に
物理学校卒の坊ちゃんを配したのだと思うのです。
そのためには、当時の物理学校のことを一通り情報収集しておく必要がある。で、神田小川町1番地
の物理学校に何度か立ち寄ることがあった筈なのです。(工事中の牛込区神楽町2丁目24番地へ
行っても誰もいませんからね。)
ですから、“幸い物理学校の前を通り掛ったら生徒募集の広告が出て居た”とあるのは、赤レンガ
の小川町校舎のこと。それに、坊ちゃんが、そのときに下宿していたのは“しばらく前途のつく迄
神田の小川町に下宿していた。”、“俺は四畳半の安下宿に籠って”、“此三年間は四畳半に蟄居
して”とあるように、神田小川町。
つまり、物理学校の近所に下宿していたことにしてあるのです。それならいつも通って目にしている
物理学校に生徒募集広告が貼り出してあって、それが目に留まった、というシチュエーションも納得
の行くものになります。
明治14年(1881)9月11日に、日本で最初の私立理学学校として誕生したときの名称は、
東京物理学講習所でした。その校舎は自前のものでなく、東京府麹町区飯田町4丁目
1番地(現在の千代田区九段下)の稚松(わかまつ)小学校の教室を夜間だけ間借りすると
いうものでした。
最初は、物理学だけでしたが、翌年9月からは算術、代数、幾何の三教科をも教授
するようになりました。椅子や机のサイズは小学生用の小さなものだし、電燈が普及
していなかったこともあり、石油ランプを使用しての授業ですから、さぞかし苦労
したものと思います。
東京物理学校と改称するのは、明治16年9月のこと。このときには自前の校舎があり
ました。前年の9月頃だと思えるのですが、神田区小川小路三丁目九番地に建坪30坪の
教室と小使い室をつけただけの小さな校舎を建てたのです。もちろん創立に加わった
21名の先生たちの拠出金でです。
この地に校舎を構えるまで、稚松小学校から神田区錦町の大蔵省簿記講習所へ移り
(明治14年暮れ)、さらに本郷区元町2丁目の進文舎に転居(明治15年)しています。
司馬先生の「神田の地」とあるのは、この自前の校舎での東京物理学校としての出発
を指します。
でもこの校舎、明治17年(1884)9月15日の台風により倒壊してしまうのです。
それでまた、あちこちでの間借りを余儀なくされます。
明治17年9月、麹町区九段坂下牛ヶ淵にある共立統計学校を間借り。
明治19年9月、神田区駿河台淡路町の成立学舎に移転。
そして、明治19年11月、神田小川町1番地の仏文会校舎を借りるようになります。
それも又借り。持ち主は、東京法学校(法政大学の前身)で、左右対称のレンガ建て平屋
の右半分を東京法学校が使用し、左半分を仏語学校である仏文会が借りて使用していた
のですが、仏文会の方は昼間だけの授業であったことから、夜間は物理学校が借りること
にしたのです。
この建物、明治10年代初期に建てられた缶工場だったものを東京法学校が購入して使っ
ていたもので、窓が少なく室内は暗かったと云います。また内部は相当荒廃していたの
で、生徒たちはトンネル学校とか北極学校と呼ぶようになったそうです。北極点ではそれ
以上北が無いので「北ない極み」、つまり「汚い極み」という意味です。
明治22年から数学の教師を勤めた野口保興という人が、回顧譚として、「小川町ノ
校舎如キ婉然罐工場ノ感アリテ教場ノ傍ニ便所ガアツテ講義スルトキナド随分臭イ思
ヒヲナシマシタ」と語っている。
そのような校舎でも、物理学校にとっては大金だったのでしょうけど、2,200円(現在
だと5,000万円位)で購入します。明治21年12月のことでした。
東京法学校の移転に伴い、購入話が出たようですが、全棟を購入したわけではなくて、それ
まで使用していた左半分だけ。(右半分は、活版工場に売却された。)
建物の真ん中に廊下があって、その両側に区切った教室があったようで、その面積は合わせて
105.5坪。そこにかなりの数の生徒(明治20年の入学者237、21年の入学者は520)
が学んでいたので、かなりのすし詰め状態であったわけです。
で、これを解消すべく、明治30年2月の入学生からは昼夜のクラスに分けられるように
なりますが、校舎の方は明治28年に物理実験室を増築したぐらいで、明治39年神楽坂に
移るまで殆ど手入がなされない有様でした。
明治30年9月にガス灯が取り付けられるまでは、石油ランプを吊るしての勉学。電気照明
になったのは、神楽坂の校舎になってからのこと。
結論から云うと、坊ちゃんが入学したのは、写真にある白亜のしゃれた校舎では
ないと。なぜなら、『坊ちゃん』が最初に掲載されたのは雑誌『ホトトギス』で、
それは明治39年の4月号。
物理学校が牛込区神楽町2丁目24番地に校舎敷地約394坪(約1300㎡)を
購入したのは、前年の11月のことで、竣工が翌年9月ですから、3月~4月は、
未だ工事半ば。
その工事現場を漱石が通りかかって、坊ちゃんを物理学校卒業生にする着想を得
たという可能性は極めて低いと思います。なぜなら、漱石が、小石川区(文京区)
西片町10から神楽坂に近い牛込区早稲田南町に移ってきたのは、明治40年9月
のこと。それに『坊ちゃん』執筆当時は、神楽坂からは大分離れた駒込千駄木町
に居を構えていたのですから。
構想を温めていたからこそ、1週間といった短期間で書き上げることができたの
だと思いますし、実際、漱石と物理学校の係わりは、それよりずっと以前にあっ
たのです。
その辺りのことをこれから見て行くことにしましょう。
文藝春秋社から刊行された『この国のかたち』(全6巻)という本があります。
司馬遼太郎が1986年から1996年にかけて雑誌「文藝春秋」の巻頭随筆欄に
連載してきたものを、6巻に分けている。第1巻は1986~1987年のものが
収録されてあって、1990年3月25日に第1刷が出版され、第6巻は1996年分
が収録されていて、第1刷は1996年9月10日に出ている。一定の枚数がたま
ると、そのつど本になったことが分かる。
その第3巻(1990~1991、1992.5.25第1刷)の中に「文明の配電盤」と題する
ものがあって、以下のように記されています。
“まことに明治初年、西欧文明受容器の日本は一個の内燃機関だった。
その配電盤にあたるものが、東京帝国大学(以下、東京大学)で、意識して
そのようにつくられた。いまでもこの大学に権威の残像が残っているのは、
そのせいである。(中略)
神田には江戸時代から文武の私塾が密集していて、明治後、いっそうふえた。
そのうちのいくつかが、こんにちでは総合大学、もしくは単科大学になって
いる。
これは、明治の配電盤と関係がるのではないか。
幕府の洋学機関開成所は神田一ツ橋におかれ、それが明治後、東京大学に
発展した。やがて本郷台にうつるこの大学は、明治初年は右の神田一ツ橋
から出発した。神田はいわば地元だった。
自然、国力を傾けてつくられたこの巨大な配電盤は、地元の神田の私学に、
いわば漏電するようにして、"新文明"をこぼした。
そのなかで高貴ともいうべき例がある。神田に設けられた私学の一つ東京
物理学校(こんにちの東京理科大学)のことである。
明治初年、東京大学の理工系を出た人達には、国家のカネによって学問を
さずかったということで、恩恵を感ずる人が多かったらしい。
とくに明治十二年(一八七九年)前後の理学部物理学科の卒業生にその意識
がつよかった。
かれら二十一人は、同盟を結び、報恩のために一私学を興そうと申しあわせた。
ただし、金がないために当初は他の学校の校舎を間借りした。さらには、夜学
にした。
明治十四年における東京物理学校の出発である。
資金はすべて"配電盤"である右の学部の卒業生たちの拠金によった。かれらは
維持同盟を結び、その規約のなかで、
「会員は三十円を寄付すべし」
という項目を設けた。当時、下級官吏が月に十数円をとればいいほうだったから、
この額は安くなかった。ただ、月賦もゆるした。月賦の場合、一円以上は納よ、
とある。むろん寄付の見返りはなく、まったく無償そのものであった。
もっとも、理学部卒業生は官庁などに就職していて、すくなくとも四十円はとって
いたから、月々一円を割くことは、過重とはいえなかった。(中略)
物理学の教授や研究には、実験用機械など膨大なカネが要る。それらは当時東京
大学しか所有しておらず、維持同盟のひとたちの毎月一円以上の拠金でなりたって
いる東京物理学校にあっては、そんなものを買う金はなかった。
この事情を東京大学理学部はよく理解した。
そこで、日中、大学がそれらを使用すると、夕方から物理学校へそれらを大学の
使丁が運搬したという。このことは、毎日、数年もつづけられた。官物が私的に
つかわれることはゆるされることではないのだが、あえて大学はこの便法をとった。
配電盤が、国家の将来のために志をもって漏電していたのである。(後略)”