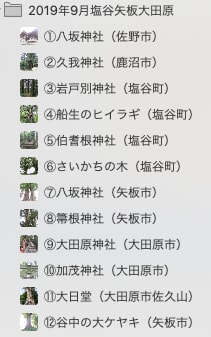2018.7.26〜27に茨城県北部の巨樹巡りをしてきました。
旅のお供は新規購入した「
Canon EOS Kiss M」(前項参照)。
「
EOS 80D」と同レベルの機能を持ちながら、ミラーレスというシステムのおかげでより軽く、一日中持ち歩いてもストレスになりませんでした。
私にとって究極の“旅カメラ”になりそうな気配。
雑誌「家電批評」で“神レンズ”と言われた広角レンズ(
EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM)で巨樹を撮影しまくりました。
一つ気づいたメリット。
このカメラ、“白飛び”しません!
神社の境内は暗めで、拝殿の屋根は太陽で光ってしまい、コントラストが強く“黒つぶれ&白飛び”しやすい撮影環境にもかかわらず、です。
これは「
オートライティングオプティマイザ機能」のおかげと思われます。
訪問・参拝したリストは以下の通り;
 1.安良川八幡宮の爺杉(高萩市)
1.安良川八幡宮の爺杉(高萩市)
常磐自動車道の高萩ICで降りて、まず向かったのは安良川(あらかわ)八幡宮。
ここには「爺杉」と呼ばれる巨樹(樹高40m/幹周10m/樹齢1000年、国指定天然記念物)があります。
スギの巨木に囲まれた参道は日陰でいと涼し。

到着して気がついたのは、風鈴の音。
ガラスの風鈴がたくさん鳴り響いていました。
「願い風鈴」と書かれていました。

正面へ進み、拝殿で参拝。本殿も立派です。


目的の爺杉を探すと、それは拝殿の左奥にありました。
巨大な樹影、圧倒的な存在感。
しばし見とれていました。
事前情報では「満身創痍で樹医の手が入っている」だったのですが、想像より元気そうで安心しました。

 2.松岩寺の山桜(高萩市)
2.松岩寺の山桜(高萩市)
次の目的地である大塚神社に向かう途中で見つけた桜の巨樹。
停車して看板を読むと「松岩寺(しょうがんじ)のヤマザクラ」とありました。
ネットで検索すると「樹高25m/幹周5m/樹齢350年、県指定天然記念物」とのこと。
花が咲く春はさぞかし美しいことでしょう。

 3.大塚神社のスギとモミ(高萩市)
3.大塚神社のスギとモミ(高萩市)
この神社は道路に面する急峻な小山の上に鎮座しています。
地方の神社ではよくあることですが、駐車場がなくて困りました。

急峻な石段を登っていくとまず目に入るのは、参道を両側から挟み込むように屹立する2本の杉の大木です。このスギが成長すると、いずれ通れなくなってしまいそうなほど狭い。


そこを通り過ぎて振り返り、上から見下ろすと、2本の杉の枝振りがすばらしい。

境内まで登ると、モミの巨樹(樹高40m/幹周5m/樹齢500年、県指定天然記念物)が目に入りました。
空に向かって迷うことなく真っ直ぐ伸びていて気持ちいい。
ここまで育ったモミの大木に出会うことは滅多にありません。




拝殿で参拝を済まし、スギの巨樹(樹高45m/幹周6.8m/樹齢500年)を探すと、それは拝殿・本殿の裏にありました。



こちらも太い幹が空に向かって真っ直ぐ伸びていています。
スギは樹齢500年を越えると自分の重さに耐えかねて寿命を全うしますが、この巨樹はとっても元気そうです。
樹皮をペタペタと叩いてエネルギーをたっぷりいただきました。
4.猿喰のケヤキ(常陸太田市)
次に向かったのは昔の街道沿いにあるらしいケヤキの巨樹(樹高23m/幹周8.8m/樹齢550年)。
“猿喰のケヤキ”という変わった名前で、“猿喰”とは地名だそうです。
が、行けども行けどもなかなか見つかりません。
あきらめかけた頃、小さな看板を見つけました。
それも進行方向からは裏しか見えず、振り返ってはじめてわかる片面看板。
なんだか「教えたくない秘密の・・・」という雰囲気を感じ、ワクワクしながら林道を車で進むこと約5分、巨樹が悠然たる姿で迎えてくれました。
その神々しい姿に思わず息をのみました。





巨樹巡りをしていると、1回の行程でひとつくらい、このような“邂逅”を経験します。
それは下調べの段階では予想がつきません。
現地に行って、見て触って初めて体感できること。
車を降りて、写真を撮りまくり、樹皮をペタペタ触りまくりました。
巨樹のそばに「山神」と彫られた石碑がありました。

なんというか・・・いつまでもそこにいたい、という気持ちになりました。
連れ合いも同じ気持ちになったようで、「ここから離れたくないね」と二人で頷き合いました。
5.武生神社の太郎杉(常陸太田市)
「たけお」ではなく「たきゅう」と読みます。
曲がりくねった細い山道をひたすら進んでようやくたどり着ける山の神社。
1人で来るには勇気が必要な林道です。
到着し、急な石段を登ると楼門や梵鐘がありました。
神仏習合の名残でしょうか。






拝殿で参拝を済ませ、目的の巨樹を探すと、それは拝殿・本殿の裏にありました。
愛称は太郎杉(樹高35m/幹周5m/樹齢700年)。


幹の太さは樹齢に比して細身と感じましたが、枝振りが勇壮です。
それも不思議なことに、北西側だけに延びているのです。
あ、説明板に理由が書いてありましたね。
昔ここには同レベルのスギの巨木が林立しており、その一番端にあったので外側にしか枝を張れなかったようです。なるほど。


 6.御岩山神社の三本スギ(日立市)
6.御岩山神社の三本スギ(日立市)
三本スギ(樹高60m/幹周8.4m/樹齢500年、県指定天然記念物)は「
森の巨人たち100選」に茨城県で唯一選ばれている名木です。
「御岩山三本杉」という看板に導かれて到着したのは午後6時。
「カナカナカナ・・・」というヒグラシの鳴き声が響き渡っていました。
その巨樹は参道脇にありました。
美しい樹形。
樹高60m・・・見上げても樹冠がよく分かりませんでした。
ここでタイムリミット。
宿泊先の「
水戸プラザホテル」に向かいました。
部屋が広く、街中にあってリゾートホテルのような、よい雰囲気のホテルでした。
さて2日目は、水戸市・那珂市周辺〜常陸太田市の「三浦杉」を回って帰路につく予定。
7.水戸八幡宮のオハツキイチョウ(水戸市)
本殿は国指定重要文化財だそうです。
水戸市内にありながら、境内の広さと、摂社・末社の数の多さに驚かされました。
オハツキイチョウ(樹高35m/幹周9.5m/樹齢600〜800年、国指定天然記念物)は「
右近の桜」の奥、拝殿・本殿の向かって左側にありました。
生命力に溢れた威風堂々たる御神木です。
老木ですが、とくに傷んだ部位は見当たりません。
参道の脇道の先に大きな樹影を見つけ、誘われるようにそちらに向かうと「烈公御涼所」と名付けられた場所に大きなケヤキ(樹齢300年?)がありました。
「茨城百景」の一つであり、「朝日御来迎の御聖地」とのこと。
8.笠原神社のスダジイ(水戸市)
茨城大学の南に接するくらい近くにある小さな神社。
御神木であるスダジイ(樹高30m/幹周7m/樹齢500年)が大きな木陰をつくっていました。
9.清水寺のスギ(那珂市)
「きよみずでら」ではなく「しみずじ」と読むそうです。
公園内にある巨大な杉(樹高30m/幹周5.2m/樹齢500年)ですが、所属は高台にある小さなお寺のようです。
枝振りが猛々しい。
安全のためか、いくつかの枝は切られていますが、それでも迫力があります。
昔訪ねた栃木県鹿沼市の「ツボ小杉」に似ているな、と思い出しました。
10.不動院のカヤとイチョウ(那珂市)
カヤ(樹高30m/幹周5.5m/樹齢650年)は均整のとれた美しい樹形です。
葉の付き方が少し薄いかな(群馬県の「横室の大カヤ」と比べると)。
ただ、周囲に電線があるのでそれを避けての写真撮影が困難なのが玉に瑕。
イチョウ(樹高20m/幹周4.6m/樹齢300年)は枝打ちされてシンプルな形になっており、巨樹としての魅力はまだまだ・・・今後の成長に期待しましょう。
11.菅谷のカヤ(那珂市)
民家の庭の中なので、許可をいただくべく呼び鈴を鳴らしたのですが、不在のようでした。
なので写真は遠景のみ。
12.鷲神社の大杉(那珂市)
「わしじんじゃ」と読みますが、地元では親しみを込めて「おおとりさん」と呼ばれているようです。
御神木のスギ(樹高23m/幹周5.2m/樹齢500年)は境内の端、道路に近いところにありました。枝が電信柱に引っかかりそう。
13.三嶋神社のスダジイ(那珂市)
小山の上に鎮座する神社で、御神木のスダジイ(樹高19m/幹周10m/樹齢800年)は鳥居のすぐ左奥にあり、鳥居に覆い被さっています。
枝振りが複雑怪奇で、800年の歳月は樹木を別物に変化(へんげ)させてしまうようです。
鎮守の杜は広く深い印象でした。
14.若宮八幡宮のケヤキ(常陸太田市)
開けた山の中腹にある神社。
参道脇にはケヤキの巨樹がボン、ボンと林立しており圧巻です。
一番大きなケヤキ(樹高30m/幹周8.4m/樹齢500年)は、鳥居のすぐ右奥。
私が見てきたケヤキの中でも幹周が半端なく大きく、樹齢表示の500年より古いのではないでしょうか。
常陸太田市街を見渡せる、眺めのよい境内でした。
15.香仙寺のスダジイ(常陸太田市)
このスダジイ(樹高29m/幹周8.2m/樹齢不明)は葉が濃いため、樹形は確認できても枝振りが分かりません。幹周は8mもなさそうですが・・・。
このお寺には「直牒洞」(じきてつどう)という、岩をくりぬいた奥に仏様が描いてある穴が3つあります。名前の由来は了誉聖冏上人という僧侶がここで書き綴った「決疑鈔直牒」という書籍だそうです。
16.静神社のヒノキ(那珂市)
「常陸国二ノ宮」として期待して参拝したのですが・・・境内は草が生え放題で手入れが行き届かない印象でした。
ちょっと寂しい。
そして目的のヒノキの巨樹は既に枯れて切り株になっていました。
その前の御神木であった杉の巨樹は、痕跡としての樹皮が小屋に保存されていました。
境内でひとり作業をしていた庭師さんが話をしてくれました。
「自分が子どもの頃は何本か大きな御神木があったが、みんな枯れてしまった」
「大きな木が見たいのなら、すぐ近くの桂木稲荷神社へ行くといい」
17.桂木稲荷神社のムクノキ(那珂市)
庭師さんに教えてもらうまでもなく、下調べを尽くした私はこの神社を次に参拝する予定でした(^^)。
静神社のすぐ東側、畑の中にポツンと緑の塊となっており、わかりやすい。
ただ、駐車場がありません。
まあ、地方の小さな神社には基本的に駐車場はありませんが。
それから、鳥居が崩れていました。
これもちょっと寂しい。
大きな樹木が2つあり、背の高い木は目的の巨樹ではなく、背が低くて幹が太く枝がクネクネしている方が目的のムクノキ(樹高30m/幹周7.25m/樹齢900年)でした。
樹皮は枯れ気味で容易に剥がせそうな雰囲気ですが、枝の先にはたくさんの緑の葉を付けており、900年という歳月を経てもなお生命力を感じます。
18.紅畔寺のイチョウ(常陸大宮市)
桂木稲荷神社と吉田八幡神社は距離があるので、その間に差し込んだ感のあるお寺です。
ここのイチョウ(樹高35m/幹周5.6m/樹齢320年)も、枝打ちされているのかシンプルな形。
19.吉田八幡神社の三浦杉(常陸大宮市)
最後の参拝先です。
三浦杉(樹高59m/幹周10m/樹齢800年)は杉野巨木に囲まれた参道の石段を登っていくと、拝殿の手前にあります。
いや〜、よい雰囲気です。
同レベルの太さのスギの巨樹が2本、真っ直ぐ空に向かって伸びており、800年という歳月を経ても樹形が全く崩れていない名木です。
ただ、枝が落ちて危険なのか、立ち入り禁止になっていて近くまで寄れませんでした(T_T)。