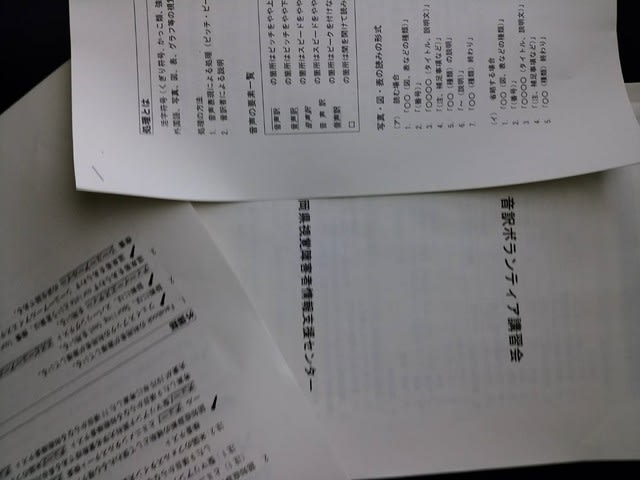9月29日 掛川市立図書館で、音訳ボランティア講習会が無事に開催されました。
参加者の方々にはコロナ感染症予防対策として、検温や手指の消毒、窓の開放(換気)、終日のマスク着用にご協力いただき、本当にありがとうございました。
広い会場で座席を離す為、机一つに一人ずつ。試行錯誤しつつ会場設営を行いました。

講師の安田知博さんからの自己紹介。コロナ禍で講演会が激減した事や、各地の様子などのお話がありました。中止にされたり、オンラインでの開催の所もあり、今回は貴重な対面講演の機会となりました。今後、Withコロナの時代の講演等や音訳活動のあり方も考えていかなくてはいけないと考えさせられました。
各地の「音訳」の現状として、本の点訳は3ヶ月かかる。パソコンの読み上げ機械だと1ヶ月でできる。でも、音訳は半年かかってしまう。とても時間がかかってしまうし、今では明瞭な発音で機械の方が正確。それでも、全てが機械の合成音声で良いというわけではない。選択できる体制がある方が聞き手にとっては良い。ところが、どこでも音訳をするボランティアは減っている。シニアは仕事が延長され、専業主婦は少なく仕事をする人が多い。音訳する人がいないから合成音声で我慢しろ・・・という話にはしたくない。音訳が継続できるシステム作りが大事とのお話がありました。
また、各地のボランティアの連携についても、問題提起をされていました。ボランティアであるがゆえに各地で活動しているが、音訳する作品が重複してしまっていたり、その場で留まってしまっている。ローカルな本の音訳など、集中して検索できるようにするなど、サービス同士の連携ができると良いとの事でした。
自己紹介の後、テキストの文章を参加者が順番に読んでいきながら、「文章を読む」という事について、センテンス事に細かく解説を頂きながらご指導頂きました。
AIの作り出す「合成音声」は、人が読み編集するのに比べてとても早く対応する事が出来ます。合成音声そのものも、AIに学習させていく事で、最近では随分と滑らかになってきました。それでも「人が読む」事も必要なのは、文章の意味をくみ取って、「伝えたい事に焦点を合わせて伝えていける読み方」ができるという事。その為には、文章を読み込んで、「何を伝えたいか」を明確に理解する「読解力」が大事である事を、テキストを読みながら学んでいきました。「伝えたい事」がはっきりしてくると、「どう読んだら、そう伝わるのか」という「音読の技術」が生きてくる。同じ、鍵カッコ内の読み方でも、速さや音の高さが違ってくる。息継ぎの場所が違う事で、聞いた時の「文意」も変わってくる。文章の「句読点」を正確に読むだけでは伝わらない。テキストを読みあいながら、実感していきました。
文章の意味をくみ取り、伝えたい事の「意味のまとまり」を作るのは、「読み人」である。「読み人」として、「必要な情報を正確に伝える」ことが「音訳」なのだと、改めて思いました。
今回、開催にあたり、市の福祉課や中央図書館の皆様には大変お世話になりました。サークル声では、講演会活動を通して様々な世代の方が「音訳」に関心を持ち、その後、スタッフとして参加して下さってます。様々な立場の方々にも協力して頂きながら、活動を「継続」していく事の大切さについても考えさせられた講習会になりました。 ありがとうございました。










 とはいえ、まだ予断を許さない状況ではありますので、コロナ感染症予防をしっかりとしながら、無事に開催できますように、祈っています。
とはいえ、まだ予断を許さない状況ではありますので、コロナ感染症予防をしっかりとしながら、無事に開催できますように、祈っています。

 (実際、窓を開けて過ごせるような陽気でしたね
(実際、窓を開けて過ごせるような陽気でしたね )
)
 と思いながら読ませて頂きました。講習会で教えて頂いた留意する所に気をつけつつ、たくさんの参加者の方達の読み方を聞く中で、何気なく聞いていた「言葉」の「音」が少しずつ明瞭に聞きとれるようになってきたように思います。あとは実践、練習あるのみ!ですね
と思いながら読ませて頂きました。講習会で教えて頂いた留意する所に気をつけつつ、たくさんの参加者の方達の読み方を聞く中で、何気なく聞いていた「言葉」の「音」が少しずつ明瞭に聞きとれるようになってきたように思います。あとは実践、練習あるのみ!ですね


 子育ての大変な中、興味関心を持って参加して頂けて嬉しかったです。図書館の方が子どもさん向けに、さっと絵本を持ってきてくださるお気遣いにもキュンキュンと萌えてしまいました
子育ての大変な中、興味関心を持って参加して頂けて嬉しかったです。図書館の方が子どもさん向けに、さっと絵本を持ってきてくださるお気遣いにもキュンキュンと萌えてしまいました また、寛容に受け入れて下さっている参加者のみなさんの暖かさにもホッコリとしておりました。有難いなぁ~
また、寛容に受け入れて下さっている参加者のみなさんの暖かさにもホッコリとしておりました。有難いなぁ~


 )、情報交換をしました。それぞれの団体で録音の手法なども違いますが、「聞きやすい音訳」を目指す者同士、お話は尽きませんでした。また、音訳に興味を持って参加して頂いた方からも、「やれるかも・・・」と言っていただきました。是非是非、お待ちしております
)、情報交換をしました。それぞれの団体で録音の手法なども違いますが、「聞きやすい音訳」を目指す者同士、お話は尽きませんでした。また、音訳に興味を持って参加して頂いた方からも、「やれるかも・・・」と言っていただきました。是非是非、お待ちしております