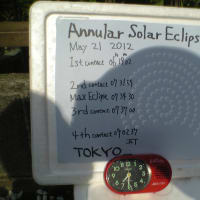各種サイトを見ると、1938年12月22日のシーラカンス発見話に関して、おかしな話が伝言ゲーム的に伝わり、奇妙なことが書いてある例が散見される。
信頼できると思われる書籍を2冊紹介したい。
さらに、信頼できると考えられるサイトへのリンクも。
生きた化石 : シーラカンス発見物語 | NDLサーチ | 国立国会図書館
著者名:J・L・B・スミス/著 梶谷善久/訳
1981年11月
恒和出版
後者はJLBスミス博士の「Old Fourlegs」の翻訳。
1938年の最初の標本と、1952年の第2標本入手の経緯が記載(後者についてがより詳細)。
博士的には、1938年の際はコートニー・ラティマー女史からの第1報を知るのが遅れたために内臓を廃棄されてしまったという痛恨の出来事*。
*1938年のどたばた(上記図書などから南面堂が理解した内容であり、正確性は保証されない。誤解しているかもしれないもん)
スミス博士は、避暑・療養(体弱い)と試験の採点(化学の教授。魚類研究は趣味)のため、クリスマス休暇中は町から離れた海岸の別荘に滞在中。
正月明けに転送されてきた女史の手紙とスケッチを見て「君、それは動物学上の大発見の可能性があるよ!」と返事を書くが、一歩遅く内臓は廃棄後。
女史としては、重要性ある標本だとの認識はあり、町の冷蔵倉庫と病院の遺体安置所に掛け合うも「腐りかけた巨大魚なんて」と保存は断られ、やむなく剥製師に作業を依頼する。
「博士に電話は通じないし、手紙の反応もないし、困ったわね。しょうがないか・・」と内臓廃棄に踏み切る。
脂分がとても強くて、独特の悪臭がすごくなってくるのだそうです。
「剥製でも仕方ないけれど、内臓は何とかしてとっておいてね!」という連絡をもらったときには遅く、清掃局に照会したら、「ごみはもう海に捨てました」との回答。後の祭り…
でもスミス博士は女史の対応を(困難な状況で最善の対応をした、科学者は彼女に感謝すべきである、と)たいへん高く評価して、学名(科名)にラティメリアを採用。
トロール船の船長からの知らせ(「とても奇妙な魚がかかったんだわ。あんたが欲しがると思ってさあ」)で・・・という1匹目に係る手紙のやりとりなど、興味深い:
Moment of Discovery
Relive the excitement of the coelacanth's first appearance.
2匹目の入手(1952年)までが大変でした!という経緯の一部:
http://www.fathom.com/feature/121979/
…スミス博士が作った懸賞金のチラシや、第2標本の引き取りに赴いた際の空軍輸送機のクルー一同と記念写真などもあり
(ちなみに同記念写真で前列左が、地元漁師から魚を引き取って博士に通報したハント)
1938年の第1号標本の後、「1尾生きて発見されたのだから、必ずまた見つかるはずだ」と戦争をはさんで14年間の執念の追跡の結果、予想外の遠隔地コモロ諸島で漁獲された。
1952年の出来事のほうが、博士本人にとっては達成感が大きいこともあってか、(首相に直訴して)南ア空軍に輸送機を仕立ててもらって引き取りに行った経緯など詳細記述あり
(このへんウィキペディアにも記載あります)。
仏領コモロ諸島(当時)の知事がその価値に気づいて待ったをかけないうちに、なごやかにかつさっさと持ち帰りたいという、表に出せない苛立ちなども。
(知事は博士一行の歓迎会を開いてくれたりする…僻地の植民地行政官が退屈しているという、ありがちな映画のような光景?)
…これを悟ったお茶目な輸送機クルーが、魚を積み込んで南アに向けて無事離陸後、「仏当局が当機追跡のため戦闘機を発進させたとの情報が!」(なーんちゃって)と博士をかつぐという一幕も。
当該輸送機の航空士だったD.M. Ralston中尉(後年、少将まで昇進)の回想
https://www.saafa.co.za/feedback/The%20Coelacanth%20Flight%20-%201952.pdf
なお、その後捕獲された標本は仏が独占。標本を他国に貸し出す場合も「展示に限る、解剖厳禁」とするなどだった由。
後年、仏以外にも標本が売られるようになった由。
アメリカ初入手は1962年(写真後掲)。
Discovery and Preservation of a Coelacanth | AMNH
「あれま、苦労して釣上げてみたら食えねえ(=売り物にならねえ)ゴンベッサかよ、ったくもう」と捨てていた漁師らは、高く売れるとわかり対応一変。
・・・これが絶滅の危機を促進しているとも。
1952年の発見は、「コモロ諸島にも懸賞チラシを配っておきますよ」という船乗りハント(スクーナーで漁業や貿易)のサポートにより情報が入った。
「見つかったらすぐ知らせますから、先生(笑)」みたいな感じで、冗談気分だったが、その10日後にハントから博士に電報入る。
「フォルマリンを注射してほしいというが、十分なフォルマリンが手に入らない場合はどうすればいいのか?」など事前に熱心に聞いていた効果が意外にすぐ発揮(塩漬けにしておいてくれ)。
coela+acanthでcoelacanth(命名者は、氷河期の発見にも登場したルイ・アガシ)。
ギリシャ語。1835年に化石が命名された。
Before 1938, coelacanths had been known exclusively as fossils, much like trilobites and dinosaurs.
Louis Agassiz, founder of the Museum of Comparative Zoology at Harvard, first described the fossil coelacanth in 1835, roughly 100 years before the living coelacanth was discovered.
A coelacanth tail was discovered in rocks 280 million years old, during excavations of a road cutting in northern England.
Agassiz was impressed by the fact that the spines which supported the tail fin were hollow and not solid, and so he coined the word "coelacanth": "coela" meaning hollow and "acanth" meaning spine.
この部分http://www.fathom.com/feature/121979/ より
…長々引用したのは、acanth=spineが脊柱のほうの意味でなく、棘(キョク)の方の意味だという話を確認できるように。
したがって、管椎類ではなく空棘類という訳語が正しい由。
たまたま脊椎骨が管状なので管椎は一見もっともらしいが、命名者が意図したのは中空の棘であると。
この部分は『シーラカンスの謎』
キース・S.トムソン著、清水長訳のあとがきより。
よく見かける記述「シーラカンスという名前はギリシア語で『中空の背骨』を意味し云々」というのは誤解に基くものであると。
Yahoo!百科事典トップ > 自然科学 > 地学 > 古生物・化石 > シーラカンス(しーらかんす)
・・・AMNHが第26標本を入手したときの写真
(西半球初!ってこういう言い方しますよね、彼らは)
インドネシア・シーラカンスはどこから来たのか
ミトコンドリアゲノムからみたシーラカンス 2 種の進化史
その後も関連事項記載サイトは色々見かけるので、見繕って貼るね:
信頼できると思われる書籍を2冊紹介したい。
さらに、信頼できると考えられるサイトへのリンクも。
生きた化石 : シーラカンス発見物語 | NDLサーチ | 国立国会図書館
著者名:J・L・B・スミス/著 梶谷善久/訳
1981年11月
恒和出版
後者はJLBスミス博士の「Old Fourlegs」の翻訳。
1938年の最初の標本と、1952年の第2標本入手の経緯が記載(後者についてがより詳細)。
博士的には、1938年の際はコートニー・ラティマー女史からの第1報を知るのが遅れたために内臓を廃棄されてしまったという痛恨の出来事*。
*1938年のどたばた(上記図書などから南面堂が理解した内容であり、正確性は保証されない。誤解しているかもしれないもん)
スミス博士は、避暑・療養(体弱い)と試験の採点(化学の教授。魚類研究は趣味)のため、クリスマス休暇中は町から離れた海岸の別荘に滞在中。
正月明けに転送されてきた女史の手紙とスケッチを見て「君、それは動物学上の大発見の可能性があるよ!」と返事を書くが、一歩遅く内臓は廃棄後。
女史としては、重要性ある標本だとの認識はあり、町の冷蔵倉庫と病院の遺体安置所に掛け合うも「腐りかけた巨大魚なんて」と保存は断られ、やむなく剥製師に作業を依頼する。
「博士に電話は通じないし、手紙の反応もないし、困ったわね。しょうがないか・・」と内臓廃棄に踏み切る。
脂分がとても強くて、独特の悪臭がすごくなってくるのだそうです。
「剥製でも仕方ないけれど、内臓は何とかしてとっておいてね!」という連絡をもらったときには遅く、清掃局に照会したら、「ごみはもう海に捨てました」との回答。後の祭り…
でもスミス博士は女史の対応を(困難な状況で最善の対応をした、科学者は彼女に感謝すべきである、と)たいへん高く評価して、学名(科名)にラティメリアを採用。
トロール船の船長からの知らせ(「とても奇妙な魚がかかったんだわ。あんたが欲しがると思ってさあ」)で・・・という1匹目に係る手紙のやりとりなど、興味深い:
Moment of Discovery
Relive the excitement of the coelacanth's first appearance.
2匹目の入手(1952年)までが大変でした!という経緯の一部:
…スミス博士が作った懸賞金のチラシや、第2標本の引き取りに赴いた際の空軍輸送機のクルー一同と記念写真などもあり
(ちなみに同記念写真で前列左が、地元漁師から魚を引き取って博士に通報したハント)
1938年の第1号標本の後、「1尾生きて発見されたのだから、必ずまた見つかるはずだ」と戦争をはさんで14年間の執念の追跡の結果、予想外の遠隔地コモロ諸島で漁獲された。
1952年の出来事のほうが、博士本人にとっては達成感が大きいこともあってか、(首相に直訴して)南ア空軍に輸送機を仕立ててもらって引き取りに行った経緯など詳細記述あり
(このへんウィキペディアにも記載あります)。
仏領コモロ諸島(当時)の知事がその価値に気づいて待ったをかけないうちに、なごやかにかつさっさと持ち帰りたいという、表に出せない苛立ちなども。
(知事は博士一行の歓迎会を開いてくれたりする…僻地の植民地行政官が退屈しているという、ありがちな映画のような光景?)
…これを悟ったお茶目な輸送機クルーが、魚を積み込んで南アに向けて無事離陸後、「仏当局が当機追跡のため戦闘機を発進させたとの情報が!」(なーんちゃって)と博士をかつぐという一幕も。
当該輸送機の航空士だったD.M. Ralston中尉(後年、少将まで昇進)の回想
https://www.saafa.co.za/feedback/The%20Coelacanth%20Flight%20-%201952.pdf
なお、その後捕獲された標本は仏が独占。標本を他国に貸し出す場合も「展示に限る、解剖厳禁」とするなどだった由。
後年、仏以外にも標本が売られるようになった由。
アメリカ初入手は1962年(写真後掲)。
Discovery and Preservation of a Coelacanth | AMNH
「あれま、苦労して釣上げてみたら食えねえ(=売り物にならねえ)ゴンベッサかよ、ったくもう」と捨てていた漁師らは、高く売れるとわかり対応一変。
・・・これが絶滅の危機を促進しているとも。
1952年の発見は、「コモロ諸島にも懸賞チラシを配っておきますよ」という船乗りハント(スクーナーで漁業や貿易)のサポートにより情報が入った。
「見つかったらすぐ知らせますから、先生(笑)」みたいな感じで、冗談気分だったが、その10日後にハントから博士に電報入る。
「フォルマリンを注射してほしいというが、十分なフォルマリンが手に入らない場合はどうすればいいのか?」など事前に熱心に聞いていた効果が意外にすぐ発揮(塩漬けにしておいてくれ)。
coela+acanthでcoelacanth(命名者は、氷河期の発見にも登場したルイ・アガシ)。
ギリシャ語。1835年に化石が命名された。
Before 1938, coelacanths had been known exclusively as fossils, much like trilobites and dinosaurs.
Louis Agassiz, founder of the Museum of Comparative Zoology at Harvard, first described the fossil coelacanth in 1835, roughly 100 years before the living coelacanth was discovered.
A coelacanth tail was discovered in rocks 280 million years old, during excavations of a road cutting in northern England.
Agassiz was impressed by the fact that the spines which supported the tail fin were hollow and not solid, and so he coined the word "coelacanth": "coela" meaning hollow and "acanth" meaning spine.
この部分http://www.fathom.com/feature/121979/ より
…長々引用したのは、acanth=spineが脊柱のほうの意味でなく、棘(キョク)の方の意味だという話を確認できるように。
したがって、管椎類ではなく空棘類という訳語が正しい由。
たまたま脊椎骨が管状なので管椎は一見もっともらしいが、命名者が意図したのは中空の棘であると。
この部分は『シーラカンスの謎』
キース・S.トムソン著、清水長訳のあとがきより。
よく見かける記述「シーラカンスという名前はギリシア語で『中空の背骨』を意味し云々」というのは誤解に基くものであると。
・・・AMNHが第26標本を入手したときの写真
(西半球初!ってこういう言い方しますよね、彼らは)
インドネシア・シーラカンスはどこから来たのか
ミトコンドリアゲノムからみたシーラカンス 2 種の進化史
その後も関連事項記載サイトは色々見かけるので、見繕って貼るね: