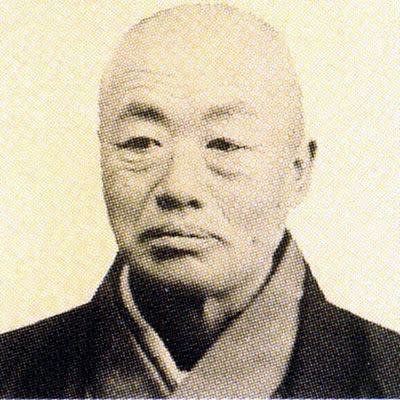ある県で集中豪雨により川が氾濫し大きな被害をだしたと、朝のテレビがニュースをながしていた。出社すると、上司がすりよってきた。「お、きたな」と思いつつあいさつすると「悪いが、これから被災地の調査に行ってくれ」。やはりそうだった。ただそのころは社会人2年生になっており、突然の出張にも慣れっこになっていたから、にっこり笑った。社宅にもどって、いつも用意してあるバッグひとつを持って寝台列車に乗った。飛行機よりも列車のほうが便利なのだ。
早朝現地の駅に到着。取引先の課長が待っていてくれた。被災地を一緒にまわることになっていた。ところが急用がはいって同行できないので、ひとりで回ってくれ、悪路でもだいじょうぶな車をあちらに用意してあるという。いささかむくれた。さらには車をみておどろいた。ダンプカーなのである。たしかにこれならば悪路にも強いが、運転したことがない。ためらっていると、課長は「平気ですよ、運転席にすわってください」と事務的に私を車に押し込む。 キーを回したが、エンジンがうんともすんともいわない。課長が笑って「いちど反対側にまわすんですよ」。やってみると一発でかかった。

マツダHPより
乗りはじめると、ダンプは快調だった。しかし外の光景をみるうちに息をのんだ。車が横転して泥まみれだ。ガードレールに大量の草木がひっかかり、道路はところどころ舗装がはげている。水の力はすさまじい。橋桁に引っかかっているのは家屋の一部らしい。橋脚には太い流木がからみついている。全壊、半壊、床上浸水の家屋は数知れない。田畑も今年の収穫は無理だ。ところどころに、片づけをしている人がいる。呆然と立ちすくんでいる人もいる。まだ行政の対応はできていないようだ。本来ならばあちらこちらで声をきくのだが、すこしはばかられたので、かわりに写真をつぎつぎに撮った。 深いぬかるみにタイヤが入っても、さすがにダンプだ。足をとられない。しばらく上流にむかって走る。しかしまもなく止まった。橋が流されているのだ。これ以上は無理だ。撤退することにした。
その晩も宿はとってなかった。課長は、宿の予約もしないできたのかとあきれていたが、いつもの流儀である。なんとか民宿がみつかった。海辺だからだろうか、刺身や魚の煮付けがじつにうまかった。醤油の味が独特で深いコクがあった。これまであれほどのうまい醤油にはお目にかかったことがない。
次の日は官公庁へのヒヤリング。終わりしだい帰ろうと思っていたら、「釣りが好きでしたね。明日は土曜だから、つきあいませんか」と課長。川釣りはベテランだが海釣りはやったことがない。快諾した。そこでもう一泊ということになった。また昨夜の民宿におせわになった。 翌朝早くに課長が迎えにきた。川の流れこむあたりの海は流出物でいっぱいで濁っていたが、すこし離れた入江は透明度が高い。わくわくしながら教わるとおりに仕掛けを海にほうりこんだ。小さなフグまじりだが、おもしろいほど釣れる。課長はとみれば、アジだか何だかきちんと食えるものを釣っている。「そろそろ上がりましょう」と課長。お昼をごちそうになったところで、課長は仕事にいくという。休みではなかったのだ。
ははあ、そうか、現地調査に同行できなかったことを詫びているのだろう、たしかに被災の現地では休みどころではない、誘われたときにその意だけをくんでやんわりと断ればよかった、迷惑をかけてしまったな。そう感じつつ、ビール片手に帰りの列車にのった。苦い味だった。