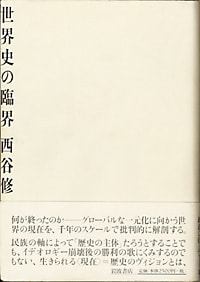
先日、知人を介して西谷修氏との知遇を得た。氏は現在、東京外国語大学の大学院教授という地位におられるが、かつて私の出身大学でも教鞭を執っておられたことがあり、親しみを感じたものである。その時話題に上ったのが本書『世界史の臨界』だった。私はこれまで、日本の歴史には随分と関心を持ち、古代史、邪馬台国論争から、戦国時代、江戸時代の再評価、幕末、近現代史における歴史認識や教科書問題など、一通りは読み漁ってきた。もちろん、道楽の域を出ていないことはいうまでもない。というわけで世界史はどちらかといえば苦手な方で、オペラやクラシック音楽を云々するわりには、西洋史も詳しくはないのである。そこで、この機会に世界史を学び直してみようと思い、一方で学生時代の一般教養の「歴史学」以来、意識の外にあった「歴史」そのものの概念を整理してみたくもあり、ちょっと難しいだろうとは思ったが、すぐにAmazonで本書を注文した。読了を機に、私なりの理解度で、ここで得た知識を整理しておこうと思う(音楽のブログにはあまり関係ありませんが…)。普段何気なく使っている「歴史」という言葉に深い意味があろうとは、これまで意識したことがなかった。まずはここから新しい知の世界が始まった。この本によると…。
歴史は文字によって記述されることで初めて歴史となる。つまり、この世に起こったある出来事は、その後に記述されることによって時間軸の過去の一点に固定され、普遍的な認識としての歴史的事実となり、後世に残っていく。文字のない文化圏の伝承による歴史は、曖昧で主観的であるため「歴史」とはいえない。
次に、歴史には主体があり、何のために誰が記述しているのか、という命題が生まれる。最初に歴史を記述したヘロドトスは、ギリシャ哲学的な理性に基づき、出来事を客観的に記述しようとした。その後、ラテン・ゲルマンを中心とする「世界」がキリスト教カトリックという宗教的・文化的・政治的な社会となり、「ヨーロッパ」という主体が生まれた。ここでいう「ヨーロッパ」とは、現在のような地理的空間を指すのではなく、民族や文化や王朝が交代しても変わらない、意志を持つ主体である。「ヨーロッパ」は、自らの存在の価値と、その成り立ちを証明するために、「歴史(=history=物語)」を記述するようになる。7世紀以降の「ヨーロッパ=キリスト教カトリック社会」は、ユダヤ人やイスラーム勢力との対立を軸に、十字軍遠征の失敗の代償として得たヘレニズム文化の影響を受け(理性的な歴史の記述ができる)、地理的な条件も含めて、より強固な「ヨーロッパ」を形成していく。「ヨーロッパ」の歴史は、「世界史」への道を歩み始めるが、この頃には、イスラームにも、中国にもすでに記述された「歴史」が存在しているので、「ヨーロッパ」の歴史はまだ「地方史」のひとつでしかない。
ここで、「歴史」という観念をもう一度見直してみる。記述されることによって成立する「歴史」は、記述する主体が「客観的」であるか「主観的」であるかによって、性格が異なるものになる。「ヨーロッパ」の歴史記述には理性により制御された客観性があるのに対し、中国のように、滅ぼした王朝が滅ぼされた王朝を記述し、新しい王朝の正当性の証明にしていくような「歴史」は、「世界史」になりうるだけの普遍性が見られない。
さて、「ヨーロッパ」はルネサンス期を経て人間的な理性が重視されるようになり、大航海時代を迎えて「世界」に向けて地理的な拡張を始める。同時に「ヨーロッパ」は、政治的・文化的・宗教的・経済的な拡張を目指し、ヨーロッパ各国の植民地獲得競争となっていく。そのプロセスにおいて、「ヨーロッパ」は世界の各地・各国を知り、それらを新たに記述し始める。同時に支配下に収めていくことで、そこにあった歴史(地方史)を併呑していく。こうして「ヨーロッパ」の歴史が「世界史」へと変貌していくことになった。私たちの住む「アジア」という概念も自らが生み出したものではなく、あくまで「ヨーロッパ」から見た東の方の地域を指す言葉である。
そして、「ヨーロッパ」で使われている暦(西暦=キリスト教暦)の時間軸で、世界の出来事が記述されるようになっていく。わが国は固有の年号(元号)を持っているが、「日本史」の教科書でさえ、西暦と元号が併記されているとはいえ、西暦重視であることは間違いない。
「ヨーロッパ」は拡張した植民地政策により「世界」のほとんどの地域を傘下に収めた。産業革命の後は経済的にも支配を強め、「ヨーロッパ」各国は世界の利権を奪い合い、二つの世界大戦を引き起こすまでになった。そしてその結果、20世紀の後半は、世界中の植民地がそれぞれ近代国家的な構造を持つ民族国家として独立を果たしていく。そしてそのことさえも「ヨーロッパ」の歴史として記述されていくことになる。さらに第一次世界大戦の後に誕生した共産主義国家社会(いわゆる東側)に拡大した、第二次世界大戦後の東西冷戦による世界の分断も、ベルリンの壁崩壊やソ連の崩壊によって、収束されていく。20世紀末、「ヨーロッパ」はある意味で世界をひとつにした。
ここでさらに、「世界史」という観念を考えてみる。「世界史」とは世界各国に固有の「地方史」を集めて編纂したものではない。「ヨーロッパ」の歴史哲学に基づき規定される、「ヨーロッパ」の尺度と時間軸で記述された「ヨーロッパ史」のことである。「ヨーロッパ」は世界中の歴史をも傘下に収め、「世界史」を構築したのである。
拡大し尽くした「ヨーロッパ」は、自らの作り出した近代社会のシステムにより、結果としてほとんどの植民地を失った。「ヨーロッパ」が作り出した「ヨーロッパ」が記述する「世界」は崩壊しつつある。それ故、「世界史」はその役割を終えることになる。ならば臨界を迎えた「世界史」は、21世紀にどこに向かおうとしているのか。
本書の後半は、臨界を迎えた「ヨーロッパ」の「世界史」に対して、別の世界からの視点から考察し、本論の傍証ともいうべき論を展開している。ひとつは小説『悪魔の詩』が引き起こした「ラシュディ事件」への考察から、イスラーム社会の視点をとらえる。ふたつめは、カリブ海の小島に「世界史」化が及んだ際の言語や文化の変容を解き明かす。さらに、20世紀のほとんどの期間を通して存在した共産主義国家とその崩壊のプロセスから「世界史」の終末を検証する。最後に、日本の宮澤賢治が書き残した「戦争」に関わる心情の中に、「世界史」の侵入を検証している。
『世界史の臨界』が出版されたのは西暦2000年。まさに世紀末であり、千年紀末のことであった。世界中で、世紀末が話題になったこと自体が、「ヨーロッパ」が世界を席巻したひとつの証でもあった。
本書で展開されている「世界史=ヨーロッパの世界化の歴史」という視点は、とても新鮮であると同時に衝撃的でもあった。何気なく使っている「歴史」という言葉にさえ、これほど深い意味が含まれていようとは考えもしなかった。新しい知に触れることができて、大変勉強になったと思う。これでは気軽に「歴史好き」などとは言えなくなってしまいそうだ。
さて、せっかく歴史学に触れたのだから、ここで少し音楽の歴史について考えてみよう。
いわゆる「クラシック音楽」が宗教から独立してそれ自体が単体の芸術へと進化したのは、主にバロック期。キリスト教とは直接関係しない物語が語られるオペラが誕生し、管弦楽が生まれた。18世紀の後半になると、ウィーン古典派の時代になる。音楽が形式的に洗練され様々なカテゴリーの音楽が確立していく。ハイドンが交響曲という形式を完成させ、モーツァルトが宮廷から独立した音楽を創造し。ベートーヴェンが市民階級に向けての交響曲や器楽曲を生み出す。19世紀になると、より人間の感情に自由に向き合おうとするロマン派の音楽へと変貌していく。シューベルト、メンデルスゾーン、シューマン、ベルリオーズらの交響曲は形式美を超えて感性の趣くままに旋律を奏でる。そしてショパンのピアノ曲の数々、リストが確立した、より自由な音楽形式が交響詩である。19世紀も後半になると、それまでドイツ・オーストリアを中心としてきた音楽が近隣の民族国家へと波及し、各国の民族性に根ざした国民楽派と呼ばれる作曲家たちが活躍する。ロシアでは5人組(ボロディン、キュイ、バラキレフ、ムソルグスキー、コルサコフ)が、ボヘミアではドヴォルザークやスメタナ、フランスではサン=サーンスやフランク、ノルウェーではグリーク、フィンランドではシベリウス、などである。一方でロシアでもチャイコフスキーのように比較的独墺系に傾倒する者もあった。その独墺系の後期ロマン派は新古典主義ともいわれる、ブラームス、マーラー、ブルックナーらがいる。ロマン派も20世紀を迎える頃になると近代音楽へとさらに進化していく。印象主義と呼ばれるフランスのドビュッシーやラヴェルの登場、新ロマン主義といわれるリヒャルト・シュトラウスやラフマニノフらによって、多様化していく。一方で、同時期に新ウィーン楽派と呼ばれるベルクやシェーンベルクなどは12音階技法を完成させ、現代音楽を生み出していく。20世紀の前半が現代音楽の時代である。ロシア(ソ連)のストラヴィンスキー、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチ、ハンガリーのバルトークらが活躍した。
一方オペラの分野では、バロック期にヘンデルがたくさんの作品を生み出し、バロック・オペラを確立した。古典派の時代には、ハイドンやモーツァルトは多作で、とくにモーツァルト台本作家ダ・ポンテと組んだ3部作「フィガロの結婚」「ドン・ジョヴァンニ」「コジ・ファン・トゥッテ」が有名だが、これらは当時の慣習に従って台本はイタリア語で書かれている。ベートーヴェンは「フィデリオ」1作のみを残すが、これはドイツ語であり、ロマン派のドイツ・オペラであるウェーバーからワーグナーへと続く系譜となる。19世紀前半のロマン派前期はイタリアのベルカント・オペラの全盛期で、ロッシーニ、ドニゼッティ、ベッリーニが活躍した。19世紀後半は、イタリア・オペラではヴェルディが君臨した時代だが、ドイツではワーグナーが君臨した時代でもある。フランスでは、グノー、オッフェンバック、サン=サーンス、ビゼー、マスネらが活躍した。国民楽派や印象主義の作曲方たちもそれぞれの作曲技法でオペラを書いている。ドイツではワーグナーを継ぐ巨人はリヒャルト・シュトラウスで20世紀前半いっぱいロマン派のオペラ作曲家として活躍した。現代音楽の作曲家たちもオペラを書いているが、作品数は少なくなっていく。
そして、20世紀の後半、第二次世界大戦の後は、クラシック音楽もオペラも新作は極端に少なくなってしまう。そして演奏家の時代といわれるようになり、著名な演奏家が次々と現れ、演奏技術もどんどん高度化していく。演奏家の時代になると、ヨーロッパだけではなく、アメリカやアジアからも優秀な音楽家たちが登場するようになった。20世紀後半は巨匠(演奏家)の時代ともいわれたが、世紀末までに巨匠たちが次々と没し、21世紀に入ると巨匠不在とさえいわれるようになってしまった。
こうしてみると、音楽の歴史も「世界史」に似ているではないか。もちろん時代は違っているが、「ヨーロッパ」に生まれた音楽が、宗教から独立し、周辺各国へと波及していき、やがて全世界に広がると、「クラシック音楽」や「オペラ」という共通の「歴史」を持つようになる。理由はまったく異なると思うが、音楽も第二次世界大戦の終わり頃に臨界を迎えたようである。宗教から宮廷へ、宮廷から市民社会へと広がり成長した音楽が、戦争や革命の時代に翻弄され、平和を求めるメッセージへと変貌するが、戦争が終わると(冷戦は残ったが)目的を失ったように、成長を止めてしまう。残された者にできることは、過去の歴史(作品)を解釈(演奏)することだ。そうした演奏(解釈)する行為によってのみ、私たちは過去の偉大なる芸術(歴史)に触れることができるのである。臨界の後、「クラシック音楽」や「オペラ」はどこへ向かったのか。かつては社会を動かす力を持っていたが(演奏や上演が禁止されたりしたのがその証)、今や現代の商業主義の中にどっぶりと浸かったカタチでしか、あるいは国家に保護されるカタチでしか、生き残ることができないというのが「クラシック音楽」や「オペラ」の現状でもある。
歴史は文字によって記述されることで初めて歴史となる。つまり、この世に起こったある出来事は、その後に記述されることによって時間軸の過去の一点に固定され、普遍的な認識としての歴史的事実となり、後世に残っていく。文字のない文化圏の伝承による歴史は、曖昧で主観的であるため「歴史」とはいえない。
次に、歴史には主体があり、何のために誰が記述しているのか、という命題が生まれる。最初に歴史を記述したヘロドトスは、ギリシャ哲学的な理性に基づき、出来事を客観的に記述しようとした。その後、ラテン・ゲルマンを中心とする「世界」がキリスト教カトリックという宗教的・文化的・政治的な社会となり、「ヨーロッパ」という主体が生まれた。ここでいう「ヨーロッパ」とは、現在のような地理的空間を指すのではなく、民族や文化や王朝が交代しても変わらない、意志を持つ主体である。「ヨーロッパ」は、自らの存在の価値と、その成り立ちを証明するために、「歴史(=history=物語)」を記述するようになる。7世紀以降の「ヨーロッパ=キリスト教カトリック社会」は、ユダヤ人やイスラーム勢力との対立を軸に、十字軍遠征の失敗の代償として得たヘレニズム文化の影響を受け(理性的な歴史の記述ができる)、地理的な条件も含めて、より強固な「ヨーロッパ」を形成していく。「ヨーロッパ」の歴史は、「世界史」への道を歩み始めるが、この頃には、イスラームにも、中国にもすでに記述された「歴史」が存在しているので、「ヨーロッパ」の歴史はまだ「地方史」のひとつでしかない。
ここで、「歴史」という観念をもう一度見直してみる。記述されることによって成立する「歴史」は、記述する主体が「客観的」であるか「主観的」であるかによって、性格が異なるものになる。「ヨーロッパ」の歴史記述には理性により制御された客観性があるのに対し、中国のように、滅ぼした王朝が滅ぼされた王朝を記述し、新しい王朝の正当性の証明にしていくような「歴史」は、「世界史」になりうるだけの普遍性が見られない。
さて、「ヨーロッパ」はルネサンス期を経て人間的な理性が重視されるようになり、大航海時代を迎えて「世界」に向けて地理的な拡張を始める。同時に「ヨーロッパ」は、政治的・文化的・宗教的・経済的な拡張を目指し、ヨーロッパ各国の植民地獲得競争となっていく。そのプロセスにおいて、「ヨーロッパ」は世界の各地・各国を知り、それらを新たに記述し始める。同時に支配下に収めていくことで、そこにあった歴史(地方史)を併呑していく。こうして「ヨーロッパ」の歴史が「世界史」へと変貌していくことになった。私たちの住む「アジア」という概念も自らが生み出したものではなく、あくまで「ヨーロッパ」から見た東の方の地域を指す言葉である。
そして、「ヨーロッパ」で使われている暦(西暦=キリスト教暦)の時間軸で、世界の出来事が記述されるようになっていく。わが国は固有の年号(元号)を持っているが、「日本史」の教科書でさえ、西暦と元号が併記されているとはいえ、西暦重視であることは間違いない。
「ヨーロッパ」は拡張した植民地政策により「世界」のほとんどの地域を傘下に収めた。産業革命の後は経済的にも支配を強め、「ヨーロッパ」各国は世界の利権を奪い合い、二つの世界大戦を引き起こすまでになった。そしてその結果、20世紀の後半は、世界中の植民地がそれぞれ近代国家的な構造を持つ民族国家として独立を果たしていく。そしてそのことさえも「ヨーロッパ」の歴史として記述されていくことになる。さらに第一次世界大戦の後に誕生した共産主義国家社会(いわゆる東側)に拡大した、第二次世界大戦後の東西冷戦による世界の分断も、ベルリンの壁崩壊やソ連の崩壊によって、収束されていく。20世紀末、「ヨーロッパ」はある意味で世界をひとつにした。
ここでさらに、「世界史」という観念を考えてみる。「世界史」とは世界各国に固有の「地方史」を集めて編纂したものではない。「ヨーロッパ」の歴史哲学に基づき規定される、「ヨーロッパ」の尺度と時間軸で記述された「ヨーロッパ史」のことである。「ヨーロッパ」は世界中の歴史をも傘下に収め、「世界史」を構築したのである。
拡大し尽くした「ヨーロッパ」は、自らの作り出した近代社会のシステムにより、結果としてほとんどの植民地を失った。「ヨーロッパ」が作り出した「ヨーロッパ」が記述する「世界」は崩壊しつつある。それ故、「世界史」はその役割を終えることになる。ならば臨界を迎えた「世界史」は、21世紀にどこに向かおうとしているのか。
本書の後半は、臨界を迎えた「ヨーロッパ」の「世界史」に対して、別の世界からの視点から考察し、本論の傍証ともいうべき論を展開している。ひとつは小説『悪魔の詩』が引き起こした「ラシュディ事件」への考察から、イスラーム社会の視点をとらえる。ふたつめは、カリブ海の小島に「世界史」化が及んだ際の言語や文化の変容を解き明かす。さらに、20世紀のほとんどの期間を通して存在した共産主義国家とその崩壊のプロセスから「世界史」の終末を検証する。最後に、日本の宮澤賢治が書き残した「戦争」に関わる心情の中に、「世界史」の侵入を検証している。
『世界史の臨界』が出版されたのは西暦2000年。まさに世紀末であり、千年紀末のことであった。世界中で、世紀末が話題になったこと自体が、「ヨーロッパ」が世界を席巻したひとつの証でもあった。
本書で展開されている「世界史=ヨーロッパの世界化の歴史」という視点は、とても新鮮であると同時に衝撃的でもあった。何気なく使っている「歴史」という言葉にさえ、これほど深い意味が含まれていようとは考えもしなかった。新しい知に触れることができて、大変勉強になったと思う。これでは気軽に「歴史好き」などとは言えなくなってしまいそうだ。
さて、せっかく歴史学に触れたのだから、ここで少し音楽の歴史について考えてみよう。
いわゆる「クラシック音楽」が宗教から独立してそれ自体が単体の芸術へと進化したのは、主にバロック期。キリスト教とは直接関係しない物語が語られるオペラが誕生し、管弦楽が生まれた。18世紀の後半になると、ウィーン古典派の時代になる。音楽が形式的に洗練され様々なカテゴリーの音楽が確立していく。ハイドンが交響曲という形式を完成させ、モーツァルトが宮廷から独立した音楽を創造し。ベートーヴェンが市民階級に向けての交響曲や器楽曲を生み出す。19世紀になると、より人間の感情に自由に向き合おうとするロマン派の音楽へと変貌していく。シューベルト、メンデルスゾーン、シューマン、ベルリオーズらの交響曲は形式美を超えて感性の趣くままに旋律を奏でる。そしてショパンのピアノ曲の数々、リストが確立した、より自由な音楽形式が交響詩である。19世紀も後半になると、それまでドイツ・オーストリアを中心としてきた音楽が近隣の民族国家へと波及し、各国の民族性に根ざした国民楽派と呼ばれる作曲家たちが活躍する。ロシアでは5人組(ボロディン、キュイ、バラキレフ、ムソルグスキー、コルサコフ)が、ボヘミアではドヴォルザークやスメタナ、フランスではサン=サーンスやフランク、ノルウェーではグリーク、フィンランドではシベリウス、などである。一方でロシアでもチャイコフスキーのように比較的独墺系に傾倒する者もあった。その独墺系の後期ロマン派は新古典主義ともいわれる、ブラームス、マーラー、ブルックナーらがいる。ロマン派も20世紀を迎える頃になると近代音楽へとさらに進化していく。印象主義と呼ばれるフランスのドビュッシーやラヴェルの登場、新ロマン主義といわれるリヒャルト・シュトラウスやラフマニノフらによって、多様化していく。一方で、同時期に新ウィーン楽派と呼ばれるベルクやシェーンベルクなどは12音階技法を完成させ、現代音楽を生み出していく。20世紀の前半が現代音楽の時代である。ロシア(ソ連)のストラヴィンスキー、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチ、ハンガリーのバルトークらが活躍した。
一方オペラの分野では、バロック期にヘンデルがたくさんの作品を生み出し、バロック・オペラを確立した。古典派の時代には、ハイドンやモーツァルトは多作で、とくにモーツァルト台本作家ダ・ポンテと組んだ3部作「フィガロの結婚」「ドン・ジョヴァンニ」「コジ・ファン・トゥッテ」が有名だが、これらは当時の慣習に従って台本はイタリア語で書かれている。ベートーヴェンは「フィデリオ」1作のみを残すが、これはドイツ語であり、ロマン派のドイツ・オペラであるウェーバーからワーグナーへと続く系譜となる。19世紀前半のロマン派前期はイタリアのベルカント・オペラの全盛期で、ロッシーニ、ドニゼッティ、ベッリーニが活躍した。19世紀後半は、イタリア・オペラではヴェルディが君臨した時代だが、ドイツではワーグナーが君臨した時代でもある。フランスでは、グノー、オッフェンバック、サン=サーンス、ビゼー、マスネらが活躍した。国民楽派や印象主義の作曲方たちもそれぞれの作曲技法でオペラを書いている。ドイツではワーグナーを継ぐ巨人はリヒャルト・シュトラウスで20世紀前半いっぱいロマン派のオペラ作曲家として活躍した。現代音楽の作曲家たちもオペラを書いているが、作品数は少なくなっていく。
そして、20世紀の後半、第二次世界大戦の後は、クラシック音楽もオペラも新作は極端に少なくなってしまう。そして演奏家の時代といわれるようになり、著名な演奏家が次々と現れ、演奏技術もどんどん高度化していく。演奏家の時代になると、ヨーロッパだけではなく、アメリカやアジアからも優秀な音楽家たちが登場するようになった。20世紀後半は巨匠(演奏家)の時代ともいわれたが、世紀末までに巨匠たちが次々と没し、21世紀に入ると巨匠不在とさえいわれるようになってしまった。
こうしてみると、音楽の歴史も「世界史」に似ているではないか。もちろん時代は違っているが、「ヨーロッパ」に生まれた音楽が、宗教から独立し、周辺各国へと波及していき、やがて全世界に広がると、「クラシック音楽」や「オペラ」という共通の「歴史」を持つようになる。理由はまったく異なると思うが、音楽も第二次世界大戦の終わり頃に臨界を迎えたようである。宗教から宮廷へ、宮廷から市民社会へと広がり成長した音楽が、戦争や革命の時代に翻弄され、平和を求めるメッセージへと変貌するが、戦争が終わると(冷戦は残ったが)目的を失ったように、成長を止めてしまう。残された者にできることは、過去の歴史(作品)を解釈(演奏)することだ。そうした演奏(解釈)する行為によってのみ、私たちは過去の偉大なる芸術(歴史)に触れることができるのである。臨界の後、「クラシック音楽」や「オペラ」はどこへ向かったのか。かつては社会を動かす力を持っていたが(演奏や上演が禁止されたりしたのがその証)、今や現代の商業主義の中にどっぶりと浸かったカタチでしか、あるいは国家に保護されるカタチでしか、生き残ることができないというのが「クラシック音楽」や「オペラ」の現状でもある。
























