バンドPAの作業って大きな音響屋だと、ハウス、モニター、ステージマンと役割が分かれていて、入りたての新人さんはまずステージマンから修行を積み、モニターを任され、そして最終的にチーフとしてハウスを担当するらしいです。ステージマンとは3番手とも呼ばれ、ステージ周りの作業、例えばマイクのラインを整えたり機材を出したり降ろしたりと言うことをします。ステージマンに関してもたくさん語りたいのですけど今回もモニターマンについて。
小さな現場での1人PAだと全ての作業を一人でやるか、バンドさんたちにある程度ステージマンを手伝ってもらったりします。中規模ステージを2人でやる時は一人がハウス、一人がステージマンです。3人の時はステージマンが2人になります。人数が増えたとしても、モニターへの返しがハウス卓返しである限り、モニターマンという係りが出てくることはありません。
演奏者への返しを重要視していないPAさんは、残念ながら多いようで、私の周りのアマチュア音響はその辺を不満に思って自らPAを始めた方が多いです。私自信がその考えでPA始めてますから、自然と返しを重要視してくるわけですね。演奏中気持ちよく演奏できているだろうか、何か合図を送ってやしないか、常に返しが気になります。でもハウス卓返しだと表の音や曲出しとか仕事が多くてステージばかり見ているわけにもいきません。
一度でいいから、ハウスとモニターを分離した現場を経験してみたいと今思っているわけです。しかし機材が増え、仕込みに時間がかかれば結局「ハウス返しでいいじゃん」となるだろうことは十分予想できます。そこまでやって、それに見合うだけの効果があるかどうか。どちらにしても、モニターを重要視する私がことあるごとに悩むことですから、少しでも効果が出そうなことはやってみたい。
モニター専用卓を設置するためには、ステージから来るラインをハウス卓へ送るラインとモニター卓へ送るラインとで2分岐しなくてはなりません。ここのやり方がよく解らない。近大社長に聞いても、モニターマン自体がよく解らないらしくて×。以前、大きな音響屋さんに聞いた時は、単純にパラっていいんじゃない、と言われてました。本とかにはスプリッターを使うと書かれています。
単純にYケーブルでラインをパラレルにしてしまうことを“純パラ”と言います。しかしこれだとゲインが下がってしまう。それほど気になるレベルではないとは思いますが出来るなら下げたくない。ファンタムかけているラインが混じるのも不安だし…。ここはやはりスプリッターで独立2分岐させたいです。


ARTの8チャンネルを全て2分岐させるマイクスプリッターです。これを2台ラックに組んでマルチボックスみたいにステージに転がしておいて、ここからスネークでモニターとハウスに送ればいいかなって考えています。
ここまではアナログで考えていますけど、時代はデジタル。従来のアナログマルチケーブルに変り、デジタル変換できるステージボックスを置けば何本だろうと好きなだけデジタルラインを分岐できます。まだまだ高価なデジタル機材ですが、べリンガーから続々と出てきそうで、デジタルが一般的になればすぐ価格は下がります。もう少し様子見ですかね。
小さな現場での1人PAだと全ての作業を一人でやるか、バンドさんたちにある程度ステージマンを手伝ってもらったりします。中規模ステージを2人でやる時は一人がハウス、一人がステージマンです。3人の時はステージマンが2人になります。人数が増えたとしても、モニターへの返しがハウス卓返しである限り、モニターマンという係りが出てくることはありません。
演奏者への返しを重要視していないPAさんは、残念ながら多いようで、私の周りのアマチュア音響はその辺を不満に思って自らPAを始めた方が多いです。私自信がその考えでPA始めてますから、自然と返しを重要視してくるわけですね。演奏中気持ちよく演奏できているだろうか、何か合図を送ってやしないか、常に返しが気になります。でもハウス卓返しだと表の音や曲出しとか仕事が多くてステージばかり見ているわけにもいきません。
一度でいいから、ハウスとモニターを分離した現場を経験してみたいと今思っているわけです。しかし機材が増え、仕込みに時間がかかれば結局「ハウス返しでいいじゃん」となるだろうことは十分予想できます。そこまでやって、それに見合うだけの効果があるかどうか。どちらにしても、モニターを重要視する私がことあるごとに悩むことですから、少しでも効果が出そうなことはやってみたい。
モニター専用卓を設置するためには、ステージから来るラインをハウス卓へ送るラインとモニター卓へ送るラインとで2分岐しなくてはなりません。ここのやり方がよく解らない。近大社長に聞いても、モニターマン自体がよく解らないらしくて×。以前、大きな音響屋さんに聞いた時は、単純にパラっていいんじゃない、と言われてました。本とかにはスプリッターを使うと書かれています。
単純にYケーブルでラインをパラレルにしてしまうことを“純パラ”と言います。しかしこれだとゲインが下がってしまう。それほど気になるレベルではないとは思いますが出来るなら下げたくない。ファンタムかけているラインが混じるのも不安だし…。ここはやはりスプリッターで独立2分岐させたいです。


ARTの8チャンネルを全て2分岐させるマイクスプリッターです。これを2台ラックに組んでマルチボックスみたいにステージに転がしておいて、ここからスネークでモニターとハウスに送ればいいかなって考えています。
ここまではアナログで考えていますけど、時代はデジタル。従来のアナログマルチケーブルに変り、デジタル変換できるステージボックスを置けば何本だろうと好きなだけデジタルラインを分岐できます。まだまだ高価なデジタル機材ですが、べリンガーから続々と出てきそうで、デジタルが一般的になればすぐ価格は下がります。もう少し様子見ですかね。


















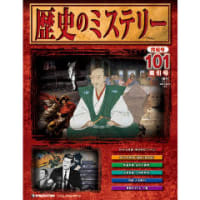

モニター卓の設置ですが、おっしゃるとおり機材がほぼ倍になるため、時間と労力の確保が必要です。それと入力の分岐ですが下手なスプリッターを使うよりは、単純にパラる方が音質・経費の面から見ても遙かに得策です。(但し、バランス・アンバランスの混在は避けることと、入力がー6dB下がるためSNの良いヘッドアンプが不可欠となります、ファンタムについては使用する機器によりますが)。
最近はデジタル機器の普及でEQによる位相ズレも少なくなりましたが、MICも含め一定レベル以上の機器を使わないとハウリングの原因等になります。(過去にハウリングに悩まされたお手伝い現場で、ボーカルマイクをたまたま持参していたSM58に変更したことでEQに頼らずハウリングが止まった事もあります(笑))
最後に、ハウスOPとのコミュニケーションが一番重要でバンド奏者(アマチュアの場合)の要望のままモニターMIXをしているとハウスの出音に影響してきますし、ハウスがモニターのことを考えずに(特に小さな会場)調整していると音の洪水になってしまい、どちらが原因でハウっているのかわからなくなってきます。
支離滅裂な戯言で長々のコメント恐縮ですが、どこかの現場でお会いできれば語り合いたいですね(笑)
実際の純パラの方法ですが、カナレの16chパラボックスでパラってしまえばいいかな~と思っています。ケーブルと合わせて高い買い物になりますが、ハウス卓返しの現場でも使えますので重宝します。ファンタムも片側にかかっていれば大丈夫と聞きました。
今のところ卓はハウス側にYAMAHAのMG32/14FXを使い、モニター側にPRESONUSです。でもモニターマンが必要な現場はそんなに多くはありませんよね。一つあるとしたら去年、防府市公会堂で行ったようなロックコンサートでしょうか。さすがにあれだけハウスがステージから離れると意志の疎通が困難でした。
音響屋って、一般の方からみたら工務店的な所謂“業者”になるんでしょうけど、私はれっきとしたアーティストの端くれだと思っています。配管工事や電気工事は求められた品を納品したり施工したりとそれこそ“業者”なんですけど、音響屋はアーティストたちと一緒になってステージを作っていく“クリエイター”でありたいと私は思っています。
常に新しいモノを求めて挑戦し続けて、良いモノを作りたいと言う情熱を惜しまない、そんな音響屋でありたいと思います。音響がルーチンワークになってしまったら後進に道を譲ってさっさと引退です。その点「照明」は新しいことを持ち込みやすいので「音響」よりはアーティストっぽいかも知れませんね。
新しいことにトライし続けて、より“安定”の部分を大きくして、どんな注文にも応えられる音響屋になりたいです(夢です)。ほんと語り始めるときりがないのでこのへんで止めときます(笑)。今後は宇部方面に出ていくことが度々あると思います。amateurPAman様と顔を合わせる日も遠くない気がします。
コメントありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
「ファンタム電源の使用する機器による」とコメントしていましたが補足です。
最近の機器にはまずあり得ないとは思いますが、片方からファンタムをかけるともう片方の入力にも当然ファンタム電圧がかかります。ミキサーのXLR入力では、カップリングコンデンサーによるDCカットがきちんとされているか、また、耐圧は十分か等の問題があります。
また、特にコネクターの抜き差しについてはハウス、モニターの双方が確認し合いながら作業する必要があります(ノイズによる機器の破損につながります)トラブル時のケーブルチェック等は要注意です。
尚、全般に言えることですが、アクティブ機器のOUT(例えばリバーブ等)がつながっている端子にファンタムは危険です。
グループでファンタムSWがある場合は特に接続先に注意です。
既にご承知の事かもしれませんが、言葉足らずだったので補足させていただきました。
私のアナログミキサーはグループでファンタムがかかるタイプなので、今まではファンタムが必要なコンデンサー、DIの他はダイナミックマイクを残して全てフォーンで入力していました。ワイヤレスとかエフェクターとかですね。
しかし純パラ分岐でモニター卓をつなぐとモニター卓の入力にファンタムがかかることになり不安です。私、結構な機械音痴でファンタムを正確に説明しろと言われたら出来ません。ただマニュアルを読んで、それに沿った使い方をしているだけ。ですからamateurPAmanさんのようにしっかり説明できる方を尊敬します。
コネクターの抜き差しの問題は更に深刻かも知れません。バタバタした中でついチャンネルミュートだけしてコネクターを抜いてしまうと、もう一台つながっているミキサーに影響を与えてしまいます。ハウスがステージから遠いからモニターを設けたいわけで、そうなるとハウス・モニター間の連携も怪しいもんです。
結局、様々な問題点を抱えながらそれでもモニター卓をやるのか?ってなると…、正直やらないかも知れません(汗)。しかし私にとってこの“あ~でもない、こ~でもない”とやってる間が一番楽しく、また勉強にもなっています。
話に付きあってくださり、ありがとうございます。