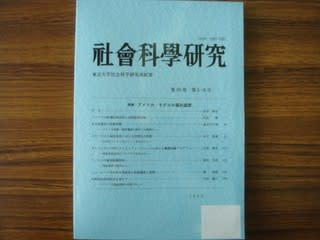今日12月5日付の厚生労働省のHPでは、たくさんの資料がアップされています。
以下の5点(年金3点、障害者政策1点、介護給付費1点)を、
「社会福祉資料集」(ブックマーク901)の関係箇所(5年金、2人権、4介護)
にリンクしました。
○ 確定拠出年金 2件
○ 第34回年金数理部会
○ 第47回障害者部会
○ 第60回介護給付費部会
*写真は、12月2日、城山展望台から。 . . . 本文を読む
厚生労働省は、本日11月27日付のホームページで
年金部会の「議論の中間的整理」を公表しました。
このブログで第1871号(11月19日)に紹介した資料を(細目の調整を終えて)正式に今日付けで公表したものです。
今後の年金制度の論議の出発点になりますので、「社会福祉学資料集」の年金の項目にアップしました。
ご関心の向きはそちらをご覧ください。
項目としては、8項目でかわりません。(19頁ありま . . . 本文を読む
桜島。11月18日です。天気がよかった日です。
いつものように「鹿児島散歩」さんから。
昨日、11月19日の年金部会の様子は、今朝の各紙に報道・解説されていました。
このブログでも、第12回(11/12)の資料をリンクしたばかりでした。(11/17 第1857号)
厚生労働省は、今日、11月20日のホームページで、この13回部会(11/19)をアップしています。
重要ですので、かなり重複があ . . . 本文を読む
写真は、
安曇野カンポンLIFEの11月19日の記事からお借りしました。秋から冬へ、場面は急転しましたね。
ヨーロッパの年金制度にも冬が来たか?
今度の世界金融危機で積立金を運用する立場の年金も従来のやり方の再考を迫られています。
ISSA国際社会保障機構は、毎日のように全世界の政策動向をアップしています。
その11月19日の欄にあったのは、
International Herald Trib . . . 本文を読む
厚生労働省は、今日のホームページで
社会保障審議会年金部会(第12回:11/12)の資料をアップしています。
○ 次期改正のための議論メモ (5ページ)
→一部新聞報道で項目が伝えられた。
このブログでもここまでにいたる経過の資料は紹介しました。
○ 財政計算の資料(このブログ第1837号。2008.11.13で紹介したもの)
○ 社会保障国民会議 最終報告
○ 参考資料(統計、説 . . . 本文を読む
年金に関しては、
○ 自分の年金がいくらなのか
○ 制度はどうなっているのか
○ これからどうなるのか
と、幾つかのレベルがありますね。
このブログでは、最後のテーマを中心に、「年金」のカテゴリでお話しています。
【基礎的な情報】
としては、厚生労働省のホームページがあります。
新聞各紙も折に触れて、解説記事をだしています。
【定期的な情報誌】
としては、
『年金時代』(月刊、社会保険 . . . 本文を読む
厚生労働省は、昨日、11月12日、ホームページで
社会保障審議会年金部会
経済前提専門委員会(第6回:11月11日開催)の資料をアップしています。
*これは、昨日の年金部会で説明されていると考えられます。
○ 公的年金の改正は5年ごとに行われる。
○ 平成16年改正の次は平成21年改正ということになり、年金部会で審議が本格化している。
○ その前提の作業として、年金論議の前提となる経済諸指 . . . 本文を読む
【東大社会科学研究所】
図書館で、
『社会科学研究』(第59巻第5&6合併号、2008.3.31)を借りました。(写真は、その表紙)
特集:アメリカ・モデルの福祉国家
は、奇異な感じを受けますね。アメリカには、公的な医療保険制度がないなど、国際的に「福祉国家」としては例外的な存在として知られているからです。
しかし、福祉国家の研究で多くの成果を発表している東大社研が、特集を組むからにはそれなりの . . . 本文を読む
年金問題の難しいことは
貰う額が一人ひとり違うことです。
ある人は充分と思い、ある人は少ないと思う。ある人には、そもそも年金がない。
平均像を知るために、
このブログでは、
男性の場合の月額 187,545円 2008.07.07付け記事
女性の基礎年金月額 48,929円 2008.04.01付け記事
を紹介したことがあります。(いずれも、出典は、厚生労働省HP)
国際的に年金の水準を比 . . . 本文を読む
厚生労働省は、今日10月1日、そのホームページに、
去る9月30日に開催された
社会保障審議会年金部会(第11回)の配布資料をアップしました。
年金部会におけるこれまでの議論の経過を整理した資料(資料3)
はじめ、最近の年金政策をめぐる主な関連資料が配布されています。
これから議論は収斂の方向へと向かうものと見込まれますが、年金改正に関するこれまでの経過を知るための基礎資料集といえます。
私 . . . 本文を読む