
先週の雪月花さんのブログの、「無常といふこと」に触発されて、たまには真面目にものを考えてみようという気になって、久しぶりに世阿弥の「風姿花伝」を読み返しています。
今日では、教科書にも一部が採択されており、世阿弥の名と共に広く「花伝書」の愛称で知られ、多くの注釈書も出ていますが、数百年の年月、能の家に秘蔵されてきた演技や演出に関した芸能論です。
世阿弥自身、「無常といふこと」を身をもって体験した生涯ですが、30代の終わりから40代半ばという若さで書かれたことが(別紙口伝を除く)信じられないほどの、人生への洞察の凄みと、一種の悟りすら感じられます。
ここ書かれているのは、芸一筋に生きる者にとっての相伝される心構えであり、なまじっかの素人の稽古の現実とは無縁の世界です。
むしろ、徒然草と同様、人生の教えといった懐の深さを持っていますし、我が子に伝えるためのすぐれた教育論でもあります。
厳しい自戒、徹底した鍛錬の積み重ね、工夫で、表現の精髄に迫ろうと励んだ中世の芸能者の語りかける一語一語には、役者であり、作者であり、演出家をも兼ね、かつ体験に立脚したすぐれた理論家でもあった稀有の天才の切実な熱い想いがあふれています。
他者の意見に耳を傾け、後進を育て、確立した芸を後世に伝承するための、厳しく、それでいて温かな指針となりえています。
「稽古は強かれ、情識は無かれ」
風姿花伝の序文の末尾の言葉です。「情識」とは思い上がった頑なな心です。
稽古は厳しく、しかも何物をも謙虚に学び取る姿勢を説いて,[問答条々]の言葉から拾うと「上手は下手の手本、下手は上手の手本なりと工夫すべし」と展開しています。下手の長所を進んで学び取る柔軟さと、そうして磨きぬいた芸、工夫を重ねて「花を知る」というのでしょう。
当分、世阿弥の名言に引き回されることになりそうです。










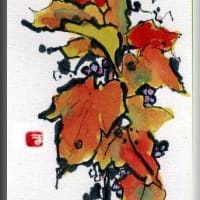





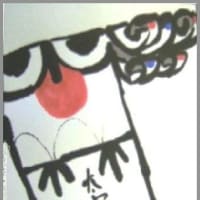

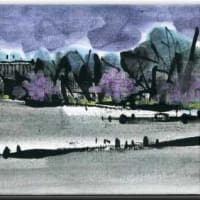
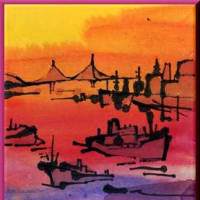
「時分の花」がまだ残っておいでの方は羨ましい。動きも、考えも柔軟です。
移ろいはてても、せめて残り香でもあればまだ救われますし、それなりの美も存在しますが。
天才などは無関係、そんな苦しい才は欲しくもありませんが、雲のように「心のまま」に生涯求め続ける気力だけは失いたくはないと思うのですが、所詮、分を超えた高望みの憧れでしょうか。
先人たちの遺されたすぐれた才を、涎をたらして堪能することにします。
以前、やはり仕舞をなさっていた目上の方にやさしく叱っていただいたことがあります。「器用で凡人より早く形を身につけてしまう者と、不器用で人一倍時間をかけて形を会得する者と、どちらがうまく舞えると思うか。それは後者だ」と。何事もいい加減なわたしへの忠言だったろうと、いまも時折思い出すのです。
世阿弥が『花伝書』を著したころと同じ年齢にしてこの始末です。「無常」も「もののあはれ」もこの身の実感から語ることができません。それを、人の生死というものが身近に感じられない現代という時代のせいにしてはいけないのでしょう。
『風姿花伝』、わたしも近いうちにきっと読み返します。有難うございました。
雪月花さま
いつも真剣勝負のような気迫でお書きになるブログの記事に接して、「後生畏るべし」と感じ入っています。
いつぞや「器用貧乏」というタイトルで、私も似たような嘆きを記しました。
趣味にすぎない遊びのグループで絵を楽しんでいますが、ひたむきに精進を続ける後発の人が、気がついてみると、理屈ばかりで、あれもこれもの欲張りを、いつのまにか追い越して、確かな自分のものをつかんで、雰囲気のある作品をものしていらっしゃいます。
こちらは葉が茂るばかり、いまだ花芽がつきません。
椿の美術館も雪月花さんに教えていただきました。いつも感謝しています。
「風姿花伝」手ごわいけれど、その求めたものを追うのは楽しみでもあります。
「無常といふこと」を書かれた雪月花さんに、(別紙口伝)の言葉をお贈りします。
「いづれの花か散らで残るべき。散るゆゑによりて咲くころあれば、珍しきなり。能も、住するところなきを、まづ花と知るべし。」
花は散るゆえに一層愛惜され、散るからこそ再び咲く。このように生滅し変化するさまを「珍しさ」の根拠とみて、変化し移ろうゆえに新鮮な感動を与えると言っているのだと思います。
「花と面白きと珍しきと、これ三つは同じ心なり。」(別紙口伝)
と述べています。
作曲は完成後は一切修正不要、そう、間然するところがない。
彼は例外中の例外。
努力の人・ブラームスは違うんですね、交響曲一番の完成に何年もかかっている、その間、多くの知人のアドバイスに耳を傾けてはったそうです。
世界の岡本プロのfanですが、好きになったキッカケが彼女のセリフでした。何か?って。
下手なアマチュアとラウンドするのは面白くないでしょう?との質問に答えて曰く”ビギナーの方々の打法に私の知らないモノを発見し、トライする場合がありますのよ・・”
この御両人の”心の自在と余裕”は正しく花伝書の真髄を習得された上での事でしょうね。
ところで、序文の①の方”飲む・打つ・買うは駄目よ
”との人生論処方箋は花伝書が最初なんでしょうか?
そう、花伝書は”如何に生きるか?”に資すると言う事でロングセラーとか。
既にロスタイムに突入した者としては急がないと・・。忙しい事です。
「古人の掟」とされていますから観阿弥以来の重い掟だったのでしょう。でも、この三つ、最大の魅力ですから、深入りすれば組織の統制を乱すし、稽古どころではなくなりますからね。
人間の歴史と共に永遠のテーマとなるのでしょう。
三拍子は、いずれ芸能関係から出た言葉でしょうが、それぞれは、酒は万葉の昔からだし,徒然草でもその戒めは何度も出てきます。博打も多種多様、「日本紀」には、天武天皇が大安殿で王卿に博戯をおさせになった記事がありました。白河法皇の双六も有名です。買うのも、世の中に男女があるからには形がどう変わってもという気がしますね。
三つセットも、探せばきっと日本にもありそうですが、どれもそこそこだと人生に「花」がと思います。勿論、世阿弥の「花」の次元ではありませんが。酒にも「大」が付いていることですし。
「春夜宴桃李園序」にもあります。
ましてロスタイム入りを自覚する身には 「爲歡幾何・・・・坐華、飛羽觴而酔月」といきましょう。お酒も辛口が好きです。