パソコンの起動をブートと言いますね。これはパソコンが登場する以前の大型コンピュータでも使われていた「ブートストラップ」という言葉の略で、革のブーツの両サイドまたはかかと側に取り付けられている、指をかけて引っ張るツマミのことです。
『ほらふき男爵の冒険』という有名な本に、穴だか沼だかに腰まではまってしまったとき、自分のブーツのツマミをつかんで自分で自分を引っ張り上げて脱出する(実際にはできません)という笑い話が載っています。「ブーツのツマミをつかんで自分を引っ張り上げる」という英文は「自力でやる」という意味の慣用句になっていて、これがパソコンのブートの正体です。
起動がなぜ「自力でやる」なのかというと、電源を入れた直後のパソコンの頭の中はからっぽですが、かすかに憶えているハードディスクの読み出し方を頼りに、自分の頭にWindowsなどのOSを詰め込んでいく、つまり自分で自分を引っ張り上げる工程だからです。もし、すでに起動している別のパソコンをもう1台使わないと起動できないのだとしたら、すごく不便ですよね。自力バンザイ。
「パソコン起動 = ほらふき男爵説」はおそらく世界標準だと思いますが、その他にもいくつか誤訳にもとづくと思われる説があります。たとえばブートストラップをブートレース(靴ひも)と取り違えて「靴ひもを編み上げていくように順を追ってOSを立ち上げていくから」という説や、あるいは「引っ張り上げる」を「自分を向上させる」と解釈して「はきにくいブーツを誰の助けも借りずにひとりではく → 困難にひとりで立ち向かう → 何もないところからがんばってOSを起動させる」という説などです。
誤訳らしき説もなかなか味があってよいのですが、私はやはりほらふき男爵説を支持したいですね。なかなか起きられない冬の朝、自分の髪の毛をつかんで自分で自分をフトンから引きずり出す(実際にはできません)みたいなイメージ。スイッチを押すたびに寝ぼけまなこのパソコンの絵が頭に浮かんでほほえましいです。
(´ー`*)
『ほらふき男爵の冒険』という有名な本に、穴だか沼だかに腰まではまってしまったとき、自分のブーツのツマミをつかんで自分で自分を引っ張り上げて脱出する(実際にはできません)という笑い話が載っています。「ブーツのツマミをつかんで自分を引っ張り上げる」という英文は「自力でやる」という意味の慣用句になっていて、これがパソコンのブートの正体です。
起動がなぜ「自力でやる」なのかというと、電源を入れた直後のパソコンの頭の中はからっぽですが、かすかに憶えているハードディスクの読み出し方を頼りに、自分の頭にWindowsなどのOSを詰め込んでいく、つまり自分で自分を引っ張り上げる工程だからです。もし、すでに起動している別のパソコンをもう1台使わないと起動できないのだとしたら、すごく不便ですよね。自力バンザイ。
「パソコン起動 = ほらふき男爵説」はおそらく世界標準だと思いますが、その他にもいくつか誤訳にもとづくと思われる説があります。たとえばブートストラップをブートレース(靴ひも)と取り違えて「靴ひもを編み上げていくように順を追ってOSを立ち上げていくから」という説や、あるいは「引っ張り上げる」を「自分を向上させる」と解釈して「はきにくいブーツを誰の助けも借りずにひとりではく → 困難にひとりで立ち向かう → 何もないところからがんばってOSを起動させる」という説などです。
誤訳らしき説もなかなか味があってよいのですが、私はやはりほらふき男爵説を支持したいですね。なかなか起きられない冬の朝、自分の髪の毛をつかんで自分で自分をフトンから引きずり出す(実際にはできません)みたいなイメージ。スイッチを押すたびに寝ぼけまなこのパソコンの絵が頭に浮かんでほほえましいです。
(´ー`*)










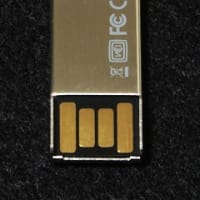







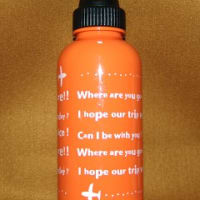
高かったのに最近はいてないなぁ
キャンプに行きたい。
使う方は面倒だろうけど。
動詞になってるから自動的に"re"付きのほうもアリです。
http://en.wikipedia.org/wiki/Reboot
ウィキペディアに載ってるから真実だとは言えないけどね。
日本で「ググる」って言うけど、あちらでも
You can google it. って言ってるのを聞いて感心した。
まあ、普通に使うって事ですね@米英