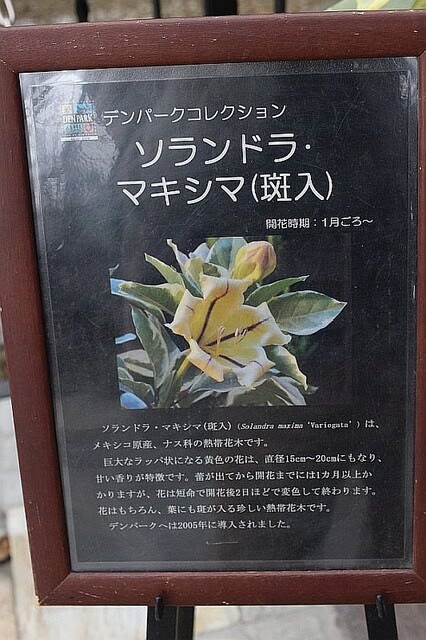ミニ花壇に植えてあった花は プリムラ・ジュリアン。
プリムラというのは サクラソウ科の花で、このジュリアン以外にも ポリアンサ、オブコニカ、マラコイデス、シネンシスなどがあるということです。雲南サクラソウもプリムラの仲間でした。

で、トピックの おしべめしべ に移りますが、この花、前のスウィートアリッサムのおしべ・めしべと比べて ちょっと変わってますね?

見えているシベは 大きな葯を付けたおしべです。めしべが見えないのです。

ということは??
キク科などのように、雄しべが成熟するときと めしべが成熟するときと タイムラグを作っているのでしょうか?

別の株の花を見てください。 こんどは 丸いめしべだけがあり、おしべは見当たりません。

もっと近づいて花筒の奥を覗き込んでみると、下のほうに 雄しべらしき環状の器官が見えます。雌しべが先行して成長したあと、これが 今の雌しべの位置まで成長して 雄しべ活動期になるのでしょうか?

調べてみると、「雌しべ期・雄しべ期」の仮説は間違っていることが分かりました。
実際は めしべとおしべは同時に活動するのだけれど、 株によって、めしべのほうが背が高くおしべのほうが背が低い花(長花柱花)と、 おしべのほうが背が高くめしべのほうが背が低い花(短花柱花)と 2種類あるというのです。
なんのために??
プリムラのばあい、ちょっと花筒があって判りにくいので、ソバの花で説明します。
ソバの 長花柱花 (めしべのほうが おしべよりずっと高い)

アリ さんが花粉媒介者(ポリネータ)になるケースで 説明します。
アリさんが長花柱花の蜜をなめにやってきました(↑)。アリさんは背の低いポリネータです。雄しべが背の低い長花柱花の蜜を吸うとき 体に花粉が付きます。(めしべは高いところにあるので 触れません)
ソバの 短花柱花(めしべは 雄しべの半分くらいの高さしかない)

さっきのアリさんが 今度は 短花柱花のところにやってきました。こんどは アリさんと同じくらいの高さにあるのは めしべの柱頭です。こうして 先ほど長花柱花のところで付けた花粉が 短花柱花の めしべに付きました。無事 他家受粉成功です(^^♪
身体の大きな ハチさんのばあいは 今の逆です。
(雄しべのほうが背が高い)短花柱花で花粉をつけ、(めしべのほうが背が高い)長花柱花に行って授粉すると、これまた他家受粉がうまくいくというわけです\(^o^)/
さらに、ミソハギのおしべには 一つの花に 長いおしべと 短いおしべとあって、
a. 長いおしべ > 短いおしべ > めしべ (短花柱花)
b. 長いおしべ > めしべ > 短いおしべ (中花柱花)
c. めしべ > 長いおしべ > 短いおしべ (長花柱花)
のように、3タイプの株があるということです。
このプリムラのばあい、先ほども言いましたように、トランペット型の花筒なので、たとえば ハチさんが筒の奥の蜜を吸おうとすると、雄しべにも雌しべにも触ることにはならないのか、少し 疑問です。
ソバのばあい、同じタイプの株同士で 人工受粉しても ほとんど結実しないと言われています。
プリムラの花の人工受粉の記事を読んでも、同じ花のおしべとめしべで手っ取り早く自家受粉させる方法が書いてありますが、「自家受粉を続けると株の性質が弱ってきます」。
植物が長い時間をかけて、自家受粉を避ける意匠を編み出してきたのですから、人工受粉するときもその心意気を大切にしたいものです。
.