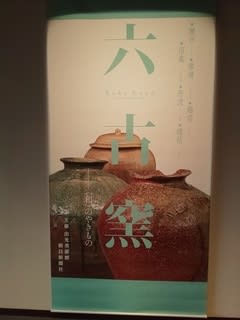
★出光美術館 サイト
『六古窯―〈和〉のやきもの』 ※6月9日(日)まで
『六古窯―〈和〉のやきもの』 ※6月9日(日)まで
六古窯といったら、茶道文化検定の勉強を思い出す。
必死で暗記したっけ。
備前、信楽、丹波、越前、瀬戸、常滑。
備前はいわずもがな。信楽は茶道を習い始めて1年半が経った頃、1泊で旅行したから覚えた。
丹波はまぁ、地元だから。(といっても、同じ兵庫県というくくり)
実家には立杭焼のお銚子とお猪口のセットや花瓶があったから、なんとなくわかる。
瀬戸は初心者の稽古道具(茶入)が瀬戸焼だったので、わかる。
常滑はまぁ、なんとなく。
越前は一番馴染みが薄く、覚えづらかった。今でもよくわからない。
印象としては、備前と信楽と丹波が同じ系統?なんて、勝手に思っていたけれど、
そうういう考え方からして、違ってた。
根本的に覆された!という感じ。
まず、六古窯は2つの系統に分けられる。
釉薬を用いない須恵器(すえき)系か、釉薬をかける瓷器(しきorじき)系か。
そして、6つの古窯のうち、須恵器系は備前のみで、他の5つは瓷器だった。
へ? でも、言われてみればそうだ。
つまり、備前焼はちょっと特殊かもしれない。
六古窯ではないけれど、須恵器系としては備前のほかに珠洲焼があるとのこと。
あ、なるほど。そうだ。
珠洲焼のお茶碗を一つ持っている。(実家に置いてきたけれど)
ほー。(と思ってしまった)
また、中世における「三種の神器」も初めて知った。
(現代でいうところの、冷蔵庫、洗濯機、テレビにあたる中世版?)
「壺」、「甕」、「擂り鉢」なんだとか。
なるほどー。水を含む食糧の貯蔵や調理には欠かせないアイテムかも。
そう思って、観ると奈良時代の壺!フムフム
中国は越州窯(五代)の青磁鉢などが展示されているのを見て、器の(使われ方の)変遷も少し理解できた。
京の都に近いということで、越前は瓶子も供給してたんだね。
壺は備前、珠洲、そして信楽。
鎌倉時代になると、通り道?なのか瀬戸、常滑。
室町時代にかけて珠洲。
だけど、お手本は大陸から南宋の青磁や高麗のもの~
中世になって、大壺がでてくる。丹波、常滑、信楽。歴史が長いから大きいものも焼ける技術がある、
そして、茶の湯。やはり、美濃が強い?
いやいや、伊賀窯や信楽窯、備前窯も侘びた水指や花生を造り出している。
だけど、美濃窯の黄天目。ステキ。 中国の灰被天目に匹敵する味わいを出している。
信楽の鬼桶水指もすごい。
黄瀬戸の立鼓花入がおデブちゃんでかわいい。(つい、「ひろい子」ちゃんを基準に考えてしまうので)
江戸時代になると瀬戸肩衝茶入。 やはり、これ代表格。
瀬戸大海茶入「置紋」の大きな口廻りが面白かった。
おぉ、御深井焼。御深井は「おふけ」と読む。尾張藩のお庭窯。
先日、名古屋城で御深井丸というエリアにも足を踏み入れたけど、関係あるのかなぁ。
(3月に滴翠美術館でも御深井焼をけっこー見た)
そして、やっぱり輸入してもほしい唐物。
南宋青磁から元代の壺、景徳鎮の青白磁。
てなことで、六古窯とその時代の国内外の陶磁器が頭の中でくるくるしてた。
近美工芸館からハシゴして鑑賞したので、めちゃ濃厚だったわ~
※出光美術館バックナンバーリスト
2018年5月『宋磁―神秘のやきもの』
2018年1月『色絵 Japan CUTE!』
2017.10月『京みやび ―仁清・乾山と色絵の競演』(門司)
2017.5月『茶の湯のうつわ ―和漢の世界』
2016.6月『美の祝典』Ⅱ(パート2)
2015.10月『日本の美・発見X躍動と回帰 ―桃山の美術』
2014.11月『仁清・乾山と京の工芸 ―風雅のうつわ』
2014.3月『没後50年・大回顧展『板谷波山の夢みたもの-〈至福〉の近代日本陶芸』』
2013.6月『やきものに親しむ10 古染付と祥瑞』
2013.5月 『源氏絵と伊勢絵』
2012.9月 『白く美しいやきもの 純なる世界』
2012.4月 『悠久の美 -唐物茶陶から青銅器まで』
2011.8月 『明・清陶磁の名品 -官窯の洗練、民窯の創造』
2011.1月 『酒井抱一生誕250年 琳派芸術 ―光悦・宗達から江戸琳派―』
2010.12月 『やきものに親しむVIII 茶陶の道 ―天目と呉州赤絵―』
2010年9月『SENGAI Zen and Humaor 仙』
2010年4月『茶 Tea-喫茶のたのしみ』
2010年1月『麗しのうつわ』
2008年12月『陶磁の東西交流』
2008年4月『柿右衛門と鍋島』
2007年11月『乾山の美術と光琳』
※2009年3月『出光美術館コレクションの至宝「茶の湯の美」』 栃木県立美術館
2018年1月『色絵 Japan CUTE!』
2017.10月『京みやび ―仁清・乾山と色絵の競演』(門司)
2017.5月『茶の湯のうつわ ―和漢の世界』
2016.6月『美の祝典』Ⅱ(パート2)
2015.10月『日本の美・発見X躍動と回帰 ―桃山の美術』
2014.11月『仁清・乾山と京の工芸 ―風雅のうつわ』
2014.3月『没後50年・大回顧展『板谷波山の夢みたもの-〈至福〉の近代日本陶芸』』
2013.6月『やきものに親しむ10 古染付と祥瑞』
2013.5月 『源氏絵と伊勢絵』
2012.9月 『白く美しいやきもの 純なる世界』
2012.4月 『悠久の美 -唐物茶陶から青銅器まで』
2011.8月 『明・清陶磁の名品 -官窯の洗練、民窯の創造』
2011.1月 『酒井抱一生誕250年 琳派芸術 ―光悦・宗達から江戸琳派―』
2010.12月 『やきものに親しむVIII 茶陶の道 ―天目と呉州赤絵―』
2010年9月『SENGAI Zen and Humaor 仙』
2010年4月『茶 Tea-喫茶のたのしみ』
2010年1月『麗しのうつわ』
2008年12月『陶磁の東西交流』
2008年4月『柿右衛門と鍋島』
2007年11月『乾山の美術と光琳』
※2009年3月『出光美術館コレクションの至宝「茶の湯の美」』 栃木県立美術館




























