福田首相のリーダーシップにおける不安について。
回避的性質を加えての分析予測。
回避的な性質とは、常に周囲からの批判や拒絶を気にしているものだ。肯定的に受け入れてもらえなければ、関係を持ちたくないという割とはっきりした考えである。このような思考が閣僚の人選に影響しているだろう。つまり福田首相としては閣僚内部からの批判には耐えられないのではないかという不安がある。この点については支持率がさらに低下してからの反応として注目すべきだ。
また大勢の応援を取り付けて自民党総裁となった経緯については政党に依存的であると言える。この点で親子二代にわたっての首相という地位が現在の自尊心そのものなのであるのだが、そんな彼の現在的な笑顔は、政党依存を無理に否定するために作られたものである。そこにこそリーダーシップを発揮しなければならないという福田首相の苦悩があるのだ。
元々、誰かに利用されてしまうのではないか、という気持ちがある。不信感が拭えない、というよりは、安心できない、リラックスできないというほどだ。しかしこれは慢心によるものであり、協調性にも問題があることを示唆している。
この慢心からの影響としては総裁選での誇大な表現が思い出される。
たとえば、2007年9月15日、自民党総裁選での共同記者会見では「改革を続けていかなければならない」と訴えていたが、最近では党内から増税論ばかりであり、結局のところ指導力のなさばかりが目立っている。また「拉致の問題については対話と圧力という姿勢で臨みたい」と語ってはいるが、今のところそのような明確な動きは何1つない。今となってみれば、これらの言葉がいかに福田首相にして適わない誇大な願望であったか、が伺える。
以前の分析では、「政党という集団に依存的なので、党内決定の正当性を強く主張しすぎる」と書いたが、2007年9月15日、自民党総裁選での共同記者会見でも「復党問題は党の原則は尊重しなければいけない」と言っている。これについては現在の分析でも、本質的な部分を無視しての結論、として分析できることだ。小泉改革を評価している割には、郵政造反議員の復党には、「党の原則」と言い換えるとは、本質を無視し、政治家にして一貫性を欠いたものである。ひじょうにご都合主義と言わざるを得ないことだ。
このような意見の不一致に関しても、党の原則に対して無理にも対応しなければならないという現実とは、笑顔を作りながらでも党への依存性を否定しなければならないと誤魔化し続けなければならないものなのだ。
支持率のためにやっているのではない、としても記者の質問に愚痴で対応するようなら、それは自信が無くなったというサインであり、政権と政局不安を意味すると予測する。
薬害肝炎問題での原告側の一律の和解という政治決断のときもそうだったが、福田首相は考えすぎて時間がかかり、さらに自ら悩むところがあると指摘できる。これも、安心できない、リラックスできない、という緊張感が、良い意味では用心深さとなり、悪い意味では頑固さとなっているからだ。
このような性質が今後も影響するとしたら、閣僚との信頼関係もさほど作れないだろう。
それにしても彼に同盟とか、盟友と呼べるほどの気の許せる政治家がいるのだろうか、と疑問を持ってしまう。本人からもそんな発言は一切聞かれない。
派閥は町村派だそうだが、小泉政権で主流派となり大所帯ともなったこの派閥で、内閣官房長官に推薦した小泉氏や、李登輝氏が病気治療目的で来日を希望した際に中国への配慮からビザ発給に共に反対した当時、外務大臣河野洋平(1995年、村山内閣改造内閣。河野氏とは早大同級生。当時は政務次官)などとの交友はあまり聞かない。
常識的には靖国の対応の違いから小泉氏とは相容れないようだし、河野洋平氏が無派閥だとしても、麻生氏がその派閥を継承しているという点から見れば、都合のいい関係ともいかないだろう。
これらの点からも、福田政権、いや福田氏の内的な不安定さはこれからも続くと思われる。
昨日は人気ブログランキング「ニュース」138位。今日は何位でしょうか?
回避的性質を加えての分析予測。
回避的な性質とは、常に周囲からの批判や拒絶を気にしているものだ。肯定的に受け入れてもらえなければ、関係を持ちたくないという割とはっきりした考えである。このような思考が閣僚の人選に影響しているだろう。つまり福田首相としては閣僚内部からの批判には耐えられないのではないかという不安がある。この点については支持率がさらに低下してからの反応として注目すべきだ。
また大勢の応援を取り付けて自民党総裁となった経緯については政党に依存的であると言える。この点で親子二代にわたっての首相という地位が現在の自尊心そのものなのであるのだが、そんな彼の現在的な笑顔は、政党依存を無理に否定するために作られたものである。そこにこそリーダーシップを発揮しなければならないという福田首相の苦悩があるのだ。
元々、誰かに利用されてしまうのではないか、という気持ちがある。不信感が拭えない、というよりは、安心できない、リラックスできないというほどだ。しかしこれは慢心によるものであり、協調性にも問題があることを示唆している。
この慢心からの影響としては総裁選での誇大な表現が思い出される。
たとえば、2007年9月15日、自民党総裁選での共同記者会見では「改革を続けていかなければならない」と訴えていたが、最近では党内から増税論ばかりであり、結局のところ指導力のなさばかりが目立っている。また「拉致の問題については対話と圧力という姿勢で臨みたい」と語ってはいるが、今のところそのような明確な動きは何1つない。今となってみれば、これらの言葉がいかに福田首相にして適わない誇大な願望であったか、が伺える。
以前の分析では、「政党という集団に依存的なので、党内決定の正当性を強く主張しすぎる」と書いたが、2007年9月15日、自民党総裁選での共同記者会見でも「復党問題は党の原則は尊重しなければいけない」と言っている。これについては現在の分析でも、本質的な部分を無視しての結論、として分析できることだ。小泉改革を評価している割には、郵政造反議員の復党には、「党の原則」と言い換えるとは、本質を無視し、政治家にして一貫性を欠いたものである。ひじょうにご都合主義と言わざるを得ないことだ。
このような意見の不一致に関しても、党の原則に対して無理にも対応しなければならないという現実とは、笑顔を作りながらでも党への依存性を否定しなければならないと誤魔化し続けなければならないものなのだ。
支持率のためにやっているのではない、としても記者の質問に愚痴で対応するようなら、それは自信が無くなったというサインであり、政権と政局不安を意味すると予測する。
薬害肝炎問題での原告側の一律の和解という政治決断のときもそうだったが、福田首相は考えすぎて時間がかかり、さらに自ら悩むところがあると指摘できる。これも、安心できない、リラックスできない、という緊張感が、良い意味では用心深さとなり、悪い意味では頑固さとなっているからだ。
このような性質が今後も影響するとしたら、閣僚との信頼関係もさほど作れないだろう。
それにしても彼に同盟とか、盟友と呼べるほどの気の許せる政治家がいるのだろうか、と疑問を持ってしまう。本人からもそんな発言は一切聞かれない。
派閥は町村派だそうだが、小泉政権で主流派となり大所帯ともなったこの派閥で、内閣官房長官に推薦した小泉氏や、李登輝氏が病気治療目的で来日を希望した際に中国への配慮からビザ発給に共に反対した当時、外務大臣河野洋平(1995年、村山内閣改造内閣。河野氏とは早大同級生。当時は政務次官)などとの交友はあまり聞かない。
常識的には靖国の対応の違いから小泉氏とは相容れないようだし、河野洋平氏が無派閥だとしても、麻生氏がその派閥を継承しているという点から見れば、都合のいい関係ともいかないだろう。
これらの点からも、福田政権、いや福田氏の内的な不安定さはこれからも続くと思われる。
昨日は人気ブログランキング「ニュース」138位。今日は何位でしょうか?










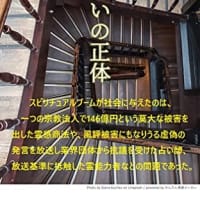
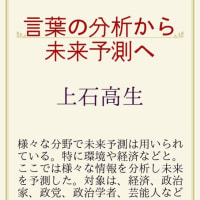
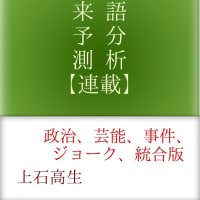
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます