■久しぶりにこのウェブログを更新しますが、その話題がこれではなあ、と思いつつ、仕方ないかなとも思う気持ち半々です。とにかく残念でならないので。
役所広司、震災記録映画の“やらせ”に怒り「二度と上映されるべきものではありません」(シネマトゥデイ)
- Y!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140305-00000033-flix-movi
「どこまで演出か難しい」 梅村太郎監督一問一答
- 朝日新聞デジタル (http://www.asahi.com) http://t.asahi.com/e50z
■岐阜で拝見しました。昨年8月であったと記憶しています。問題とされたシーンも確かにありました。監督さんはいろいろ言ってらっしゃいますが、私は2つの意味で納得がいかない。ひとつはドキュメンタリー映画で「演出」がつくことがさも余分なもの、意図的に足すもののような認識でいらっしゃるような受け答えをされていますが、そんなことはないと思います。ノンフィクションはその題材を選定する段階において必ず取捨選択が起こります。そこに最初の意図、言ってみれば作為が生じるのです。それでも作り手が対象に起こったものごとをそのまま記録するのであれば、何よりもそこに起こった「事実」を曲げてはならない。事実が邪魔であれば最初からドキュメンタリーとして撮らなければいいのです。
■もうひとつは、なぜいわゆる「盛った」のが、聴く側である被災者の、お子さんとお孫さんを亡くした母親であったのかということ。リスナーがいたから「FMみなさん」は成立し得た1年間があったのではないのですか。もっといえば、盛らなければならないほど聴取者の少ないメディアであったのですか?大して起伏はないとしても、普通に放送を聴いていた人は南三陸町にたくさんいらっしゃったのではないのでしょうか。その中の誰かの日常を切り取る(この言い方も十分にイヤですが)だけで、十分ドキュメンタリーとなり得たのではと思うのです。
■いくら喋る側が信じてくれと言っても、対するリスナーの存在が虚ろで信頼は揺らぎます。もちろん、実際に映画に出てこないところでの放送を通じたリスナーとのやり取りはあったと思います。たぶん。しかし、ラジオというメディアが作る空間は、金魚鉢の中だけで成立しているのではないし、仮設のスタジオの中だけで生まれるものではないのです。その可能性に想像が及ばないラジオの映画って、一体どういうことなの?と思ってしまうのです。
■役所さんの怒りは当然だと思います。取り急ぎ、もう少し書きたいと思います。
役所広司、震災記録映画の“やらせ”に怒り「二度と上映されるべきものではありません」(シネマトゥデイ)
- Y!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140305-00000033-flix-movi
「どこまで演出か難しい」 梅村太郎監督一問一答
- 朝日新聞デジタル (http://www.asahi.com) http://t.asahi.com/e50z
■岐阜で拝見しました。昨年8月であったと記憶しています。問題とされたシーンも確かにありました。監督さんはいろいろ言ってらっしゃいますが、私は2つの意味で納得がいかない。ひとつはドキュメンタリー映画で「演出」がつくことがさも余分なもの、意図的に足すもののような認識でいらっしゃるような受け答えをされていますが、そんなことはないと思います。ノンフィクションはその題材を選定する段階において必ず取捨選択が起こります。そこに最初の意図、言ってみれば作為が生じるのです。それでも作り手が対象に起こったものごとをそのまま記録するのであれば、何よりもそこに起こった「事実」を曲げてはならない。事実が邪魔であれば最初からドキュメンタリーとして撮らなければいいのです。
■もうひとつは、なぜいわゆる「盛った」のが、聴く側である被災者の、お子さんとお孫さんを亡くした母親であったのかということ。リスナーがいたから「FMみなさん」は成立し得た1年間があったのではないのですか。もっといえば、盛らなければならないほど聴取者の少ないメディアであったのですか?大して起伏はないとしても、普通に放送を聴いていた人は南三陸町にたくさんいらっしゃったのではないのでしょうか。その中の誰かの日常を切り取る(この言い方も十分にイヤですが)だけで、十分ドキュメンタリーとなり得たのではと思うのです。
■いくら喋る側が信じてくれと言っても、対するリスナーの存在が虚ろで信頼は揺らぎます。もちろん、実際に映画に出てこないところでの放送を通じたリスナーとのやり取りはあったと思います。たぶん。しかし、ラジオというメディアが作る空間は、金魚鉢の中だけで成立しているのではないし、仮設のスタジオの中だけで生まれるものではないのです。その可能性に想像が及ばないラジオの映画って、一体どういうことなの?と思ってしまうのです。
■役所さんの怒りは当然だと思います。取り急ぎ、もう少し書きたいと思います。











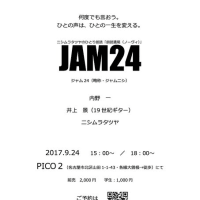




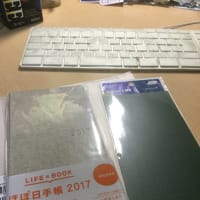


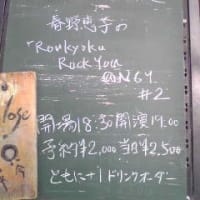
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます