今回は、柳田国男全集の編集委員で古くからの全面教育研究会同人である小田富英さんとの宇都宮・烏山への11月19日~20日の小さな旅です。目的の一つは、小田さんがこの度作新学院大学に赴任したので、宇都宮市郊外のキャンパスまで研究書籍の運搬をお手伝いすること。二つは明治39(1906)年4月1日~3日に柳田国男(旧姓松岡)が、甥の谷田部雄吉をともない養嗣子先である柳田家の歴史を調べに出かけた「柳田採訪」の旅を小田さんと追ってみることです。それは柳田が満31歳になる年のことでした。こちらの時間がなくて4月2日の夕方から3日午前中にかけての烏山での行動を追うことしかできませんでしたが、いくつかは現地に行かねば分からなかった、といえる旅でした。東京小金井の小田さん宅から大学まで車でおよそ3時間かかりました。
まず、小田さんの真新しい研究室にたくさんの書籍を運びましたが、大きな本棚にはまだまだ余裕がありました。天気の良い日には窓からは正面に筑波山が見えるそうです。隣県茨城に出自をもつ小田さんは小金井小田家の3代目。ここに赴任することになにか因縁めいたものを感じていたようです。ところでこの大学、今年で創立20周年というまだ新しい大学ということで、いまでも広いキャンパスの校舎内外はとてもきれいです。私が70年代に通った大学とは大違い。また、すれ違う学生が見知らぬはずの私に挨拶をしてくれます。またエレベータではおそらく職員の方でしょう、意外にも宇都宮は寒いところだと話しかけてくれる、とても気さくにふるまえる大学のようです。周囲の自然環境がそうさせるのかも知れません。
さてここから烏山市まで出かけます。およそ30分ぐらいでいけそうな距離なのに、13年前の地図をたよりのドライブだったのでだいぶ迷ってしまいましたが、ようやく市内の柳田家の菩提寺である善念寺に到着です。ここは「お寺の多い町だ」とは、道を教えてくれた新聞販売店やガソリンスタンドでの地元の声でした。柳田国男は明治34年満26歳になる年に柳田家の養嗣子として入籍します(当主柳田直平の4女孝との結婚は明治37年)が、この柳田家は旧飯田藩士です。つまり柳田家は寛文12(1672)年に、領主・堀家の下野烏山藩から信州飯田藩への移封にしたがい、同じく烏山から飯田に転住したのです。飯田に移ってからの墓は現在の飯田市で確かめられます。明治39年の烏山来訪は烏山時代の柳田家の探訪だったのです。同年の柳田の日記から烏山採訪の箇所を拾ってみます。
≪四月二日、月よう、朝雨少し降り後晴る。昨日よりは寒し。(中略)烏山の町には五時頃到着、まず天性寺といふ禅寺に行きて、浄土宗の寺を尋ね、その教へによりて善念寺といふに行きて見る。前年火に遭へりとて焼け残りたる過去帳少しあり。それを出させて見るに、我家の旧記中の先人たちの名皆録せられあり。年来の望みを達したれば、明朝回向を頼むことにして帰り来る。墓石は皆無くなりたりといふ。旅館は叶屋、夜に入り散歩し、帰りて按摩をとらせて寝る。≫
≪四月三日、火よう、曇 早天に再び善念寺に行き、庭内をあるくうちに、ゆくりなく家の墓数基を発見す。代々の住持の墓と接して、かなめ垣にて囲われてあり。これは元町の関谷、又青木といふ饅頭屋の墓所と心得居たりといふ。我家の先祖烏山を去るに臨み、管理をこの青木家に託せしものと思はれ、その青木は今大に微禄せるも、寺に功労ある家なれば粗末にしてはならぬと、代々住職の言ひ置きなりといへり。回向はてゝ後、寺僧の案内にてその家の行き見るに、今は街道ばたの茶店のやうなる小家にて、四十余りの後家一人住し、娘のみ三人ありて皆他処に行きてあり。此婦人の代も夫婦養子にて、仏壇の位牌も別に今まで改めて見たことが無かつたといふ。言ひ伝へも書き付けも無しとのことなり。先々代は婆一人のところへ来たといへば、よくよく昔の事が幽かになつて居たものと思はる。/九時にこゝを引上げ喜連川に向ふ。此あたり一体に、漆を掻いた後の古木を、門の柱などに使ふ風習あり。黒い横筋のある木にて最も趣きあり。道々の村に梅多し。けふはちやうど散りの盛りなり。≫(『定本柳田國男集別巻4』。漢字と仮名遣いの一部を現代風に改めた。)
烏山を後にして喜連川に向かう途中での漆の見聞について記してありますが、これは今回の「採訪」が、単に柳田家の先祖探しだけでなかったことを示唆しています。「柳田採訪」を追体験した中山一さんの労作『追憶の柳田國男 下野探訪の地を訪ねて』(2004 随想舎)に詳しいのですが、中山さんは烏山の東を流れる那珂川左岸の八溝山地が古くは、国内で最上品質の漆の山地として知られ、その良質な漆を求めてシーズン中は遠くから漆を取るために、ここ烏山には大勢の職人が出入りしたことを調べています。つまり柳田はこの旅で烏山の漆産業を確かめた旅でもあったことを示しているわけです。ところで、柳田国男は生涯に三回、この時の烏山体験に触れています。明治39年採訪から25年後の「芳賀郡と柳田氏」(1931)では以下のように回顧しています。柳田満56歳になる年のことです。
≪・・・私の家の、ある時代に宇都宮殿の家来であったことだけは、ほぼ確実な証拠がある。家で大切にしているたった一通の古文書は、宇都宮最後の主たる国綱公の感状であった。牛込の宅に蔵ってあるからちょっと出して見られぬが、年号は天正であったと記憶する。何とか阪の働き比類なく、満足に思うというような文字があって、宛名は柳田監物となっている。この人が私の家の系図において、生死年月がわかっている最初の人だから、まず自分としては元祖と心得ている。墓は烏山の善念寺という浄土寺に、つい近年までかなり立派なものが残っていた。それをまた私が行って発見したのである。この柳田氏は後の主人堀美作守親昌に随うて、寛文十二年の閏六月に、烏山から信州の飯田に転住し、それから今日までずっと本籍を飯田に置いている。それがかく申す自分の家であった。始祖の監物は七十何歳まで長命したが、この時はむろんもう死んでいた。それと若干の族人の墓を、烏山の名門であった青木という家に託して去ったのであるが、後にこの青木も衰微し、私の家にもいろいろの事件があったために交通が絶えて久しく埋没していたのである。それが二三基の墓石の発見と寺の焼け残りの過去帳によって、一々家にある位牌と引き合せることができ、いよいよ西暦一六七一年以前の数十年間、私の家が烏山にあったということが確かめられたのである。≫(文庫版『柳田國男全集 第31巻』)
最後の回顧は『故郷七十年』(1959)のなかで述べています。柳田満85歳になる年のことでした。
≪柳田の家は私の養父に当る人もやはり養子で、先祖の墓を何かと気にして過ごしていたが、忙しくて見に行く折がなかった。柳田家は寛文年間まで下野の烏山にいたが、飯田の脇坂家が播州竜野へ移った後、堀家にしたがって飯田へついて行った。それ以後の墓所は飯田にあるが、それ以前の古い墓が烏山にあるにちがいないという気がしていた。しかし父はどうしても行く暇がないので、たしか日露戦争のすぐ後であったと思うが、私と、今谷中に葬られている甥の谷田部雄吉と、二人で出かけていった。/寺にゆくと、「どうもお気の毒様でした。寺では整理の必要があって、無縁仏を片付けましたので、おそらくお宅様のもないでしょう」といいながら、「火事がありましたが、過去帳はこれだけ残っています」と、過去帳を出してくれた。それを繰ってみると、先祖の戒名がいくつも出てくる。「ここにありますよ。これは私の家の戒名です」こうして戒名は見つけ出し、翌日はお経を上げてもらうことになったが、肝腎の墓石がない。「墓石がなくてはねえ」と甥と話しながら、翌朝もう一度寺に行ってみた。/住職が読経の仕度をする間に、墓石のことを気にかけながら境内をぐるぐる歩いていると、お寺の代々の住職の墓というのがあり、そのすぐ脇をふっと見ると、探していた私の家の戒名がずっと並んでいるではないか。さっそく和尚さんを連れてきて見せると、「これは青木という、この地でいちばん主な旦那の墓です」という。しかし墓石に柳田と書いてあるのだから間違いはないということになり、お経を上げて大変成功して帰って来た。青木というのは町の饅頭屋で、念のため訪ねて行ってきくと、何でも先祖が柳田家から頼まれたというので、代々墓所を守ってくれているということだった。長い間の好意に感謝し、今後のことも頼んで帰ってきた。/その話が伝わったので、旧藩のお爺さんたちが大変喜んでくれて、羽織袴でうち連れてやって来、「承ればご先祖の墓所がお見つかりになりましたそうで・・・・・」と、わざわざあいさつしてくれたことを憶えている。その後父が母といっしょに烏山へ墓参に行ったところ、驚いたことに、墓がないのである。寺で処分してしまったのであろう。父が非常に憤慨し、夜も眠られぬくらい怒ってしまった。「わしはこっちへ立て直す」といって、谷中へ代りの墓所を建てたのが、現在の墓である。父にとって烏山というところは、長い間の先祖の墓所を保存してくれて、じつに有難い所であったのが、急に印象の悪い所になってしまったらしい。もうそれっきり一族のものがだれも行かないのである。≫(『柳田國男全集 第21巻』)
以上、三つの烏山体験の記述を比べると、疑問がわいてきます。それは飯田に転住したあと、柳田家の墓所を青木家が代々守ってきたという話は誰が述べたのかという点です。明治39年の日記では、「我家の先祖烏山を去るに臨み、管理をこの青木家に託せしものと思はれ、その青木は今大に微禄せるも、寺に功労ある家なれば粗末にしてはならぬと、代々住職の言ひ置きなりといへり。」と、ここでは青木家が飯田に去ったあとの柳田家の墓所を守ってきたという話は柳田国男の推測です。つぎに一篇「芳賀郡と柳田氏」では、「それと若干の族人の墓を、烏山の名門であった青木という家に託して去ったのであるが、後にこの青木も衰微し」と記し、去った柳田家が墓守を頼んだように読めます。最後の『故郷七十年』の記述は、「青木というのは町の饅頭屋で、念のため訪ねて行ってきくと、何でも先祖が柳田家から頼まれたというので、代々墓所を守ってくれているということだった。長い間の好意に感謝し、今後のことも頼んで帰ってきた」とあるように、青木家の先祖が去って行く柳田家から頼まれたということを、当時の青木家が伝承していたことになります。しかし、これは明治39年日記の記述と矛盾します。青木家にはそういう言い伝えがなかったと記しているからです。(続)














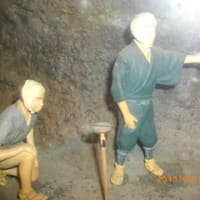




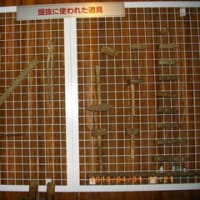
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます