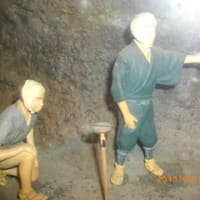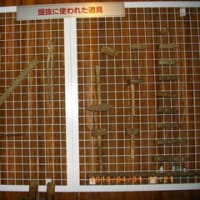前回(3/15)は、敬語は全国で一様に発達してきたわけでなく、その使われ方には地方差があることを知りました。とくに南島や東北にはシンプルな形の古い敬語が残されていることを知りました。たとえば、奄美大島では対等な物言いの「ある」「あらぬ」の句尾に、「居る」を強めた意味の「オウル」を加えて、アリオウル・アリオウラヌと言うことで目上に対する敬意を表現しました。また八重山諸島ではもっと簡単に、「ユウ」をつけてアルユウ・アラヌユウと言うだけでした。「ユウ」は本土で使う「よ」と同系語だと柳田は考えているようです。
次に東北へ行くと、六県の広い範囲でやはりシンプルな敬語が見られます。句尾に「スまたはネス」あるいは「シあるいはネシ」を付けて相手に敬意を表します。これらの意味はもと「申す」だったらしいことは、「ムシ」とも「ンス」とも、ときに「マス」と付け加えることからわかります。「おれ行くとこァどこだべマス」(=私の行く所はどこでしょうか 岩手県中部)の「マス」は標準語の「あります」などの「マス」とは全く別のものだという指摘は印象深いものがあります。以上は「敬語の新旧という地方差」でしたが、敬語の地方差にはもう一つ別種類のものがあるのです。それは敬語が使われている地方とそうでない地方の存在です。言ってみれば、「敬語の有無という地方差」です。柳田はここから何を導きだそうと言うのでしょうか。
≪敬語の地方差はこの他に今一つのものがある。右の南北の二例では、極度に単純だというばかりで、とにかくあることは確かにあり、また相応に繁く使用せられている。これに対しては別になお一種、ほとんと「ござる」「あります」の存在を忘れたのかと思われる地方が、少なくも元はたしかにあった。私が五十年前にびっくりした下総の一隅では、それでもまだ小児とこれを相手とする者との群だけに限られ、ただその場におり合さぬ第三者についてのみ、成人もこれを無視するというまでであったが、稀にはまだずっとこの程度を越えた例がある。地域ではないが学校の生活、ここだけには敬語が甚だしく不人望で、今でも純然たる仲間の言葉が行われ、人によってはそれが世の中へ出るまでも続いている。行儀作法を好いことと心得ておりながら、一方にはまたひどく他人行儀ということを憎む階級が、社会の中堅にもいるのだから、この問題はむつかしいわけである。しかし解決の鍵もやはりここにあると私などは狙っている。だから最初にまずこれと地方の敬語使用圏の消長とを比較してみる必要をも感ずるのである。文学はだいたいに敬語使用者の記録といってよいのであるが、それでもまだその中には京と江戸との、かなり際立った地方差が見られる。これも若い頃の自分の経験であるが、江戸はあれほどまでに二本差した人に対して、遠慮した物の言い方をする土地柄であったにかかわらず、仲間同士の会話はいわゆるぞんざいでいかついものだった。ことに中分(ちゅうぶん)以下の婦人などは、男に対しても別に女言葉も使わず、平気で行くか来るかどうするのだなどと言っていたことは、近世の中本(ちゅうほん)類にもよく描写せられている。湛念(たんねん)な学者だったら例は何百でも並べてくれるであろう。それが明治に入って程もなく影を潜めたのは、隣近所へ雑多の他処者(よそもの)が入って来て住んだからで、つまり敬語を必要としなかった「仲間」が、崩壊してしまったのである。学校でも中央の出入りの多いものでは、ほんの目礼ぐらいで話をする折も少なく、いわゆる他人行儀が普通になって、もう坪内さんの『書生気質』のような、特色の多い書生言葉も亡びかかっている。この二つの経過には似通うたものがあるかと私には思われる。敬語をよい言葉と呼ぶ名に絆(ほだ)されていたけれども、これを使わずともよい間柄の減少することは、考えてみると必ずしも幸福とは言えなかった。
少なくとも以前は互いに敬語を交さず、私たちがこういう文章で書くような、また外国語でみるような平常の言葉で、意思を通じていた人及び場合が、今よりずっと多かったことは確かである。それが現在のいわゆる丁寧な言葉に、改まって来たのは最近であるゆえに、人で言うならば少年とか学生とか、労働の団体とかが後に残り、婦人とか客商売の者とかが、一足先に進んでしまったのである。土地を目標にして見て行っても、まだまだ意外な方面に敬語の使用の著しく尠(すくな)い小社会が残っている。過渡期に生まれ合せた我々学徒の、これがまことに大きな仕合せで、これあればこそ始めて今までの経過を認識し、それを参考にして残りの未決を、できるだけ国民に都合のよいように、解決することも望み得られるのである。いちがいにそれを下品と評したり、または人物粗野などと報告したりすることは、手短かに申せば因習のしもべであった。また歴史を正しく視ることのできぬ者の、あわれなる現状維持説であった。≫(ちくま文庫版『柳田國男全集22』 一三三~五頁)
全国には敬語の有無という地方差があることから、何を導けるのか。柳田はまず地域ではなく学校生活に注目します。そうすると、ここでは今でも仲間同士の言葉が盛んに使われており敬語は人気がない。だが世の中に出るようになると礼儀作法を求めるようになる。つまり敬語がほとんど使われない場所から使われる場所へ、と敬語の扱われ方の変遷を認めることができるはずです。この筋道を手がかりに、地方における敬語の消長(盛衰)と比較しようというのです。そこで選ばれるのは江戸です。なぜ江戸なのかというと、文学の世界をみるとだいたいは敬語使用者の記録になっており、京と江戸の間には、敬語の有無という地方差が描かれています。そう、江戸では意外にも敬語があまり使われておらず、仲間同士の物言いは「ぞんざいでいかつい」ものだったことが見えてきます。
ところが明治の世を迎えるようになると、「隣近所へ雑多の他処者(よそもの)が入って来て」住み始めます。すると、従来の仲間同士の物言いは減少し、増加した他処者(よそもの)との間には他人行儀な言葉遣いすなわち「敬語」が増えていくというわけです。このような江戸における敬語使用の消長に関する記述には、学校生活でみた敬語の変遷と似た筋道を見つけることができます。そうすると、ここから柳田は何を導き出そうとしているか、が見えて来ます。それは、かつて敬語が使われていない地域や時代が確実に存在し、今も残っているし、他方で敬語が「発達」している、そのような過渡期に我々が生まれ合せたという事実です。
また、柳田はここで敬語の価値に関わる一言を記しています。すなわち、「(敬語を)使わずともよい間柄の減少することは、考えてみると必ずしも幸福とは言えなかった」。仲間同士の物言いが減っていけば自分の肚を語り合う機会は減っていきます。こういう機会が減れば、公共は強者の独占物と化してしまい、たしかに幸福な社会からは遠ざかるだけです。