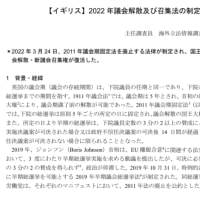《原子力災害伝承館の見学と展示内容》
1 プロローグ
館内に入ると巨大なスクリーンで映像を見せられる。西田敏行のナレーションで、原発建設が雇用創出と高度経済成長を支えたこと。
震災や事故の様子、復興を目指す高校生の姿で5分間の映像が終わる。
2 災害の始まり
地震と津波、原発事故の複合災害で人々はどのように行動したかの資料・証言・記録。
「原子力明るい未来のエネルギー」の看板の写真や原発事故前の小学生の作文の紹介。
「原発で地域が発展し生活が豊かになった」「人や自然に優しい発電所を願う」の内容など。
3 原子力発電所事故後の対応
写真パネルや避難者の証言映像の展示だが、広い場所の壁に説明パネルの展示や展示品
コーナーもあるが訴えが弱い気がする。
4 県民への想い
① 災害時に感じた不安
②楽しかった学校生活の突然の別れ
③家族や地域との別れ
④生活基盤の変化 将来への想い
被災者や避難者の映像は多くあるが、国や東電の責任を問うものは見つからない。
②の中で違和感を感じたのは「事故をきっかけにして、人生が良い方に変わって、やさしくなった」という楢葉北小教員の証言。
5 長期化する原子力災害の影響
除染の説明映像や空間線量率の推移模型で放射線量が低くなったことを強調し、子どもや高齢者の目を引く展示に
6 復興への挑戦
大画面の画像で早送りして、復興が進んでいるとの印象を受けやすい
「みらいのまち」の模型展示
7 海のテラスからは 広大な空き地が海まで広がり一望できる。
取り壊されていない一軒家があり、豊かな生活をしていた街や集落があったことを忍ばせる。
8 屋外には津波で壊れた赤い消防自動車と「原子力明るい未来のエネルギー」のパネル
大槻さんの感想にもあったが、広島の平和資料館に比べると小中学生が興味関心を引きつける内容とは思えない。
やはり「復興」に重点が置かれて、原発災害の多くの問題点が薄らいでいる気がした。

《震災遺構 浪江町立請戸小学校の見学》
海岸から300mの距離にある請戸小学校は、地震発生直後(15:56)から避難開始をした。
児童82人と教職員は1.5km先の大平山を目指した。
遅れた校長教頭が合流(15:35)する。
その直後(15:38)に津波が校舎を襲い掛かる。
津波が大平山に到着したのは、2分後の15時40分だったが全員無事避難できた。
浪江町は学校を震災遺構として整備・保存し、後世に伝えるため2021年10月から一般公開を始めた。
津波に襲われた教室や保健室や放送室を見る。
壁は崩れコンクリートがむき出し、天井からは蛍光灯がぶら下がり、床にはロッカーと物が散乱。
鉄骨はへしまがっている。
倒れた校長室の大きな金庫や、給食室の大きな釜もそのまま見ることが出来る。
印刷室の壁や内部は当時のまま残してあり津波の脅威を感じる。
二階はわずか10cmしか浸水しなかった。
当時の状態が保存され明るさを感じる展示になっている。
津波被害の航空映像や立ち入り解除になって卒業生らが黒板に書いたメッセージ、震災前の請戸地区の模型展示などもある。
請戸小は第一原発からわずか5.7kmの距離しかなく、廃炉処理作業が教室からはっきりと見えた。

<Y.F>
1 プロローグ
館内に入ると巨大なスクリーンで映像を見せられる。西田敏行のナレーションで、原発建設が雇用創出と高度経済成長を支えたこと。
震災や事故の様子、復興を目指す高校生の姿で5分間の映像が終わる。
2 災害の始まり
地震と津波、原発事故の複合災害で人々はどのように行動したかの資料・証言・記録。
「原子力明るい未来のエネルギー」の看板の写真や原発事故前の小学生の作文の紹介。
「原発で地域が発展し生活が豊かになった」「人や自然に優しい発電所を願う」の内容など。
3 原子力発電所事故後の対応
写真パネルや避難者の証言映像の展示だが、広い場所の壁に説明パネルの展示や展示品
コーナーもあるが訴えが弱い気がする。
4 県民への想い
① 災害時に感じた不安
②楽しかった学校生活の突然の別れ
③家族や地域との別れ
④生活基盤の変化 将来への想い
被災者や避難者の映像は多くあるが、国や東電の責任を問うものは見つからない。
②の中で違和感を感じたのは「事故をきっかけにして、人生が良い方に変わって、やさしくなった」という楢葉北小教員の証言。
5 長期化する原子力災害の影響
除染の説明映像や空間線量率の推移模型で放射線量が低くなったことを強調し、子どもや高齢者の目を引く展示に
6 復興への挑戦
大画面の画像で早送りして、復興が進んでいるとの印象を受けやすい
「みらいのまち」の模型展示
7 海のテラスからは 広大な空き地が海まで広がり一望できる。
取り壊されていない一軒家があり、豊かな生活をしていた街や集落があったことを忍ばせる。
8 屋外には津波で壊れた赤い消防自動車と「原子力明るい未来のエネルギー」のパネル
大槻さんの感想にもあったが、広島の平和資料館に比べると小中学生が興味関心を引きつける内容とは思えない。
やはり「復興」に重点が置かれて、原発災害の多くの問題点が薄らいでいる気がした。

《震災遺構 浪江町立請戸小学校の見学》
海岸から300mの距離にある請戸小学校は、地震発生直後(15:56)から避難開始をした。
児童82人と教職員は1.5km先の大平山を目指した。
遅れた校長教頭が合流(15:35)する。
その直後(15:38)に津波が校舎を襲い掛かる。
津波が大平山に到着したのは、2分後の15時40分だったが全員無事避難できた。
浪江町は学校を震災遺構として整備・保存し、後世に伝えるため2021年10月から一般公開を始めた。
津波に襲われた教室や保健室や放送室を見る。
壁は崩れコンクリートがむき出し、天井からは蛍光灯がぶら下がり、床にはロッカーと物が散乱。
鉄骨はへしまがっている。
倒れた校長室の大きな金庫や、給食室の大きな釜もそのまま見ることが出来る。
印刷室の壁や内部は当時のまま残してあり津波の脅威を感じる。
二階はわずか10cmしか浸水しなかった。
当時の状態が保存され明るさを感じる展示になっている。
津波被害の航空映像や立ち入り解除になって卒業生らが黒板に書いたメッセージ、震災前の請戸地区の模型展示などもある。
請戸小は第一原発からわずか5.7kmの距離しかなく、廃炉処理作業が教室からはっきりと見えた。

<Y.F>