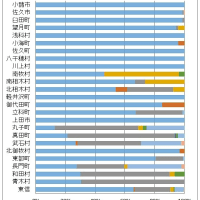盆はいつから始まるのか。長野県内では、13日に始まり16日までを盆ということが多い。しかし、地獄の釜の蓋が開く日とか、仏様が黄泉の国に立つ日などとい、1日に墓掃除を行うというところも多い。そんなことから、1日から盆の入りというところもある。とくにこの1日にこだわっている地域が、佐久地方である。
寛保二年戌年(1742年)に佐久地方をおそった 戌の満水にまつわるものといわれる。7月27日から降り続いた集中豪雨が、8月1日には大暴風雨になり、村々の河川から土石流が押しだし、千曲川をはじめ支流すべてが未曾有の洪水に見舞われ、多数の死者を出し、農作物の収穫も少なく、生き残った人も飢えに苦しんだという。あまりの被害に死者を弔うこともできなかった人々は、以来1日には墓参りをしてその霊を慰めてきたといわれている。
いっぽう新盆のことをアラボンとか、シンボンといい、普段の盆よりは早く灯篭や提灯を吊るすところが多い。上伊那郡辰野町平出では、1日から長い竿の先に組子灯篭をつけて庭先に立てた。このように地域、あるいは新盆であるかないかによっても、盆の始まりは異なるようである。先ごろ飯田下伊那地方を主に発行されている信州日報という新聞に、「伊那谷の民俗世界」という記事があって、盆の始まりについて触れていたが、柳田國男の記述から引用して、1日のあり方を意味付けようとしていた。しかし、知識をもってフィールドに関連付けようとするのは、よく勉強しましたね、とはいえるが、実際聞き取れないものをつなげようとすると、こじつけではないかといわれればその通りということになってしまう。わたしたちが気をつけなくてはならないのは、年寄りですら昔を知らない時代になって、さぞ意味ありげに地域に既存の概念を植え付けてしまうことである。また、過去をノスタルジックに持ち上げてしまうことは、よいことではないし、「かつてが良かった」などという、若者へ年寄りが口癖のようにいう単語は避けたい。もちろん意識としても。
近ごろ飯田市近辺で、新盆の家に切子灯篭が飾られるようになった。三河との国境あたりでは、新盆の家に切子灯篭が贈られるが、飯田あたりではそういう風習はなかった(昔のことは知らないが)。ところが最近は、店で売るようになったりして、急にちまたに広がった。確かに普通の灯篭よりにぎやかで、新盆さんを迎え、また送るにはよいかもしれないが、どこでも切子灯篭になってしまってはいまどきの政治、行政と同じじゃないか。
寛保二年戌年(1742年)に佐久地方をおそった 戌の満水にまつわるものといわれる。7月27日から降り続いた集中豪雨が、8月1日には大暴風雨になり、村々の河川から土石流が押しだし、千曲川をはじめ支流すべてが未曾有の洪水に見舞われ、多数の死者を出し、農作物の収穫も少なく、生き残った人も飢えに苦しんだという。あまりの被害に死者を弔うこともできなかった人々は、以来1日には墓参りをしてその霊を慰めてきたといわれている。
いっぽう新盆のことをアラボンとか、シンボンといい、普段の盆よりは早く灯篭や提灯を吊るすところが多い。上伊那郡辰野町平出では、1日から長い竿の先に組子灯篭をつけて庭先に立てた。このように地域、あるいは新盆であるかないかによっても、盆の始まりは異なるようである。先ごろ飯田下伊那地方を主に発行されている信州日報という新聞に、「伊那谷の民俗世界」という記事があって、盆の始まりについて触れていたが、柳田國男の記述から引用して、1日のあり方を意味付けようとしていた。しかし、知識をもってフィールドに関連付けようとするのは、よく勉強しましたね、とはいえるが、実際聞き取れないものをつなげようとすると、こじつけではないかといわれればその通りということになってしまう。わたしたちが気をつけなくてはならないのは、年寄りですら昔を知らない時代になって、さぞ意味ありげに地域に既存の概念を植え付けてしまうことである。また、過去をノスタルジックに持ち上げてしまうことは、よいことではないし、「かつてが良かった」などという、若者へ年寄りが口癖のようにいう単語は避けたい。もちろん意識としても。
近ごろ飯田市近辺で、新盆の家に切子灯篭が飾られるようになった。三河との国境あたりでは、新盆の家に切子灯篭が贈られるが、飯田あたりではそういう風習はなかった(昔のことは知らないが)。ところが最近は、店で売るようになったりして、急にちまたに広がった。確かに普通の灯篭よりにぎやかで、新盆さんを迎え、また送るにはよいかもしれないが、どこでも切子灯篭になってしまってはいまどきの政治、行政と同じじゃないか。