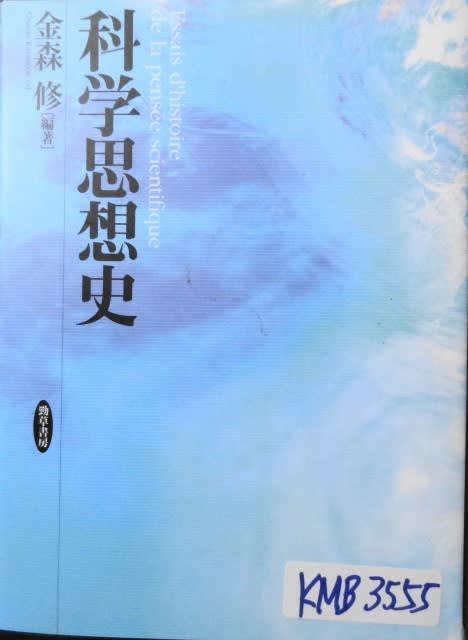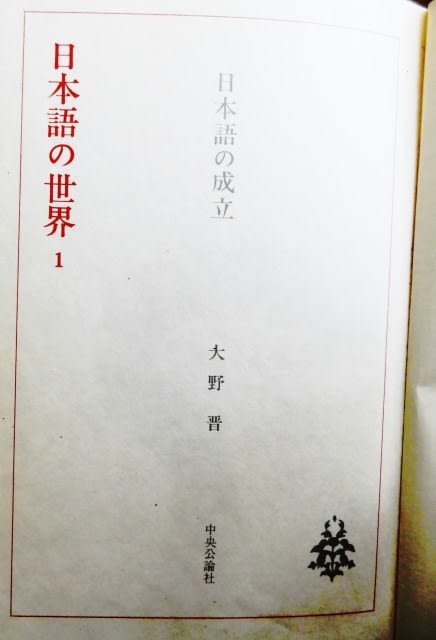メタエンジニアの眼シリーズ(133)
TITLE: ワールド・カフェ
書籍名;①「ワールド・カフェをやろう」 [2009]
著者;香取一昭、他 発行所;日本経済新聞出版社
発行日;2009.11.12
書籍名;②「ワールド・カフェから始める地域コミュニティづくり」 [2017]
著者;香取一昭 発行所;学芸出版社
発行日;2017.11.20
初回作成日;R1.7.25 最終改定日;R1.
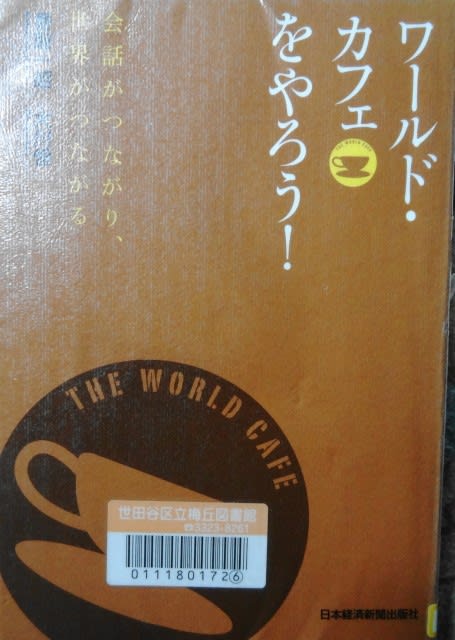

このシリーズはメタエンジニアリングを考える際に参考にした著作の紹介です。『』内は,著書からの引用部分です。
ワールド・カフェとは、1995年経営コンサルタントのアニータ・ブラウンとデイビッド・アイザックスによって考案された。カフェは、1768年にパリで初めてできたが、次のようなその特徴を引き継いでいる。
この二つの書は、表題に関する著作だが、「多様化し、複雑化する社会問題への異業種連携による対応」について、ワールド・カフェ以外の手法についても述べている。
『カフェがつくるそうした場は、他の場とどこが違うのでしょうか?カフェには次のような特徴があるのだと考えます。
・人間関係が対等である(地位の違いや、年齢の差が持ち込まれない)
・職場や家庭では出会えない人に出会える
・自由参加である
・参加者が主役である
・言いたいことが言える(ふと思ったことでも言える)
・オープンである(開放性)
・知識や価値が創造される』①(pp.4)
つまり、リラックスした雰囲気の少人数の会話から、集合知を生み出す手段となっている。
開催は、日本よりも諸外国が盛んで、学会、研究会、地域コミュニティ、企業戦略、ビジョン作成などの場で広く使われている。
ディスカッションとは、根本的に異なる「ダイアローグ」の場としての特性を引き出すもので、その違いを次の9つの観点で纏めている。( ディスカッション;ダイアローグ)
『
① 前提 自分が正しいと主張:誰もが良いアイデアを持っている
② 態度 戦闘的:協力的
③ 目的 議論に勝つこと:共通の基盤作り
④ 聴き方 反論を組み立てる:相手を理解し、意義を見出だす
⑤ 主張 自説の正しさ:再評価のための機会
⑥ 評価 相手を批判:すべての立場を再調査
⑦ 自説の扱い 自説の主張:自分の考えの改善
⑧ 相手の評価 欠点と弱点探し:相手の強さと価値を探す
⑨ 結論 自への説是認を求める:新たな選択肢を見出だす
』①(pp.185)
その違いは、スタートの方法にある。
『両者の最もきわだった違いは、ディスカッションが相手を論破して自分の考えを通そうとするのに対して、ダイアローグでは相互理解を深めようと、相手の考えの背景を理解しようとするという点にあります。』①(pp.225)
・越境リーダー
『「越境リーダーシップ」とは、“想いを持った個人が既存の枠組の境界を越えて、社内外の必要なリソースとつながり新しい社会的な価値をつくる行為”のことです。そのような行動をとっている人を「越境リーダー」と呼んでいます。イキイキとした地域コミュニティにおいては、異なる組織に属する人が共通の目的を持って力を合わせて地域課題の解決に取り組んでいます。
一つの企業、自治体、NPO など個別組織だけでは取り組むべき地域課題を解決できないので、組織を超えた協働、共創による価値創造や課題解決が必要とされるようになり、越境リーダーシップが日本社会の様々な場所や機会で求められています。しかしながら、内側に閉じる傾向の強い組織で働いている人は、なかなか組織を超えた協働は難しいようです。』②(pp.33)
日本における初期のプロジェクトは、次のようなものだった、とあります。
『越境リーダーシップ・プロジェクトを産学連携で設立したのは、2012年10月のことでした。自分の想いを起点として越境し、社会の課題を解決する事業を共創することで、社会的なインパクトをもたらす「生き方(職業人生)」に挑戦する企業内個人の支援に取り組むプロジェクトを 進めてきました。』②(pp.34)
・OTS( Open Space Technology)
『OTSでは、参加者が検討したいテーマを提案し、それに賛同する人が集まってチームをつくり話し合います。その結果、テーマに対する理解が深まり、具体的なプロジェクトが生まれやすいのです。
ワールド・カフェの場合は、主催者がテーマを「問い」という形で提示して、それについて参加者が話し合いますが、OTSの場合は、参加者自身が話し合うテーマを決めるという点が大きな違いとなっています。』②(pp.110)
つまり、ワールド・カフェとの基本的な違いは、
『OTSでは、参加者の内発的な動機から提案したテーマについて話し合いが行われるので、検討が深まり、具体的なプロジェクトや行動に結びつきやすいというメリットがあります。
従って、ワールド・カフェでテーマに関する理解を深め、具体的なアクションを導くためにOTSを実施するという組み合わせがよく行われています。』②(pp.111)
・フューチャーサーチ
ワールド・カフェへの追加項目として、「フューチャーサーチ」という手法が挙げられている。
『過去を振り返る;検討するテーマにとって重要と思われる過去の出来事を参加者全員で年表に書き込みます。年表は過去10~20年をカバーし、検討対象となる組織など(ローカル)、検討対象となる組織を取り巻く環境(グローバル)、および参加者(個人)の3枚の年表が用意されます。』①(pp.224)
次に現在について探求し、さらに理想的な未来のシナリオを思い描く。
次に、MECIサイクルのConvergingに相当することを行う。
『モングラウンドを発見する; 各グループが発表し、演じた「理想的な未来のシナリオ」に込められているビジョンについて、共通のよりどころになると思われるものを抽出します。その際、合意できないものは深追いせずに、合意できるものだけに絞って話し合いを行います。』①(pp.226)
最後に、MECIサイクルのImplementingに相当することを行う。
『アクションプランを作る; 抽出したコモングラウンドに基づいて、理想的な未来を実現するために必要なプロジェクトを考えついた参加者が提案し、それに同調する参加者とアクションチームを編成して、フューチャーサーチ終了後も活動を継続します。』①(pp.228)
このように並べると、ワールド・カフェはメタエンジニアリングのMECIプロセスのMとEの部分を行い、Convergingの初期段階に踏み込むまでをカバーするともいえる。しかし、きちんとした結論を出すにはダイアローグだけでは不足で、当然しかるべきディスカッションを経なければならい。
TITLE: ワールド・カフェ
書籍名;①「ワールド・カフェをやろう」 [2009]
著者;香取一昭、他 発行所;日本経済新聞出版社
発行日;2009.11.12
書籍名;②「ワールド・カフェから始める地域コミュニティづくり」 [2017]
著者;香取一昭 発行所;学芸出版社
発行日;2017.11.20
初回作成日;R1.7.25 最終改定日;R1.
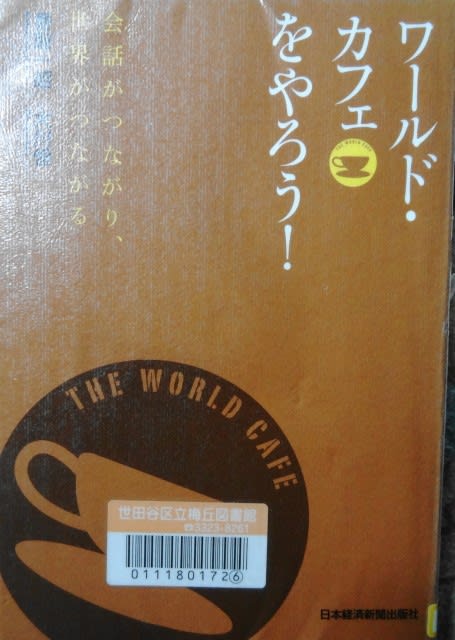

このシリーズはメタエンジニアリングを考える際に参考にした著作の紹介です。『』内は,著書からの引用部分です。
ワールド・カフェとは、1995年経営コンサルタントのアニータ・ブラウンとデイビッド・アイザックスによって考案された。カフェは、1768年にパリで初めてできたが、次のようなその特徴を引き継いでいる。
この二つの書は、表題に関する著作だが、「多様化し、複雑化する社会問題への異業種連携による対応」について、ワールド・カフェ以外の手法についても述べている。
『カフェがつくるそうした場は、他の場とどこが違うのでしょうか?カフェには次のような特徴があるのだと考えます。
・人間関係が対等である(地位の違いや、年齢の差が持ち込まれない)
・職場や家庭では出会えない人に出会える
・自由参加である
・参加者が主役である
・言いたいことが言える(ふと思ったことでも言える)
・オープンである(開放性)
・知識や価値が創造される』①(pp.4)
つまり、リラックスした雰囲気の少人数の会話から、集合知を生み出す手段となっている。
開催は、日本よりも諸外国が盛んで、学会、研究会、地域コミュニティ、企業戦略、ビジョン作成などの場で広く使われている。
ディスカッションとは、根本的に異なる「ダイアローグ」の場としての特性を引き出すもので、その違いを次の9つの観点で纏めている。( ディスカッション;ダイアローグ)
『
① 前提 自分が正しいと主張:誰もが良いアイデアを持っている
② 態度 戦闘的:協力的
③ 目的 議論に勝つこと:共通の基盤作り
④ 聴き方 反論を組み立てる:相手を理解し、意義を見出だす
⑤ 主張 自説の正しさ:再評価のための機会
⑥ 評価 相手を批判:すべての立場を再調査
⑦ 自説の扱い 自説の主張:自分の考えの改善
⑧ 相手の評価 欠点と弱点探し:相手の強さと価値を探す
⑨ 結論 自への説是認を求める:新たな選択肢を見出だす
』①(pp.185)
その違いは、スタートの方法にある。
『両者の最もきわだった違いは、ディスカッションが相手を論破して自分の考えを通そうとするのに対して、ダイアローグでは相互理解を深めようと、相手の考えの背景を理解しようとするという点にあります。』①(pp.225)
・越境リーダー
『「越境リーダーシップ」とは、“想いを持った個人が既存の枠組の境界を越えて、社内外の必要なリソースとつながり新しい社会的な価値をつくる行為”のことです。そのような行動をとっている人を「越境リーダー」と呼んでいます。イキイキとした地域コミュニティにおいては、異なる組織に属する人が共通の目的を持って力を合わせて地域課題の解決に取り組んでいます。
一つの企業、自治体、NPO など個別組織だけでは取り組むべき地域課題を解決できないので、組織を超えた協働、共創による価値創造や課題解決が必要とされるようになり、越境リーダーシップが日本社会の様々な場所や機会で求められています。しかしながら、内側に閉じる傾向の強い組織で働いている人は、なかなか組織を超えた協働は難しいようです。』②(pp.33)
日本における初期のプロジェクトは、次のようなものだった、とあります。
『越境リーダーシップ・プロジェクトを産学連携で設立したのは、2012年10月のことでした。自分の想いを起点として越境し、社会の課題を解決する事業を共創することで、社会的なインパクトをもたらす「生き方(職業人生)」に挑戦する企業内個人の支援に取り組むプロジェクトを 進めてきました。』②(pp.34)
・OTS( Open Space Technology)
『OTSでは、参加者が検討したいテーマを提案し、それに賛同する人が集まってチームをつくり話し合います。その結果、テーマに対する理解が深まり、具体的なプロジェクトが生まれやすいのです。
ワールド・カフェの場合は、主催者がテーマを「問い」という形で提示して、それについて参加者が話し合いますが、OTSの場合は、参加者自身が話し合うテーマを決めるという点が大きな違いとなっています。』②(pp.110)
つまり、ワールド・カフェとの基本的な違いは、
『OTSでは、参加者の内発的な動機から提案したテーマについて話し合いが行われるので、検討が深まり、具体的なプロジェクトや行動に結びつきやすいというメリットがあります。
従って、ワールド・カフェでテーマに関する理解を深め、具体的なアクションを導くためにOTSを実施するという組み合わせがよく行われています。』②(pp.111)
・フューチャーサーチ
ワールド・カフェへの追加項目として、「フューチャーサーチ」という手法が挙げられている。
『過去を振り返る;検討するテーマにとって重要と思われる過去の出来事を参加者全員で年表に書き込みます。年表は過去10~20年をカバーし、検討対象となる組織など(ローカル)、検討対象となる組織を取り巻く環境(グローバル)、および参加者(個人)の3枚の年表が用意されます。』①(pp.224)
次に現在について探求し、さらに理想的な未来のシナリオを思い描く。
次に、MECIサイクルのConvergingに相当することを行う。
『モングラウンドを発見する; 各グループが発表し、演じた「理想的な未来のシナリオ」に込められているビジョンについて、共通のよりどころになると思われるものを抽出します。その際、合意できないものは深追いせずに、合意できるものだけに絞って話し合いを行います。』①(pp.226)
最後に、MECIサイクルのImplementingに相当することを行う。
『アクションプランを作る; 抽出したコモングラウンドに基づいて、理想的な未来を実現するために必要なプロジェクトを考えついた参加者が提案し、それに同調する参加者とアクションチームを編成して、フューチャーサーチ終了後も活動を継続します。』①(pp.228)
このように並べると、ワールド・カフェはメタエンジニアリングのMECIプロセスのMとEの部分を行い、Convergingの初期段階に踏み込むまでをカバーするともいえる。しかし、きちんとした結論を出すにはダイアローグだけでは不足で、当然しかるべきディスカッションを経なければならい。