
アシモフの『銀河帝国の興亡』(ファウンデーション・シリーズ)など、早川書房のSFの文庫本をみると、アシモフの顔写真がある。(是非書店にてご覧ください。) それを見て、僕が思ったことは、こうだ。
「なんだ、この意味不明のモミアゲは!?」
アイザック・アシモフは3歳の時からの、ニューヨーク・ブルックリンっ子である。 生まれは、ロシア。
1923年2月、家族(父、母、アイザック、妹の4人)は船に乗ってロシアからニューヨークへやってきた。父ユダは工場で働いてお金を貯めて、ブルックリン区でキャンデーストアを始めた。今でいうコンビニエンスストアのようなもので、新聞、雑誌、キャンデー、タバコ等を売る雑貨屋である。この小さな店は繁盛したが、たいへんなのは、こういう店というのはけっして休めないということである。だから息子のアイザックも子供ながら毎日店を手伝った。
アイザックはずっと男子ばかりの学校に通い、そしてこのように家業を手伝う毎日であったから、女の子と遊ぶなどという経験がまるでなかった。ところが…
〔 男子ばかりの教室で7年間過ごした私は、突如として、21歳になりかけの若く美しい金髪女性と、席を隣りあわせることになった。彼女の名はアイリーンだった。 〕
アイザック・アシモフは19歳、コロンビア大学の大学院一年生で、専攻は化学。 (アシモフはめっちゃ記憶力がよかったので、11歳で高校生になり、15歳で大学生になったのだ!)
うぶなアイザックの心は、金髪美女に舞い上がった。しかも彼女は化学においてクラスで一番の、(アイザック以上の)秀才なのだった。 隣り同士の席で化学の実験などするうち、アイザックはアイリーンとやがて親しくなり、ハドソン川の辺を一緒に散歩したりするようになる。
プラトニックなまま二人の交際は半年続き、そして…、こうなった。
〔 地下鉄で世界博覧会に行った。夜までまるまるの時間を、ここで過ごしたのである。私にとっては、このうえもない牧歌的なひと時だった。われわれは学校からも店からも遠く離れて、誰も手の届かない場所にいるのだった。私は11時間というもの、彼女といっしょに、博覧会という天国の中で、いっさいの心配苦労から隔絶された一種の泡の中に存在していた。
唯一の不運な出来事は(私の発案で)ジェットコースターに乗ったことだった。私の夢想の中では、彼女が悲鳴をあげて私にしがみつき、その際に(たぶん)彼女にキスできることになっていた。
車がゆっくりと頂上まで登ってゆく間、私は悪魔のような色情的な計画に意気揚々としていた。頂上を過ぎて落下が始まると、私は彼女の方を向いた__そして生まれて初めて、自分がひどい高所恐怖症であることを発見したのだった。私は高さに震えおののき、落下の感覚にきちがいのようになった。
(中略)
私はアイリーンに必死でしがみつき、ジェットコースターが止まる頃には、まったくの恐怖で死んだようになっていた。私にわかるかぎりでは、アイリーンは平気の平左だった。 〕
このデートを最後に、アイザックの初恋…アイリーンとの半年にわたるこの交際は終了した。
そして…
〔 私は口ひげを生やすことで、アイリーンを失ったことのせめてもの慰めとしようとした。初めてひげをたくわえるこの試みは、実際には1940年5月16日から始まり、一ヶ月たつと床屋で刈りこむ必要が生ずるほど長くなった。
ひげは失敗だった。何もそれだけの毛がなかったわけではない。毛は充分にあった。単一の色にならなかっただけのことだった。私の髪は褐色だったが、母方の家系には赤毛も金髪もあり、ひげには明らかにそれが勢揃いしたのである。
ひげは、赤色、金色、褐色、それに黒い毛さえちょっぴり混じっていて、全体の色は、これまで見たことのないようなものになった。私の知るかぎりでは、だれも気にいった者はいなかった。誰にも受けいれられない場合に発揮される、伝統的な母の愛を当てにするわけにもゆかなかった。母は、このひげが誰にもまして嫌いだったのである。
しかし、私は剛情にひげをたくわえ続けた。たぶん、自分が徐々に(きわめて徐々にだが)大人になっていることの証しとしてだったかもしれない。私は、大学院も一年近くもなるというのに、知力を除いては、依然として、あらゆる点で、年齢の割に世間知らずだった。 〕
以上は『アシモフ自伝』から。この部分は1940年頃のニューヨークのコロンビア大学を舞台としたエピソード。(ヨーロッパではこの時、ヒトラーの勢力が暗雲のように台頭して騒然としていた時代である。)
口ひげはやめたけど、そのかわりに、モミアゲを?
SF小説界の巨匠アイザック・アシモフ__彼の書いた『自伝』がこんなに面白いとは、知らなかった。明るいし、えらぶらないのがとてもいい。 アシモフ、最高!!
<ファウンデーション・シリーズ>、再読中です。
「なんだ、この意味不明のモミアゲは!?」
アイザック・アシモフは3歳の時からの、ニューヨーク・ブルックリンっ子である。 生まれは、ロシア。
1923年2月、家族(父、母、アイザック、妹の4人)は船に乗ってロシアからニューヨークへやってきた。父ユダは工場で働いてお金を貯めて、ブルックリン区でキャンデーストアを始めた。今でいうコンビニエンスストアのようなもので、新聞、雑誌、キャンデー、タバコ等を売る雑貨屋である。この小さな店は繁盛したが、たいへんなのは、こういう店というのはけっして休めないということである。だから息子のアイザックも子供ながら毎日店を手伝った。
アイザックはずっと男子ばかりの学校に通い、そしてこのように家業を手伝う毎日であったから、女の子と遊ぶなどという経験がまるでなかった。ところが…
〔 男子ばかりの教室で7年間過ごした私は、突如として、21歳になりかけの若く美しい金髪女性と、席を隣りあわせることになった。彼女の名はアイリーンだった。 〕
アイザック・アシモフは19歳、コロンビア大学の大学院一年生で、専攻は化学。 (アシモフはめっちゃ記憶力がよかったので、11歳で高校生になり、15歳で大学生になったのだ!)
うぶなアイザックの心は、金髪美女に舞い上がった。しかも彼女は化学においてクラスで一番の、(アイザック以上の)秀才なのだった。 隣り同士の席で化学の実験などするうち、アイザックはアイリーンとやがて親しくなり、ハドソン川の辺を一緒に散歩したりするようになる。
プラトニックなまま二人の交際は半年続き、そして…、こうなった。
〔 地下鉄で世界博覧会に行った。夜までまるまるの時間を、ここで過ごしたのである。私にとっては、このうえもない牧歌的なひと時だった。われわれは学校からも店からも遠く離れて、誰も手の届かない場所にいるのだった。私は11時間というもの、彼女といっしょに、博覧会という天国の中で、いっさいの心配苦労から隔絶された一種の泡の中に存在していた。
唯一の不運な出来事は(私の発案で)ジェットコースターに乗ったことだった。私の夢想の中では、彼女が悲鳴をあげて私にしがみつき、その際に(たぶん)彼女にキスできることになっていた。
車がゆっくりと頂上まで登ってゆく間、私は悪魔のような色情的な計画に意気揚々としていた。頂上を過ぎて落下が始まると、私は彼女の方を向いた__そして生まれて初めて、自分がひどい高所恐怖症であることを発見したのだった。私は高さに震えおののき、落下の感覚にきちがいのようになった。
(中略)
私はアイリーンに必死でしがみつき、ジェットコースターが止まる頃には、まったくの恐怖で死んだようになっていた。私にわかるかぎりでは、アイリーンは平気の平左だった。 〕
このデートを最後に、アイザックの初恋…アイリーンとの半年にわたるこの交際は終了した。
そして…
〔 私は口ひげを生やすことで、アイリーンを失ったことのせめてもの慰めとしようとした。初めてひげをたくわえるこの試みは、実際には1940年5月16日から始まり、一ヶ月たつと床屋で刈りこむ必要が生ずるほど長くなった。
ひげは失敗だった。何もそれだけの毛がなかったわけではない。毛は充分にあった。単一の色にならなかっただけのことだった。私の髪は褐色だったが、母方の家系には赤毛も金髪もあり、ひげには明らかにそれが勢揃いしたのである。
ひげは、赤色、金色、褐色、それに黒い毛さえちょっぴり混じっていて、全体の色は、これまで見たことのないようなものになった。私の知るかぎりでは、だれも気にいった者はいなかった。誰にも受けいれられない場合に発揮される、伝統的な母の愛を当てにするわけにもゆかなかった。母は、このひげが誰にもまして嫌いだったのである。
しかし、私は剛情にひげをたくわえ続けた。たぶん、自分が徐々に(きわめて徐々にだが)大人になっていることの証しとしてだったかもしれない。私は、大学院も一年近くもなるというのに、知力を除いては、依然として、あらゆる点で、年齢の割に世間知らずだった。 〕
以上は『アシモフ自伝』から。この部分は1940年頃のニューヨークのコロンビア大学を舞台としたエピソード。(ヨーロッパではこの時、ヒトラーの勢力が暗雲のように台頭して騒然としていた時代である。)
口ひげはやめたけど、そのかわりに、モミアゲを?
SF小説界の巨匠アイザック・アシモフ__彼の書いた『自伝』がこんなに面白いとは、知らなかった。明るいし、えらぶらないのがとてもいい。 アシモフ、最高!!
<ファウンデーション・シリーズ>、再読中です。










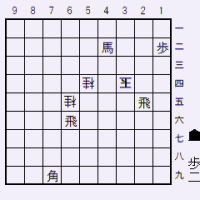
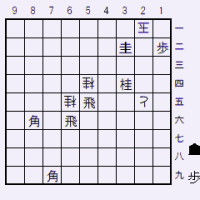
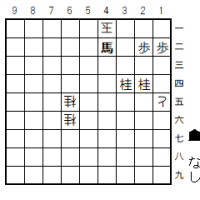
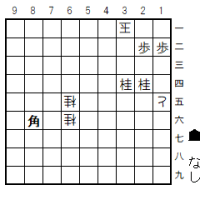
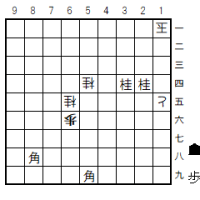
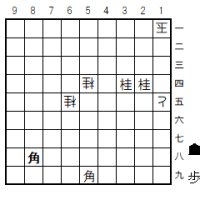
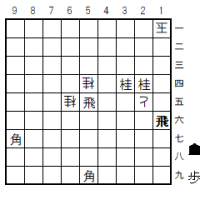
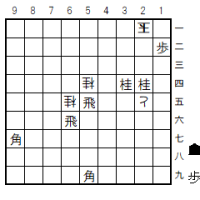
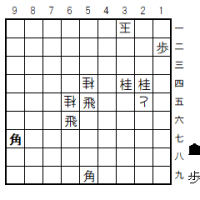
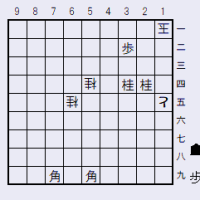






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます