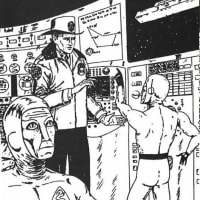日々の出来事 4月7日 インド人もビックリ
今日は、芦屋雁之助が亡くなった日です。(2004年4月7日)
芦屋雁之助は、京都市出身の喜劇俳優です。
実家は友禅屋でしたが、父親が芸人で18才から父の一座に入ります。
その後、一時期、中国服を着て手品をしていましたが、弟の芦屋小雁と漫才に転向、演芸場をまわります。
4年ほどで漫才を止め、兄弟で花登筺が興した劇団“笑いの王国”の旗揚げに参加、解散後の1964年には“喜劇座”を主宰しました。
テレビでは、1959年3月にスタートしたコメディー“番頭はんと丁稚どん”で、薬屋の番頭を演じ、人気を集めます。
このころのギャグでは、“いやいや、もの凄いこと言わはる”、“いやっ、えらいとこ見つかってしもうた”、“わてが雁之助だす”などがあります。
また、1984年に歌“娘よ”が150万枚を超える大ヒットとなり、紅白歌合戦に出場しました。
その後、テレビドラマ“裸の大将放浪記”で、芦屋雁之助は山下清を演じ、当たり役となりました。
それは、芦屋雁之助の本名が西部 清であったことや、小さいころ山下清に実際に会い、絵を教わったことがあることなど、何かの縁があったからかも知れません。

芦屋雁之助
☆今日の壺々話
“インド人もビックリ”
1964年にヱスビーカレーのテレビCMで、芦屋雁之助がインド人に扮し、カレーが美味くってビックリして飛び上がっていました。
これ以降、“インド人もビックリ”と言う怪しいフレーズが地下にもぐって生き続けています。
もっとも、インド人がビックリするのは、ヘビ使いがヘビに噛まれて死んだときぐらいであると思われます。
コレです
↓

ヘビ
二匹のヘビが、散歩に出かけました。
その途中、片方のヘビがもう片方のヘビに訊きました。
「 オレたち、毒もってるの?」
もう片方のヘビが答えました。
「 なんだい突然、もちろんさ。」
再び、片方のヘビが訊きました。
「 オレたち、本当に毒もってるの?」
「 ああ。オレたちゃ本当に毒もってるんだ。
実際、オレたちは世界の中で一番の猛毒をもったヘビなんだぜ。
なんでまたそんなこと訊くんだい?」
「 ああ、今、ちょっと、舌を噛んじゃってさ。」
こだま
かれこれ五年ほど前の夏、家で昼寝をしていた。
二階で風が気持ち良かったんで窓を開けて寝てたんだけど、ふと変な音がして目が覚めた。
何だ?と思って目をやって気絶しそうになった。
ガラガラヘビがいた。
TVで出てくるような奴が。
手を伸ばしたら本当に届きそうな距離。
変な音は尻尾を鳴らす音だった。
何で?
ここ日本なのに?
これ夢?
起きようとしたけど、ヘタに動いたら飛び掛ってきそうで動けない。
そのままガタガタ震えていたら、ふすまが開いた。
良かった!誰か帰ってきた・・・と思ったら、飼い猫のこだま(当時13歳)だった。
こだまは、もうお婆ちゃん猫でよぼよぼしてたので、これは絶対噛まれる!と思い、何とか逃がそうとして叫んだ。
・・・が、こだまの方が早かった。
サササッとヘビの背後に回ると、フーッと唸る。
ヘビがこだまへ向いた途端猫パンチしてパッと下がる。
凄い動きに一瞬ポカーンとなったけど、こだまは婆ちゃん猫。
そんなの続く訳無いんで、飛び起きて武器になる物を探した。
とりあえず麦茶のポットを掴んで振り向くと、何とこだまが前足でヘビを押さえて頭に食いついていた。
そのままヘビとこだまが転げ回る。
苦しがったヘビがバンバン暴れ回り、こだまが跳ね飛ばされた。
そこへ私も乱入して、弱ったヘビの尻尾を踏みつけ、麦茶ポットが割れたくらい滅多打ちにしてトドメをさした。
その後、警察を呼んで分かったんだけど、ヘビは本物のガラガラヘビだった。
多分、ヘビマニアの人がこっそり飼ってたのが、逃げたんじゃないかと言ってた。
(飼い主は捕まらなかった)
毒もちゃんと持ってて、噛まれたら本当に危なかったらしい。
こだまがいなかったら死んでたかもしれない。
この後、地元ではしばらくちょっとした騒ぎになった。
こだまも(メスだけど)しばらくヒーロー扱いで、近所の人が見に来たりした。
ただ、ヘビを噛んだせいか右側の犬歯が上下とも折れてしまい、しばらくマグロの刺身とカルカン三昧の日になった。
それからもこだまは元気だったけど、一昨年の冬に老衰であっさり死んでしまった。
ガラガラヘビと一騎打ち出来るくらい強い猫なんで、きっと今頃あの世でも楽しく過ごしていると思う。
水くさいカレー
ガキの頃の夏休み、父方の祖父母の家へ行くと、絶対に出るのがカレーだった。
ばぁちゃんが「水くさくないか?」とか言ってきた。
なんのことかと思ったがすぐに“水っぽい”ということだと気が付いた(兵庫弁らしい)。
確かにすごい“水くさいカレー”だった。
普通のカレーを倍くらいに水増ししたような感じと思ってもらえればいいだろうか。
おまけにご飯も水くさい。
正直まずかったのだが、いつも「いえ…おいしいです」と答えていた。
ここらへんは、こずかいを期待する孫としての、当然の発言だろう。
“ガキが喜ぶもの=カレー”という考えだったのか、そこにいる間は毎晩カレーカレーカレー。
もう勘弁してくれよ!と思った。
俺以外の兄弟もそう思っていただろう。
親父も苦笑して「外食にしようか」と言って、みんなでカレーから逃げ出した。
親父が言うには、前からばぁちゃんのカレーは“水くさい”ものなんだそうだ。
金のことでは苦労したひとだったから、必然的にそうなったのかもしれない、と。
文字通り水増ししたカレー。
そういや、こずかいもあんまりくれないよなぁ、ケチだよなぁと子供心に思ったものだ。
かなり前、ばぁちゃんは天寿を全うした。
じいちゃんは老人ホームへ行った。
親父の実家には誰もいなくなり、そこへ遊びに行くこともなくなった。
俺といえば社会人になり、もうばぁちゃんのことなんて、ほとんど忘れていた。
あるとき、たまたまお袋がいなくて、俺が夕飯をつくることになった。
とくに、何も考えずにカレーを作った。
適当に作ったもんだから、それが大失敗。
とってもうすいカレーになってしまった。
仕事から戻ってきた親父にそれを出して、「いや~“水くさいカレー”になっちゃった、ははは」と笑いながら言ったら、親父は突然ボロボロと泣いて、カレーを食いはじめた。
完全に忘れていたのだが、その日はばぁちゃんの命日だった。
俺だけじゃなくて、家族みんなが忘れていた。
すごく、気まずい気持ちで、みんな黙ってカレーを食った。
それ以降、ウチではばぁちゃんの命日はカレーの日となった。
水くさいカレーの日。
東洋の神秘の国
西洋人がいう「東洋の神秘の国」は何処か?
この疑問にインド人は「中国」と言い、中国人は「日本」と言い、日本人は「インド」と互いに押し付けあってたという話を思いだした。
その理由(うろ覚え)
・インド人「中国って仙人いるじゃん。スゲーよなあ。雲乗って飛べるんだぜ」→中国人「オメーは中国馬鹿にしてんのか。そんなのいるわけねぇだろ。山奥ならって・・・・・、いや、やっぱりいない。」
・中国人「やっぱり日本だろ。忍者だ。忍者。」→日本人「あのなあ、お前日本に来て5年たつよな。俺らいろんなとこに旅行したけど、一人でも忍者をみたか?」
・日本人「やっぱ東洋の神秘といえばインド。神秘の力を持つヨガ行者。」→インド人「あんな大道芸の何が凄いんだ。」
アジア人同士ですらこれだから、欧米人がどんな勘違いをしているか想像もつかない。
23歳女性カレー好き
近所にできた、インド人が経営するカレー屋さんで、店員さんと隣に座った。
割とイケメンな20代男性客の会話。
店「 ゴチュウモンハー。」
客「 この、チーズナンとマトンのカレー、辛さは5で。あとドリンクバー付けて下さい。」
店「 エエー?ソレ、チョウチョウカラーイヨウ?」
客「 ・・・大丈夫、ノープロブレム。」
店「 ダイジョブ~?カシコマッター。」
店員さん一旦去るが、すぐ戻ってくる。
店「 チョットオジカンカカルガヨロシイカー?」
客「 オーケーオーケー。」
10分くらいで男性客の注文したものが来る。
店「 オマタセダタカラ、コレサービスネー。」
皿に山盛りのサモサをドンと置いて行く。
男性苦笑い。
その後、
「 あの食べきれないので良かったら・・・。」
と自分に半分分けてくれた。
残したら失礼なので全部食べた。
男性が帰った後、物足りないのでカレーを2種とナンを3枚追加した。
満腹。
童話・恐怖小説・写真絵画MAINページに戻る。
大峰正楓の童話・恐怖小説・写真絵画MAINページ