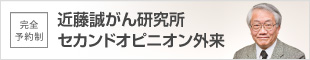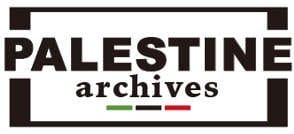父が2年前に亡くなり、其の後自宅にてお骨を保管していましたが、此度建立したお墓に家族のみで納骨しました。父が亡くなった後暫くの間は精神面で整理が付かず、書を読んだり何かの行動を起こす気持ちにもなれませんでした。そして、納骨・供養について解りませんでしたので、本やインターネットの文献等を読んで勉強しました。そうする中、私自身がキリスト者(クリスチャン)であると言う事が、その事について考える上での「根拠」になりました。
しかし実は、他のキリスト者の方と比べても劣る様に、私は今まで失敗ばかりの繰り返しで、受洗は小学生の時にしていたものの凡そ形だけでキリスト者とは言い難い様な状態に陥っていました。つまり、神に背を向ける様な状態に在りました。失敗する度に反省しては神様に向き直すも、直ぐまた元の状態に戻ってしまいました。過去の週末の教会学校や、常に継続しては行っていない教会での神父や牧師による指導や、その他関係する本から、拾い読みをする様な形では「聖書」の御言葉に触れる事は有りましたが、自分で聖書の通読をした事は一度も有りませんでした。因みに、現在は聖書の通読を行なっています。
キリスト者として「根拠」とするのは、勿論「聖書」です。そして、聖書の中にお墓に関する記述が有る事によって、「墓碑」を建立する事を決断しました。又、供養とは死者の霊を治め鎮めるもので呪って出て来ない様にする為のものとされていますが、キリスト教においては供養と言う概念は全く無く、其れを行う必要は有りません。キリスト教においては霊魂は神の御許に行っているとされていますので、墓は其の入り口に過ぎません。墓は故人の「記念碑」であり、墓を拝むのではなく、故人を懐かしむ「追懐」の場所となります。偶像崇拝が禁じられていますので、唯一の創造主である神以外を崇める事は間違いとなります。納骨前の自宅保管時においても、線香をあげる事も必要とせず、勿論、仏壇も戒名も必要有りません。
「千の風になって」と言う歌にも、霊魂は墓の中には居ないと在ります。私自身も現在独身ですが、後継ぎの問題等も含めて、墓を建てずに、火葬のみの直葬、海洋葬等の散骨、樹木葬等の自然葬、手元供養、納骨堂、永代供養等、選択肢が多く増えています。私自身の事であればその様な方法でも良かったのですが、飽く迄も父の納骨であり、且つ、家族もおりますので、単純にその様な方法にしようとは思えませんでした。又、一般的に車等で同程度の額を消費してしまう事を考えた場合に、前記の問題に関して同じ様にも思えました。そして、建立後の納骨後には、母からはありがとうと言う言葉を頂きました。
前記の様に霊魂は天の神の御許に行っていると信じますので、墓のデザインや形、素材等は関係無いので、それらに全くこだわりは有りませんでした。出来るだけ簡素・質素で安価なものにしようと思いました。
因みに追記として、私は当初に本等を読んで勉強していた時や元々それ以前から、世間一般的な葬儀の習慣に関しては疑問を感じていたのですが、以下の様な批判的な思いを抱いていました。
葬儀や供養について宗教により異なる為に、亡くなった人の考えをあくまで尊重するべきですが、葬式や墓・供養が故人の為というよりも、結局は故人の遺族の為に行っている様に思われます。世間体を気にしたり、確かな根拠の無い習慣やしきたりに従ったり、自分(遺族)が死後に入る所が在るという安心感が得られる為等です。それらの事が本当に故人の為になっているとは限りません。遺族が自分の都合の良い様に、納得して信じているだけかもしれません。少なくとも従来からの高価な葬式や墓は間違いで、戒名や位牌に掛ける金額によって死後の行く先が決まってしまうと言う理屈は、昔のカトリックの免罪符と同じで、腐敗に値すると思います。又、人間の手によって死者を供養する事等は、人間の傲慢・思い上がりでもある様に思います。差別化を図った江戸時代に、身分の高く無い庶民は公に苗字を名乗る事が出来なかった訳で(公文書である宗門人別帳への記載を許されませんでした。但し、私称として過去帳や墓碑には記していたらしいです。)、「何々家之墓」とは言っても、所詮、明治以降に過ぎません。又、火葬率が上がって来た事も昭和に入ってからで、土葬で同じ墓に何体も入れる事が出来る訳がありません。檀家制度は、江戸時代に現在の役所の役割である戸籍の管理を寺が負わされたもので、担当する檀家の者が亡くなった後、其の寺で合葬しました。現在でも永代供養は、例え個別に分けて納骨しても、30年~50年経てば合葬されます。其れは遺族の為故の期間です。合葬後は、他の地に改葬出来ません。それに、お骨上げの時に既に、骨壺に入りきれなかった分のお骨は合葬されています。江戸時代より前は、山に野捨て等も一般大衆の間では行われていました。手元供養は他の葬儀と併用されますが、遺族が身近に死者を感じていたいという場合等に良いみたいです。大体、遺骨をさっさと納骨してしまうというのは、其の遺骨が家族から邪魔者扱いされている様にも感じます。
聖書にあるお墓に関する記述として、以下の御言葉が在ります。
旧約聖書・創世記23章19~20節「こうして後、アブラハムは自分の妻サラを、カナンの地にあるマムレすなわち今日のヘブロンに面するマクペラの畑地のほら穴に葬った。こうして、この畑地と、その中にあるほら穴は、ヘテ人たちから離れてアブラハムの私有の墓地として彼の所有となった。」。
創世記25章8~10節「アブラハムは・・・長寿を全うして息絶えて死に、自分の民に加えられた。彼の子らイサクとイシュマエルは、彼をマクペラのほら穴に葬った。このほら穴は、マムレに面するヘテ人ツォハルの子エフロンの畑地の中にあった。この畑地はアブラハムがヘテ人たちから買ったもので、そこにアブラハムと妻サラとが葬られたのである。」。
旧約聖書・エレミヤ書26章20~24節「ほかにも主の名によって預言している人がいた。すなわち、キルヤテ・エアリムの出のシェマヤの子ウリヤで、彼はこの町とこの国に対して、エレミヤのことばと全く同じような預言をしていた。エホヤキム王と、そのすべての勇士や、首長たちは、彼のことばを聞いた。王は彼を殺そうとしたが、ウリヤはこれを聞いて恐れ、エジプトへ逃れて行った。・・・彼らはウリヤをエジプトから連れ出し、エホヤキム王のところに連れて来たので、王は彼を剣で打ち殺し、そのしかばねを共同墓地に捨てさせた。しかし、シャファンの子アヒカムはエレミヤをかばい、エレミヤが民の手に渡されて殺されないようにした。」。
新約聖書・マタイの福音書27章57~61節「夕方になって、アリマタヤの金持ちでヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。この人はピラトのところに行って、イエスのからだの下げ渡しを願った。・・・ヨセフはそれを取り降ろして、きれいな亜麻布に包み、岩を掘って造った自分の新しい墓に納めた。墓の入口には大きな石をころがしかけて帰った。そこにはマグダラのマリヤとほかのマリヤとが墓のほうを向いてすわっていた。」等、其の外にもイエス・キリストが死後三日目の復活まで葬られた事についての記載が在ります。
又、イスラエルのエルサレム東にあるオリーブ山には数多くの墓が建てられていますが、此の世の終わりの最後の審判の日に主が再降臨してオリーブ山に立ち、死者がよみがえる場所とされている為に其処に墓地が作られるようになりました。その事については以下の御言葉が在ります。
旧約聖書・ゼカリヤ書14章4節「その日、主の足は、エルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山は、その真中で二つに裂け、東西に延びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。」。
新約聖書・ヨハネの福音書5章28~29節「このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者がみな、子の声を聞いて出て来る時が来ます。善を行なった者は、よみがえっていのちを受け、悪を行なった者は、よみがえってさばきを受けるのです。」。「子」とは、天の父なる神の子のイエス・キリストの事です。「父」と「子」と「聖霊」の「三位一体」の創造主である唯一の神です。
同・ヨハネの黙示録20章4~5節「また私は、多くの座を見た。彼らはその上に座った。そしてさばきを行なう権威が彼らに与えられた。また私は、イエスのあかしと神のことばとのゆえに首をはねられた人たちのたましいと、獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返って、キリストとともに、千年の間王となった。そのほかの死者は、千年の終わるまでは、生き返らなかった。これが第一の復活である。」。
ヨハネの黙示録14章1~5節「また私は見た。見よ。子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊とともに十四万四千人の人たちがいて、その額には子羊の名と、子羊の父の名とがしるしてあった。・・・彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは、子羊が行く所には、どこにでもついて行く。彼らは、神および子羊にささげられる初穂として、人々の中から贖われたのである。彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のない者である。」。「子羊」とはイエス・キリストの事です。
旧約聖書・ダニエル書12章2節「地のちりの中に眠っている者のうち、多くの者が目をさます。ある者は永遠のいのちに、ある者はそしりと永遠の忌みに。」。
同・ヨブ記19章25~27節「私は知っている。私を贖う方は生きておられ、後の日に、ちりの上に立たれることを。私の皮が、このようにはぎとられて後、私は、私の肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。私の目がこれを見る。ほかの者の目ではない。私の内なる思いは私のうちで、絶え入るばかりだ。」。
しかし実は、他のキリスト者の方と比べても劣る様に、私は今まで失敗ばかりの繰り返しで、受洗は小学生の時にしていたものの凡そ形だけでキリスト者とは言い難い様な状態に陥っていました。つまり、神に背を向ける様な状態に在りました。失敗する度に反省しては神様に向き直すも、直ぐまた元の状態に戻ってしまいました。過去の週末の教会学校や、常に継続しては行っていない教会での神父や牧師による指導や、その他関係する本から、拾い読みをする様な形では「聖書」の御言葉に触れる事は有りましたが、自分で聖書の通読をした事は一度も有りませんでした。因みに、現在は聖書の通読を行なっています。
キリスト者として「根拠」とするのは、勿論「聖書」です。そして、聖書の中にお墓に関する記述が有る事によって、「墓碑」を建立する事を決断しました。又、供養とは死者の霊を治め鎮めるもので呪って出て来ない様にする為のものとされていますが、キリスト教においては供養と言う概念は全く無く、其れを行う必要は有りません。キリスト教においては霊魂は神の御許に行っているとされていますので、墓は其の入り口に過ぎません。墓は故人の「記念碑」であり、墓を拝むのではなく、故人を懐かしむ「追懐」の場所となります。偶像崇拝が禁じられていますので、唯一の創造主である神以外を崇める事は間違いとなります。納骨前の自宅保管時においても、線香をあげる事も必要とせず、勿論、仏壇も戒名も必要有りません。
「千の風になって」と言う歌にも、霊魂は墓の中には居ないと在ります。私自身も現在独身ですが、後継ぎの問題等も含めて、墓を建てずに、火葬のみの直葬、海洋葬等の散骨、樹木葬等の自然葬、手元供養、納骨堂、永代供養等、選択肢が多く増えています。私自身の事であればその様な方法でも良かったのですが、飽く迄も父の納骨であり、且つ、家族もおりますので、単純にその様な方法にしようとは思えませんでした。又、一般的に車等で同程度の額を消費してしまう事を考えた場合に、前記の問題に関して同じ様にも思えました。そして、建立後の納骨後には、母からはありがとうと言う言葉を頂きました。
前記の様に霊魂は天の神の御許に行っていると信じますので、墓のデザインや形、素材等は関係無いので、それらに全くこだわりは有りませんでした。出来るだけ簡素・質素で安価なものにしようと思いました。
因みに追記として、私は当初に本等を読んで勉強していた時や元々それ以前から、世間一般的な葬儀の習慣に関しては疑問を感じていたのですが、以下の様な批判的な思いを抱いていました。
葬儀や供養について宗教により異なる為に、亡くなった人の考えをあくまで尊重するべきですが、葬式や墓・供養が故人の為というよりも、結局は故人の遺族の為に行っている様に思われます。世間体を気にしたり、確かな根拠の無い習慣やしきたりに従ったり、自分(遺族)が死後に入る所が在るという安心感が得られる為等です。それらの事が本当に故人の為になっているとは限りません。遺族が自分の都合の良い様に、納得して信じているだけかもしれません。少なくとも従来からの高価な葬式や墓は間違いで、戒名や位牌に掛ける金額によって死後の行く先が決まってしまうと言う理屈は、昔のカトリックの免罪符と同じで、腐敗に値すると思います。又、人間の手によって死者を供養する事等は、人間の傲慢・思い上がりでもある様に思います。差別化を図った江戸時代に、身分の高く無い庶民は公に苗字を名乗る事が出来なかった訳で(公文書である宗門人別帳への記載を許されませんでした。但し、私称として過去帳や墓碑には記していたらしいです。)、「何々家之墓」とは言っても、所詮、明治以降に過ぎません。又、火葬率が上がって来た事も昭和に入ってからで、土葬で同じ墓に何体も入れる事が出来る訳がありません。檀家制度は、江戸時代に現在の役所の役割である戸籍の管理を寺が負わされたもので、担当する檀家の者が亡くなった後、其の寺で合葬しました。現在でも永代供養は、例え個別に分けて納骨しても、30年~50年経てば合葬されます。其れは遺族の為故の期間です。合葬後は、他の地に改葬出来ません。それに、お骨上げの時に既に、骨壺に入りきれなかった分のお骨は合葬されています。江戸時代より前は、山に野捨て等も一般大衆の間では行われていました。手元供養は他の葬儀と併用されますが、遺族が身近に死者を感じていたいという場合等に良いみたいです。大体、遺骨をさっさと納骨してしまうというのは、其の遺骨が家族から邪魔者扱いされている様にも感じます。
聖書にあるお墓に関する記述として、以下の御言葉が在ります。
旧約聖書・創世記23章19~20節「こうして後、アブラハムは自分の妻サラを、カナンの地にあるマムレすなわち今日のヘブロンに面するマクペラの畑地のほら穴に葬った。こうして、この畑地と、その中にあるほら穴は、ヘテ人たちから離れてアブラハムの私有の墓地として彼の所有となった。」。
創世記25章8~10節「アブラハムは・・・長寿を全うして息絶えて死に、自分の民に加えられた。彼の子らイサクとイシュマエルは、彼をマクペラのほら穴に葬った。このほら穴は、マムレに面するヘテ人ツォハルの子エフロンの畑地の中にあった。この畑地はアブラハムがヘテ人たちから買ったもので、そこにアブラハムと妻サラとが葬られたのである。」。
旧約聖書・エレミヤ書26章20~24節「ほかにも主の名によって預言している人がいた。すなわち、キルヤテ・エアリムの出のシェマヤの子ウリヤで、彼はこの町とこの国に対して、エレミヤのことばと全く同じような預言をしていた。エホヤキム王と、そのすべての勇士や、首長たちは、彼のことばを聞いた。王は彼を殺そうとしたが、ウリヤはこれを聞いて恐れ、エジプトへ逃れて行った。・・・彼らはウリヤをエジプトから連れ出し、エホヤキム王のところに連れて来たので、王は彼を剣で打ち殺し、そのしかばねを共同墓地に捨てさせた。しかし、シャファンの子アヒカムはエレミヤをかばい、エレミヤが民の手に渡されて殺されないようにした。」。
新約聖書・マタイの福音書27章57~61節「夕方になって、アリマタヤの金持ちでヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。この人はピラトのところに行って、イエスのからだの下げ渡しを願った。・・・ヨセフはそれを取り降ろして、きれいな亜麻布に包み、岩を掘って造った自分の新しい墓に納めた。墓の入口には大きな石をころがしかけて帰った。そこにはマグダラのマリヤとほかのマリヤとが墓のほうを向いてすわっていた。」等、其の外にもイエス・キリストが死後三日目の復活まで葬られた事についての記載が在ります。
又、イスラエルのエルサレム東にあるオリーブ山には数多くの墓が建てられていますが、此の世の終わりの最後の審判の日に主が再降臨してオリーブ山に立ち、死者がよみがえる場所とされている為に其処に墓地が作られるようになりました。その事については以下の御言葉が在ります。
旧約聖書・ゼカリヤ書14章4節「その日、主の足は、エルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山は、その真中で二つに裂け、東西に延びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。」。
新約聖書・ヨハネの福音書5章28~29節「このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者がみな、子の声を聞いて出て来る時が来ます。善を行なった者は、よみがえっていのちを受け、悪を行なった者は、よみがえってさばきを受けるのです。」。「子」とは、天の父なる神の子のイエス・キリストの事です。「父」と「子」と「聖霊」の「三位一体」の創造主である唯一の神です。
同・ヨハネの黙示録20章4~5節「また私は、多くの座を見た。彼らはその上に座った。そしてさばきを行なう権威が彼らに与えられた。また私は、イエスのあかしと神のことばとのゆえに首をはねられた人たちのたましいと、獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返って、キリストとともに、千年の間王となった。そのほかの死者は、千年の終わるまでは、生き返らなかった。これが第一の復活である。」。
ヨハネの黙示録14章1~5節「また私は見た。見よ。子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊とともに十四万四千人の人たちがいて、その額には子羊の名と、子羊の父の名とがしるしてあった。・・・彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは、子羊が行く所には、どこにでもついて行く。彼らは、神および子羊にささげられる初穂として、人々の中から贖われたのである。彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のない者である。」。「子羊」とはイエス・キリストの事です。
旧約聖書・ダニエル書12章2節「地のちりの中に眠っている者のうち、多くの者が目をさます。ある者は永遠のいのちに、ある者はそしりと永遠の忌みに。」。
同・ヨブ記19章25~27節「私は知っている。私を贖う方は生きておられ、後の日に、ちりの上に立たれることを。私の皮が、このようにはぎとられて後、私は、私の肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。私の目がこれを見る。ほかの者の目ではない。私の内なる思いは私のうちで、絶え入るばかりだ。」。