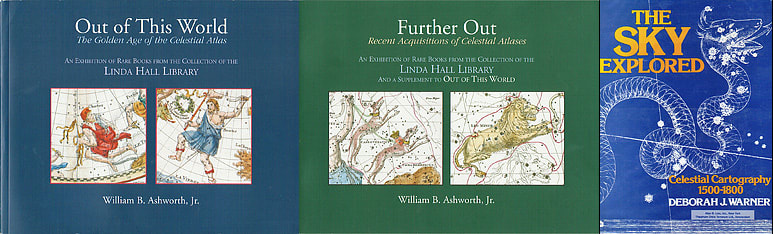今回は参考図書について.
(1)千葉市立郷土博物館 天文資料解説集No.1 「グロティウスの星座図帳」
126頁(モノクロ) A4変形 1999年刊行
前掲したとおり,古書として購入しすでに本棚に入っていたが,挿入されている星座図の印刷の質については,残念ながら満足のいくものではなく,コントラストを高く設定しすぎて,暗部はつぶれ,明部の細い線も消えて途切れてしまっていた.もともと漠然とこんなものかと思っていたのだが,最近実物を見て違いがわかった.ただし,これは裏の印刷活字が表に見えてしまっているため,やむを得ずの設定だったのかもしれない.重ねて述べるが,テキストのラテン語の邦訳は極めて貴重である.
・同館サイトよりの引用
同館では平成8年度から所蔵資料の翻訳調査おこなっており、その成果報告として天文資料解説集を刊行している。第1集は17世紀に活躍した法学者フーゴー・グロティウス(Hugo Grotius 1583-1646)の「星座図帳」(『シュンタグマ・アラテオルム-研究者にとってきわめて有益な詩的・天文学的著作(SYNTAGMA ARATEORVM:OPVS POETICAE ETASTRONOMIAE STVDIOSIS VTILISSIMVM)』を収録した。1600年にライデンのプランタン書店から刊行された天文書で、前半はギリシャ時代の詩人アトラスの天象誌「ファイノメナ」がギリシャ語とラテン語で紹介され、後半はオランダの美術家ヤーコブ・デ・ヘイン(Jacob de Gheyn 1565-1629)による星座絵の銅版画が掲載されている。「ファイノメナ」は現存する著作の中で星座について組織だった記述が見られる最古のものとされ、星座の歴史を探る貴重な資料である。本書では「ファイノメナ」の邦訳とヤーコブ・デ・ヘインの星座絵についての解説を掲載した。
その後,「天文古玩」のサイトの同博物館の「大星座展」の記事を拝読させていただいて,同館の刊行物のバックナンバーの存在を知り,以下の四冊を購入した.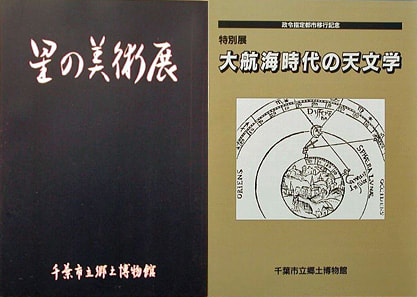
(2)星の美術展
49頁(カラー4頁) B5判 1989年刊行
巻末のリストをみると,20年前すでに同館が収集を始めていてシラー星図の原書やゾイッター星図を所蔵していたことがわかる.ほかに「覆刻」とされているものが少なからずあるが,セラリウス星図は初版,バイエル星図やボーデ星図(ウラノグラフィアでは無く,Vorstellung der Gestirneの初版[フラムスティードパリ版の独語訳にあたる])についても誤解があり,後述「星座の文化史」では訂正され実物になっている.当時,草下英明氏(氏所蔵のセラリウス星図の1枚は初版と思われるが右下に番号はない)や金子功氏もこの分野で蒐集されていたこともわかる.カラー図版が少ないのが残念.
・同館サイトよりの引用
平成元年に開催した特別展「星の美術展―東西の貴重な古星図を集めて―」の展示資料解説図録。東洋・西洋の古星図や星を題材にした美術作品を展示し、星座の歴史と星図の変遷、美術作品に込められた人々の星空への想いを探った。
<収録資料>ゾイッター天球図、地球・天球・渾天儀図、天文分野之図、天文成象、天象総星之図、佐倉藩天球儀(複製)、シラーのキリスト教星図、天球豆図、鹿児島征討記之内西郷星之図、西郷星の珍説、他
(3)大航海時代の天文学
43頁(カラー4頁) B5判 1992年刊
ややくだけた内容で解説されていて,望遠鏡や四分儀・六分儀,世界地図なども展示されていたらしい.3年の間に同館の収蔵品は増えていたかのようで,例えばアピアヌスの書籍やドッペルマイヤーの天文図などが追加されている.憶測で間違っているかもしれないが,金子氏などの所蔵品が同館に譲られたとすれば他の所蔵品の変化が説明しやすいかもしれない??
・同館サイトよりの引用
平成4年に開催した特別展「大航海時代の天文学」の展示資料解説図録。「星と航海術」をテーマに古星図や航海関連資料を展示し、15世紀の大航海時代の天文学の役割を探った。
<収録資料>レギオモンタヌス「天体暦」、アピアヌス「宇宙形状誌」、アピアヌス「天文学教科書」、バイヤー星図、シラーのキリスト教星図、セラリウス天球図、ヘヴェリウス「月面誌」、フラムスチード星図、ゴルトバッハ星図、ドッペルマイヤーの天文図、天球豆図、ゾイッター天球図、地球・天球・渾天儀図、携帯用地球儀天球儀 他 
(4)天文資料解説集No.3 東西の天球図
60頁(モノクロ) A4変形 2002年刊行
パルディー天球図(彩色された6枚)やド・ラ・イール天球図(彩色された北天・南天2枚)などをさらに購入したらしい.大したものである! パルディー天球図の年代は特定されていなかったが,うしかい座の右足元に1682年の彗星の軌跡が描かれていることから1690年の第二版(LHLによる[Warnerの1a?])と推定される.ド・ラ・イール天球図のほうは北天図が1766年,南天図が1760年とあり,少なくとも北天のほうはWarnerの4aだろう. 印刷がカラーでないのが残念だが,比較的大きく図版は掲載されており,星図の周囲に印刷されている献辞や解説も翻訳して載せられている.
・同館サイトよりの引用
同館が所蔵する天球図8点と,仙台市天文台が所蔵する「黄道中西合図」を掲載しました。掲載資料は,「淳祐天文図」(1247年・中国),「天象列次分野之図」(1395年・朝鮮),「天文分野之図」(1677年・日本),「天文成象」(1699年・日本),「黄道中西合図」(1807年・中国),「ブルナッチ天球図」(1687年・イタリア),「ド・ラ・イール天球図」(18世紀後半・フランス),「パルディー天球図」(17世紀後半・フランス),「コルデンブッシュの天球図帳」(1789年頃・ドイツ)の計9点です。各資料には,星図の部分だけではなく,その周りに様々な解説文が書かれています。ラテン語やフランス語,中国語などで記述された解説文には,いったい何が書かれているのでしょうか。本書では各資料の写真とともに解説文の翻訳を掲載しています。東西の天球図の詳細を比べていただき,当時の天文学の概要や東西の民族による星空の見方,星座や宇宙観の違いなどをご覧ください。
(5)天文資料解説集No.4 西洋の天文書
60頁(モノクロ) A4変形 2002年刊行
ガリレイのディアローゴ,へヴェリウスのセレノグラフィア,ドッペルマイヤーのアトラス・ヌーヴス・コエレスティスなどが追加されている.このレベルになると研究者やマニア向けになるかもしれず,日本に原著が存在していること自体稀で,他では一部の大学図書館の稀覯書部門に数冊あるかどうかであろう.一般向けにはその図版でどのような書物なのかが良くわかるように構成紹介されている.
・同館サイトよりの引用
同館が所蔵する西洋の天文書13点を掲載しました。掲載資料は、ゲルマニクス「アラテア」(9世紀)、ヨハネス・レギオモンタヌス「天体暦書」(1474年頃)、ヒギヌス「宇宙と天球について」(1517年)、パオロ・ニコッティ「宇宙の構造について」(1525年)、ペトルス・アピアヌス「天文学教科書」(1540年)、ペトルス・アピアヌス「宇宙形状誌(コスモグラフィア)」(1544年)、ガリレオ・ガリレイ「天文対話」(1632年)、スタニスラフ・ルービエンニッツキー「彗星の世界」(1640年)、ヨハネス・へヴェリウス「月面誌(セレノグラフィア)」(1647年)、フーゴー・グロティウス「星座図帳」(1600年)、ヨーハン・ガブリエル・ドッペルマイヤー「最新天文図帳」(1742年)、ジョゼフ・ハリス「天球儀・地球儀・太陽系儀の利用法」(1768年)、G・ルビー「英国天体図帳」(1830年)です。
すでに品切れになっている2000年に刊行された天文資料解説集No.2は「ボーデの星図書」で無料頒布だったことがわかった.ここで平成7年の特別展図録「星座の文化史」の存在を知り,手を尽くして検索した結果,共同開催で巡回した府中市郷土の森博物館に残っていることがわかり,入手することが出来た.
(6)星座の文化史
71頁(カラー図版多数) A4版 1995年5月
結局,千葉市立郷土博物館ではド・ラ・イール天球図・パルディー天球図もドッペルマイヤーの最新天文図帳も95年以前に購入されていたことがわかった.この図録をみると,同館の天文書以外の蒐集品の全貌が明らかになる(多分).古星図としてはピッコロミニ星図初版,グロチウスのアラテア初版,バイエル星図第6版(第4版ではなくWarnerによると1655年は第6版になる),シラーのキリスト教星図第二版(初版とされているが天球図のタイトルのラテン語がDeiでなくDEIなので,第二版[Warnerの1a]),セラリウス天球図は3枚とも初版(右下に番号あり),ヘヴェリウス星図初版,パルディー天球図第二版,ド・ラ・イール天球図第二版,フラムスティード星図第三版(1795年パリ版第二版),ボーデ星図(Vorstellung....)初版を所蔵されていることがわかった.
さらに驚くべきことに,ドッペルマイヤーの天球儀も所蔵されていた! 直径20cmの1730年初版もののW.P.イェーニッヒによる1790年代の再版である(じつは当館所蔵品もそうだったのだが32cm).ニスの軽い黄変以外,コンディションは良好で,当館所蔵品に無い水平環の目盛りと北極の時刻ダイヤルが残っている.
(7)特別展「遠くを望む~江戸時代の望遠鏡」
B5版20頁 1991年7月
府中市郷土の森博物館を検索したときに発見したので併せて購入したが,同館の特別展で,いまは無き五島プラネタリウム所蔵の1820年製グレゴリー式反射望遠鏡以外は,和物であった.望遠鏡以外で,北斎の富岳百景の「鳥越の不二」の中に浅草天文台の渾天儀が前景に大きく描かれていたのがわかって新鮮だった(展示は複製).
(Ⅰ)"Out of This World"
112頁 A5版 2007年
Linda Hall Libraryでの'96.11/1~'97.2/1の企画展"Out of This World"の図録で展示された43点が掲載され,2007年に補遺の"Further Out"(15点;36頁)の出版とともに再版され,改めて展覧された.すべてカラーで解説も平易なため,初学者(私)向きの入門書として大変重宝している.サイトのほうで同一のテキストと図版を見ることが出来るし,直販もある(二冊で$20).
(Ⅱ)"The Sky Explored:Celestial Cartgraphy 1500-1800"
293頁 A4版 Deborah J.Warner, N.Y.,1979
出版されてから30年経過しているが,主要な古星図の目録としていまでも有用である.図版は多いが,個々の星図の版による差についてはテキストに表記されているだけなので確認に時間がかかる.天球儀が載っていないのが残念.