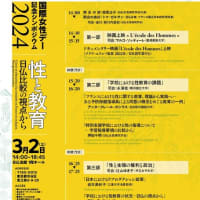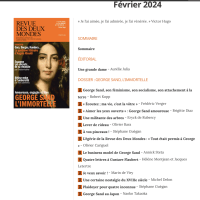サンドの『コンシュエロ』の続編、『ルードルシュタッド公爵夫人』には、フリーメイソンの世界が描かれている。当初は気軽な物語として書き始められたものであった。しかし、『ルードルシュタッド公爵夫人』は、歌姫コンシュエロがヨーロッパを横断する壮大なロマンとなった。
あるとき、コンスエロは政治的陰謀に巻き込まれ投獄されてしまうが、彼女を牢獄から助け出したのは、フリーメイソンを連想させる団体の「見えざる人々」であった。サンドが、親しい友人であったリストを通し、彼が入会していた秘密結社について知っていたことは類推に難くない。フランス語ではフランマソンヌリFranc-maçonnerieとよばれるが、この部分を描くために、サンドは関連する資料を取り寄せ、読み漁っていたことが知られている。
ーーー
では、フリーメイソンとは一体どのようなものなのだろうか。
フリーメイソンの起源や具体的な歴史については対外的な資料が少ないため、諸説存在する。フリーメイソンリーは、16世紀後半から17世紀初頭に、判然としない起源から起きた友愛結社とされている。起源については、中世イギリスの石工職人のロッジ説、テンプル騎士団説、ソロモン神殿建築家説、近代設立説、ピラミッド建設の際の石工集団説など、諸説があるようだ。
石工組合としての実務的メーソンリーが前身として中世に存在した、とする説もある。こうした職人団体としてのフリーメイソンリーは近代になって衰えたが、イギリスでは建築に関係のない貴族、紳士、知識人がフリーメイソンリーに加入し始めた(思索的メイソンリー。「思弁的-」)。それと共に、フリーメイソンリーは職人団体から、友愛団体に変貌したとされている。または、実務的メイソンリーとの直接の関係はなく、その組織を参考に、貴族たちが別個に作ったのが、思索的メイソンリーであるともいう。中世ヨーロッパでは、建築はあらゆる分野の技術に精通する必要がある「王者の技術」とされ、建築学や職人の社会的地位は高かった。また、技術の伝承についても厳しい掟が設けられた。その神秘性から、実務的メイソンリーが貴族などに注目され、薔薇十字団の正体ではないかと期待する者もあった。これについては実務的メイソンリーはあくまでも石工団体であり、期待は裏切られた結果に終わったようである。
民間人を対象とする国際的な互助組織がない時代には、会員であれば相互に助け合うというフリーメイソンリーは、困難を抱えた人間にとって非常にありがたい組織だった。ウィーンのロッジに加入していたモーツァルトが、同じロッジのフリーメイソンに借金の無心をした記録が残っている。
フリーメイソンリーが広まった時期は、絶対王政から啓蒙君主、市民革命へと政治的な激動が続く時代でもあり、特定の宗教を持たずに理性や自由博愛の思想を掲げるヨーロッパ系フリーメイソンリーは、特定の宗教を否定することから、自由思想としてカトリック教会などの宗教権力からは敵視された。とりわけフランス革命の当事者たちの多くがフリーメイソンであったため、しばしば旧体制側から体制を転覆するための陰謀組織とみなされた。ナチス・ドイツの時代にはマルクス主義や自由主義とともに民族の統一を阻む抹殺されるべき教説として扱われ、弾圧を受けた。独立戦争にかかわった多くの会員がいたアメリカにおいても白眼視される傾向があった。ちなみにニューヨークの自由の女神像はフランス系フリーメイソンリーとアメリカ系フリーメイソンリーの間に交わされた贈り物という側面もあり、台座の銘板にはその経緯とメイソンリーの定規・コンパス・Gの紋章がきざまれている。
現在では、多様な形で全世界に存在し、その会員数は600万人に上り、うち15万人はスコットランド・グランドロッジならびにアイルランド・グランドロッジの管区下に、25万人は英連邦グランドロッジに、200万人は米国のグランドロッジに所属している。
「自由」、「平等」、「友愛」、「寛容」、「人道」の5つを基本理念としている。
「非正規」派のグランド・ロッジとして有力なのは、フランスの「フランス大東社」(GODF)である。
フランスでフリーメイソンリーが政治的影響を強めるのは19世紀後半、第三共和制期に入ってからである。政治活動を禁じた「正規派」と異なり、仏大東社は圧力団体としても機能した。
1877年9月13日、仏大東社は憲章を改訂して「至高の存在への尊崇と信仰」の義務規定を撤廃し、「良心の自由と人間性の確立」を新たな基本理念と定めた。これを基本理念の逸脱と見なした英系ロッジは、仏大東社の認証を取り消した。ただし、「正規派」メイソンの片桐三郎によれば、1867年、仏大東社がアメリカ・ルイジアナ州に設立したスコティッシュ・ライト評議会(上位階級授与のための組織、後述)が、同州のグランド・ロッジに管轄権を要求したため、米国系ロッジはこれを不服とするルイジアナ州のグランド・ロッジの要請に基づき、仏大東社の認証を取り消した事件があった。仏大東社は「無神論者」のレッテルを貼られたが、これは信仰しない自由を認めたものであり、信仰そのものの否定ではない。
フランスのロッジに女性会員(仏大東社自体は認めていない)やアフリカ系(黒人系)会員を認めたことも、「正規派」による非難の理由とされた。すなわち、当時の「正規派」が人種差別思想を多分に持っていたことを意味する。
現在でも、フランスでは仏大東社系のフリーメイソンリーが最大勢力である[150]。政治的には、19世紀末から20世紀初めに、カトリックとの対立の所産でもある政教分離推進に強い影響力を持った。そのため、1904年にはフランスはローマ教皇庁との国交断絶に至った(現在は国交回復)。その後影響力を低下させたが、1936年の総選挙で人民戦線が勝利した背景にも、仏大東社の仲介があったという。戦後も、民族自決の立場からフランス植民地だったアルジェリア独立を支持するなど、仏大東社は政治的発言を行っている。
ーーー
参考文献:
吉村正和 『フリーメイソン 西欧神秘主義の変容』 講談社 1989年
赤間剛 『フリーメーソンの秘密 世界最大の結社の真実』 三一書房、1983年
吉田進 『フリーメイソンと大音楽家たち』 国書刊行会、2006年
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%82%BD%E3%83%B3
日本では「秘密組織」で「世界を裏から操る団体」のように言われているが、諸外国では、フリーメイソンであることは特別なことではないようである。
特に、米国やヨーロッパでは、フリーメイソンのメンバーであることは、社会的なステイタスが高いと評価されることもあり、自慢のネタとして公表する人も多いそうだ。
もともとフリーメイソンはイギリスから伝わったもので、一種の紳士クラブのようなもので社交場として広がっていった。有名な政治家や企業家が入会しているために、世界を牛耳っているとする陰謀説もあるが、今では「社交クラブ」のようなもので、会員同士で宗教的、政治的な目的をもった活動をしないことも約束されている。
現在は会員を統括する「ロッジ」という組織が各国に存在し、各ロッジが独自に会員を管理、運営している。日本では港区に「日本グランドロッジ」が構えられており、堂々と看板が出されている。
フリーメイソンに入会できる条件としてはは、まず「20歳以上の男子であること」「決まった宗教を持っていること」「メンバーの投票で全会一致で承認される必要があること」などである。
公序良俗に反する仕事でなければ、入会条件をクリアしているようである。フリーメイソンといえば「ロックフェラー」や「ロスチャイルド」など、大金持ちの権力者でなければ入れない印象があったが、そうではないと思われる。
入会にあたっては、会員の審査がある。
ちなみに、漫画家の西原理恵子のパートナー、高須クリニックの高須克弥氏は、Twitter上でフリーメイソンに入会したことを堂々宣言している。
世界中に500~700万人の会員数がいるといわれるフリーメイソン。「秘密結社」と名乗るにはあまりにも大きな団体となってしまい、米国ではフェイスブックを通じてフリーメイソンの会員が募集されるなど、極めてオープンマインドな団体へと変化している。
そのため、人脈づくりに期待をはせたり、裏の世界を見たくて入会した人は、収穫のなさにやめていくことさえあることも指摘されている。
ーーー
コンスエロは、結社の掟を守って位階を獲得し、遂には最高位の位階を得て、結社を統率する女性トップのワンダに謁見している。
正統派のフリーメイソンは女性メンバーを認めていないが、フランスでは必ずしもそうではなく、フランス大東社は女性会員を認めていたという。したがって、サンドの着眼点は、フランスのリーメイソンの歴史的流れから必ずしも逸れていたわけではなかったと理解してよいだろう。しかしながら、最高位をワンダのような女性をトップにしていたかどうかについては、詳しく調べてみる必要があると思われる。